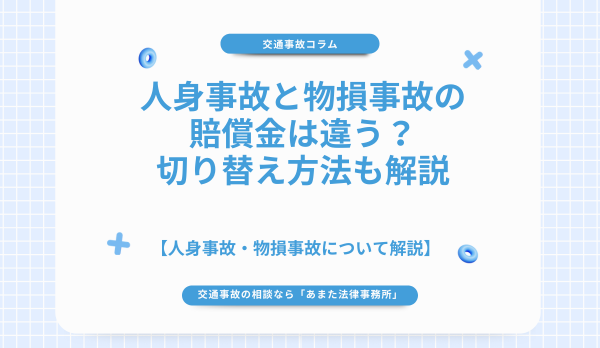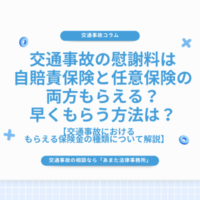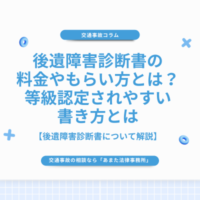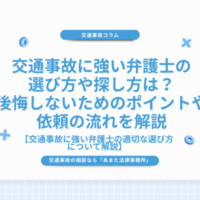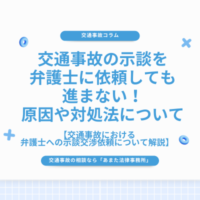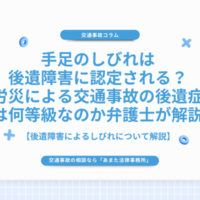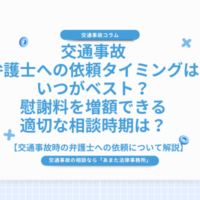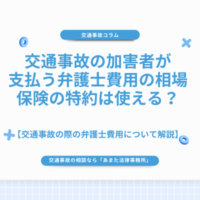交通事故には人身事故と物損事故の2種類がありますが、被害者が加害者に請求できる損害賠償金には大きな違いがあります。少しでもケガをした事故であれば、人身事故で処理するのが良いでしょう。

この記事の目次
人身事故・物損事故とはどんな事故?
交通事故には、大きく「人身事故」と「物損事故」と2つの種類があります。それぞれどのような事故をさすのかを解説します。
人身事故とは
交通事故のうち、人の生命や身体に被害を与える死傷事故を人身事故といいます。
運転手がケガをした場合だけでなく、車に同乗していた人がケガをした場合も人身事故になります。また車と人の両方に被害が出た場合も人身事故として扱われます。軽症、重症といったケガの具合は関係ありません。たとえ軽微であったとしても、ケガをしていれば人身事故になります。
物損事故とは
人の身体や生命に影響が出ず、車など物のみに被害が出る交通事故を物損事故と呼びます。警察では「物件事故」という表記を使うことがありますが、物損事故と同じ意味です。
例えば車同士がぶつかったものの、お互いドライバーや同乗者はケガをしなかった場合、駐車中の車にぶつかった状況などが物損事故になります。ちょっとだけ車にキズがついたなど、軽微であっても物損事故は変わりありません。
また、車でひいてしまったなどペットに被害があった事故も、物損事故として扱われます。ペットは生き物であっても法律上は人間ではない「物」として扱われるためです。
加害者が受ける処分や責任の違いについて
人身事故と物損事故の違いは、被害の内容だけではありません。加害者が受ける罰則や処分、被害者が請求できる賠償金の種類など、様々な部分に違いがあります。
それぞれの違いについて、押さえておきたいポイントを詳しく説明していきます。
人身事故と物損事故の処分・責任の違い
交通事故を起こすと、以下の3つの責任に問われる可能性があります。
・刑事責任……事故の内容が刑法等で定められた犯罪に該当する場合に、懲役など法的な罰則を受ける。
・民事責任……被害者や破損してしまった車に対する損害賠償の支払い。
・行政責任……点数制度による免許の停止や取り消しなどの処分。
人身事故と物損事故の刑事・民事・行政上の処分、責任の違いは以下のようになっていますので一覧を御覧ください。
| 人身事故 | 物損事故 | |
|---|---|---|
| 刑事責任 | 危険運転致死傷罪等の罪に問われる恐れがある。 | 刑事罰の対象にはならない。 |
| 民事責任 | ・「治療費」や事故で仕事を休んだことに対する「休業損害」、後遺障害に対する「後遺障害逸失利益」など様々なお金を請求できる。 ・慰謝料請求も可能。 | ・請求できるのは車の修理代や代車費用など一部のお金に限られる。 ・自賠責保険は適用されない。 ・慰謝料請求は認められないケースが多い。 |
| 行政責任 | 必ず免許点数が加算される。 | 基本的に点数は加算されない。 |
人身事故は物損事故と比べると加害者の責任や処罰の範囲が広く、重くなっています。
相手を死亡させてしまった人身事故では、「懲役刑7年以下もしくは禁錮刑または100万円以下の罰金」の刑事処分が科せられます。
物損事故は刑事事件にならない
物損事故は刑事事件にはなりません。
人身事故の場合、加害者は「自動車運転処罰法」に定められた「過失運転致死傷罪(5条)」や「危険運転致死傷罪(2条)」などの罪になり、懲役や罰金といった刑事罰に問われる可能性があります。しかし、物損事故では人身事故のような罰則はありません。
刑法には「器物損壊罪(261条)」と言われる罪があり、物損事故でも適用になると思うかもしれません。ですが、器物損壊罪の対象は、故意に他人の物を壊した場合に適用となります。交通事故は過失ですので当てはまらないため、裁く規定はないのです。

ただし、物損事故でも建物などに突っ込んだなど建造物を損壊した場合、当て逃げを起こした場合は、刑事処分や行政処分の対象になることがあります。
物損事故には自賠責保険が適用されない
自賠責保険は人身事故による損害を補償するもので、物損事故は対象になっていません。自賠責保険は車を運転する上で必ず加入しなければならない保険で、交通事故では加害者が任意保険に入っていなくても、自賠責保険によって最低限の補償を受けられるようになっています。
請求できる損害賠償が異なる
人身事故と物損事故では加害者に請求できる損害賠償の種類が異なります。
人身事故では、
- ケガの「治療費」やケガを負ったことへの精神的苦痛に対する「傷害慰謝料」
- 事故によって仕事を休んだ場合の補償である「休業損害」
- 後遺障害が残った場合の慰謝料である「後遺障害慰謝料」
- 後遺症によって受け取れなくなった将来的な利益の補償である「後遺障害逸失利益」
など、様々な賠償金を請求できます。
しかし、物損事故の場合は自動車修理等に関するもののみです。
- 修車両の理費
- 車両の価値が下がる評価損
- 代車の費用
- 休車損害
- 積荷などの損害
受け取れる賠償金は以上のようになり、人身事故の場合と比べると請求できる種類は限られています。
物損事故では慰謝料請求が認められない場合が多い
物損事故を起こしても、原則として加害者に慰謝料の支払いを求められません。慰謝料とは、損害賠償のうち、被害者の精神的・肉体的苦痛に対する補償として支払われるものです。人身に損害が出ていない物損事故では、精神や肉体への補償をする必要がないのです。
また、法律でペットは「物」として扱われるため、交通事故でケガをしたり死んでしまっても治療費や慰謝料を請求することはできません。しかし「物」が壊れ修理したと捉えれば、治療費を請求することは不可能ではありません。またペットは家族同然との考えは広く周知されていますので、裁判で慰謝料が支払われたケースもあります。
ただ相手側の保険会社が支払いを渋り交渉が難しくなると考えられますので、ペットが事故に遭い治療費や慰謝料を請求したいときは弁護士に相談してみてください。
物損事故だと免許点数が加算されない
物損事故では、原則として免許に点数は加算されません。人身事故は行政上の処分として違反点数が加点され、点数によっては運転免許の取り消しや停止といった処分を受けます。
運転免許は交通違反や事故を起こすたびに決められた点数が加点されていき、過去3年間の違反点数が一定になると処罰される点数制をとっています。
減点と言われることがありますが、実際には点数が加算されていくシステムです。違反点数が0だった場合、6点以上になると免許停止、15点以上で免許取り消しの処分を受けます。事故によっては、一発で免停、取り消しになることもあります。しかし、加点されるのは人身事故のみで、物損事故は行政処分を受ける可能性はありません。
免許上の「無事故」とは、人身事故を起こしていないことなのです。
物損事故として届け出るほうが加害者にはメリットが多い
交通事故の加害者にとって、人身事故よりも物損事故として届け出したほうがメリットが多いです。罰金はなく免許の点数に影響を及ぼしませんし、被害者に支払いする慰謝料などの賠償金の金額も低くなります。
逆に言うと被害者は、物損事故で処理されると損をする可能性が高いです。ケガをしても治療費や通院費を支払ってもらえず、慰謝料も請求できないのは大きなデメリットになってしまいます。交通事故の被害者になった場合は、人身事故として扱ってもらうのが良いでしょう。
人身事故が起きてからの流れ
人身事故は物損事故を比べると、人身事故のほうが処罰や責任が重くなっています。人身事故は人の身体や生命に関わる、重大な損害を与える事故だからです。
人身事故に遭遇した場合は、きちんと補償を受けられるよう、適切な損害賠償を請求し、警察等に対して加害者に対する処分を求めていく必要があります。実際にどのようにして加害者の責任を問うのか、事故が起きてから示談までの流れをみていきます。
1、事故発生
交通事故が起きたときは人身事故でも物損事故でも、まず警察に届け出をします。道路交通法72条にも定められている運転者の義務ですから、勝手に通報せずに済ますことはできません。
また、警察が来る前に相手側の連絡先を聞いておきましょう。警察が到着する前に、相手側がいなくなってしまう可能性があるためです。連絡先がわからないと相手の保険会社もわからないので、保険金を請求できなくなってしまいます。相手の免許証を確認させてもらい名前や住所などの情報をメモしてください。スマートフォンで免許証を撮影させてもらっても良いでしょう。
通報義務を怠ると、3年以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法119条1項10号)。特に人身事故の場合は警察に通報しておかないと「自動車安全運転センター」から「交通事故証明書」が発行されず、人身事故として処理されなくなってしまいます。
免許取り消しや免停になると不都合が出るため、加害者側から「人身事故ではなく物損事故として処理して欲しい」と依頼されることがあります。しかし、「ケガが大したことないからいいか」とはなりません。
物損事故で処理をして、治療費や慰謝料は自分で支払うという提案をする加害者がいます。しかし本当にお金を支払ってくれる保証はありません。保険会社を通さないと受け取れない可能性が出てきますので、応じないようにしてください。
2、ケガの治療を行う
ケガをした場合は事故当日に必ず病院へ行き、医師の診断を受けましょう。医師に交通事故によるケガであることをきちんと伝えます。
打ち身や捻挫など軽傷のケガだと、病院に行かずに済ませる人がいます。しかし事故の直後はなんともないと思っても、交通事故のケガは後から痛みが出てくることがあります。事故から時間が経過して病院に行くと事故とケガとの因果関係を証明するのが難しくなりますし、後遺障害の認定でも不利になる可能性があります。

3、完治または病状固定
ケガの治療は医師から完治または病状固定の診断を受けるまで続けます。病状固定とは、これ以上治療を続けても症状が良くならない状態を指します。症状によりますが、目安はむちうちで6か月、骨折で1年程度です。
人身事故の損害賠償請求は、治療費や後遺症に関する慰謝料なども含んでいるため、治療が完全に終わり、後遺症の度合いが明らかになってからでないと正確な損害が計算できません。
そのため、示談交渉はケガの治療が済んでからはじめられるのが一般的です。ただ、治療費に関しては、病院に通っている間から必要になるため、治療が終わる前でも相手方の保険会社から支払いを受けられる場合が多くなっています。
4、後遺障害等級の申請
事故によって、なんらかの後遺症が残ってしまったら、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。交通事故の後遺症に関する損害賠償請求には、後遺障害等級と言われる後遺症の重さによる等級の認定を受ける必要があり、等級によって受け取る金額が決まります。
後遺障害の認定を受けるには、医師が作成した「後遺障害診断書」という書類を、「損害保険料率算出機構」に提出して申請します。1~2か月の調査期間を経て後遺症が認められると、1級から14級までの後遺障害等級が認定されます。
交通事故では、後遺症が残る事例は多いです。比較的軽いと言われるむちうちでも、首や肩の痛み、頭痛やめまいといった症状が残ることがあります。頭部に強い衝撃を受けることで起こる高次脳機能障害など、重度の後遺症が残ることも珍しくありません。人身事故では後遺障害の慰謝料を受け取れる可能性が高いと言えるでしょう。
5、示談交渉
ケガの治療と後遺障害等級の認定が終わると、示談交渉がスタートします。
どの時期に示談交渉をはじめなければいけないという決まりはありませんが、ケガの治療などが終わり、正確な損害が計算できるようになってから行うのが普通です。
あまり早くはじめてしまうと正確な損害額が分かっておらず、不当に低い金額で示談させられてしまう恐れがあるので避けましょう。治療終了後または後遺障害認定の取得後にするのがおすすめです。ただし、交通事故の<strong>示談には時効があります。人身事故は起算日から5年、物損事故は3年となっていますので、長期間何もしていないと賠償金を受け取れなくなる可能性が出てくるので注意してください。
人身事故で請求できる示談金
人身事故はケガの治療や後遺症によって、被害者の生活や将来にも影響を与える可能性が高く、物損事故と比べて加害者の責任が重くなっています。人身事故では実際にどのような賠償金を請求できるのか、示談金の内訳について解説します。
示談金とは
交通事故の示談交渉では、全ての損害をお金に換算し、被害者と加害者の話し合いで両者の合意により示談金を決定し示談を結びます。示談で決められた損害賠償金と慰謝料をあわせたお金を示談金と呼び、これが事故の被害者に支払われるお金の総額になります。
示談金にはどのような項目が含まれているのか、損害賠償と慰謝料に分けてみていきましょう。
損害賠償金
示談金のうち、事故によって必要のない出費が生まれた、仕事を休まざるを得なくなり本当ならもらえたはずの利益が手に入らなくなったなど、財産的な損害に対する補償が損害賠償金です。主な損害賠償金には以下のものがあります。
・治療費……交通事故によるケガの治療にかかる費用。診療費や薬代、入院費、リハビリ費用などが含まれ、医師に完治または病状固定と診断されるまで請求できます。
・休業損害……事故によって会社を休まなければならなくなり、減少してしまった給与への補償。給与所得者だけでなく、自営業でも対象になります。また学生や専業主婦(主夫)でも請求できる場合があります。
・葬儀費用……被害者が死亡してしまった場合、葬儀および四十九日法要にかかった費用を請求できます。
・後遺障害逸失利益……事故で後遺症が残ってしまったために働けなくなった、仕事を変わらないといけなくなったなどの理由で、将来得られたはずの収入が手に入らなくなった分への補償として「後遺障害逸失利益」を請求できます。
・死亡逸失利益……被害者が死亡したため、将来の収入などが手に入らなくなったことへの補償。
・入院に関する諸費用……通院のための「交通費」や、誰かに病院まで付添をしてもらったときの「付添看護費」、入院中に必要となった着替えや日用品などの費用である「入院雑費」など。
・弁護士費用……示談金の支払いに関して裁判を行い、勝訴した場合に裁判所からの命令で弁護士費用の10%程度を請求できます。
・損害遅延金……金銭債務の支払いが遅れた場合に発生するお金で、弁護士費用と同じく裁判に勝訴した場合に請求できます。
慰謝料
精神的な損害に対する補償は慰謝料として支払われます。本来、精神的な苦痛は個人差がありますし金額に換えられるものではありませんが、法律上はすべて金銭で支払うこととされています。
・傷害慰謝料(入通院慰謝料)……交通事故でケガを負い、医療機関に入通院しなければならなくなった精神的苦痛への補償。治療期間をもとに計算され、入通院日数が長いほど高額になります。事故に遭った日に1日だけ通院した場合も請求可能です。
・後遺障害慰謝料……事故で後遺症が残ってしまったことへの精神的苦痛を補償する慰謝料。後遺障害等級によって金額が異なります。
・死亡慰謝料……被害者が死亡したことへの精神的苦痛を補償する慰謝料。被害者本人に対するものと遺族に対するもの2種類を合わせて計算されます。
人身事故の示談交渉について
人身事故での示談交渉の流れを詳しくみていきます。また、話し合いが平行線のまま示談が進まないときの対処法も紹介します。
人身事故の示談交渉の流れ
人身事故における慰謝料などの損害賠償金の金額を決定するのが示談交渉です。減額されるか増額されるかは交渉次第になりますので、非常に重要なものといえるでしょう。
1、相手方の保険会社から示談案が出される。
交通事故の損害賠償に関する交渉は加害者と直接の交渉ではなく、相手方が加入している任意保険会社と行います。通常は、交渉がはじまるタイミングになると、保険会社から示談金や過失割合などが記載された示談案が送られてきます。
2、提示された示談内容をもとに交渉を行う
保険会社が提示してきた示談案をみて、妥当な内容かを確認・検討します。示談金の増額などの要望があれば交渉を開始します。
保険会社はなるべく支払う保険金を少なくしたいと考えるのが普通です。提示された内容のままで示談してしまうと、相場よりも低い金額しか受け取れない危険性があります。

3、納得のいく示談内容になった場合は合意する
両者が納得し合意がとれれば示談成立となります。「示談書」や「免責証書(示談書の一種で人身事故の示談で作成される場合が多い)」といった書類を取り交わします。
4、示談金の支払い
示談成立から示談金の支払いまでは2週間ほどかかります。保険会社から送られてくる「示談書」に署名・捺印をして送り返すと、指定の口座に保険会社から賠償金が振り込まれます。
話し合いで示談に至らなかった場合は?
損害賠償の金額や過失割合などで揉めてしまうことは珍しくありません。過失割合などに食い違いがあり話し合いで示談が成立しなかったときは、民事裁判で決着を目指すことになります。裁判所へ提訴を行いますが、裁判は長ければ1年以上の時間を要する可能性があります。
裁判は大ごとすぎると考えるときは、裁判所が話し合いを仲介する「調停」を検討してみてください。
示談の内容が適正なのか、自身だけで判断するのは難しい面があります。悩むよりも法律に詳しい弁護士の力を借りるのが早いでしょう。
物損事故は人身事故へ切り替えられる
物損事故として成立させたものを、後から人身事故に切り替える方法はあります。
交通事故の被害にあったとき、軽いケガだからと物損事故で処理してしまうと、加害者の責任が軽くなるうえ、示談の際に損害賠償を減額されるなど金額の面で不利になります。軽症でもケガをしているなら、人身事故として処理できるようにするのがおすすめです。
物損事故から人身事故への切り替えは可能
もし物損事故として処理した交通事故でも、ケガをしているのなら、人身事故への切り替えは可能です。

物損事故を人身事故に切り替える方法
物損事故を人身事故に切り替えるときは、警察に連絡し必要書類を提出し行います。
1、病院を受診して診断書をもらう
医療機関で事故によるケガであることを説明し、医師から診断書を作成してもらいます。診断書を発行できるのは医師だけです。整骨院や接骨院ではなく、医師のいる病院を受診しましょう。
事故が発生した日、初めて受診した日、治療期間などを記載してもらい、ケガと事故の因果関係がわかるようにしておくのがポイントです。
2、警察に診断書などの必要書類を提出
事故のあった地域を管轄している警察署に行き、診断書などの必要な書類を提出します。自身が住んでいる地域の警察署ではない点に注意してください。あらかじめ連絡しておくと、スムーズに対応してもらえます。
診断書のほかには、運転免許証、車検証、自賠責保険の証明書、印鑑、事故を起こした車両(写真や映像でも可)などを用意してください。
物損事故から人身事故への切り替えはいつまでという期限はなく、必要に応じて申請してかまいません。しかし、事故から時間が経ち過ぎていると、ケガと事故の因果関係がはっきりしない、現場の状況が確認できないといった理由で断られるケースもあるので、なるべく早くに警察に提出するようにしてください。できれば事故に遭った日から1週間~10日後くらいまでが望ましいです。
本来、警察署へは事故の当事者全員が出向かなければなりません。被害者だけでなく加害者や、事故でケガをした人などの協力も必要になるのです。しかし加害者が協力してくれなければ、被害者ひとりで手続きを始めてください。

3、人身事故への切り替え
提出した必要書類が認められると、人身事故に切り替えられます。警察により被害者・加害者への事情聴取や実況見分といった捜査がはじまります。
人身事故へ変更となったら、警察から「事故証明書」をもらいコピーを相手側の保険会社へ連絡しましょう。物損事故では車両の修理代などしか補償されませんが、人身事故としての扱いになれば治療費や慰謝料といった損害賠償金の請求ができるようになります。
切り替え手続きが不安なら弁護士に相談を
決められた手続きを行えば、物損事故から人身事故への切り替えは可能です。
切り替えは自分自身でもできます。しかし提出した書類などに不備があると、警察に拒否されてしまう可能性はあります。自分だけでは不安というならば、弁護士に依頼するようにしてください。
また相手側の保険会社が人身事故と認めてくれないトラブルが生じると、裁判で人身事故として認定してもらわなければなりません。訴訟を起こすためにはたくさんの書類を用意するなど、手間や時間がかかりますので、個人で対応するのは大変です。
困ったときは、弁護士に対応してもらうのが良いでしょう。勝ち目が少ないため、保険会社は法律に強い弁護士と争うことは避けたいのが本音です。弁護士が登場した時点で人身事故としての対応に切り替えてくれる事例は少なくありません。
無料相談サービスがある弁護士事務所であれば、費用をかけずに相談することが可能です。

軽傷でもケガの可能性があるなら人身事故で処理すべき
交通事故では人身事故のほうが、物損事故よりも加害者の処分や責任が重くなります。慰謝料を含む損害賠償金も増額されますので、ケガとは言えないような軽傷の事故でも、人身事故で処理すべきといえます。
もし一旦、物損事故として処理してしまっていても、その後に人身事故へ切り替えることができます。ただ知識がない個人が手続きをすると、不備が起きやすく完璧に行うのは困難でしょう。時間も手間もかかりますので、早期の解決を目指すなら交通事故に強い弁護士に相談するのがおすすめです。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ