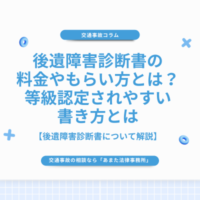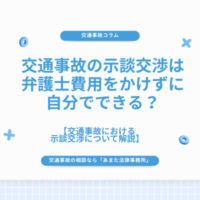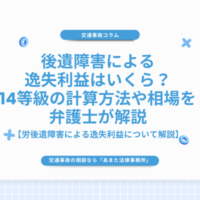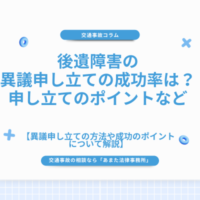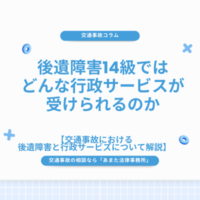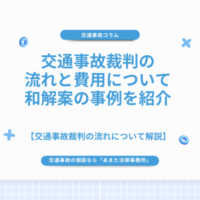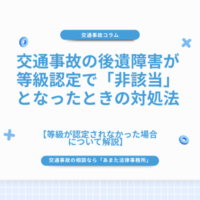交通事故の被害者が弁護士に相談するさい、ベストとなるタイミングはあります。
弁護士に依頼すると被害者の希望に沿った結果になるよう示談交渉をしてくれ、慰謝料を含む損害賠償額を増額できる可能性があります。
しかし、相談するタイミングがずれてしまうと、弁護士に対応してもらえなかったり、弁護士の費用倒れになり損をすることがあるため注意が必要です。

執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
交通事故の被害者が弁護士に相談するメリット
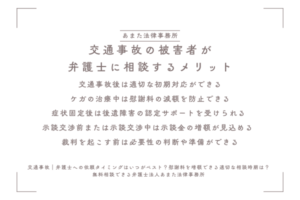
交通事故の被害者は、加害者に対して被った損害の賠償を請求できます。しかし、一人で対応すると、期待するような示談金を獲得できない可能性がでてきます。
損害賠償請求するためには、示談交渉という話し合いに参加する必要があり、加害者が加入している保険会社と何回もやり取りしなければなりません。相手方の保険会社は、個人相手では低い示談金を提示しなんとか安く済ませようとしてくることが多いです。わざと難しい文言を並べるなど、法律の知識がないと反論できないような雰囲気を作ることもあります。
弁護士に相談すると、被害者にとって示談交渉を有利に進められます。保険会社は交渉のプロであるといっても、弁護士を言葉巧みに丸め込むのはまずできません。弁護士に訴訟を起こされても敗訴する可能性が高いという理由から、弁護士の主張には応じてくれる傾向があります。
よって、被害に遭った本人だけで示談交渉をするよりも、弁護士を介したほうが慰謝料を含む賠償金を増額できるといったメリットが生じるのです。
交通事故後は適切な初期対応ができる
事故直後のタイミングで弁護士に相談すると、適切な初期対応が可能になります。
事故直後はケガの治療に専念する事が最優先です。しかし、同時に警察や保険会社などに連絡しなければならず、被害者の負担は非常に大きくなります。
そこで、事故後すぐのタイミングで弁護士に依頼すれば、事故の初期対応についてアドバイスがもらえたり、保険会社との対応を代わりにおこなってくれたりします。

ケガの治療中は慰謝料の減額を防止できる
ケガを治療しているタイミングで弁護士に相談すると、慰謝料の減額につながらない通院方法がわかります。
ケガの治療のため病院に通えば、入通院慰謝料を請求できます。入通院慰謝料は通院日数の長さによって請求できる金額が変動するのですが、誤った通院方法は請求できる慰謝料が減らされてしまう事態につながります。
例えば、通院頻度が著しく少なかったり、医師の指示がないのに整骨院(接骨院)に通ったりするのは、慰謝料の減額に繋がります。治療方針について弁護士に相談すれば、適切な金額の慰謝料を受け取るための方法を指南してくれます。
症状固定後は後遺障害の認定サポートを受けられる
後遺障害への申請前のタイミングで弁護士に依頼すれば、後遺障害として認定されるために必要なサポートを受けられます。
交通事故で負ったケガは、治療をおこなっても完治せずに後遺障害として残るケースがあります。これ以上治療しても症状の改善が望めないと医師に判断されることを「症状固定」といい、損害賠償上ではこのタイミングで治療終了となります。
症状固定後に残っている後遺障害については、加害者に対して後遺障害慰謝料を請求できます。また、後遺障害によって労働能力が低下すると、将来に得られたはずの収入が減少しまう事態を補償する逸失利益も加害者に請求できます。
ただし、後遺障害慰謝料や逸失利益を獲得するには、後遺障害等級の認定を受けなければなりません。等級が認められるためには厳正な審査に通る必要があり、場合によっては適切な等級に認定されなかったり、等級認定の申請そのものが通らなかったりするリスクがあります。
示談交渉前または示談交渉中は示談金の増額が見込める
示談交渉の前や最中のタイミングで弁護士に依頼すると、示談金の増額が見込めます。
弁護士「弁護士基準」という計算方法での慰謝料算出が可能になるためです。
被害者は基本的に加害者側の保険会社と交渉をおこないますが、保険会社は弁護士が見積もる示談金よりも低額の示談金を提示してくるのが普通です。
保険会社は「任意保険基準」という計算方法で慰謝料を算定します。任意保険基準は、保険会社が自社の支出を極力抑えるように設定された計算方法となり、弁護士基準よりも金額は低くなります。
弁護士基準は実際に裁判実務でも用いられる計算方法であり、被害者側の精神的苦痛をきちんと補填できる金額に設定されています。法的に適正な金額であるともいえ、任意保険基準と比較すると2倍以上の賠償額になる事例も少なくありません。

裁判を起こす前は必要性の判断や準備ができる
裁判を起こす前のタイミングで弁護士に相談すれば、裁判の必要性や裁判で勝てる見込みについてアドバイスしてくれます。
訴訟提起するのであれば裁判に必要な手続きを代理してくれる上に、被害者側の主張を裏付ける証拠の収集・提出もおこなってくれるため、裁判を有利にすすめられるでしょう。
交通事故の示談は当事者双方の合意によって成立します。どちらかが納得しなければ示談は成立しないのですが、主張が食い違い合意に至らなければ、最終手段として民事裁判所で決着をつけるしかありません。
裁判では弁護士基準で慰謝料の金額を計算しますので、勝訴すれば高額の慰謝料を受け取れます。ですが、証拠などが集まっていない状態で訴訟を起こすと敗訴する可能性が高くなってしまいます。訴訟費用分の損失を負担するおそれもあり、裁判を考えているなら弁護士への依頼は必須です。
被害者が弁護士に相談する適切なタイミングはいつ?
被害者が弁護士に相談する適切なタイミングは、基本的に怪我の治療を終えて損害が確定した時点です。
相談自体は初診を受けた後から示談成立まで、いつ行ってもかまいません。もちろん相談タイミングが早いに越したことはないのですが、怪我の状態がわからない段階で相談しても弁護士が十分に示談金の見積もりをできず、今後の計画を立てにくくなるおそれがあります。
弁護士側は損害が確定した後のほうが示談金を見積もりやすい事情があります。治療が終了してからの相談なら、今後の流れや対策をアドバイスしやすくなります。反対に見積もりが出せない段階で弁護士に依頼すると、怪我の程度が思ったよりも軽いようなケースでは十分な示談金を受け取れなくなってしまいます。
ただ、治療中に相手方の保険会社から治療費の打ち切りを宣告されたり、示談を提案されたりする場合があります。実際にこういった対応をされたら、随時弁護士に連絡して指示を仰いでください。
すぐに弁護士に依頼したほうがいいケース
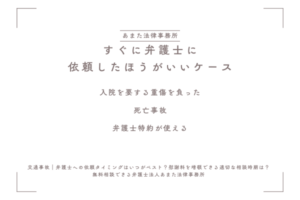
交通事故の中には、治療の完了を待つよりもすぐに相談した方が良いケースがあります。状況により、弁護士へ依頼するタイミングを考える必要があります。
入院を要する重傷を負った
入院が必要なほどの重傷を負ったときは、事故直後に弁護士に相談するのがおすすめです。
基本的には全治1ヶ月以上の怪我は重症に分類されます。そして、治療期間が1ヶ月以上に及ぶほどの怪我は、受け取れる示談金も高額になります。
よって、重症の事故では弁護士への依頼料より示談金の方が高くなることがほとんどであり、弁護士の費用倒れになるデメリットはありません。収支がプラスになるのであれば、損害が確定する前に弁護士に依頼しても問題なく早期相談によって今後の対策を立てやすくなります。

死亡事故
被害者が亡くなってしまった死亡事故は、事故の発生直後のタイミングで弁護士に相談するのがおすすめです。
死亡事故は入通院や後遺症にかかる損害が発生せず、事故発生直後に損害賠償金額が確定します。
また、死亡事故では損害賠償金が高額になるため、ほとんどのケースで弁護士の依頼にかかった費用以上の示談金を受け取れます。
近親者が交通事故で亡くなるというのは、遺族の方にとって大変辛い経験です。その上、葬儀をどうするか、相手保険会社との協議をどうするかなどの決断を迫られるため、精神的に大きな負担がかかる日々が続くことになります。
ストレスが溜まっている状態で、さまざまな手続きを慎重に進めるのは困難でしょう。そこで、弁護士から今後の見通しや注意点などをアドバイスしてもらうのがおすすめなのです。

弁護士特約が使える
被害者の方が加入している自動車保険に「弁護士特約」がついていれば、事故直後のタイミングで弁護士に相談して構いません。
弁護士特約はご自身が加入している保険会社が、弁護士への委任料や相談料を代わりに支払ってくれる特約です。被保険者1名あたり300万円を限度として、任意保険会社が弁護士の費用を支払いしてくれます。法律相談の料金についても10万円まで保険会社が負担してもらえます。
補償対象は契約内容により異なりますが、被保険者とそのご家族、または契約している車両に搭乗していた方などです。交通事故の被害に遭ったタイミングで、弁護士特約サービスが付帯する保険に加入していないかを確認してください。
弁護士への相談が手遅れとなるタイミング
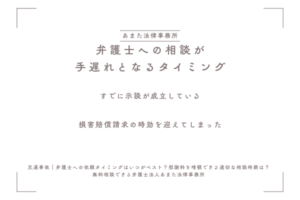
弁護士に相談しても手遅れになるケースはあります。
弁護士に相談するタイミングは治療終了後がベストですが、相談時期が多少前後しても基本的には問題ありません。しかし一定のタイミングを過ぎると、いくら弁護士でも対応できなくなる事例はあると頭に入れておきましょう。
すでに示談が成立している
保険会社との示談書に合意のサインをした後は、原則として内容を変更・撤回することはできません。弁護士に相談しても無理です。
一般的に加害者側が提示する示談書には、「清算条項」が記載されています。清算条項とは、「示談書に記載されている損害賠償金以外は請求できない」ということを相互に確認する示談上の条件です。
もし、示談が成立したにもかかわらず、被害者の方が「新たな損害があったので追加請求したい」「示談内容が誤っていたので撤回したい」と言い出すと、せっかく解決できた問題についてもう一度話し合わなければなりません。そこで、示談書に清算条項をつけることで、一度解決したトラブルや紛争を蒸し返せないようにするのです。
もっとも予測し得ないことが起きれば、例外的に示談の内容を変更・撤回できる場合もあります。例えば、示談成立後に後遺障害が発症したときや、相手方の詐欺・脅迫で示談の成立にいたった際には、示談の撤回または再交渉の余地があります。

損害賠償請求の時効を迎えてしまった
交通事故の損害賠償請求権は無期限ではなく、一定期間をすぎると時効を迎えてしまいます。
被害者は加害者に対して損害賠償請求権がありますが、民法で時効制度が定められています。権利があるのに行使しようとしない者を法律上で保護する必要はないと考えられているからです。
交通事故の加害者は時効成立を迎え時効制度を使う旨を被害者に伝えると、時効の効果を主張できます。時効の効果とは被害者が有する損害賠償請求権の消滅を意味しており、一旦時効が完成してしまうと被害者は加害者に損害賠償請求できなくなるのです。
物損事故と人身事故の時効
交通事故における損害賠償請求権の時効成立時期は、物損事故と人身事故それぞれに分けて設定されています。
物損事故の時効は、被害者が交通事故の加害者及び損害を知った日の翌日から3年です。
人身事故の時効は、被害者が交通事故の加害者及び損害を知った日の翌日から5年になります。なお、交通事故の加害者及び損害が不明なままであっても、事故発生日の翌日から20年経てば時効が成立します。
一旦時効が成立したタイミングでは、弁護士の力をもってしても加害者に損害賠償請求することは不可能です。交通事故にあったらできるだけ早くに弁護士などに相談して対処しなければなりません。また、時効成立の間近であれば、弁護士は裁判上の請求などをおこない時効成立阻止してくれます。時効成立までの時間が差し迫っているタイミングときは、急いで弁護士に相談してみましょう。
示談成立後も相談できる例外的なケース
例外的に示談内容の撤回や再交渉ができるケースもあります。
示談成立後に予期せぬ損害が発覚した場合や、詐欺・脅迫によって示談を成立させられた場合、示談の前提、重要な事実について誤解したまま示談が成立してしまった場合などは、撤回や再交渉ができる可能性があります。示談成立後であっても弁護士に相談しアドバイスを受けるとよいでしょう。
弁護士に相談するさいの注意点

弁護士に相談するさいの注意点をしっかり押さえておくことは、納得できる慰謝料を含む賠償金を獲得することにつながります。
タイミングに迷ったらできるだけ早くに相談する
弁護士に相談するタイミングに迷うときは、なるべく早めの行動をおすすめします。
早期に相談すると今の状況から今後の見通しも立てやすいですし、委任契約を結んだ後に幅広いサポートを受けられます。
相談が遅れると対応できなく、取り返しがつかなくなることがあるので気を付けてください。

早いタイミングで相談したからといって弁護士費用が高くなることはなく、経済的にお得です。
現時点でやるべきことや注意するべきことを教えてもらえますので、自力での解決に不安や心配があれば、弁護士にコンタクトを取ってみましょう。無料相談を使えば、気軽に利用できます。
弁護士費用の料金体系には、依頼した時に着手金が発生し、依頼が解決した時に成功報酬が発生する着手金・成功報酬方式と、依頼の処理に要した時間に応じて、費用を計算するタイムチャージ方式の2種類があります。
着手金・成功報酬方式であれば、早いタイミングで依頼したからといって弁護士費用は高くなりません。
信頼できる弁護士の選び方
信頼できる弁護士を選択することは重要です。
先ず、交通事故について見識が深く、経験豊富な弁護士に相談しましょう。相談時に交通事故分野にどのくらい力を入れているかを確認してください。HPで記載されている実績などの情報を参照するのも有効です。
実は全ての弁護士が交通事故の案件に精通しているわけではなく、それぞれに得意・不得意分野があります。
交通事故の分野では損害賠償金や過失割合を算定する際に専門的な知識が必要です。また、怪我が完治せずに後遺障害が残ったケースでは、医学的な詳しい知識もなければ適切な等級認定を受けられません。
交通事故の事案に強く、解決件数が豊富な弁護士を選ぶのがおすすめです。
不利な事実もきちんと話す
弁護士に相談する際には、自身にとって不利な事実も正しく伝えましょう。
こちら側にも過失があるなど被害者に都合の悪い情報もきちんと伝えていないと、示談交渉の際に返って不利な結果となってしまう場合があります。話しにくいと感じる事情があるかもしれませんが、事実を正直に説明することは大切です。

交通事故時の弁護士への相談タイミングについてまとめ
交通事故で弁護士に相談するタベストなタイミングは、基本的に怪我の治療が終了した段階です。しかし被害者が重症を負った事故や死亡事故など、早めに弁護士の力を借りたほうが良いケースもあります。
弁護士に相談するタイミングが遅すぎると、対応が難しく取り返しがつかなくなるケースも存在します。疑問や悩みが生じたら、弁護士への相談を検討してください。
電話やメールなど都合の良い方法で、いつでも相談できます。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ