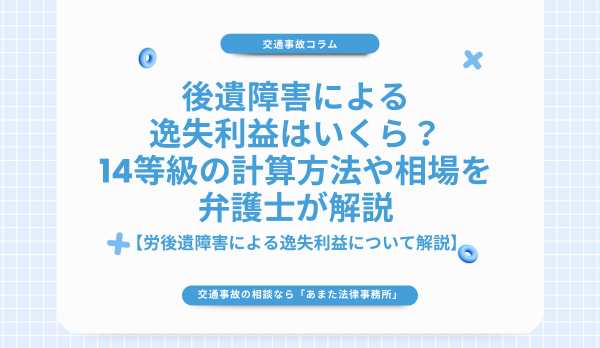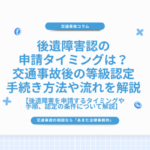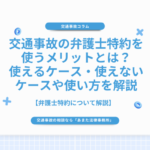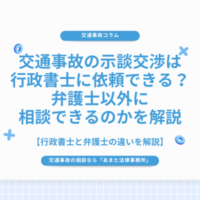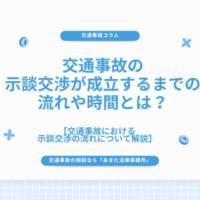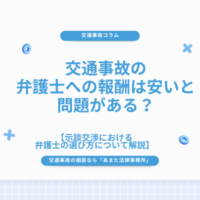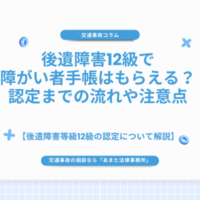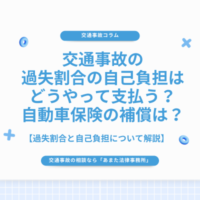逸失利益は後遺障害により減った収入の補償です。
逸失利益は後遺障害14級でも請求できますが、受け取れる金額は計算方法によって大きく異なる点に注意が必要です。


2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 ▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
この記事の目次
逸失利益とは何か
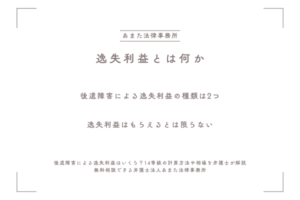
逸失利益は交通事故に遭わなければ将来的に得られるはずだった利益を意味します。交通事故で怪我が回復せず後遺障害が残ったり被害者が亡くなったりすると、以前のように働けなくなり収入を得られなくなります。入らなくなってしまったお金の補償を、相手方に求める権利があるのです。
後遺障害による逸失利益の種類は2つ
後遺障害による逸失利益は「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類があります。
後遺障害逸失利益
交通事故で後遺障害が残ったことで、被害者が将来稼げなくなったことによる減収に対する賠償金です。
交通事故が原因で発生した労働能力の低下をもたらす機能障害・神経症状である後遺障害が残ったとき、加害者側の自賠責保険に後遺障害の等級認定を申請し認められると逸失利益を請求できるようになります。
死亡逸失利益
交通事故の被害者が亡くなったことで被害者本人がこの先に得られるはずだった所得を全て失ったことに対する賠償金が死亡逸失利益です。ただし、交通事故の被害に遭った本人は既に亡くなっているため、被害者の相続人となる父や母、妻、子供などの家族が死亡逸失利益の損害賠償請求権を相続することになります。
逸失利益はもらえるとは限らない
逸失利益は後遺障害が残ったからといって、必ずしも受け取れるとは限らないという注意点があります。逸失利益の請求を認めてもらうには、後遺障害により実際に減収が発生している必要があります。
ただし、現在まで減収はしていなくても、逸失利益の請求対象になるようなケースもあります。
- 将来の昇進や昇給に影響を及ぼす可能性がある
- 勤務先の協力により減収されていない
- 本人の努力でカバーしている
上記のような状況では、逸失利益の対象になる可能性があります。しかし実際に減収されてないため、相手側が認めず争いになりやすい面があります。揉めそうなときは、弁護士に相談し解決するのが早いでしょう。
逸失利益と休業損害との違い
「休業損害」は交通事故によるケガを治療するまでの期間中に、仕事を休んだことで減少した収入分を補償するお金です。どちらも消極的損害(交通事故が起こったことで得られなくなった利益)という意味では、逸失利益と休業損害は似ています。
ただ、休業損害は事故によって既に失った「過去の収入」になります。逸失利益は後遺障害により失うことが予想される「将来の収入」という違いがあります。
逸失利益と慰謝料との違い
「慰謝料」は精神的苦痛を与えられたときに、相手に慰謝させることを目的とした賠償金です。
交通事故で身体に後遺障害が残ると、以前のような生活はできなくなります。そのために被害者に生じた大きな不安やストレスという精神的苦痛を、加害者に金銭で償ってもらうためのものが慰謝料です。
対して、逸失利益は「将来の収入がなくなった」という実損に対する賠償金です。財産的損害を受けたことで請求できるものなので、精神的損害に対して支払われる慰謝料とは全く性質は違います。
後遺障害逸失利益の計算方法を詳しく解説
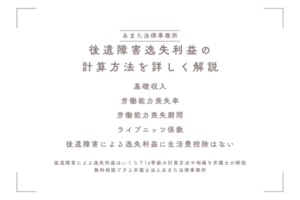
後遺障害逸失利益の計算式は以下のようになります。
それぞれの用語をわかりやすく解説します。
基礎収入
基礎収入は逸失利益算定の基礎となる収入です。被害者が給与所得があるサラリーマンや事業所得がある自営業者などのときは、原則として事故前年の年収が基礎収入になります。
なお、家事従事者(主婦・主夫)や学生などは会社員や自営業者と異なり、働いておらず収入を得ていません。被害者が無職であるときは、賃金センサス(厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」に記載された労働者の平均賃金)をもとに基礎収入を算出します。
労働能力喪失率
労働能力喪失率は交通事故で失った労働能力の割合を意味します。
死亡事故では労働能力喪失率が100%になりますが、後遺障害による逸失利益は「労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日基発第551号)別表1」の労働能力喪失表を参考に算出します。
後遺障害等級 労働能力喪失率 1級 100/100 2級 100/100 3級 100/100 4級 92/100 5級 79/100 6級 67/100 7級 56/100 8級 45/100 9級 35/100 10級 27/100 11級 20/100 12級 14/100 13級 9/100 14級 5/100
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は労働能力を失ったことで減収の影響を受ける期間を意味します。原則的に「症状固定日から67歳までの年数」が労働能力喪失期間になります。
しかし、軽度の後遺障害では年数が経つにつれて症状が軽くなりやすいため、14級では5年、12級では10年程度になるのが一般的です。交通事故の後遺障害で多いむちうちはほぼ14級~12級にあてはまりますので、労働能力喪失期間は5年または10年程度と思って良いでしょう。
また、例外として被害者が未就労者や高齢者は、それぞれに期間が設定されています。
| 被害者の属性 | 労働能力喪失期間 |
|---|---|
| 18歳未満 | 18歳〜67歳の年数 |
| 大学生 | 大学卒業時〜67歳の年数 |
| 67歳までの期間が短い者 | 「67歳までの年数」と「平均余命の2分の1」のうち長い方 |
| 67歳を超える高齢者 | 平均余命の2分の1 |
ライプニッツ係数
ライプニッツ係数は「中間利息控除」の考えに基づいて損害額を算出するための指数です。わかりやすく言うと、もらいすぎる分の利息をあらかじめ損害額から差し引く処理になります。
逸失利益は将来発生する損害を前払いで補償してもらうものです。そのまま受け取ると利息のもらいすぎが発生してしまいます。そこで、最初から過剰な利息部分を差し引く調整を行っておきます。
ライプニッツ係数は法定利率の影響を受けます。2020年の民法改正では法定利率と市中の金利水準の乖離を是正するために、法定利率が5%から3%に引き下げられました。これに伴ってライプニッツ係数の数値が変動しています。

後遺障害による逸失利益に生活費控除はない
死亡逸失利益には生活費控除率が設定されていますが、後遺障害による逸失利益に生活費控除はありません。
死亡事故による逸失利益を算定する際には、被害者が生きていれば支出していたと考えられる生活費を収入から差し引く処理を行います。
被害者が亡くなると得られるはずの将来の収入は全て失われます。しかし、生存していれば発生していたはずの必要経費(生活費)はかからないことになります。そのため、遺族の方が被害者の将来の収入をそのまま受け取ると、被害者が生存していたときと比べて取得する金額が多くなってしまうわけです。
後遺障害逸失利益の具体的な計算例を紹介
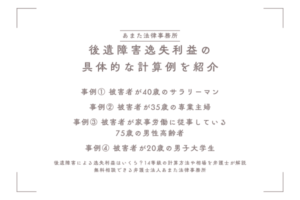
後遺障害逸失利益は収入を得ているサラリーマンや自営業者だけでなく、収入がない専業主婦(主夫)や学生なども基本的に請求できます。
交通事故の後遺症の中でも多く見られるむちうち症で14級9号・労働能力喪失率5%(ライプニッツ係数4.580)で計算した具体例を紹介します。なお、事故は全て2020年4月1日以降に発生したものとします。
事例① 被害者が40歳のサラリーマン
40歳のサラリーマンの事例です。前年度は年収(基礎収入)800万円の給与所得があったとします。
このケースでの計算式は以下のとおりです。
8,000,000円×5%×4.580=1,832,000円
事例② 被害者が35歳の専業主婦
35歳の専業主婦の事例です。
令和3年賃金センサスの女性・学歴計・全年齢の平均賃金を見ると「きまって支給する現金給与額」は270,200円、「年間賞与その他特別給与額」は617,000円になっています。したがって、本事例における被害者の基礎収入は、270,200円×12 + 617,000円=3,859,400円になります。
上記の結果、逸失利益の計算式は3,859,400円×5%×4.580=8,838,026円になります。
事例③ 被害者が家事労働に従事している75歳の男性高齢者
75歳になる高齢者の事例です。
こちらの事例では、高齢者でも家事労働に従事していた事実が考慮されます。専業主婦(主夫)と同じとみなされ、女性労働者の全年齢平均賃金を基準に基礎収入を用いて計算します(家事従事者は男性でも女性労働者の全年齢平均賃金を参照します)。女性労働者の全年齢平均賃金である3,859,400円が基礎収入になります。
3,859,400円×5%×4.580=8,838,026円
ただ、67歳を超える高齢者の労働能力喪失期間は原則として厚生労働省が公表している簡易生命表の平均余命の2分の1になりますので、専業主婦(主夫)と同じ金額にならないケースは出てきます。
事例④ 被害者が20歳の男子大学生
収入がない学生でも逸失利益を請求できます。将来的に、就職し収入を得ると想像できるためです。
大卒男子の平均給与額を基礎収入として、金額を計算していきます。ただ大学を卒業した22歳から働くと想定し、労働能力喪失期間のライプニッツ係数は5年4.580-―2年1.913となり、2.667になります。
6,379,300円(令和2年の大卒男性の平均給与額)×5%×2.667=85,042,448円
しかし就職先が決まっていた大学生は、採用されるはずだった企業の給与で計算するケースもあります。
逸失利益を請求する流れ
逸失利益は「治療→後遺障害に申請→示談交渉→賠償金を受け取る」という流れになります。
交通事故でケガを負ったら、まずは病院で診察を受けましょう。外傷がなく痛みもないので大丈夫と思っても、後から後遺症が発覚することはあります。事故後は必ず診察を受けるようにしてください。

医師に症状固定と診断されたら、加害者側の自賠責保険に後遺障害等級の認定を申請します。申請には後遺障害診断書など、後遺症を証明する資料や書類を提出しなければなりません。
申請方法には加害者側の任意保険を介して提出する「事前認定」と、被害者が自分で提出する「被害者請求」の2種類から選択します。
後遺障害の認定通知が届くまでには、通常1〜2か月程度かかります。もし認定された等級に納得できなければ、異議申立てを行う権利があります。
自賠責保険で認定された等級に基づいて、加害者側の任意保険会社と損害賠償額について話し合いをする「示談交渉」を始めます。示談交渉は逸失利益の金額だけでなく、治療費や慰謝料を含むさまざまな賠償金の取り決めを行います。
示談が成立したら、だいたい1〜2週間後に保険会社から示談金が支払われます。
後遺障害逸失利益を請求するさいのポイント
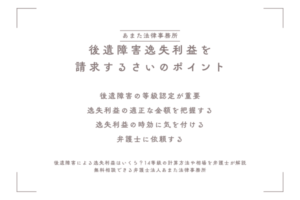
後遺障害逸失利益を受け取るとき、注意すべきポイントがあります。
後遺障害の等級認定が重要
後遺障害逸失利益の請求には、後遺障害等級の認定が必須です。
後遺障害の等級は1~14に分けられており、等級により労働能力喪失率や労働能力喪失期間が設定されています。本来は12級であるところが14級で認定されてしまうと、労働能力喪失率は14%から5%になってしまいます。等級が下がるほど不利な条件となってしまうため、適正な等級に認定されないと受け取る逸失利益の額が減ってしまう可能性が出てきます。
認定時に重要となるのは医師が作成する「後遺障害診断書」の内容です。どのような症状があるのか詳しく記載されており、この診断書をもとにどの等級にあてはまるか審査が行われます。診断書の内容によっては一番軽い14級にも該当せず、障害が認められない場合もあります。

逸失利益の適正な金額を把握する
逸失利益は怪我の治療費や入院費といった賠償項目と比較すると、かなり高額となるのが一般的です。しかし計算方法などをきちんと理解したうえで請求しないと、適正金額を大幅に下回る事態になりやすく損をしてしまいますので注意しましょう。
逸失利益は職業、年齢、性別などの被害者の個別的な事情を勘案して算出されます。普段から計算に慣れていないと、正しい金額を算出するのは困難と思われます。
逸失利益を請求するなら弁護士に相談するのがおすすめです。逸失利益の詳しい計算方法や最終的に賠償金がいくらになるか目安を教えてもらえます。
逸失利益の時効に気を付ける
逸失利益の損害賠償請求には時効があります。法律で定められた時効期間をすぎると、被害者が有していた損害賠償請求権が消滅してしまいます。
交通事故の損害賠償請求権は不法行為にもとづく損害賠償請求権となり、時効期間は「損害及び加害者を知ってから3年間(民法724条)」です。これを過ぎると時効が適用されるので、なるべく早くに請求権を行使する必要があります。

弁護士に依頼する
後遺障害逸失利益を請求するなら、弁護士にやってもらうのがおすすめです。弁護士へ依頼する3つのメリットを紹介します。
適切な後遺障害等級が認定されやすくなる
後遺障害による逸失利益を請求するためには、適正な等級認定を得なければなりません。有効手段になるのが弁護士への依頼です。
弁護士は治療の段階から通院方法や診断書の内容についてアドバイスをしてくれます。また、後遺障害の申請手続きを一任できるため、被害者の負担を緩和できます。
また、後遺障害は申請書類に不備があると低い等級になってしまったり、後遺障害自体が認められないことがあります。後遺障害や逸失利益についての知識がない個人が、1人でたくさんの書類を正確に用意するのは簡単ではありません。認定で重要視される診断書についても、弁護士は適正な等級になる記載になるように医師に働きかけてくれます。
慰謝料を増額できる
弁護士に依頼すると、慰謝料を増額できる可能性が高まります。
交通事故の被害者は逸失利益以外にも精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。しかし、相手方の任意保険会社は自社の支出を減らすために、できるだけ低い金額を提示してくるのが一般的です。
また慰謝料の計算方法は、「任意保険基準」という低額の基準で算定した金額を主張するのが普通です。慰謝料の計算方法には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準と3つあるのですが、なかでも高い慰謝料を受け取れるのは弁護士基準です。自賠責基準や任意保険基準と比較すると、受け取れる金額は100万円、1,000万円単位で高くなることもあり大きな差が出ることは珍しくありません。
弁護士特約があれば実質タダで依頼できる
弁護士特約を使うと、費用を気にせずに逸失利益の請求を任せられます。
弁護士特約は保険加入者が交通事故にあったとき、保険会社が代わりに弁護士費用を支払ってくれるサービスです。自身が加入している自動車保険に、弁護士特約がオプションとしてついていないか確認してみましょう。
弁護士特約を利用できれば、保険会社が最大300万円まで弁護士費用を支払ってくれます。現在は相談料や着手金は無料という法律事務所もありますが、すべての弁護士費用を実質無料にして弁護士へ相談することも可能です。
逸失利益の請求についてまとめ
交通事故で後遺障害が残り収入が減ってしまったら、加害者に対して逸失利益を請求できます。
逸失利益は後遺障害の等級により計算されるため、認定された等級により金額が決まるといえます。また逸失利益の計算方法は複雑であり、個人が1人で適正な金額を把握するのは難しいのが現状です。
適正な逸失利益を請求するためには、交通事故の案件に強い弁護士に任せるがおすすめです。弁護士が行うことで適正な後遺障害の等級に認定されやすくなりますし、逸失利益の計算もしてくれます。加害者側との示談交渉も行ってくれますので、慰謝料を含む損害賠償金の増額も望めます。
後遺障害による逸失利益を請求したいなど交通事故に関する困りごとや悩みがあれば、いつでも弁護士に相談してください。交通事故の案件に強い弁護士は、適切な対処法をアドバイスしてくれます。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ