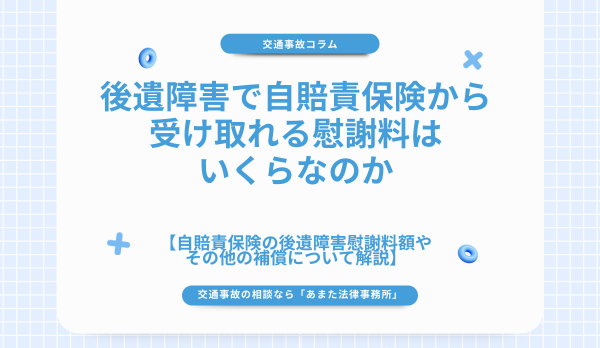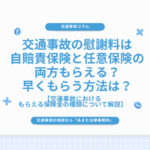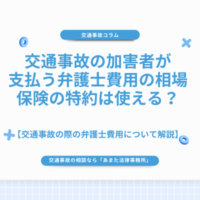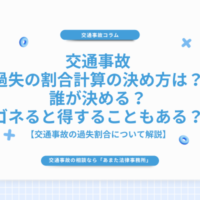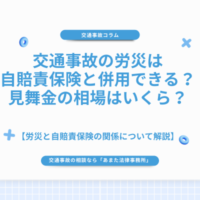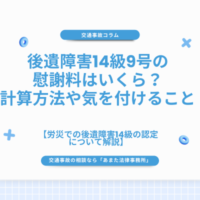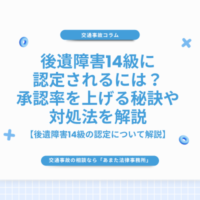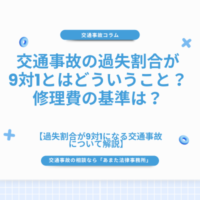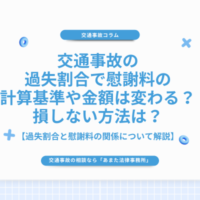交通事故の被害者になり後遺障害が残った場合、相手方から支払われる保険にはいくつか種類があります。そのうち、自賠責保険(共済)から受け取れる慰謝料はいくらになるでしょうか。


2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 ▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
この記事の目次
自賠責保険だけでは後遺障害慰謝料はかなり少ない
交通事故の被害に遭い、後遺障害が残った場合、自賠責保険からは入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などの慰謝料を受け取れるほか、治療費、休業損害、逸失利益など、さまざまな補償を受けられます。
しかし、ほかの算定基準と比較して自賠責保険から支払われる賠償金は低額で、交通事故の損害賠償で非常に高額となる弁護士基準と比べると慰謝料が半分~3分の1程度の金額になるケースも少なくありません。交通事故の慰謝料はケガの治療や今後の生活に関わる大切なお金です。
適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士を立てて交渉を行い、弁護士基準で慰謝料を請求できるようにするのが望ましいといえるでしょう。

自賠責保険から後遺障害の慰謝料はもらえるのか
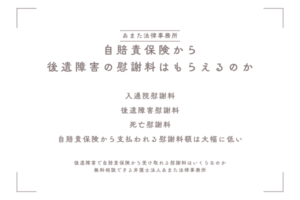
交通事故の被害者になった場合に自賠責保険から受け取れる慰謝料には次の3種類があります。
「入通院慰謝料」……傷害慰謝料とも呼ばれ、交通事故により医療機関に通院または入院が必要となった場合に生じる精神的苦痛に対する慰謝料です。
「後遺障害慰謝料」……事故によるケガで後遺症が残ってしまった精神的苦痛への慰謝料。
「死亡慰謝料」……事故により死亡させられた精神的苦痛に対する慰謝料で、本人分と遺族分の2種類が支払われる。
つまり、交通事故では「医療機関での治療を行った場合」「後遺障害が残った場合」「被害者が死亡した場合」の3つのケースで慰謝料を請求できるのです。それぞれの慰謝料の金額は以下のように計算されます。
入通院慰謝料
自賠責基準では、傷害慰謝料における入通院1日あたりの金額が4,300円と決められており、
①4,300×通院期間
②4,300×実通院日数×2
の2通りの計算を行い、金額の低い方が実際に支払われる慰謝料額となります。
②4,300×(入院1か月(30日)+(12日×3か月=36日)=66日)×2=56万7,600円
となり、金額の安い①の51万6,000円が適用されます。
後遺障害慰謝料
自賠責保険の後遺障害慰謝料は等級によって以下のように金額が決められており、32万円~1,850万円となっています。
| 等級 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 1級(要介護)被扶養者あり | 1,850万円 |
| 1級(要介護)被扶養者なし | 1,650万円 |
| 2級(要介護)被扶養者あり | 1,373万円 |
| 2級(要介護)被扶養者なし | 1,203万円 |
| 等級 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 1級 被扶養者あり | 1,350万円 |
| 1級 被扶養者なし | 1,150万円 |
| 2級 被扶養者あり | 1,168万円 |
| 2級 被扶養者なし | 998万円 |
| 3級 被扶養者あり | 1,005万円 |
| 3級 被扶養者なし | 861万円 |
| 4級 | 737万円 |
| 5級 | 618万円 |
| 6級 | 512万円 |
| 7級 | 419万円 |
| 8級 | 331万円 |
| 9級 | 249万円 |
| 10級 | 190万円 |
| 11級 | 136万円 |
| 12級 | 94万円 |
| 13級 | 57万円 |
| 14級 | 32万円 |
死亡慰謝料
死亡慰謝料は本人分と遺族分に分かれており、自賠責保険では本人分の400万円に加え、遺族の人数によって慰謝料額が変わり、金額幅は400万円~1,350万円となっています。
| 関係者 | 死亡慰謝料 |
|---|---|
| 本人分 | 400万円 |
| 遺族1人 | 550万円 |
| 遺族2人 | 650万円 |
| 遺族3人 | 750万円 |
| 被害者に被扶養者がいる場合 | 上記+200万円 |
例えば、夫と妻、子どもの3人家族で事故により夫が死亡した場合、
本人分400万円+遺族2人分(妻と子ども)650万円+被扶養者(子ども)200万円=1,250万円
となります。
自賠責保険から支払われる慰謝料額は大幅に低い
以上のように見ていくと、自賠責保険による慰謝料額は数百万から1,000万を超える場合もあり、かなり高額になるように思えます。しかし、実際には自賠責基準による金額は、交通事故で請求できる慰謝料の中では極めて安く、本来もらえる慰謝料の総額よりも大幅に低い金額しか受け取れなくなってしまうのです。
交通事故の慰謝料算定方法には、自賠責基準のほかにも加害者の任意保険会社の支払い基準である「任意保険基準」、弁護士に依頼した場合に適用される「弁護士基準」があります。
例えば、後遺障害慰謝料の場合、自賠責保険では、最高の1級要介護で受け取れる慰謝料は1,850万円ですが、弁護士基準なら2,800万円と1,000万円近くプラスになります。また、死亡慰謝料に関しても同様に「一家の支柱となる人物」が死亡した場合の慰謝料は2,800万~3,600万円と自賠責保険の2倍以上です。

自賠責保険から後遺障害慰謝料以外にもらえる補償
自賠責保険では、慰謝料のほかにも次のように、さまざまな損害賠償の受け取りが可能です。
「治療費」……ケガの治療にかかった費用で、実費での請求が可能です。
「休業損害」……事故によるケガで仕事を休んでいた期間の収入に対する補償で、休業1日につき6,100円が支払われます。
「後遺障害逸失利益」……ケガによる後遺障害のために仕事を続けられなくなったり、これまでより労働力が低下してしまったりして収入面への影響が出た場合に、将来もらえるはずだった給与等に対する補償として請求できる賠償金です。
※「ライプニッツ係数」……逸失利益の計算において、被害者による利息分のもらいすぎを防ぐために用いられる指数。
「死亡逸失利益」……被害者が死亡してしまったため、将来働いて得られるはずだった給与等の収入が失われてしまった損害に対する賠償金です。
※「生活費控除率」……死亡により必要なくなった被害者の生活費相当分を逸失利益の請求から差し引くための控除。
「通院交通費」……ケガの治療で医療機関に通うためにかかった交通費で、実費で請求できます。
「入院雑費」……入院中に必要となる日用品などの購入費用で、1日あたり1,100円が支払われます。
「付添看護費」……入院や通院、自宅での看護が必要になった場合に、入院1日につき4,100円、通院1日につき2,100円が支払われます。
労災保険と自賠責保険の後遺障害認定と支給調整
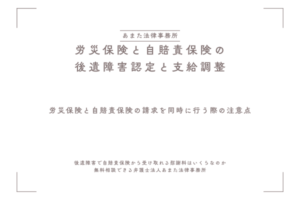
後遺障害に対する自賠責保険の補償に加え、業務中の事故などで労災保険の適用も受けられる場合、労災保険と自賠責保険の両方で補償を受けられる可能性があります。ただし、二重で同じ補償を受けることはできません。
労災保険と自賠責保険の請求を同時に行う際の注意点
労災保険と自賠責保険の請求を同時に行う際には、補償額の支給調整が必要です。まず自賠責保険が優先して支払われ、労災保険はその不足分を補填する形となります。また、両方の保険に対して共通する書類が必要になる場合が多いため、効率的な手続きを行うための準備が重要です。それぞれの後遺障害等級の認定基準も異なる場合があるため、正確に理解し、適切な手続きを踏むことが求められます。
支給調整
自賠責保険からの補償額が優先され、労災保険はその補填として支給される形になります。そのため、先に自賠責保険の請求が基本です。
請求の流れ
両方の保険に対して請求を行う手順と、必要書類の確認が重要です。特に診断書や後遺障害等級の認定は共通するため、一度の申請で両方の保険に利用できることもあります。
後遺障害の認定基準
労災保険と自賠責保険では、後遺障害等級の認定基準が異なる場合があります。双方の基準を理解し、それに応じた申請が重要です。
自賠責保険とは
改めて自賠責保険とは、交通事故による被害者を救済し、発生した事故に対する最低限の補償を行うための保険を「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」といいます。
自動車事故の保険には大きく分けて加入が義務付けられている自賠責保険と任意で加入する任意保険の2種類があり、自動車を運転する全てのドライバーに加入することが求められている自賠責保険は法律によって義務化されており、強制保険とも呼ばれています。
自賠責保険により、自動車の運転によって他人を負傷させたり、死亡させたりした場合に、被保険者(保険の補償を受ける対象、具体的には事故の加害者で車の保有者または運転者)が負うべき損害賠償責任に対する経済的な負担が補填され、保険金等の支払いが行われます。
交通事故による後遺障害とは
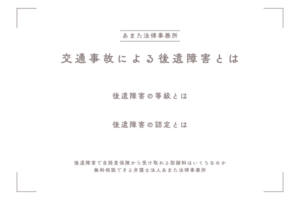
交通事故の被害に遭い、ケガのために治療後も何らかの症状が残ってしまった状態を「後遺障害」と呼び、後遺障害と認められると自賠責保険から一定の保険金が支払われることになり、慰謝料などの補償も受けられるようになります。しかし、医師から後遺症が残るといわれた場合でも、必ずしも後遺障害に認定されるとは限りません。
日常生活では病気やケガの後に症状が残る状態を指して「後遺症」という言葉が使われますが、交通事故における後遺障害と後遺症は厳密には異なります。後遺障害は交通事故による後遺症のみを指す用語で、次のような定義が決まっており、以下の4つを全て満たす場合のみ認定を受けられます。
- 交通事故のケガによる症状が治療後も治りきらずに残存しており、将来的にも回復が難しいと考えられる。
- 障害と交通事故の間に医学的な相当因果関係(AとBの間に社会通念上の原因と結果の関係性が認められること)が証明できる。
- 後遺症の存在により労働能力の低下または喪失が生じている。
- 後遺症の程度が「自動車損害賠償保障法施行令」に規定される1~14級までの等級のいずれかに該当する。
つまり、単に後遺症が残るだけではなく、交通事故との関係性がはっきりしており、労働力に影響が出ていて、自賠責施行令に定められた等級に当てはまっていなければ後遺障害の認定は受けられないのです。
後遺障害の等級とは
後遺障害には1級~14級までの等級が定められており、それぞれで該当する症状や補償の内容が異なります。後遺障害等級は数字が小さいほど症状が重く、補償も手厚くなるのが特徴で、自賠責保険による後遺障害慰謝料も等級ごとに決められています。
後遺障害の認定とは
交通事故による後遺障害の補償を受けるためには、所定の機関(「損害保険料率算出機構」の「自賠責損害調査事務所」)に申請を行い、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
等級に該当する後遺症が残っていても自動的に認定されるわけではなく、申請を行っても認められず「非該当」になってしまえば慰謝料などは受け取れません。後遺障害の申請は「書面主義」が採用されており、審査は提出した申請書類の内容のみで行われます。
そのため、書類作成時は不備のないようしっかり行わなければならず、神経症状のように外見から判断しづらい障害の場合は、レントゲンやCT、MRIなどの画像資料や神経学的検査の結果などを添付する必要があります。

事前認定
相手方の任意保険会社に診断書などを送付して手続きを任せる方法です。面倒な書類作成などをすべて保険会社にやってもらえるため、時間や手間などの負担を最低限に抑えられ、画像資料など必要な医療情報の取得費用も保険会社が負担してくれます。
被害者請求
相手方の自賠責保険会社を通じて、被害者自身が自分で申請を行う方法です。自分で全ての手続きを行うため、透明性が高く、納得のいく申請が行えますが、その分、書類作成などの手間がかかり、医療情報を入手するための費用も自己負担となります。

交通事故における慰謝料請求についてまとめ
交通事故でケガの治療後も何らかの症状が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定を受けると、自賠責保険から後遺障害慰謝料や逸失利益などの補償を受けられるようになります。
しかし、自賠責保険から支払われる慰謝料や賠償金は、弁護士に依頼した場合と比べて非常に低く、被害者にとって十分な金額とはいえないのです。交通事故の被害者に遭われた場合は、弁護士への相談・依頼を行い、弁護士基準での慰謝料請求ができるようにすると良いでしょう。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ