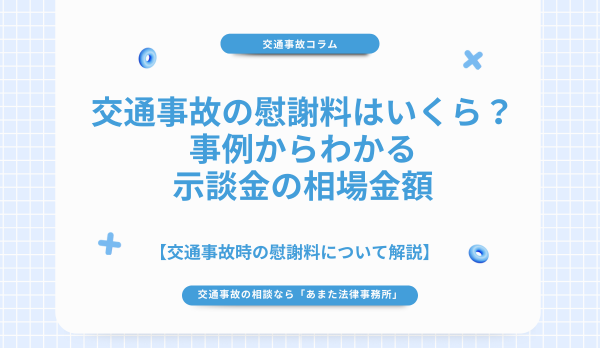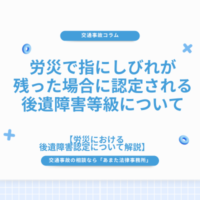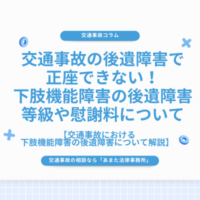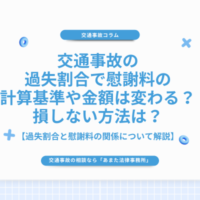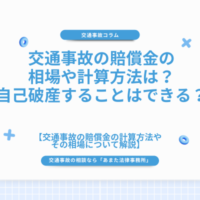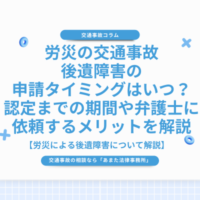交通事故の慰謝料は、弁護士基準で請求するのがおすすめです。

交通事故の慰謝料は実際どのくらいもらえるのか、慰謝料をもらい損ねないためにはどうすれば良いのかがわかります。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 ▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
この記事の目次
交通事故の慰謝料とはなにか
交通事故の慰謝料とは、事故による精神的苦痛に対して支払われる賠償金のひとつです。
慰謝料は、不法行為による精神的苦痛に対し支払われる損害賠償金であると民法に定められています。
民法709条では故意または過失により他人の権利や法律上の利益を侵害すると、損害賠償を支払うとされています。そして、民法710条では「他人の身体、自由、名誉、財産権を侵害した者は、財産以外の損害も賠償しなければならない」としています。
財産以外の精神的な損害に対しても賠償金を支払う必要があり、交通事故によるケガで病院に行く状況になったという精神的苦痛に対し、慰謝料を請求することができます。
交通事故で請求できる慰謝料
交通事故の被害に遭ったとき、請求できる慰謝料には主に3つの種類があります。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料です。
傷害慰謝料
交通事故の傷害慰謝料は入通院慰謝料とも呼ばれ、医療機関への入院や通院が対象です。ケガの治療期間に基づいて計算しているため、原則的に重いケガを負い長期の入院や通院になるほど相場は高額になります。
事故のケガで通院や入院をしたのであれば、請求しておくべき慰謝料です。
後遺障害慰謝料
交通事故によるケガで後遺症が残ってしまったときに請求できる慰謝料です。後遺障害の事例は人によりさまざまで、むちうちのように比較的軽傷から、失明や手足を失うなどこれまで通りの生活を送れなくなるような重症まであります。
ただし後遺症があればどんなものでも請求できるわけではなく、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
後遺障害等級には1級から14級までがあり(1、2級のみ要介護有)、1級が一番重く、数字が大きくなるほど軽症になります。いくつかの等級が同時に当てはまるケースもあり、重い方の等級を繰り上げる「併合」の制度が適用される事例もあります。
後遺障害慰謝料は、医師の診断がないともらえません。ケガが治ったのに身体に不調があるのなら、医師に相談し後遺障害慰謝料の申請を検討してください。
死亡慰謝料
不幸にも被害者が亡くなってしまった死亡事故で請求できるのが死亡慰謝料です。被害者本人を死に至らしめられたことに対する精神的苦痛に加え、近しい人を突然失くしてしまった遺族の悲しみや無念さといった精神的苦痛に対する補償でもあります。

交通事故の慰謝料を増額しやすいのは弁護士基準
交通事故による慰謝料の事例において、増額されやすいメリットがあるのは弁護士基準です。
「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」3種類の計算方法で、慰謝料の相場を比較してみましょう。
自賠責基準
交通事故ではほぼすべてのケースで、自賠責基準での慰謝料は受け取れます。すべての自動車に加入が義務付けられている、自賠責保険から支払われるためです。
ただ、自賠責保険は事故に対する最低限の補償を目的としているため、もらえる金額は非常に安くなってしまいます。最も高額な弁護士基準の事例と比較すると、約2~3倍もの違いが出ることもあります。
自賠責保険の慰謝料は、入通院1日につき4300円と決まっています。
①4300×通院期間
②4300×実通院日数×2
これら2つのうち、金額の低いほうが実際に支払われる金額になります。
任意保険基準
交通事故の相手方が加入している自動車保険会社が提示する慰謝料算定基準です。
任意保険基準は会社ごとに計算方法が異なり、どのような方法を用いるかは各社が自由に決めてよいとされています。外部には非公開のため詳細は不明ですが、基本的には自賠責基準を少し上回る程度の示談金となる事例が多くなっています。
相場の参考として、以前、すべての保険会社で使用されていた「旧任意保険支払基準」を掲載します。
| 入院→ 通院↓ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 0 | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 128.5 |
| 1か月 | 12.6 | 37.8 | 63 | 85.7 | 104.6 | 121 | 134.8 |
| 2か月 | 25.2 | 50.4 | 73.1 | 94.5 | 112.2 | 127.3 | 141.1 |
| 3か月 | 37.8 | 60.5 | 81.9 | 102.1 | 118.5 | 133.6 | 146.1 |
| 4か月 | 47.9 | 69.3 | 89.5 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.1 |
| 5か月 | 56.7 | 76.9 | 95.8 | 114.7 | 129.8 | 143.6 | 154.9 |
| 6か月 | 64.3 | 83.2 | 102.1 | 119.7 | 134.8 | 147.4 | 157.4 |
単位:万円
交通事故の慰謝料額は治療期間によって決まり、入院と通院で金額が異なります。自賠責基準と違い、実際の通院日数が直接影響することはありません。
任意保険基準は自賠責基準より高い相場とはいえ、弁護士基準より大幅に少ない金額になる事例が多くなると思って良いでしょう。保険会社は民間企業のため、支払う保険金はなるべく安く抑えたいという事情があるからです。
弁護士基準
交通事故の慰謝料計算方法の中でも、弁護士基準は高額な慰謝料を受け取れるのがメリットです。
別名「裁判所基準」ともいわれ裁判を起こしたときに適用される基準ですが、実際に裁判を起こさなくても、弁護士に依頼するだけで適用されるようになります。
弁護士基準は公益社団法人「日弁連交通事故相談センター」が発刊している「交通事故損害額算定基準」(通称:青い本)や、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)などを参考に慰謝料の相場を算定します。
弁護士基準の慰謝料も任意保険基準と同様に治療期間によって決まり、計算表は軽症用と重症用の2種類に分かれています。
| 入院→ 通院↓ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 0 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 |
| 1か月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |
| 2か月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |
| 3か月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |
| 4か月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |
| 5か月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |
| 6か月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |
単位:万円
| 入院→ 通院↓ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 0 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 |
| 1か月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |
| 2か月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |
| 3か月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |
| 4か月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |
| 5か月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |
| 6か月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |
単位:万円
上記の表を見るだけでも、任意保険基準より獲得できる金額が高額になるのが分かります。自賠責基準と比べると慰謝料額が約2倍以上になる事例もあり、弁護士基準こそ交通事故の被害者が本来受け取るべき金額といえます。

交通事故による慰謝料の事例を紹介
交通事故の慰謝料における、実際の事例を紹介します。
弁護士基準と自賠基準ではどのくらいの金額を受け取れるのか、いくらくらい金額に違いがあるのか、歩行者と自動車の事故、そして軽傷、重傷、死亡事故のケースで相場を比較していきましょう(任意保険基準は計算方法が保険会社により違っているため省略していますが、相場は自賠責基準よりもやや高い程度の示談金になります)。
事例① 歩行者と自動車の衝突による交通事故の慰謝料
歩行者と自動車の交通事故における、慰謝料の事例です。
Aさんは信号のない交差点で横断歩道を渡っている途中、侵入してきた自動車と接触し右足を骨折。1か月の入院に加え、2ヶ月通院(週に3日)しました。しかし、病状固定後も膝の痛みといった症状が残り、後遺障害14級の認定を受けることになりました。
自賠責基準は上の計算式をもとに
①4300×30日×3か月=38万7000円
②4300×(入院30日+(週3回通院×2か月))×2=46万4400円
となり、このうち金額の低い①の38万7000円が適用されます。
さらに、後遺障害慰謝料も発生しているため、自賠責基準で14級の慰謝料は32万円です。合計金額は70万7000円となります。
弁護士基準による慰謝料の相場を見ていきます。
弁護士基準では、骨折の場合は重症用を用いるため、1か月入院2か月通院したときの慰謝料は98万円になります。さらに、14級の後遺障害慰謝料は110万円となり、もらえる金額の合計は208万円です。

事例② 打撲など軽傷の交通事故の慰謝料
交通事故による打撲やねんざなど、ケガの程度が比較的軽傷な慰謝料の事例です。
Bさんは自動車を運転中、後方から相手の車に衝突され、腰や腕に打撲のケガを負いました。打撲自体はどれも軽いもので、3か月の通院(週2~3日で月に10日)により完治。入院なしで後遺障害も残りませんでした。
自賠責基準による交通事故の慰謝料は以下のとおりです。
①4300×30日×3か月=38万7000円
②4300×10日×3か月×2=25万8000円
低いほうの②の25万8000円が適用されます。
軽症用の算定表から、3か月通院した場合の慰謝料は53万円となります。
軽傷でも、弁護士基準の相場は、自賠責基準の約2倍以上の金額です。
事例③ 後遺障害が残った交通事故の慰謝料
交通事故で後遺障害が残ったケースの慰謝料事例です。
10代の学生であるCさんは道路を横断中に自動車に衝突され、頭蓋骨骨折や脳挫傷といった重篤なケガを負いました。幸い一命はとりとめたものの、完治までに入院期間6か月、通院期間6か月(月10日)かかった上、病状固定後も1級(要介護)という非常に重度の後遺障害が残る状況になりました。
自賠責基準では、後遺障害慰謝料も対象となります。
①4300×30日×12か月=154万8000円
②4300×(入院30日×6か月+通院10日×6か月)×2=206万4000円
となり、①の154万8000円が適用されます。
後遺障害慰謝料は自賠責基準で1級(要介護)では1650万円ですから、総額は1804万8000円です。
弁護士基準では重症の算定表を使用します。
入院6か月、通院6か月の慰謝料相場は282万円です。そして、後遺障害慰謝料は1級(要介護)だと2800万円になり、金額の合計は3080万円です。
Cさんの状況のように介護が必要になる後遺障害が残る重傷では、弁護士基準とほかの基準では金額が約1000万以上違ってくることは珍しくありません。

事例④ 死亡交通事故の慰謝料
被害者が死亡してしまった死亡事故の慰謝料の事例です。
バイクに乗って公道を走行中だったDさんは、後ろからきた自動車と接触。転倒して道路に投げ出され、自動車に撥ねられて亡くなりました。Dさんはまだ30代で家族(妻と子ども1人)もおり、一家の生計を支える立場にありました。
自賠責保険の死亡慰謝料は次のように定められています。
本人に対する死亡慰謝料:400万円
遺族への死亡慰謝料
| 請求権者(被害者の父親・母親、配偶者、子) | 金額 |
|---|---|
| 1人 | 550万円 |
| 2人 | 650万円 |
| 3人 | 750万円 |
| 被扶養者 | 1人につき+200万円 |
死亡事故では、Dさんへの死亡慰謝料400万円と妻と子どもの遺族2人に対する死亡慰謝料650万円の計1050万円が支払われます。
弁護士基準の死亡事故による慰謝料は、被害者の家族内における地位や属性などの状況を考慮して金額が決定されます。
| 一家の支柱となる人物 | 2800万~3600万円 |
|---|---|
| 一家の支柱に準ずる人物 | 2000万~3200万円 |
| 子ども | 1800万~2600万円 |
| 高齢者 | 1800万~2400万円 |
Dさんの例では死亡したのは一家の生計の柱であり、支柱といえる人物です。最高3600万円の死亡慰謝料を受け取れます。自賠責基準の相場と比べると、実に約3倍以上となり、差額は2000万以上に上ります。
さらに、将来のDさんの収入に対する補償として逸失利益を獲得できます。
交通事故による慰謝料を見ると、弁護士基準と自賠責基準では大きな違いがあります。重傷や死亡など重大な人身事故になるほど金額の差は大きくなり、同じ事故やケガでも1000万円以上変わってくるケースはあります。
交通事故の被害に遭った際は、弁護士基準で慰謝料を計算することが望ましいといえるでしょう。
交通事故の慰謝料を増額する5つの方法
交通事故による慰謝料を、相場より増額できた事例はいくつもあります。
交通事故の慰謝料は、被害者の事故後の行動や手続きの有無によっても変わってしまいます。損をしないためにも、受け取れる金額を増額する方法を実践しておくのがおすすめです。
診断書を警察に提出する
交通事故の慰謝料をもらうために、人身事故として処理してもらえるよう警察にも診断書を提出しましょう。
どのような理由や状況であれど人身事故として扱われないと、慰謝料や治療費などの金額の面で大きく不利になります。すでに物損事故として処理されていても、診断書を提出すれば人身事故に切り替えてもらうことは可能です。
警察に提出する診断書には以下の項目を記載します。
- 傷病名……打撲、むちうち、骨折など部位とケガの種類。
- 全治日数……ケガの完治までにどれくらいの期間がかかるか。初診時の見立てで良い。
警察に提出する診断書は、初診のタイミングで作成を依頼します。怪我が事故によるものであることを証明するのが目的ですので、症状について詳細に書かれている必要はありません。全治日数が実際の日数と変わっていても問題なく、訂正や再提出が求められることもありません。
提出期限は特に決まっていませんが、遅くとも事故発生から10日以内には提出するようにしましょう。あまり時間が空き過ぎると、事故とケガの因果関係を証明するのが難しくなる恐れがあります。

交通事故が起きたときにきちんと警察に届け出るのは道路交通法でも定められている義務です。警察への事故届は事の直後でなくてもかまいません。もし物損事故として届けてしまっていても、必ず警察で人身事故への切り替えを申請してください。
ケガが完治または病状固定まで治療を続ける
病状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善等が望めない状態のことです。交通事故での慰謝料を相場より増額するために、医師から完治または病状固定の診断を受けるまで治療は続けるようにしましょう。
途中で治療を止めてしまうと「大したケガでない」と判断され、示談交渉の際に慰謝料を減額する口実にされてしまう可能性があります。
またもし病状固定後も何らかの症状が残っていたら後遺障害に申請することになりますが、後遺障害等級の認定に悪影響を与えてしまい慰謝料の増額ができなくなる危険性も出てきます。
それに、なんといってもきちんと治りきっていないのに治療を止めてしまうのは、あなた自身のこれからの生活にもマイナスになることは確実です。
保険会社は「そろそろ病状固定にしませんか」などと、治療費の打ち切りを提案してくることがあります。しかし、症状が残っているなら従う必要はありません。途中で治療費を打ち切られたとしても、自分の健康保険を使って最後まで治療を続けてください。
後遺障害等級を申請する
交通事故によるケガが病状固定と診断された後に何らかの症状が残っていれば、後遺障害等級の認定を受けましょう。
後遺症が認められると後遺障害慰謝料を請求できるようになるため受け取れる金額が増額されます。
後遺障害慰謝料は等級がきちんと認定されないと対象になりません。医師から後遺障害診断書を書いてもらい、損害料率算出機構(自賠責損害調査事務所)といわれる専門機関に提示して申請します。
後遺障害の認定には、保険会社に手続きを委ねる「事前認定」と被害者自身が手続きを行う「被害者請求」の2種類があります。事前認定だと、必要な書類を送れば手続きをすべてやってもらえるため、被害者としては手間が省けて非常に楽です。
ただ、保険会社は示談金の支払額をなるべく少なく抑えたいと考える傾向があります。高い後遺障害等級の認定を受けることにあまり協力的とはいえません。不当に低い等級認定になってしまった事例もあります。後遺障害の認定は被害者請求での手続きをおすすめします。

後遺障害の等級による自賠責基準と弁護士基準での慰謝料額は以下のようになります。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級(要介護) | 1650 | 2800 |
| 1級 | 1150 | 2800 |
| 2級(要介護) | 1203 | 2370 |
| 2級 | 998 | 2370 |
| 3級 | 861 | 1990 |
| 4級 | 737 | 1670 |
| 5級 | 618 | 1400 |
| 6級 | 512 | 1180 |
| 7級 | 419 | 1000 |
| 8級 | 331 | 830 |
| 9級 | 249 | 690 |
| 10級 | 190 | 550 |
| 11級 | 136 | 420 |
| 12級 | 94 | 290 |
| 13級 | 57 | 180 |
| 14級 | 32 | 110 |
単位:万円
損害賠償項目の請求漏れを防ぐ
交通事故の慰謝料は、請求する損害賠償の項目に漏れがないように注意しましょう。
被害者が最終的に受けとる示談金には、慰謝料の他にも治療費や逸失利益、休業損害、自動車の修理費など様々な項目が含まれています。加害者側に任せきりにしていると、慰謝料や賠償金の額を低く見積もる、抜けている項目があってもそのまま処理されるなど、適切な対応ではない事例が発生しています。

慰謝料は弁護士基準で請求する
交通事故の慰謝料を増額したいなら、高額請求ができる弁護士基準を選択しましょう。
弁護士基準で計算するためには、裁判に訴えるか弁護士への依頼が必要です。裁判は判決が出るまでに時間を要するため、慰謝料の支払い時期は遅れてしまいます。それに、訴訟を起こしての解決は手間がかかり大変です。
そのため、まずは弁護士の利用を検討してください。弁護士に相談するだけで、慰謝料を含む示談金の額が約2~3倍に増額された事例もあります。
ただし、弁護士費用が発生すること、どの弁護士でも良いわけではないことを、頭に入れておくことが大切です。
交通事故による弁護士費用の相場
交通事故による慰謝料の示談交渉を弁護士に依頼すると、弁護士費用が発生します。相談料、着手金、成功報酬、弁護士の日当・実費などに分けられており、各費用の相場は以下のとおりです。
| 相談料 | 弁護士への相談費用 | 30分5000~10000円程度 |
|---|---|---|
| 着手金 | 依頼する際に払う初期費用 | 10万~20万円 |
| 成功報酬 | 依頼の終了後に支払うお金 | 実際に回収できた金額(慰謝料)の10~30%程度(慰謝料が500万円で報酬率10%なら50万円) |
| 日当・実費 | 事務処理にかかる郵送費や印紙代、診断書発行手数料、弁護士の交通費など。依頼で遠方に出張する場合などは弁護士への日当も必要になる。 | 日当:1日あたり3万~5万円 |
すべてあわせると、数十万から100万近い金額になる事例もあります。交通事故の慰謝料よりも弁護士費用の方が高くなるのは困りますから、いくらくらいの金額がもらえるのかを事前に調べておくようにしましょう。
交通事故の弁護士費用は節約できる
交通事故による慰謝料を増額するための弁護士費用を節約する方法はあります。
初回相談無料の弁護士事務所や法律事務所であれば、費用をかけずに相談できます。
また、着手金0円のところや、着手金のみで成功報酬はいらないといったサービスもありますので、公式サイトなどで料金体系を確認してください。
そして、任意保険の弁護士特約を使用する方法もあります。
自動車の任意保険などに付帯する弁護士特約は、交通事故の示談交渉などを依頼したさいの弁護士費用を負担してくれるサービスです。
交通事故の慰謝料は増額したいけれど、弁護士費用に不安がある…と考えるなら、任意保険の特約を確認してみましょう。弁護士特約があれば、金銭面を心配せずに事故の慰謝料を請求できます。

交通事故の事例に強い弁護士を選ぶ
交通事故の慰謝料を増額するポイントとなるのが、交通事故の事案に強い弁護士に依頼することです。
弁護士基準で計算すると、自賠責基準や任意保険基準よりも多額の慰謝料をもらうことができます。しかし算定方法はあくまでも目安で、過失の割合などで示談金の額は違ってきます。加害者側との示談交渉が上手く行かないと、相場から増額どころか減額される可能性もあります。
なるべく高額な金額をもらうためには、交通事故の示談交渉に慣れた弁護士への依頼が重要です。弁護士事務所のホームページなどで、得意分野や実績を調べてみましょう。交通事故に強い弁護士に依頼すれば、後悔しない金額の慰謝料を受け取れる可能性が高くなります。
交通事故による慰謝料についてまとめ
交通事故の慰謝料は事例を見てもわかるように、計算方法や請求方法により金額に差が出てしまいます。慰謝料を増額するためにやるべきことを無視すると、損をする可能性が高いでしょう。
しかし加害者側の保険会社に個人の主張は聞き入れてもらいにくく、対等に示談交渉するのは大変です。それに知識や経験がない人が手続きをするのは困難という現実があります。
交通事故の慰謝料を含む示談金についてお悩みなら、弁護士へ相談するのが解決への近道です。弁護士に対応してもらえば、弁護士基準での計算となり高額をもらいやすくなります。また交通事故の事例解決が豊富な弁護士であれば、示談交渉によりさらに増額することも可能です。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ