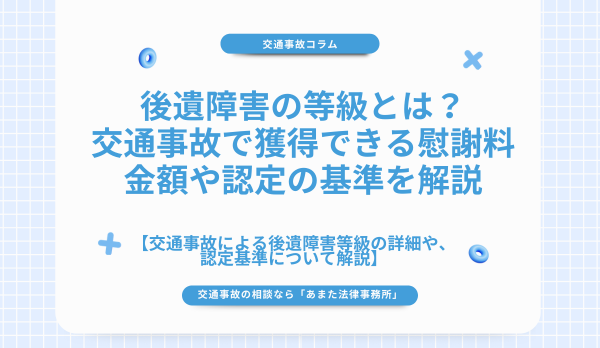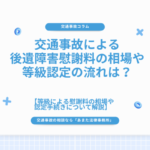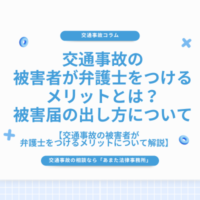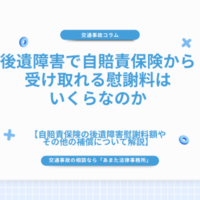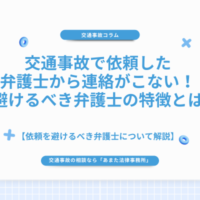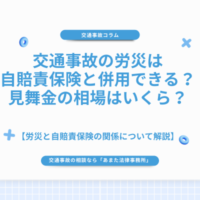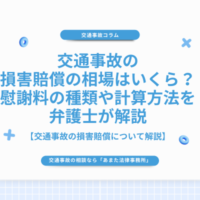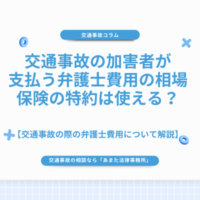交通事故の後遺障害には等級があります。等級により損害賠償金額は大きく変わるため、適切に認定される必要があります。

この記事の目次
交通事故による後遺障害とは?
後遺障害とは、交通事故の怪我により残ってしまった後遺症のひとつです。痛みや麻痺、視力や聴力の低下、認知機能の障害などを、度合いに応じて1~14に等級化しています。
ただ、厳密にいうと後遺障害と「後遺症」は異なるものでもあります。
「後遺障害」は交通事故のケガによる後遺症
後遺障害とは、交通事故によるケガが「病状固定」の状態になっても何らかの症状が残ってしまった状態のことです。治療を続けても、良くなる見込みがないと医師に判断されると病状固定となります。
後遺障害が残ったと認められるためには、専門の機関で後遺障害等級の認定を受ける必要があります。低下した労働能力の程度などにより「後遺障害等級」と言われる等級が決まります。
「後遺症」は交通事故以外の症状も含まれる
「後遺症」は、治療を行っても完治しない機能障害や神経症状などが残ってしまう状態を指します。後遺障害よりも後遺症のほうが意味の範囲が広いのが特徴です。
後遺症は病気によるものなど、交通事故によるものではないケガや疾病に対しても適用されます。対して、「後遺障害」は交通事故によるケガに限られており、労働に支障をきたす場合しか認められないという特徴があります。
そのため、
後遺障害等級が認定されると慰謝料や逸失利益を請求できる
後遺障害の認定を受けると受けないでは、請求できる慰謝料の金額は大きく違ってきます。また後遺障害の等級によっても、慰謝料の金額が異なる点に注意してください。

後遺障害等級の認定を受けるには
交通事故の後遺障害として認めてもらう方法は、必要な書類を準備→専門の機関に「申請」→「認定」を受けるという手順になります。
まずは医師から「病状固定」の診断を受けた後に「後遺障害診断書」を書いてもらいます。
そして診断書をはじめとした必要な書類を、後遺障害等級の判定を行っている「損害保険料率算出機構」の「自賠責損害調査事務所」という機関に提出し申請します。
- 後遺障害診断書
- 自賠責保険支払請求書兼支払指図書
- 診療報酬明細書及び診断書(毎月発行されるもの)
- レントゲンやMRI等の検査画像
- 交通事故証明書、事故発生状況報告書
以上のような書類を準備したら相手方の任意保険会社(自分自身で申請する場合は相手方の自賠責保険会社)に送付します。保険会社から調査事務所へ書類を回してもらうと、審査が行われます。
後遺障害が認められた場合
後遺障害等級の審査を通過し認定を受けられると、加害者に請求できる損害賠償の金額が大きく増額されます。後遺障害に関するお金が損害賠償額の6~9割を占めるケースも存在します。
認定を受け請求できる損害賠償には、下記のようなものがあります。
・「後遺障害慰謝料」……後遺障害を負ったことに対する精神的・肉体的苦痛への補償
・「後遺障害逸失利益」……後遺障害が残ったため働けなくなったり、現在の職場を変えなければならなくなったりして、将来手に入るはずだった給与等の利益が失われたことへの補償。
慰謝料等は相手方との示談が成立すると、示談金として保険会社から一括して支払われます。ただし、「被害者請求」の制度を利用すると、自賠責保険の限度額の範囲内ではありますが保険金の先払いを受けられます。
被害者請求の上限は120万円までと決められていますが、示談交渉中でもまとまったお金を受け取れることになります。治療費などの出費がかさみ、経済的に厳しいという状況では有力な方法です。
また、被害者が加入している自動車保険の内容によっては、加害者側との示談に関係なく保険金の請求が可能になります。
「搭乗者障害保険」……契約している車が事故を起こしたとき搭乗者全員に対して補償する保険。

後遺障害が認められなかった場合
後遺障害等級の申請を行ったにもかかわらず「非該当」となる事例はあります。認められなかった場合は、異議申立を行って再度申請を考えましょう。損害保険料率算出機構に対する異議申立には回数制限がないので、納得がいかなければ何度でも再審査の要求は可能です。
ただ、何度も結果が非該当になるケースでは、書類などに不備がある可能性が高いと思われます。後遺障害等級の審査に通らず認定を受けられない時は、申請方法を見直すことを検討してください。個人で問題点を見つけるのは難しい面がありますので、交通事故に強い弁護士への相談が解決への近道になるでしょう。
後遺障害が認定される条件
後遺障害等級を申請して認定を受けるには、決められた条件を満たしている必要があります。
- 事故によって受傷したケガが治った(病状固定)後も身体に障害が残る状態である。
- 労働能力の低下あるいは喪失が認められる。
- 事故と後遺障害の間に相当因果関係が認められると医学的に証明・説明できる。
- 症状の程度が「自動車損害賠償保障法施行令」に定める等級に該当する。
後遺障害等級の決め方にはルールがある
後遺障害は14種類の等級に分類されており、後遺症や障害がどの項目に当てはまるか審査され認定に至ります。また後遺障害等級には独自のルールも存在しています。
交通事故における後遺障害等級は14種類
交通事故による後遺障害は、1級から14級までの等級があります。加えて140種類、35系列のグループに細かく分けられています。
障害の残った部位や症状の程度によって等級が決定され、1級が一番重く数字が大きくなるほど障害の程度も軽くなっていきます。
等級認定の要件は「後遺障害等級表」に記載されており、労働能力に及ぼす影響により等級や系列が決めらます。
例えば、同じ眼の障害でも、両眼の失明は第1級、一眼が失明し他眼の視力が0.02以下なら第2級、両眼の視力が0.06以下なら第4級など、失明や視力の低下、視野障害の度合いにより違ってきます。また同じグループの中でも、序列と言われる障害の上位、下位関係が決められています。
後遺障害等級の3つのルール
後遺障害等級の認定にあたっては、特殊なルールも存在しています。中でも重要な併合、加重、準用の3つを紹介します。
等級および系統が異なっている2つ以上の障害がある場合に、等級の繰り上げる制度を「併合」といいます。
- 5級以上の障害が2つ以上残った場合→重い方を3等級繰り上げ
- 8級以上の障害が2つ以上残った場合→重い方を2等級繰り上げ
- 13級以上の障害が2つ以上残った場合→重い方を1等級繰り上げ
- 14級の障害が複数残った場合→14級
| 重い方の等級→ ↓2番目に重い等級 | 1~5級 | 6~8級 | 9~13級 | 14級 |
|---|---|---|---|---|
| 1~5級 | 重い方の等級にプラス3級 | |||
| 6~8級 | 重い方の等級にプラス2級 | 重い方の等級にプラス2級 | ||
| 9~13級 | 重い方の等級にプラス1級 | 重い方の等級にプラス1級 | 重い方の等級にプラス1級 | |
| 14級 | 重い方の等級 | 重い方の等級 | 重い方の等級 | 14級 |
一例として、5級と6級の2つの障害が残った場合、重い方の等級にプラス2となり等級は3級として認定されます。
| 4級と5級→1級 | 8級と13級→7級 |
| 5級と5級→2級 | 12級と12級→11級 |
| 5級と6級→3級 | 12級と13級→11級 |
| 5級と8級→3級 | 13級と13級→12級 |
| 5級と13級→4級 | 13級と14級→13級 |
| 8級と8級→6級 | 14級と14級→14級 |
併合にはほかにも、上記の表にあてはまらないケースや特殊なケースも存在します。
・みなし系列……片方の腕と手の指の両方に障害が残るとケースのように、系列が違う後遺障害でも同じ箇所に残った場合は同一の系列とみなされるケースがあります。
・組み合わせ等級……両腕を肘より上で喪失したケースのように、部位や系列が異なる後遺障害のなかには例外的にまとめられるものがあります。
交通事故の後遺障害の等級は、様々な個別のケースごとに判断する必要があります。自身のケースがどこに当てはまるか知りたいときは、交通事故の法律に詳しい弁護士などに相談してください。
過去に交通事故などで後遺症がある方が再度事故に遭い、さらに重度の後遺障害が認定されたときは「加重障害」が適用されます。加重では、後遺障害の慰謝料等を支払うときに、過去に受け取った金額を差し引いた差額のみが支払われます。
例えば、過去に13級の認定を受けて180万円の慰謝料を受け取ったとします。二度目の事故後に12級に認定されると、支払われる慰謝料は12級の290万円から180万円を引いた110万円のみになります。ただし、障害の度合いが以前より重くなっていなければ慰謝料が支払われません。

準用とは本来なら後遺障害の等級にない症状であっても、後遺障害に準ずる等級を適用する制度です。障害の内容・程度に応じて各基準の「相当」とみられる症状が対象で、別名「相当」とも言われます。
後遺障害に認定される症状は「後遺障害等級表」で記載されている基準を満たすものだけです。しかし、交通事故の内容や後遺障害の度合いは誰でも同じなわけではなく、ケースバイケースという側面があります。等級表の基準だけではすべての被害者に対応できない可能性が出てきてしまいます。
後遺障害等級表では、頭や眼、腕、脚などの部位に関しては細かい分類がある一方、味覚、嗅覚などに関してはほとんど規定がありません。手指の一部を失う、骨折や骨の変形があるなど、目に見えない症状の規定は難しいためです。
一般の方であれば、味覚や嗅覚の低下が労働能力の低下に結びつかないと思われます。しかし、料理人であれば味覚に障害が残ると仕事になりませんので、労働能力に関わる重大な問題になります。味覚や臭覚の障害も、職業によっては直接的な労働能力の低下につながってしまうでしょう。
そういった理由から、被害に遭った本人の事情を考慮する相当が適用されています。本来なら認定されない嗅覚や味覚の障害であっても後遺障害等級が認定され、慰謝料額に影響を与えることがあるのです。
- 嗅覚喪失、味覚脱失……12級
- 味覚減退……14級
準用は味覚・嗅覚だけでなく、該当する後遺障害がない場合にも適用されることがあります。耳鳴りは12級相当または14級相当、鼻の呼吸困難は12級相当、上肢の習慣性脱臼は12級相当といった具合で、労災保険による準用が交通事故の後遺障害にも適用されています。
後遺障害等級の認定基準はわかりにくい
後遺障害等級の基準にはあいまいな部分があり、どこに当てはまるのかがわかりにくいという注意点があります。
例えば、
- 両上肢を手関節以上で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
- 両耳の聴力を全て失ったもの
両方の上肢や下肢を関節から欠損した、両方の耳が聞こえなくなったなど、具体的ではっきりとわかる障害であれば、どの等級に当てはまるかは予想しやすいかと思われます。
しかし、抽象的で判断に苦しむような基準もあります。
- 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 外貌に著しい醜状を残すもの
神経や精神の障害は外部の人にはわかりにくいですし、どのくらい仕事に支障があるのかも感じ方には違いがあります。また醜状の度合いの判断も難しいものがあり、後遺障害の審査を担当する人により判断が異なることは考えられますし、自身が予想していたよりも低い等級になってしまうのは、珍しいことではありません。
適正ではない等級に認定されることがないためにも、申請には十分な準備が必要と言えます。よくわからない点があれば、法律の知識が豊富な弁護士に相談し、適切な対策をして手続きしてもらうのが良いでしょう。
後遺障害慰謝料の算定基準は3種類
後遺障害慰謝料を含め、交通事故の損害賠償計算には「自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準」3つの算定基準があります。どの基準を適用するかによって、もらえる慰謝料額が異なる点に気を付けてください。
自賠責基準
すべての車が加入を義務付けられている自賠責保険による慰謝料算定基準です。事故に対する最低限の補償や賠償を目的としているため、受け取る金額は3つの基準の中で最も低額になります。
任意保険基準
加害者が加入する任意の自動車保険会社が、独自に定めている慰謝料の算定基準です。計算方法は各社が自由に決めることができ、外部には非公開とされているため、詳細ははっきり分かりません。
一般的には自賠責基準より高額と言われていますが、実際には数十万円の差になっています。自賠責基準と任意保険基準の金額はそれほど大きく違わないのが普通ですので、自賠責基準の金額を目安としてください。
弁護士基準
弁護士に依頼すると適用される算定基準で、3つのうち最も高額な慰謝料が受け取れます。
別名「裁判基準(裁判所基準)」とも言われ、交通事故で裁判になった場合に適用される基準です。裁判を起こすまでもない…と思う方が多いかと思われますが、弁護士に依頼することで裁判を起こさなくても弁護士基準での高額な慰謝料を請求できます。
弁護士基準は公益社団法人「日弁連交通事故相談センター」から発刊されている「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)や日弁連交通事故センター東京支部から刊行されている「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)などを参考に計算されています。
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害の慰謝料額は等級および算定基準によって決まります。自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準、3つの算定基準による後遺障害慰謝料の相場を比較していきます。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級(要介護) | 1650 | 2800 |
| 1級 | 1150 | 2800 |
| 2級(要介護) | 1203 | 2370 |
| 2級 | 998 | 2370 |
| 3級 | 861 | 1990 |
| 4級 | 737 | 1670 |
| 5級 | 618 | 1400 |
| 6級 | 512 | 1180 |
| 7級 | 419 | 1000 |
| 8級 | 331 | 830 |
| 9級 | 249 | 690 |
| 10級 | 190 | 550 |
| 11級 | 136 | 420 |
単位:万円
任意保険基準に関しては詳細が不明のため省略していますが、自賠責基準の金額にプラス数十万円程度が目安です。
以下、具体的な症状を例に解説していきます。
追突や衝突の衝撃により、首などに痛みやしびれ、違和感が残ったり、眩暈や吐き気、耳鳴りといった症状が残る後遺障害を「むちうち」といいます。
むちうちは交通事故では比較的起こりやすい障害の1つであり、等級としてはそれほど重くはありません。局部に神経障害が残ると14級、著しい頑固な神経障害だと12級が該当します。
それぞれの慰謝料相場は、
- 14級:自賠責基準では32万円、弁護士基準では110万円
- 12級:自賠責基準では94万円、弁護士基準では290万円
どちらも弁護士基準での慰謝料は、自賠責基準の3倍以上にもなります。
骨折が起こる交通事故は多くみられます。後遺障害の等級は、どの部位にどの程度の障害が残ったかで決まります。
骨折が該当する等級は多岐にわたりますが、今回は頭蓋骨の骨折と腕の骨折を例にあげました。
頭蓋骨の骨折は重度の障害が残りやすい骨折です。骨が折れるだけではなく、頭部に大きな衝撃を受けるため高次脳機能障害を伴うことも多くなります。一番重い介護が必要な1級に認定されると、慰謝料額は自賠責基準1650万円、弁護士基準2800万円です。
腕の骨折で偽関節が生じて運動障害が残ってしまったときは、7級9号の等級が当てはまります。慰謝料額は自賠責基準で419万円、弁護士基準で1000万円です。

・両腕が使えなくなる→1級
自賠責基準1150万円 弁護士基準2800万円
・片腕が使えなくなる→5級
自賠責基準618万円 弁護士基準1400万円
後遺障害の眼に関する障害では、左右の眼の状態によって等級が決まります。
・両目とも失明→1級
自賠責基準1150万円 弁護士基準2800万円
・両目とも視力0.02以下または片方が失明でもう一方の視力が0.02以下→2級
自賠責基準998万円 弁護士基準2370万円
・片方を失明し、もう一方の眼が視力0.06以下→3級
自賠責基準861万円 弁護士基準1990万円
等級が大きくなるほど自賠責基準と弁護士基準の差額は大きくなり、1000万円以上とかなり違ってくることもあります。交通事故の慰謝料は今後の生活や後遺障害の治療費などに充てる大切なお金ですから、受け取る金額はなるべく多いほうが望ましいでしょう。
おすすめは弁護士基準
相場を見ても分かる通り、交通事故の後遺障害の賠償金は金額が大きくなります。弁護士基準を使用するのがお得といえるでしょう。
もらえる金額を加味すれば、弁護士費用を払ったとしても赤字になるケースは少ないのが現状でしょう。弁護士費用がかかるので弁護士に依頼できないという声はあるのですが、後遺障害がある交通事故の解決では費用面での大きな心配はないといえます。
もし加入している自動車保険に弁護士特約が付帯していれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。実質負担金ゼロで、弁護士基準で交通事故の慰謝料を請求できる可能性があります。

後遺障害の等級認定から慰謝料支払いまでの流れ
交通事故の後遺障害等級の認定を受けるまでの流れや申請方法、認定までにどのくらいの時間がかかるかを解説します。
1、申請のタイミングは「病状固定後」
交通事故の後遺障害等級の申請を実施するのは、医師から「病状固定」と診断を受けてからです。病状固定になるまではきちんと通院し治療を受けてください。病状固定と診断されたら「後遺障害診断書」を医師に書いてもらい、後遺障害等級の申請準備を開始します。
相手方の保険会社から病状固定にして治療費の打ち切りを打診してくることがあります。しかし、治療を続けるか否かは医師が判断するものです。保険会社ではなく、医師の指示に従うようにしましょう。
2、申請方法は2種類
損害保険料率算出機構に交通事故の後遺障害等級申請する方法は2つの種類があります。
1つは加害者の任意保険会社に申請を仲介してもらう「事前認定」です。もう1つは加害者の自賠責保険会社を介して、被害者自身が申請をする「被害者請求」です。
メリット
・必要な手続きは相手方の保険会社が一括して行ってくれるため、書類の作成や資料収集の手間がかからない。
・資料や画像を入手する費用を保険会社に負担してもらえる。
デメリット
・保険会社はなるべく保険料を安くしようと考えるので、「認定を受けられない」「不当に低い等級で認定される」などの不都合が生じる恐れがある。
・保険料の支払いが一括になる。
・被害者請求で自賠責分だけ先に受けとれなくなるので、示談が終わるまで保険金が入ってこなくなる。
・経済的に余裕がない場合は注意が必要。
メリット
・加害者との示談が成立する前でも、自賠責分のみ保険料を先払いで受け取れる。
・上限120万円で限度額に達するまで何度でも利用可能。
デメリット
・必要書類を自分で用意する必要があり、書類を作成する手間や費用がかかる。
自分自身で後遺障害等級の手続きをする「被害者請求」は、病状固定から原則3年以内が申請期限になっています。
3、認定までの期間は平均2か月
交通事故の後遺障害等級は、申請から認定まで通常1か月~2か月ほどかかります。保険会社に依頼する事前認定で2か月経っても連絡が来ないときは、忘れられている可能性があるので連絡して確認してください。
保険会社は常に数十件ほど、交通事故の案件を抱えています。処理が遅れたり、連絡が来なかったりすることは珍しくありません。認定までの期間は保険会社を介さない被害者請求のほうが短くなる傾向にありますが、書類の不備で差し戻しがあったりすると時間を要することがあります。

4、認定から慰謝料の支払いまで
交通事故の後遺障害等級認定後は、加害者と示談交渉して後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を含めた損害賠償を請求します。計算基準で定めている交通事故の慰謝料額はあくまでも目安であり、実際に支払ってもらえる金額は交渉によって決まります。
示談成立後は2週間程度で、加害者側の保険会社から損害賠償が支払われます。
交通事故の損害賠償請求は、示談交渉でお互いの主張がかみ合わず進展が困難になることはあります。最終的に裁判になる可能性もありますので、慰謝料を含む損害賠償金を早く受け取るためにも、弁護士への相談をおすすめします。
弁護士がついていれば、後遺障害等級の認定手続きから示談交渉までスムーズに行えます。さらに弁護士基準が適用され、慰謝料の大幅な増額が期待できます。もし裁判になってしまってもケースに応じた適切なアドバイスをもらえますので、ぜひ弁護士への依頼を検討してください。
まとめ
交通事故でケガをして後遺障害等級の認定を受けると、後遺障害慰謝料等を請求できるようになります。
後遺障害は部位や度合い別に14の等級があり、どの等級に認定されるかで損害賠償の金額は変わります。また、算定方法によって損害賠償の金額は変わってきます。
交通事故による後遺障害の慰謝料を含む損害賠償金は、適正な等級に認定してもらい、弁護士基準で請求することで増額が狙えます。
後遺障害に申請しても妥当な等級に認定されるのか不安、弁護士基準で損害賠償を請求したいと考えるのであれば、交通事故の案件に強い弁護士に相談するのがおすすめです。相談の受付はいつでも行っています。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ