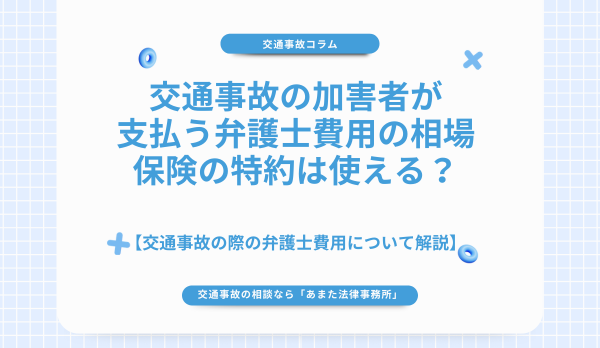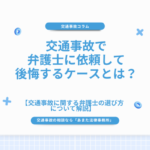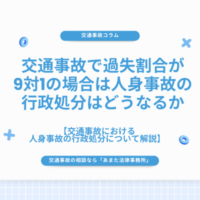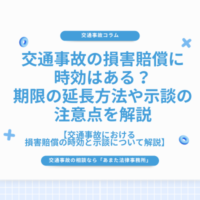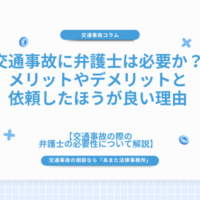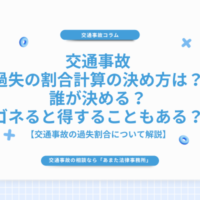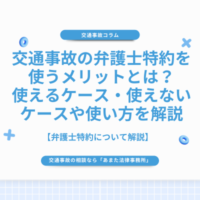交通事故の加害者でも弁護士に対応してもらうのがおすすめですが、気になるのが費用です。
刑事や民事など法的責任を問われたとき、示談交渉などを弁護士に依頼するときなど、弁護士に依頼すると様々なメリットがあります。しかし費用がかかるのはデメリット。費用が高すぎると、弁護士には依頼できない…となってしまうでしょう。


2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 ▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
この記事の目次
弁護士費用の相場を解説
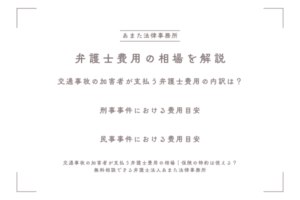
交通事故の対応を弁護士に依頼するとき、気になるのは費用面だと思います。
交通事故の加害者が弁護士に支払いする費用相場はどれくらいになるのか、内訳や刑事事件・民事事件で必要になる費用を解説します。
交通事故の加害者が支払う弁護士費用の内訳は?
交通事故の弁護士費用は、相談料や着手金、成功報酬などがあります。
相談料 30分あたり無料もしくは5000円~10000円
弁護士に法律相談を行うための費用です。加害者が正式に依頼する前に行うもので、相談だけして正式な依頼はしなくても大丈夫です。「初回無料」や「〇回まで無料」などのサービスを行っている弁護士事務所もあります。無料であれば費用が心配でも安心して相談できるでしょう。
着手金 10万円~
弁護士に加害者が正式な依頼を行うと発生する費用です。依頼が成功したかどうかに関係なく、依頼した時点で支払いすることになります。
計算方法は事務所ごとに違いますが、最低でも10万円程度になることが多くなっています。ただ、大きな被害が出た事故や警察の捜査を受けるような事故などでは高額になります。弁護士事務所によっては着手金を0円にしていて、成功報酬のみのところもあります。
成功報酬 20万円~
弁護士への依頼が成功した際に支払う費用です。交通事故では示談金額の大きな事故になるほど高額になるのが普通です。弁護士が介入することによって得られた利益をもとに計算され、「賠償金額の〇%」といった金額になるためです。
事務所によっては、成功報酬をもらわず着手金のみのところもあります。大きな事故では成功報酬は無料というサービスを選ぶと、弁護士費用を節約できるでしょう。
日当
出張など弁護士が事務所外で活動を行った場合に発生する費用です。移動距離や活動日数によって金額が決まります。着手金などに含まれる場合もあり、請求されるかどうかは事務所により異なります。
その他の費用
病院や警察、事故現場、裁判所などに移動するときに必要になる「交通費」や、郵便物の切手、配送料、通信にかかる「通信費」、「収入印紙代」などの実際にかかった費用が加害者に請求されることがあります。
刑事事件における費用目安
刑事裁判の弁護士費用の相場をみていきましょう。
| 相談料 | 5000~10000円 |
|---|---|
| 着手金 | 0~40万円 |
| 成功報酬 | 0~100万円 |
| 日当・実費 | 依頼内容による |

民事事件における費用目安
民事事件における着手金・成功報酬は、交通事故の示談金をもとに計算されることが多いです。正確な算定方法は事務所によって異なりますが、弁護士費用の自由化以前に使用されていた日弁連による旧報酬規程が参考になります。
| 経済的利益 | 報酬の算定基準 |
|---|---|
| 125万円以下 | 0~10万円 |
| 300万円以下 | 8% |
| 300万円越え3000万円以下 | 5%+9万円 |
| 3000万円越え3億円以下 | 3%+69万円 |
| 3億円以上 | 2%+369万円 |
| 経済的利益 | 報酬の算定基準 |
|---|---|
| 125万円以下 | 0~20万円 |
| 300万円以下 | 16% |
| 300万円越え3000万円以下 | 10%+18万円 |
| 3000万円越え3億円以下 | 6%+138万円 |
| 3億円越え | 4%+738万円 |
| 相談料 | 5000~10000円 |
|---|---|
| 日当・実費 | 依頼内容による |
例えば、被害者と500万円での示談が成立したケースで、着手金・成功報酬とも請求される場合の弁護士費用は、
相談料10000円+着手金(500万×5%+9万=34万)+成功報酬(500万×10%+18万円=68万円)=103万円
程度が目安になります。
交通事故の加害者が負う3つの責任
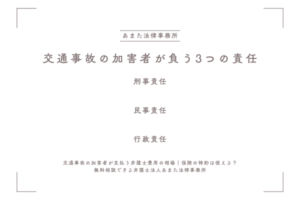
交通事故を起こした加害者は「刑事責任」「民事責任」「行政責任」の3つの責任を負うことになります。
自動車を運転していると、どんなに気をつけていても事故を起こしてしまうことがあります。交通事故の加害者になると、被害者への謝罪やお見舞いといった道義的な責任のほかに様々な法律上の責任を問われます。
刑事責任
刑事責任とは、犯罪行為に対し刑罰を受る法律上の責任です。交通事故で相手を死傷させたり、ものを破損させたりすると、道路交通法違反や自動車運転処罰法の過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などに当たり、罰金や懲役などの刑罰に処せられる可能性があります。
交通事故を起こしても逮捕されないケースは多いですが、被害者が重症になる事故やひき逃げ、無免許、飲酒運転など悪質な事故では逮捕されることもあり、罪が重くなることもあります。
交通事故で適用される罪と刑罰を解説します。
過失運転致死傷罪 自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)5条
交通事故で被害者を負傷・死亡させた場合に問われる罪。刑法211条の2にあった「自動車運転過失致死傷罪」が2020年7月の法改正により移行されたものです。ここでいう「過失」とは、故意ではありません。
わき見運転や前方不足、巻き込み確認不足、歩行者に気づかなかったことやウインカーなしでの進路変更など不注意・ミスによる事故の場合にも適用されます。加害者本人が注意していたつもりでも、事故を防げた可能性があると判断されれば罪になる可能性があります。
危険運転致死傷罪 自動車運転処罰法2条
過失運転致死傷罪よりもさらに過失の度合いが酷い事故に適用される罪。もともとは刑法208条の2に定められていた危険運転致死罪から移行されたものです。
飲酒運転や薬物使用、車を制御できないほどのスピードを出す運転、信号無視を繰り返す行為、高速道路の逆走、あおり運転や悪質な幅寄せのように他人を妨害する運転などが該当します。
傷害罪、傷害致死罪 刑法204、205条
交通事故で相手にケガをさせたり、死亡させたりした場合に適用される罪。傷害罪が成立するには故意であった必要があり、加害者が自動車をぶつけることで相手にケガをさせてやろうという意図をもっていたと認められた場合に適用されます。
運転過失建造物損壊罪 道路交通法116条
車の運転者が必要な注意を怠ったため、他人の建造物などを傷つけてしまった事故に適用される罪。駐車場に停車させているとき、アクセルとブレーキを踏み誤り、建物に突っ込んでしまったケースなどが当てはまります。
緊急措置義務違反(ひき逃げ) 道路交通法117条
いわゆるひき逃げといわれる交通事故です。事故を起こしたとき、道路交通法第72条に定められている被害者の救護義務を果たさなかった場合に適用されます。
飲酒運転 道路交通法117条の2、2の2
お酒を飲んだ状態で運転すると飲酒運転として処罰されます。道路交通法65条には「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められています。呼気の中からアルコールが検出される状態は酒気帯び運転、明らかに酔っていると見られるときは酒酔い運転になります。
通報義務違反 道路交通法119条の10
事故が起きたとき警察に通報せずに済ませた場合に適用されます。道路交通法72条に定められている通報義務違反となり、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
無免許運転 道路交通第117条の2の2
免許をもたない状態で運転すると無免許運転となります。3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
民事責任
民事責任は、交通事故の加害者が相手に与えた損害を賠償する責任です。
交通事故の損害は自動車などが破損する物損と被害者にケガなどをさせる人身損害の2種類に分けられています。民法709条では故意または過失により他人の権利や法律上の利益を侵害した場合には損害を賠償する責任を負うとされており、人身事故にも物損事故に適用されます。

| 物損 | 車の修理代、代車使用料など。 |
|---|---|
| 人身(被害者がケガをした場合) | 治療費や通院費、慰謝料、休業損害(事故で仕事を休んだことへの補償)、後遺障害慰謝料(事故で後遺症が残った場合の慰謝料)、後遺障害逸失利益(後遺症が残ったことで将来得られるはずの収入が入らなくなったことへの補償)など。 |
| 人身(被害者が死亡した場合) | 死亡慰謝料、死亡逸失利益(被害者が生きていれば将来得られたであろう利益に対する補償)、葬儀費用など。 |
損害賠償の金額は被害者側との示談交渉で決められ、両者が合意に達しなかった場合は裁判になります。任意の自動車保険に加入していれば、相手との交渉は保険会社に示談代理で行ってもらえるため、通常、加害者自身が相手と直接交渉する機会は多くありません。
行政責任
交通事故の加害者が、運転免許の取り消しや停止といった、自動車の運転に関する行政上の責任を問われるのが行政責任です。
運転免許は交通違反を犯すごとに決められた点数がついていき、過去3年間の違反点数が一定になると処罰される点数制がとられています。以前の違反がゼロの場合、点数が6点になると免停、15点以上で免許取り消しになります。
交通事故と付加点数および処分
| 被害者のケガの度合い | 加害者の過失の度合い | 付加点数 | 処分内容 |
|---|---|---|---|
| 治療期間15日未満 | 加害者の不注意 | 3点 | |
| それ以外 | 2点 | ||
| 治療期間15日以上 30日未満 | 加害者の不注意 | 6点 | 30日の免許停止 |
| それ以外 | 4点 | ||
| 30日以上3か月未満 | 加害者の不注意 | 9点 | 免許停止60日 |
| それ以外 | 6点 | 免許停止30日 | |
| 3か月以上または後遺症が残った場合 | 加害者の不注意 | 13点 | 免許停止90日 |
| それ以外 | 9点 | 免許停止60日 |
| 加害者の過失の度合い | 付加点数 | 処分内容 |
|---|---|---|
| 加害者の不注意 | 20点 | 免許取り消し |
| それ以外 | 13点 | 免許停止90日 |
相手の症状が重くなるほど免許停止期間も長くなります。被害者のケガの度合いが2週間(15日)を越える場合は6点で一発免停になります。酒気帯び運転など故意の悪質な違反の場合は15点以上になり、一発免許取り消しになることもあります。
加害者が弁護士に相談するほうがいいケース
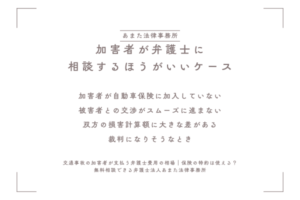
交通事故の内容や加害者の状況により、弁護士に相談するほうがいい場合は多いです。
交通事故では加害者が任意保険に加入していれば、保険会社が代理で示談交渉などを進めてくれるため、弁護士に相談しなくても大丈夫なようにも思われます。弁護士費用がかかるのもデメリットでしょう。
しかし、加害者には、刑事・民事・行政と多くの重い責任がかかってしまいます。任意保険に加入していないケースや、被害者との示談交渉がうまく進まないトラブルが発生しているケースなどでは、弁護士の力を借りるのがおすすめです。
加害者が自動車保険に加入していない
交通事故の加害者が自賠責保険にしか加入していない場合には、弁護士に相談するのが良いでしょう。
通常、相手方との示談交渉は保険会社が行ってくれますが、任意保険に加入していないと加害者自身が相手と話し合わなければならないためです。

被害者との交渉がスムーズに進まない
被害者との交渉がスムーズに進まないときは、弁護士に相談すると早期解決できやすくなります。
被害者は事故によって肉体的・精神的に大きな苦痛を負っています。加害者に対して感情的になり、強い怒りなどをぶつけてくることがあります。冷静な話し合いになりにくく、交渉がこじれて長引くことも考えられます。
示談が成立しないうちは、どれくらいの損害賠償を支払うかもわからないため、示談交渉の長期化は加害者にとっても大きな負担になります。
双方の損害計算額に大きな差がある
交通事故の加害者側と被害者側で算定した損害賠償の金額に大きな開きがあるときは、弁護士への相談を考えるのが良いでしょう。
交通事故の加害者が支払うべき損害賠償の種類は多岐にわたります。計算方法は複雑で法律知識も必要になります。ある程度の相場はあるものの、事故の状況や双方の過失割合などによっても変わってしまい、正確な損害賠償額を計算するのは非常に難しいのが現状です。
被害者側はより多くの賠償金をもらいたいと思うものですし、加害者側は逆に少しでも払う額を減らそうと考えます。結果、それぞれの算定額に大きな開きが生じる事態は珍しくありません。どちらも主張を譲らなければ、当事者間の話し合いが平行線のまま決着を付けるのは難しいでしょう。示談交渉の長期化が予想されます。

裁判になりそうなとき
交通事故の示談交渉で合意が得られず民事裁判になりそうならば、弁護士に依頼するようにしましょう。
裁判には複雑な手続きを伴い専門的な知識も必要とされるため、一般の方が対応するのは難しいです。また、刑事上の責任も問われる事故の場合も刑事裁判では弁護についてくれる人が必要になるため弁護士へ依頼を検討すべきといえます。
加害者が弁護士に相談するメリット
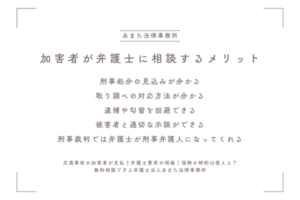
交通事故の加害者が、弁護士に対応を依頼すると、いくつものメリットを得られます。
自分にどうのような処分が下るのがわかり、適切な対処法を教えてくれます。また示談交渉をスムーズに進められるのも、弁護士の強みです。
刑事処分の見込みが分かる
交通事故で刑事責任を問われた場合、弁護士に相談すると自分下される処分のがどのくらいになるのか、見込みがつけられるようになります。
弁護士であれば、これまでの経験や判例からあなたの事故がどれくらいの処分になるのかわかります。
逮捕されるか、有罪になるかどうかや刑罰などはどれくらいになるのか、といったことが分かれば、今後の方針や生活の見通しなどもつきやすくなります。もし、まだ発覚していない事故であれば、自首をして刑罰が軽くなることもあります。

取り調べの対応方法が分かる
弁護士にアドバイスを受けることで、交通事故後の警察・検察の取り調べ(事情聴取)にどのように対応すればいいかが分かります。
多くの人にとって警察の取り調べを受けるのは初めての経験になるでしょうし、場の雰囲気に流されて、追及されるまま事実と異なることを言ってしまう可能性もあります。しかし、そうした加害者に不利な証言も調書に書かれてしまえば正式な証拠として裁判で有効になります。
供述調書の内容は一度署名してしまうと後から覆すことは困難なため、取り調べの段階から慎重な対応が求められます。取り調べに当たっては、弁護士からアドバイスを受けることが望ましいでしょう。
逮捕や勾留を回避できる
弁護士に依頼することで加害者が刑事責任を問われるとき、逮捕や勾留などを回避できるようになります。
相手が死亡するような重大な交通事故を起こすと、加害者は警察に逮捕されたり勾留(逮捕後の刑事施設への拘禁)されて身柄を拘束されてしまう可能性があります。しかし、弁護士に依頼すれば、勾留しないよう検察官や裁判官への申し入れや決定後の準抗告などを行ってもらえます。
準抗告とは、勾留の決定に対する裁判所への不服申し立て手続きで、認められれば釈放されます。逮捕前であれば、逮捕を防止するための弁護活動をしてもらうことも可能です。交通事故の加害者になってしまい逮捕されないか悩んでいるならば、弁護士に相談してみると良いでしょう。
被害者と適切な示談ができる
弁護士に依頼することで、交通事故の被害者と適切な示談ができるようになります。早期に示談ができれば、加害者が刑事責任を問われている場合に罪が軽くなる可能性があります。交通事故の刑事裁判においては、量刑の判断で加害者と示談が成立しているかどうかが重視されるためです。
示談書や刑事処罰を求めないとする被害者からの嘆願書を裁判所に提出することで、相手側の処罰感情も緩和されている点が考慮されるようになります。結果として、加害者が不起訴処分になったり、起訴されたとしても刑が軽くなったりすることがあります。
交通事故で刑事責任を問われると、前科がつくことを気にされる方もいるでしょう。警察による事情聴取や捜査を受けても、前科がつくことはありませんので安心してください。逮捕されると逮捕歴は残りますが、前科とは異なります。前科がつくのは起訴され裁判で有罪判決が出た場合です。不起訴・不送致には前科がつくのを防止する効果もあり、そのためにも、刑事裁判への対応では被害者との早期の示談成立が必要となります。
刑事裁判では弁護士が刑事弁護人になってくれる
交通事故の被害者との示談が思うようにいかず、最終的に刑事裁判での起訴が行われてしまっても、弁護士に依頼していれば刑事弁護人として裁判でも刑事弁護人として弁護を行ってもらえます。
刑事裁判では国に弁護士をつけてもらえる国選弁護人の制度もあるため、加害者が弁護士なしで裁判に臨まなければならない心配はありません。しかし、これまで示談交渉を行い事故の詳しい事情を知っている弁護士がついてくれたほう、が刑事裁判も有利に進む可能性が高いです。
裁判での国選弁護人は自由に選べませんし、自分に合った弁護士のほうが納得のいく弁護活動が期待できるでしょう。

加害者でも弁護士特約は使えるのか
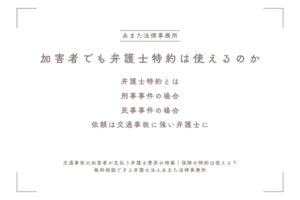
交通事故の加害者が支払う弁護士費用はかなりの金額になります。弁護士に依頼したいけれど、費用が払えないからと躊躇する方もいるかもしれません。
任意保険には弁護士費用を補償してもらえる弁護士特約がついていることがあります。加害者でも、弁護士特約を使える可能性はあります。
弁護士特約とは
弁護士特約とは、自動車保険などの任意保険に付帯するサービスの1種です。交通事故の対応で必要になった弁護士費用を、保険会社に負担してもらうこができます。相談料10万円、弁護士費用300万円まで補償してもらえるのが一般的です。
一部の医療保険やクレジットカードについていることもあり、家族が加入している保険のものでも利用できることがあります。弁護士特約が使えるかは補償内容により変わってきます。
刑事事件の場合
交通事故の刑事事件では、一般的に弁護士特約を利用することはできません。弁護士特約は基本的に民事事件を対象にしており、刑事事件での弁護費用は補償範囲外になっているというデメリットがあります。
しかし、最近では、刑事裁判も対象にした弁護士特約を販売している保険会社はあります。加入している保険によっては利用可能かもしれませんので、約款をよく確認してみましょう。もしわからないことがあれば、保険会社に問い合わせてみてください。弁護士費用がかかるというデメリットを、感じずに済む可能性があります。
民事事件の場合
民事事件では交通事故の加害者であっても、弁護士特約を利用できる可能性があります。弁護士特約は損害賠償を請求するためのものですから、加害者では無理だと思われている方もいるかもしれません。しかし民事においては加害者でも特約を使える可能性があります。
弁護士費用を負担してもらえるかのポイントは、被害者に損害賠償が請求できるかどうかです。
交通事故では過失割合を10として、3:7や4:6など被害者と加害者の双方に割り振り、過失の少ない方が被害者とされています。つまり、被害者であっても全く落ち度がないわけではないのです。
交通事故ではお互いに損害が出ることが多いです。相手側にも過失が認定されると、加害者側にも損害賠償請求の権利があります。とはいっても、お互いが同時に損害賠償を請求することはなく、加害者の請求分は被害者の示談金から差し引かれるのが一般的です。加害者が一方的に請求を受けるわけではないため、弁護士特約の利用対象になるわけです。
ただ、どのような事故でも弁護士特約の対象になることはありません。例えば、後方からの追突事故のように加害者の過失が100%になる事故では利用できません。そのほか、飲酒運転や無免許運転など悪質な行為・過失によって起きた事故は弁護士特約の補償範囲外になるため利用不可です。

依頼は交通事故に強い弁護士に
依頼する際の注意点として、交通事故案件に強い弁護士を選ぶようにしてください。
弁護士特約を利用しても保険会社から特定の弁護士を指定されることはありません。通常の場合と同じように自由に弁護士を選べます。
示談交渉には専門的な知識や経験が求められるため、交通事故の案件に精通している弁護士を選んだほうがスムーズに進むと考えられます。また、交通事故に強い弁護士のなかでも、加害者の弁護の実績があり得意としているかのチェックも大切になります。
交通事故を主として扱っている弁護士事務所は多数ありますが、その多くは被害者向きで加害者の依頼は引き受けていないところもあります。
交通事故の加害者でも弁護士費用は節約できる
交通事故の加害者でも弁護士特約を利用でき、弁護士費用を節約できる可能性はあります。
交通事故では刑事・民事で責任を問われますが、弁護士に依頼しておくと示談交渉をスムーズに進められたり、刑事事件で弁護活動をしてもらえるなどの多くのメリットがあります。
弁護士費用が高額になるデメリットがあるため躊躇する方もいるかもしれませんが、弁護士特約が利用できれば費用面の負担を大きく減らせます。事故を起こしてしまったら、保険会社に弁護士特約が付いているか、利用できるかを聞いてみてください。
また無料相談を行っている事務所はたくさんあります。交通事故の加害者になってしまったら、まずは問い合わせてみるのが良いでしょう。交通事故の実績がある弁護士なら頼もしい味方になってくれ安心できます。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ