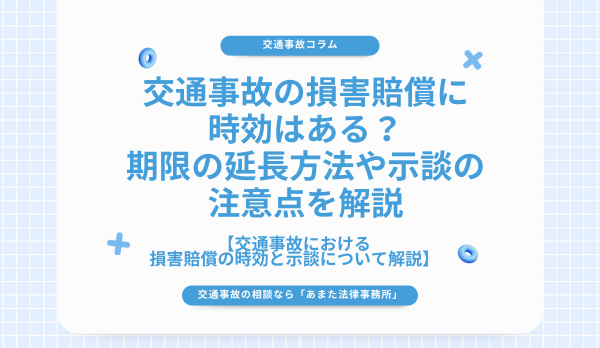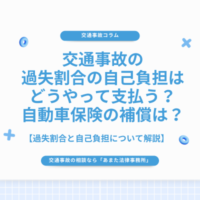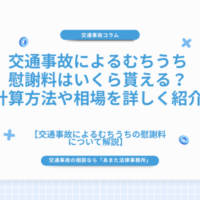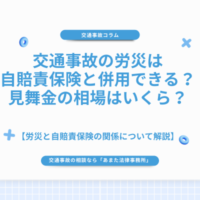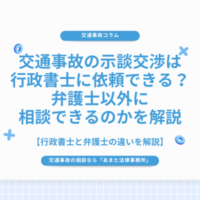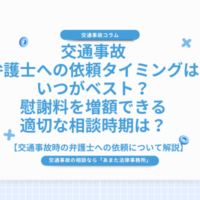交通事故の被害者から加害者に対する損害賠償には時効があります。
物損事故の時効は3年、人身事故の時効は5年。
事故に遭っても放っておくと請求自体ができなくなる危険性があります。

執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
交通事故の損害賠償請求権には時効がある
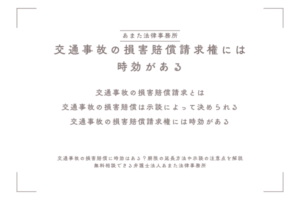
交通事故の損害賠償請求権には時効が存在し、なにもせずに一定期間が経過すると時効によって加害者への請求が不可能になってしまいます。請求漏れで損をしないためにも、交通事故における損害賠償と時効の関係を確認していきましょう。
交通事故の損害賠償請求とは
交通事故でケガをしたり、車が壊れた場合、被害者は加害者に対して損害賠償を請求できます。これは「損害賠償請求権」と呼ばれ、加害者にお金で被害の補償を求める権利のこと。
そもそも、人にケガをさせたり物を壊したりした場合には、その損害を補償する義務があります。
民法709条では、「故意や過失により他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者はそれによって生じる損害を賠償する責任(債務)を負う」と定められています。これを金銭によって支払うのが損害賠償です。
実際に損害賠償の対象になるものには、次のようなものがあります。
治療費や通院費(ケガをした場合)
修理費や買い替え費用(車が壊れた場合)
休業損害(働けなくなった場合の収入補償)
慰謝料(ケガや事故による精神的な苦痛)
交通事故の損害賠償は示談で決められる
交通事故の損害賠償額は、示談により決められます。
示談とは法律上の紛争を裁判によらず、当事者の話し合いと合意によって解決する手段のこと。事故の責任や賠償金の金額について、お互いが納得できれば、裁判に頼らなくても損害賠償を受け取ることができます。
交通事故の損害賠償請求では、被害者は加害者側が加入している任意保険会社を相手に示談交渉を行います。それぞれが納得した結果になり示談が成立すると、被害者は示談金として慰謝料を含む損害賠償の支払いを受けられるようになります。
軽いケガだけの事故であれば、治療が終わるまでに必要な費用が明らかになりやすいため、示談交渉は比較的早く進みます。通常、2ヶ月ほどで示談が成立するケースが多いです。
一方で、死亡事故や重い後遺症(高次脳機能障害など)が残った事故では、被害の内容が複雑になるため、交渉が長引き、示談成立までに1年以上かかることもあります。
なお、示談には「いつまでに終わらせなければならない」といった期限は法律上定められていません。ですが、いつまでも放置していると、損害賠償を請求する権利が「時効」によって消えてしまうリスクがあります。
ただし、示談は一度成立すると後から覆すのが困難なため、交渉には慎重さが求められます。
交通事故の損害賠償請求権には時効がある
交通事故の損害賠償請求権には、消滅時効があります。一定期間、損害賠償の請求権利を行使しないと、請求できなくなってしまいます。
被害者だからといって永遠に請求権をもつわけではなく、事故から何年か過ぎると賠償金を請求する権利自体を失ってしまうのです。
交通事故における損害賠償請求権の時効は、物損、人身と事故の種類で違います。
- 物損事故:被害者が交通事故の損害および加害者を知ったときの翌日から3年間
(民法724条1号) - 人身事故:被害者が交通事故の損害および加害者を知ったときの翌日から5年間
(民法724条の2)
以前は物損、人身事故とも3年だったのですが、2020年4月の改正民法施行に伴い、人身事故では時効期間が長くなりました(自賠責保険への請求時はのぞく)。
2020年4月1日以前に起きた事故でも、改正前に時効が成立していないものに関しては、改正後の法律が適用されます。改正前に時効が成立してしまっているものについては、以前の通り3年のままで延長されることはありません。
また、不法行為が起きたときの翌日より20年が経過した場合も時効が成立し、損害賠償請求はできなくなります(民法724条2号)。
損害賠償請求の時効の起算日はいつ?
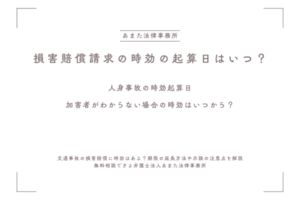
交通事故における損害賠償請求で注意すべき点なのが、時効期間のカウントがいつからはじまるかです。民法724条では、消滅時効が開始するのは「被害者が損害および加害者を知ったときの翌日」からとされています。

人身事故の時効起算日
人身事故の時効起算日は、ケガが完治した日、または医師によって後遺症が残ると診断を受けた日(病状固定日)の翌日から開始されるケースが一般的です。基本的には、長い間通院する必要があるなど、治療に時間がかかるだけ時効が開始となる日も伸びていくことになります。
事故当日からではない理由は、事故直後には治療費や今後の補償がどれくらいかかるか計算できず、正確な損害金額がわからないからです。むちうちといった軽傷から骨折など重傷な怪我まで、症状はさまざまです。また後遺症は残るのか、後遺症が残ったとしたらどの等級になるのかといった問題もあり、ケガの詳細が判明しないと賠償金額を算定するのは難しいのです。
被害者が亡くなってしまう死亡事故では本人が死亡した時点で損害がわかるので死亡日の翌日から時効期間がはじまります。ただ、死亡事故は翌日に時効がはじまるケースが多いのですが、被害者が入院してから死亡したときなど時効の開始が遅くなるケースもあります。
事故から時間が経ってから当初は予想できなかったような後遺症が発生した場合は、これまでの後遺症に関する損害分とは別に時効は進行します。示談が成立した後でも、新たに損害賠償金を請求できるとした判決事例もあります。しかし、時間が過ぎるほど事故との因果関係を証明するのが難しい状況になりますので、必ずしも慰謝料などの賠償金を受け取れるとは限りません。
加害者がわからない場合の時効はいつから?
ひき逃げや当て逃げのように、犯人がわからない事故では、加害者が判明した日の翌日から時効がスタートします。
しかし民法には不法行為から20年が経過すると時効が成立する決まりがあり、犯人が不明のままでも20年経過すると時効になります。ひき逃げ事故等では、「加害者が明らかになった日から物損なら3年、人身(傷害)なら5年」または「事故の翌日から20年」のうち、どちらか早いほうが適用されます。
損害賠償の時効は起算日が複雑な面があります。何の対応もしないでいると、知らないうちに時効間近になっていたという事例は珍しくありません。損害賠償請求についての知識がないから、加害者がわからないからと放置していると、気が付かないうちに時効を迎えてしまう恐れがあります。
損害賠償請求権の時効を延長させる方法
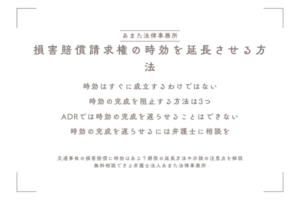
損害賠償の請求権は決められた手続きを行えば、時効を阻止したり完成を遅らせたりすることができます。
交通事故の示談交渉は予想以上に時間がかかってしまい、時効が近づいてくることもあります。損害賠償請求権が消滅しそうになると焦るかもしれませんが、落ち着いて対処することが重要です。
時効を延長させる方法は、以下の通り。
- 裁判を起こす
- 強制執行などの申立を実施する
- 加害者に承認してもらう

時効はすぐに成立するわけではない
損害賠償請求権の時効は、すぐに成立するわけではありません。時効成立には、被害者による「時効の援用(民法145条)」が必要です。
被害者が「時効が成立した」と主張しない限りは、期間が経過してもすぐに時効は完成しないのです。
交通事故の示談交渉では直接加害者と話し合うのではなく、相手方の保険会社と交渉するケースがほとんどです。保険会社には被害者に対して事故の損害を補償する社会的な責務もあるので、時効が成立したとたんに慰謝料などの保険金を打ち切りとする判断はしないと考えられます。諦めずに対処すれば、時効を延長して成立を阻止することは可能です。
時効の完成を阻止する方法は3つ
損害賠償の時効成立を阻止する方法は主に3つあります。
裁判などを起こす (民法147条)
加害者に対して、裁判所に訴訟を提起する、支払いの督促をするといった裁判上の請求を実行すると、手続きが終了するまで時効の完成を猶予できます。和解や民事調停、破産手続きへの参加も、同様に時効の完成を遅らせる可能性が出てくる方法です。
裁判で確定判決または判決と同一の効力をもつもの(和解調書、調停調書など)が出されると、時効の更新が行われます。これまでの時効期間は無効となり、新しく10年の時効が開始されます(民法169条1項)。もしも判決等で権利が確定することなく手続きが終了してしまっても、時効期間は6か月猶予されます。
また、時効が目前に迫っており、訴訟を起こす時間もないのであれば、加害者への催告を実施する方法があります。一時的に時効の完成を阻止できるようになります。
裁判を起こすと弁護士が必要となり、弁護士費用がかかります。交通事故裁判の弁護士費用は、相談料や着手金、成功報酬などで安いと相場は20万~30万円程度です。ただ高いと100万円を超えるケースもあり、担当する弁護士や事案によって異なります。
和解・調停について依頼するときも、同様に数十万円程度かかると考えておきましょう。支払い督促では裁判所に手数料などを支払い、必要になるのは数千円~数万円程度です。しかし必要な書類の作成を弁護士に依頼すると、数十万円の弁護士費用が必要になります。
交通事故の弁護士費用は、獲得した損害賠償金から支払うのが一般的です。また勝訴すれば費用の一部を、加害者に請求することも可能です。また、加入している自動車保険に弁護士特約がついていれば、保険会社が弁護士費用を負担してくれ金銭面での心配がなくなります。
強制執行などの申立を実施する(民法148条)
強制執行を行った場合にも時効の完成を中断できます。
裁判の結果が出たにもかかわら、相手側がお金を支払ってくれないとき、裁判所に申立を行います。担保権の実行や財産開示手続きにも同様の効力があります。
強制執行の申立が行われると、手続きが終了するまでの間は時効が猶予されます。終了した時点で時効が更新されて、一から新たな時効期間のカウントがスタートします。申立が取り下げや法律の規定に従わないことで取り消しとなり終了した場合は、終了時から6か月のみ時効完成の期間が延長されます。
裁判所に納める手数料として1万~2万円程度かかります。手続きを弁護士に依頼するなら、10万~30万円程度の弁護士費用がさらに必要になります。費用の相場は担保権実行や財産開示に関しても同様です。
加害者に承認してもらう(民法152条1項)
承認とは、加害者が被害者のもつ損害賠償請求権の存在を認めることをいいます。加害者自身が損害賠償請求を認めたわけですから、承認が行われると時効はその時点で一旦リセットとなり、更新されて新たに時効期間が開始されます。
法律上、承認の方法や手続きなどは定まっておらず、明確な発言によってなされるものだけでなく、黙示でも問題ないとされています。時効の成立によって利益を受ける者(加害者)が行う必要がありますが、承認によって時効の更新効果を発生させる意思はなくてもかまいません。
具体的に承認にあたる行為としては、
- 被害者への支払い猶予の申し入れ
- 損害賠償の一部の弁済
などがあります。
承認に関しては制度的にきまった手続きがあるわけではないのですが、支払い猶予の申し入れや一部弁済といった加害者の行動が必要になります。また、加害者を説得するため弁護士を利用する場合は、他の手続きと同様20万~30万円程度の弁護士費用を用意しなければなりません。
ADRでは時効の完成を遅らせることはできない
ADR(裁判外紛争解決手続き)を利用しても、損害賠償請求の時効を止めたり遅らせたりすることはできません。
時効が迫っているときは、別の方法を取る必要があります。
ADRは様々な法律上の紛争を裁判に頼らず解決するための機関で、原則として無料で利用できるので上記の方法のように費用負担がありません。しかし、ADRは法的手続きに含まれていないため、利用しても時効の進行は止まりません。
時効の完成を遅らせるには弁護士に相談を
自分では交通事故の示談交渉が上手く進められなく時効が近づいてきているのなら、弁護士といった法律の知識が豊富な専門家にアドバイスをもらうのがよいでしょう。
弁護士に依頼すれば、示談交渉の期間や後遺障害認定の申請にかかる期間を短縮できます。また早期解決が見込めるだけでなく、万一、時効が迫っているタイミングでも、時効の完成を遅らせるための最適な方法を提示してもらえます。
時効を更新するための手続きにはいずれも費用がかかります。弁護士も費用はかかりますが、書類の作成など複雑な手続きを代行してもらえます。交通事故に関する法律にも詳しいですから、適切な手段で時効を延長できるようになります。

まとめ:交通事故の損賠賠償に時効はあるが延長できる
交通事故における損害賠償請求権には時効がありますが、裁判手続きや相手方の承認など決められた方法をとれば、時効の完成を遅らせるだけでなく、いったんリセットし事項を更新することが可能です。
時効の時期が迫っているなど時効に不安がある、時効の猶予や更新に関して詳しく知りたい、といったお悩みを解決したいなら、交通事故の解決実績が豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ