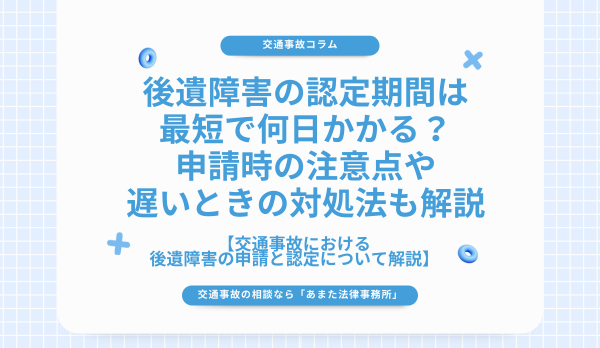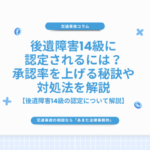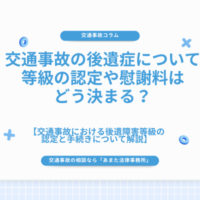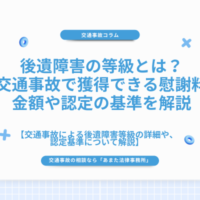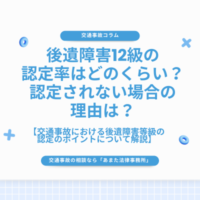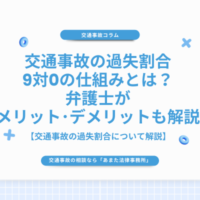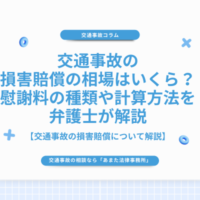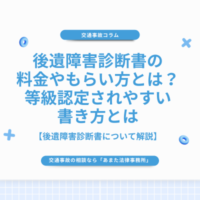後遺障害の等級が認定されるまでの期間は、最短でも1か月ほどかかります。
多くのケースでは60日(2か月)以内に認定されてはいますが、事故や負ったケガの状況によっては90日(3か月)以上、長ければ1年ほどの期間が経っても結果が出ないこともあります。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
後遺障害が認定されるまでの期間は最短で何日かかる?

後遺障害等級が認定されるまでの期間は、最短でも1か月程度はかかると思っておきましょう。
最短だと1ヶ月程度で認定される
後遺障害に申請後、早ければ1ヶ月程度で等級認定の結果が通知されます。
損害保険料率算出機構が公表している統計データによると、73.7%の事案は30日以内に、約90%が60日以内に調査が完了するとされています。
| 認定期間 | 割合 |
|---|---|
| 30日以内 | 73.7% |
| 31日~60日 | 14.0% |
| 61日~90日 | 6.7% |
| 90日以上 | 5.6% |
(参考:損害保険料率算出機構「2023年度自動車保険の概況」)
ただし、高次脳機能障害が残った事例では、気が遠くなるほど長い経過観察を要します。高次脳機能障害は労働力の低下だけでなく、日常生活にも支障をきたしやすい後遺障害です。しかし見た目では障害の度合いがわかりにくかったり、時間が経過することで症状が軽減する傾向もあることから、高次脳機能障害の審査は、6ヶ月以上かかることも少なくありません。
後遺障害が最短で認定されない理由
後遺障害は最短だと申請から1か月以内に結果が通知されます。ですが、事故状況が複雑であったり、複数の部位にケガがあるなど受傷の状況から等級の判定が困難であったりすると、調査に3ヶ月以上と長期間かかることがあります。
また、任意保険会社が申請手続きを後回しにしていたり、医師の治療情報照会が遅れたりしているのも、等級認定が遅くなる要因になります。
後遺障害診断書を作成した医師に内容を照会することがありますが、医師と連絡がつかないことも起こります。多忙な医師だと長いこと確認ができず、後遺障害の認定に時間がかかってしまうことになります。
そして保険会社は何件もの事案を抱えているため、どうしても処理が遅れる状況があります。申請から2ヶ月以上経過しても何の音沙汰もないときは、どのくらい進行しているのか、保険会社に問い合わせてみてください。
後遺障害に最短で認定されたないなら被害者請求がおすすめ
最短での後遺障害認定を希望するなら、被害者請求がおすすめです。
被害者請求では症状を正確に伝えられるため、事前認定よりもスムーズに審査を進められる可能性があります。
さらに認定までの期間を短縮する有効手段が、弁護士への依頼です。交通事故による後遺障害の申請に慣れている弁護士であれば、スピーディーに書類集めなどの手続きを進めてくれます。
事前認定では相手方の任意保険会社に申請手続きを一任しますので、手続きを後回しにされる、書類の漏れといったトラブルが生じるといったおそれが出てきます。その結果、被害者請求よりも事前認定は認定まで時間がかかってしまうでしょう。
交通事故による後遺障害とは?
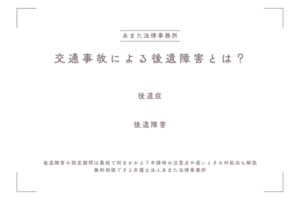
交通事故に遭ったために、残ってしまった障害を「後遺障害」といいます。
一般的に「後遺症」と「後遺障害」はほとんど同じ意味で使われていますが、実際のところ大きな違いがあります。
後遺障害は労働力の低下が認められる状態であると申請できます。よって、すべての後遺症が後遺障害に認定されるわけではありません。
後遺症
後遺症は怪我や病気を治療したにもかかわらず、将来的に完治するの見込みがない機能障害や神経症状などのことを指します。
交通事故の後遺症の具体例として主にあげられるのがむちうちです。むちうちは交通事故で首や背中などに強い衝撃が加わったため、背中、肩、首、手足に痛みや痺れが残る症状です。
後遺障害
後遺障害は後遺症の中でも、交通事故が原因であることが医学的に証明されるとともに、労働能力の低下(あるいは喪失)が認められる必要があります。そして後遺症の程度が、自賠責保険の等級に該当するものになります。
交通事故などが原因で生じた高次脳機能障害、手足の切断、関節の可動域の制限など、様々な症状が後遺障害として認定されます。なお、むちうち症などの神経障害でも、後遺障害の等級に認定される事例は多々あります。
むちうちは後遺障害の14級9号に認定されることがほとんどですが、症状によっては12級の基準に該当することもあります。
後遺障害の認定には申請→審査が必要
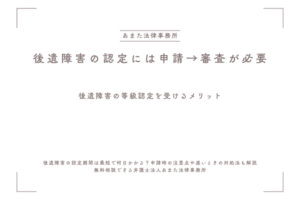
交通事故で残った後遺症が自賠責保険が定める基準に当てはまれば、後遺障害に認定されます。後遺障害の等級は障害の部位や重症度別に1〜14級に分類されており、1級に近づくほど重い症状が残っているとみなされます。
後遺障害等級は自動的に認定されるわけではなく、所定の機関に申請を行い審査を受ける必要があります。
審査は基本的に提出された複数の書類で行われ、自賠責の認定基準を満たしていれば等級が認定されます。書類の内容が不適切だったり不備があったりすると、認定されるまで長い期間がかかる、低い等級に認定される、後遺障害には当てはまらないといった不本意な結果をもたらします。
特に重要となるのは、医師が作成する後遺障害診断書とレントゲンやMRIなどの画像検査の結果です。
医師には症状を詳細に伝え、診断書を作成してもらいましょう。加えて誰が見ても障害が分かる画像があれば、審査に有利に働きます。逆に、画像による証拠を提示できないと、後遺障害の審査では不利になってしまいますので注意しましょう。
後遺障害の等級認定を受けるメリット
後遺障害として認定されると、慰謝料などの賠償金を受け取れるといった金銭的なメリットが生じます。
加害者に対して賠償金を請求できる
後遺障害等級が認定されると、加害者に対して「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を請求できるようになります。
「慰謝料」とは、加害者に与えられた精神的苦痛を慰謝してもらうための賠償金です。交通事故で後遺障害を負うと、被害者は以前と同じような生活を送ることができなくなるため、これらの苦痛や不安に対する賠償として「後遺障害慰謝料」を請求できるようになります。
逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下または喪失していなければ、被害者が将来得られるはずだった収入のことです。
交通事故でケガを負ったために会社を休む退職する、自営業者であれば休業するといった事態になれば、収入が減ってしまいますよね。交通事故にあわなければ将来の収入が減少することはないため、将来の収入の減少した分を加害者に対して請求できるのです。

自賠責保険から保険金を先払いで受け取れる
後遺障害と認定されると相手方保険会社と示談を始める前に、自賠責保険から一定の保険金を受け取れるようになります。
被害者請求での申請が必須との注意点はありますが、14級であれば75万円(支払限度額)、12級であれば224万円(支払限度額)を先払いしてもらえます。
交通事故の保険金は通常、示談が成立するまではを受け取ることはできません。示談では揉めることも珍しくなく、決着がつくまで長期間かかることもあります。ケガの治療費や入院費といった費用は加害者側に請求できるといっても、いったんは自腹で支払いしておくことになります。医療機関からの請求は高額になることは珍しくなく、被害者にとっては金銭的な負担が大きいといえるでしょう。しかしいくらかでも先に支払ってもらえれば、治療費などに保険金を充てられます。
保険金を増額して請求できる
後遺障害の等級が認定されると、自身が加入している保険会社から保険金を支払ってもらえる可能性があります。例えば、被害者の方が搭乗者傷害保険や県民共済に加入している場合、認定を受けることで後遺障害に関する保険金や共済金を請求できることがあります。
後遺障害に認定されなければ相手方の自賠責保険や任意保険会社からしか受け取れなかったのですから、保険金を増額して獲得できる能性があるのです。
後遺障害の等級認定の流れ
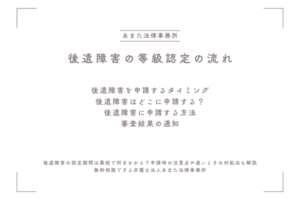
後遺障害の等級認定の申請手続きの流れを解説します。いつ、どこに申請するのか、どのような申請方法があるのかを確認しておきましょう。
後遺障害を申請するタイミング
後遺障害へ申請するタイミングは、「症状固定」の後になります。
症状固定とは「医学的に認められた治療を施しても、これ以上症状が改善されない状態」を指します。原則として医師が判断します。
症状固定と診断される期間は打撲が3か月程度、むちうちが6か月程度となるのが一般的です。骨折だと6ヶ月〜1年6ヶ月かかることもあります。ただし、個人差がありますので、あくまでも目安の期間と考えてください。「もう治った」と自己判断をせずに、医師の診断に任せるようにしましょう。
後遺障害はどこに申請する?
後遺障害は相手方の自賠責保険に申請します。
自賠責保険に提出した各種書類は、「損害保険料率算出機構」に送付され審査が行われます。損害保険料率算出機構は、損害保険料率算出団体に関する法律に基づいて設立された法人で、任意保険会社等から独立して等級認定の調査を行う機関です。
後遺障害に申請する方法
後遺障害等級の申請手続きには、「事前認定」と「被害者請求」と2つの種類があります。それぞれのメリットとデメリットを確認し、申請方法を決定してください。
事前認定
加害者側の任意保険会社を介して、自賠責保険に後遺障害を申請する方法です。
・手間がかからない
・資料の収集などにかかる費用を節約できる
・適切な等級が認定されにくくなる
・自賠責から保険金を先払いで受けられなくなる
事前認定では医師に書いてもらった後遺障害診断書を、加害者側の任意保険会社に提出します。その後、相手方保険会社が申請手続きを代わりに行ってくれるため、被害者側は手間や負担がかからないのが特徴です。
保険会社は自社の支払う保険金を、最小限に抑えようとするものです。加害者側の過失を低く見せるような書類を提示されることも考えられ、被害者にはおすすめの申請方法ではありません。
被害者請求
被害者本人が直接相手方の自賠責保険に、後遺障害の申請を行う方法です。
・手続きの透明性を確保できる
・適切な資料を提出できれば等級が認定されやすくなる
・示談成立前に自賠責から保険金を受け取れる
・手間や時間がかかる
・資料を集める際に費用がかかる
・等級認定の知識が必要になる
被害者請求では、被害者自身が後遺障害の申請に必要な書類を全て揃える必要があります。そのため、事前認定よりも申請手続きにかける時間や労力が大きくなってしまいます。時間に余裕がある人でも面倒と感じるでしょうし、仕事や家事で多忙という人にとっては負担が大きいといえるでしょう。
一方で、当事者である被害者本人が書類を集めて提出するため、後遺障害の等級認定に有利な資料を選んで提出できるのが大きなメリットです。認定基準を満たす資料を提出できれば、短期間で認定される、適切な等級に認定されるといった状況が期待できます。

審査結果の通知
自賠責保険の損害保険料率算出機構による調査が終わると、後遺障害の等級認定または等級非該当の通知がなされます。被害者請求では自賠責保険から直接通知が届くのですが、事前認定では任意保険会社を経由して結果が通知されます。
後遺障害の認定期間を最短にするポイント
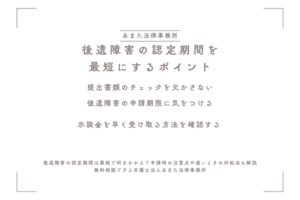
後遺障害は申請のポイントを押さえておくと、スムーズに審査が進み最短で認定されやすくなります。
提出書類のチェックを欠かさない
後遺障害は、提出資料に不備があると認められません。後遺障害診断書をはじめとする様々な資料は、事前にしっかりと確認してから提出するようにしましょう。
書類不備などで無駄に時間をかけたくないときは、弁護士に相談してチェックしてもらうのが良いでしょう。
書類の不備が起きる原因は、後遺障害についての詳細な知識を持っていない点があります。インターネットサイトや書籍を調べしっかり準備したつもりでも、短期間の独学では何かしらの見落としが出やすいのです。不備により何度もやり直すことになるなら、最初から法律の専門家である弁護士の力を借りてください。

後遺障害の申請期限に気をつける
後遺障害の認定申請には期限があり、期限を過ぎてしまうと申請ができなくなってしまいます。また申請している間も時効は進行しますので、認定結果が出る前に時効を迎えてしまう可能性もあります。
事前認定と被害者請求の期限
事前認定での後遺障害申請は、期限は設けられていません。いつ申請しても良いとされています。
被害者請求の時効は、症状固定時から3年間です。ただ、自賠責保険に対して「時効中断申請書」を差し入れると時効を中断することができます。書類を1枚提出するだけで良いので、時効が差し迫っているときは活用してください。
後遺障害の損害賠償請求の時効にも注意
後遺障害が認定されると加害者に対し損害賠償を請求できますが、請求権の時効にも注意しなければなりません。
後遺障害への申請は事前認定だと期限はありませんが、任意保険に対する損害賠償(保険金)の請求権には時効が定められています。
人身事故の損害賠償の請求権は3年~5年です。
- 2020年3月31日までに起こった事故:時効3年
- 2020年4月1日以降に起こった事故:時効5年
後遺障害の認定に時間がかかると、時効により賠償金が請求できないといった事態にもなりかねないでしょう。裁判中は時効がストップするのですが、示談中も時効は進行していきます。症状固定となったら、早めに後遺障害に申請するのがおすすめです。
示談金を早く受け取る方法を確認する
後遺障害に認定される前でも、「内払金」や「仮渡金」を請求すると示談成立前に賠償金の一部を前払いしてもらえる可能性があります。
相手方の保険会社から示談金(賠償金)を受け取れる時期は、基本的には示談が成立してからになります。ただし、示談交渉を開始するためには、後遺障害認定を完了していなければなりません。これでは、示談金を得られるまでにかなりの次官を要してしまうため、当面の治療費や生活費に困ってしまうでしょう。
そこで、少しでも経済的な負担を減らす手段として、内払金や仮渡金が有効になります。
内払金
示談が成立する前に、保険金の一部を内払金として支払ってもらえることがあります。
しかし、全ての任意保険会社が内払い対応をしている訳ではなく、確実にもらえるとは限りません。アテにしていたら、支払いしてもらえない保険会社だったということもあり得ます。内払いを希望するときは、事前に問い合わせをしておきましょう。
仮渡金
仮渡金は診断書を添付して自賠責保険に請求することで、示談金を受け取る前にまとまったお金を受け取れる制度です。加害者が加入している自賠責保険に対して、死亡事故は290万円、人身事故による傷害では程度に応じて5万円、20万円、40万円を請求できます。
なお、以前は自賠責保険にも内払い制度がありましたが、平成20年10月1日に廃止されています。示談交渉の前に自賠責保険に保険金の一部を請求したい場合は、仮渡金のを選択してください。
後遺障害の認定結果が出ないときの対処法
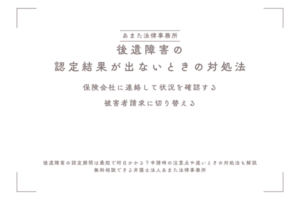
後遺障害の等級認定は申請してから2ヶ月ほどで結果が届くことがほとんどですが、中には認定の審査がなかなか進まないこともあります。なかなか認定結果が届かないときは、対処法がありますので試してみてください。
保険会社に連絡して状況を確認する
後遺障害の申請状況がどうなっているか、保険会社の担当者に問い合わせてみましょう。
後遺障害は事前認定で申請すると、認定手続きが遅くなりやすいといわれています。申請手続きを担当する任意保険会社は他にも多くの事故を取り扱っているため、優先順位が低いと判断されれば手続きを後回しにされることがよくあるためです。
また、任意保険会社としては保険金を支払う立場ですので、等級認定に有利な資料をきちんと収集してくれないこともあります。意図的に被害者側に不利になるような書類しか用意しない悪質な例もあります。その結果、申請手続きに長い期間かかってしまい、最悪のケースだと後遺障害に該当しないとの結果になることもあります。

被害者請求に切り替える
後遺障害を事前認定で申請したときは、被害者請求への切り替えを検討してください。
事前認定では任意保険会社が適切な資料を揃えられているとは限らないため、書類の不備などが生じると手続きに時間がかかります。もし、審査に通らなければ、せっかく申請に費やした時間が無駄になってしまいます。
自分で自賠責保険に直接申請する被害者請求では、適切な資料を送付することでスムーズに審査ができるようになります。被害者自身が資料を準備するのは非常に大変ですが、被害者請求に変更することで後遺障害認定までの期間を短縮できる可能性が高くなります。
後遺障害の認定についてまとめ
後遺障害に認定されるまでの期間は、最短でも1ヶ月、遅い場合は2〜3ヶ月程度かかります。
後遺障害の認定期間を短縮したい、最短で認定を得たいのであれば、書類を不備なく完璧に用意して被害者請求で申請するのがおすすめです。自分自身で必要な書類をすべて集めるのは難しいのが現状です。交通事故の案件に強い弁護士に相談しスピーディーに手続きを進めてもらいましょう。
また申請したけれどなかなか認定されない…というときも、弁護士にアドバイスを求めてください。豊富な経験から最適な対策を講じてくれますので、後遺障害の申請に関する悩みを解決できます。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ