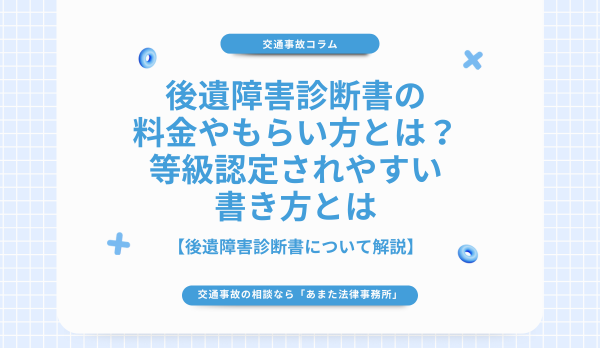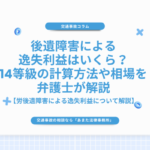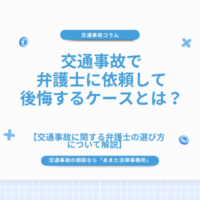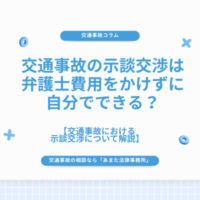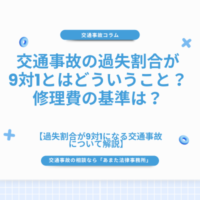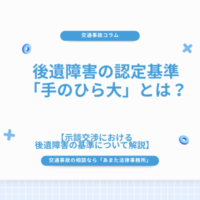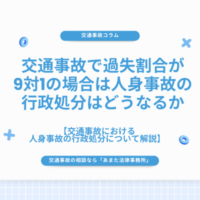後遺障害の認定を受けるには後遺障害診断書を用意しなければなりません。料金は医療機関により異なりますが、5,000円~10,000円程度が一般的です。また、診断書の内容により後遺障害が認定されなかったり、認定されても低い等級になってしまうことがあります。

執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
後遺障害診断書とは
後遺障害診断書は後遺障害の等級認定には必須になる書類です。正式名称は「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」と言います。
交通事故で後遺障害が残ると、被害者は加害者に対して後遺障害に関する「慰謝料」や「逸失利益」といった賠償金を請求できます。これらの賠償金を請求するためには「後遺障害等級」が認定されなければなりません。後遺障害を具体的に証明するための書類が後遺障害診断書なのです。
後遺障害診断書の書式は自賠責保険会社から取り寄せる方法と、インターネット上で<ダウンロードする方法の2つがあります。書式を手に入れたら医師に作成を依頼してください。
なお、業務中・通勤中の交通事故による後遺症は、労災認定を受けると後遺障害に関する労災保険を利用できます。ただし、労災の後遺障害は診断書の書式や提出先が異なる点に注意してください。厚生労働省のホームページから請求書(業務災害用・通勤災害用)や診断書をダウンロードし、所轄の労働基準監督署に提出することで等級認定へ申請できます。
後遺障害診断書に記載する事項
後遺障害診断書を作成はケガを治療している医師が行います。適正な後遺障害等級に認定してもうためにも、記入漏れや誤りがないように正確に記入してもらいましょう。
ちなみに、後遺障害診断書に秘匿性はなく封を切っても構いません。封をせずに渡す医療機関は多いですし不備がないか中身を確認しないとならないため、必然的に封は切ることになります。
①被害者の基本情報
被害者の氏名・性別・生年月日・年齢・住所・職業などの基本的な情報です。
②受傷年月日
交通事故にあった年月日です。むちうちのように事故の後から現れた症状であっても、事故当日の年月日を記入してください。
③症状固定日
医師が「症状固定」と判断した年月日です。症状固定とはケガや病気の治療を続けても、これ以上改善が見込めない状態のことを意味します。
④当院入院期間・通院期間
入院と通院していた期間です。後遺障害診断書を作成してもらう病院以外で入通院した期間は含まれません。
⑤傷病名
症状固定になった時点で残存していた傷病の名称です。正式な傷病名が記載されているか確認してください。交通事故の後遺症でよくみられる「むちうち症」は医学的に正式な名称ではありませんので、診断書には「むち打ち」ではなく「頸椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」などと記入されることになります。
⑥既存の障害
事故以前に患っていた精神または身体の障害です。症状、部位、程度について正確に記入されているか確認してください。
⑦自覚症状
自覚症状は「痛い」「しびれる」など被害者本人が自覚している症状のことです。被害者の訴えをもとに医師が診断書に記入します。画像検査で異常が見られなかった神経障害などでは、自覚症状の記入内容によって審査結果が大きく左右されます。些細な症状であっても、医師に伝えて記載してもらうのがおすすめです。
⑧他覚症状および検査結果
他覚症状は医師などの第三者が客観的に確認できる症状のことです。MRIやレントゲンなど後遺症が誰でも一目でわかるような画像検査や、神経学的な検査の結果で確認できます。

⑨障害内容の増悪・緩解の見通し
症状が今後改善するか、それとも悪化するかという医師の見解です。「症状が緩解している」などと記入していると、改善の余地があるとして等級不該当になるおそれがあります。
後遺障害診断書の入手方法
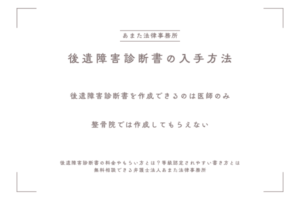
後遺障害診断書を作成できるのは医師のみで、整体師など医師ではない人は記載できません。誰からでももらえるわけではないので気を付けましょう。
後遺障害診断書を作成できるのは医師のみ
後遺障害診断書は医師のみが記入、作成できます。ただし、医師であれば誰でも良いわけではなく、後遺障害への申請時点で診察を担当している主治医に書いてもらいます。
整骨院では作成してもらえない
整骨院や接骨院で施術を担当するのは柔道整復師になり医師ではないため、後遺障害診断書の作成はできません。交通事故の後にしびれや痛みがあると整骨院(接骨院)に通われる方もいらっしゃると思います。整骨院のほうが自分に合っていると感じることもあるでしょう。しかし後遺障害へ申請することを考えると、医師がいる医療機関での治療が必要になります。
また、整形外科などの病院に通う前に整骨院で施術を受けると、交通事故との因果関係が不明瞭になるおそれが出てきます。結果、診断書の作成が困難になる可能性が生じるため、交通事故に遭った後は医療機関で診察を受けるようにしてください。
後遺障害診断書の作成にかかる料金や期間
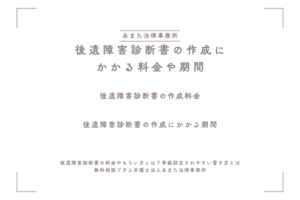
後遺障害診断書の作成にかかる料金や期間は、病院や医師によって違いがありますので注意しなければなりません。
後遺障害診断書の作成料金
後遺障害診断書の作成にかかる料金は、病院が独自に設定しておりまちまちなのが現状です。
一般的には5,000円〜10,000円程度が相場になりますが、中には20,000円を超える病院もあります。請求書の金額を見て、びっくりしたという話もあります。「こんな金額支払いできない」とならないよう、依頼をする前にいくらになるか確認してください。
後遺障害診断書の料金は原則として作成を依頼した本人が負担しますが、後遺障害等級に該当すれば相手方の保険会社に請求できます。逆に言うと、後遺障害等級に該当しなければ、そのまま被害者が負担するかたちになります。
後遺障害診断書の料金を節約するためにも、等級認定されるような診断書を作成してもらえるようにしましょう。
後遺障害診断書の作成にかかる期間
後遺障害診断書の作成期間は、通常だと2週間程度です。しかし数日で書いてもらえる病院もあれば、1ヶ月程度と長期間要する病院もありケースバイケースと言えます。完成までどのくらいの時間がかかるのか、作成期間についても依頼時に確認してください。
後遺障害診断書を作成するタイミングはいつ?
後遺障害診断書を作成できるタイミングは、担当医より「症状固定」と診断されてからです。これ以上治療しても症状の改善が見込めない状態を症状固定といい、損害賠償上では治療が終了したものと扱われます。
症状固定の時期はだいたい事故発生から6ヶ月程度を目安と思っておくと良いでしょう。ただ症状の程度は人それぞれなので、6ヶ月経っても症状固定にならないことはあると頭に入れておいてください。
症状固定以降に残っている症状は、認定された後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益などといった賠償金を加害者側に請求できます。
しかし、ケガの症状は医師が判断するもので、保険会社ではありません。保険会社に症状固定を打診されても、安易に従わないようにしましょう。医師の指示にしたがって治療を続けるようにしてください。
後遺障害診断書を適切に作成してもらうための注意点
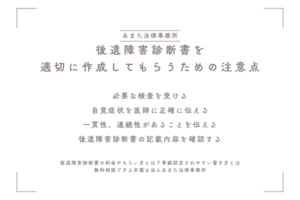
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、等級の基準を満たす内容の後遺障害診断書を作って貰わなければなりません。作成する前に、適切な診断書を書いてもらうポイントを確認しておきましょう。
必要な検査を受ける
適切な後遺障害診断書を作るためには、MRIやレントゲンといった検査で後遺障害の存在を証明しなければなりません。画像は後遺症を判断しやすいツールです。後遺障害等級の審査では、MRIやレントゲンなどの検査で明らかな異常所見が見られなと等級不該当になる事例が多く見られます。
ただ、交通事故の後遺症で多いむちうち症は、画像検査では異常所見がわかりにくい後遺症です。画像での判断が難しいと思われるのであれば、医師に「スパーリングテスト」や「ジャクソンテスト」などの神経学的な検査をしてもらってください。
スパーリングテストとジャクソンテストのやり方は以下のとおりです。
医師が椅子に座った患者の頭を後ろから掴み痛みやしびれがあるほうに傾け、さらに後ろに反らし圧迫する方法です。痛みやしびれが誘発されれば、診断書に陽性(+)と記載されます。
患者が椅子に座った状態で頭を後ろに倒し、さらに医師が上から下に押し下げて圧迫する方法です。痛みやしびれが誘発されれば、診断書に陽性(+)と記載されます。
自覚症状を医師に正確に伝える
「痛みを感じる部位」「痛みの度合い」「どのようなシーンで痛むか」「日常生活にどう影響するか」などの自覚症状を、細かく医師に正確に伝えましょう。
後遺障害等級認定の審査では現時点で被害者が感じている自覚症状も考慮されます。特に、むちうち症のような神経障害でMRIやレントゲンでは症状を証明できないときは、自覚症状の詳細を診断書に記載してもらうことが大切です。
一貫性、連続性があることを伝える
後遺障害として認められるためには、事故と後遺障害の発生に因果関係が存在している必要があります。初診のときから症状に「一貫性(同じ部位に痛みがあること)」と「連続性(事故からずっと症状が続いていること)」がなければ、事故と後遺障害との関係がないとして等級不該当になるおそれがあります。

後遺障害診断書の記載内容を確認する
後遺障害診断書の内容が不適切であれば、被害者本人が医師に診断書の訂正・追記を求める必要があります。
医師は等級認定の基準を満たす診断書の書き方を熟知しているわけではありません。医師によって記入方法が異なるうえ、曖昧な表現で症状を説明することはあります。しかし、医学的な知識がない一般の方がどこが誤っているか、問題があるかを見つけ説明するのは困難でしょう。それに医師に意見するのは、気がひけてしまうこともあり得るのではないでしょうか。もし、プライドが高い医師だと指南をしても嫌な顔をしたり、無視するなど感じが悪い対応をされることも考えられます。

後遺障害診断書を医師が書いてくれないときの対処法

後遺障害診断書を医師が書いてくれない場合があります。医師が作成を断る理由と、断られたときの対処法について解説します。
まだ症状固定ではないと判断された
医師が症状固定と判断しなければ、後遺障害診断書は作成してもらえません。だいたい初診から6ヶ月程度で症状固定になりますが、症状の程度は個人差があり人それぞれです。6ヶ月以上経っても、治療の継続を勧められることはあります。
治療経過がわからない
後遺障害診断書にはいま現在残っている症状だけでなく、怪我がどのように回復したのかという治療経過を記載する必要があります。そのため、被害者が途中で通院を中断してしまったり、当初とは別の病院に通院したケースなどでは、治療の経過がわからないことを理由に作成してもらえない可能性があります。
途中で通院を中断していたときは、改めて一定期間通院を継続してください。そして再度、診断書を書いてもらうように頼んでください。

後遺症が残っていないと判断された
後遺障害診断書は後遺症が残っていることを前提とする書類なので、後遺症がなければ作成してもらうことはできません。
ただし、MRIなどの画像検査で後遺症を証明できなくても、現時点で痛みやしびれが残っていれば後遺障害等級に該当する可能性はあります。
まずは、医師に現在の自覚症状をきちんと伝えて、診断書に記載してもらえないかお願いしてみましょう。医師がどうしても作成を渋るときは、交通事故の事案に詳しい弁護士に相談し、医師を説得してもらうのも一つの手です。
健康保険を使っている
健康保険を使って治療していると、後遺障害診断書の作成を断られることがあります。理由は「自賠責関係の手続きに健康保険を適用できない」と、医師が誤解しているためです。
しかし、健康保険を使って交通事故の治療を受けることは認められています。自賠責保険へ後遺障害等級の認定を申請することも何ら問題ありません。
なかには詳細を理解していない医師もいるという現実があります。医師に健康保険を利用していても後遺障害診断書を作成できることを説明し、再度依頼してください。
自分でうまく説明する自信がないのであれば、法律の知識がある弁護士にお願いすると良いでしょう。患者の話をあまり聞いてくれない医師でも、弁護士の話には耳を傾けてくれるというケースは少なくありません。
後遺障害診断書の書き方を知らない
医師に後遺障害診断書の作成を依頼しても、「当院では対応できない」と断られることがあります。背景には、医師が書き方をよくわかっていない事情があります。
医師の仕事はケガの治療であり、治癒せずに残ってしまった後遺障害診断書の作成は専門外の作業になってしまいます。なので書き方を知ろうともしない医師は実際に存在しています。
また、治療を終わっている患者の後遺障害診断書を作成することで、余計なトラブルに巻き込まれるのが嫌だと考える医師もいます。
しかし、医師には診断書を作成する義務があります。そのため、正当な理由なしに断ることはできません。「書き方がわからない」や「トラブルに巻き込まれたくない」などは正当な理由に当たらないと医師に伝えましょう。
後遺障害診断書をもらってから申請する流れ
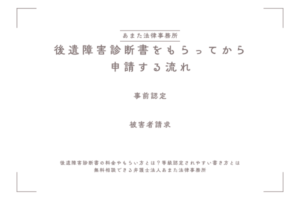
後遺障害診断書を手に入れたら、加害者側の自賠責保険に後遺障害等級の認定を申請します。等級認定を受けると、交通事故の加害者に対して後遺障害慰謝料や逸失利益といった賠償金の請求が可能になります。
等級認定の申請方法には「事前認定」「被害者請求」と2つの方法があります。どちらも申請から1〜2ヶ月程度で、結果が通知されます。
事前認定
加害者側の任意保険会社を経由して、後遺障害の等級認定を申請する方法です。被害者が相手方の任意保険会社に後遺障害診断書を提出すれば、残りの申請手続きは全て保険会社がおこなってくれます。事前認定では手続きのほとんどを相手方の任意保険会社が行ってくれるため、被害者の負担はかなり少なくなるのが特徴です。
一方で、書類の準備を保険会社に任せることになるため、手続きの透明性を確保できないデメリットが出てきます。被害者側は加害者側の保険会社が用意した書類を確認できません。保険会社は支払いする金額を少なくするために、被害者が不利になるような措置を取る可能性は否めません。
事前認定では適正な書類を提出できるとは言い難く、正しい等級認定が受けられない可能性が高いといえるでしょう。
被害者請求
被害者本人が相手方の自賠責保険会社に必要書類を提出する方法です。全ての書類を被害者が集める必要があるため、事前認定に比べるととても手間がかかります。
しかし、被害者自身が必要書類を集めますので、等級認定に有利な資料を選べるメリットがあります。適切な資料を提出できれば、事前認定よりも後遺障害等級が認定されやすくなります。
とはいっても、後遺障害の等級認定に必要な書類を自分ひとりで集めるのは大変であり、素人では不備も起こりやすいです。弁護士にアドバイスをもらいつつ、用意するのが安心です。
事前認定で申請すると、むちうち症などの神経症状は資料不足が原因で等級認定されにくい傾向があります。手足の切断など目に見える明らかな後遺障害でない限りは、被害者請求で申請するのがおすすめです。
後遺障害診断書についてまとめ
後遺障害診断書は医師に作成してもらいます。料金は5,000円~10,000円程度ですが、もっと高額になることもあります。
症状固定と診断されたら担当医に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。料金がかかっても、等級が認定されれば後遺障害診断書の作成料金は加害者側に請求できます。
後遺障害診断書は後遺障害の等級認定に大きな影響を与えますので、記述されている内容が正しいかしっかり確認することが大切です。不備があるのか自分ではよくわからなかったり、医師が書いてくれないなどの疑問やお悩みがあれば、弁護士への依頼を検討してください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ