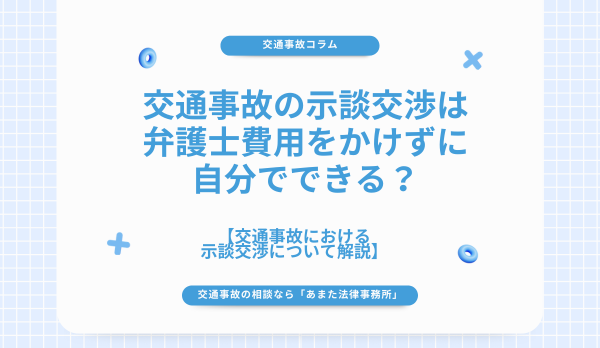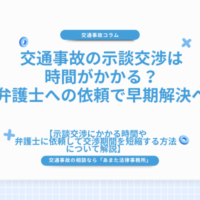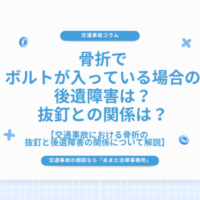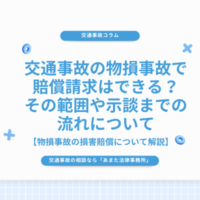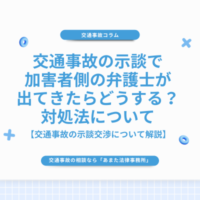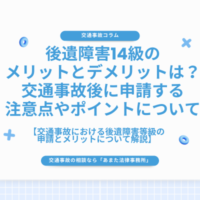交通事故の示談交渉は弁護士や保険会社に代理してもらう方法が一般的ですが、自分で行うこともできます。ただし、自分で示談交渉してもスムーズに進まないことがあります。

執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
示談交渉は弁護士に依頼せずに自分でできる?
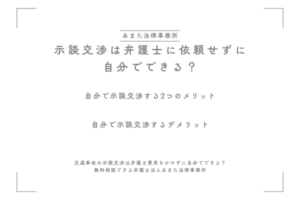
交通事故の示談交渉を自分で行うことは可能です。保険会社に示談の代行を依頼できない被害者に過失がゼロのような状況では、弁護士を立てず被害者本人のみで示談交渉することもあります。ただし、満足した結果を出すことは難しいため、弁護士へ相談することで解決となる可能性は高まります。

自分で示談交渉する2つのメリット
被害者本人のみで示談交渉するメリットは、費用を節約できることと、自分の好きなように交渉できる点です。
費用がかからない
弁護士に依頼すると、弁護士費用という依頼料がどうしても発生してしまいます。弁護士もボランティアではないので、成功した時の報酬が必要になるのは仕方がないでしょう。しかし自分で示談交渉すれば、弁護士費用は発生しません。
特に、物損事故など損害の規模が小さい事故では、賠償金額が低くなるため、弁護士に依頼すると費用倒れを起こしてしまうリスクがあります。自分で示談交渉することで、弁護士費用などを抑えられ金銭的に得をする場合があります。
自分の裁量で交渉できる
自分で行うと、自分の思ったように交渉をすすめやすくなります。
示談交渉を保険会社や弁護士に依頼すると、主張する内容は代理人に一任することになります。被害者と代理人との間で情報共有がうまくできてないと、示談交渉の結果が被害者の思っていた通りになりにくくなってしまいます。

自分で示談交渉するデメリット
一人で示談交渉を進めるメリットもありますが、基本的にはデメリットの方が多くなります。交渉が不利になり、適正な賠償金を受け取れないなどの事態が起きやすくなります。
交渉が不利になりやすい
示談交渉は基本的に相手方の保険会社と行います。保険会社は自社の支出をできるだけ抑えようとするため、賠償金の金額を低めに提示してきます。過去の判例を基にした賠償金の相場を大きく下回ることも珍しくありません。
被害者が損害賠償の知識に詳しくなければ、低い金額を提示されても気がつかず了承してしまうおそれがあります。また賠償金の増額を主張たとしても、個人の言うことは法的な根拠がないとして保険会社は相手にしてくれないことがほとんどです。
示談金を増額できる可能性に気付けない
損害賠償に詳しくない被害者が一人でチェックしてしまうと、示談金が増額できることに気付かないおそれがあります。
交通事故による怪我の治療が終わると、相手方の保険会社から賠償金の提示があります。治療費、慰謝料、休業損害、通院交通費などが含まれ、項目ごとに損害額が算定されています。
しかし、これらの金額は保険会社が独自の計算方法で算出したものなので、適正な金額であるとは限りません。交渉すればもっと増額できたのに、低額で応じてしまい損をする事例はあります。
適切な後遺障害等級が認定されない
交通事故で後遺障害が残ったときは、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。ですが、自分で等級申請をすると、適切に認定されないことがあります。
一人で示談交渉に臨むということは、後遺障害の等級認定も一人で申請することになります。
後遺障害診断書などの必要書類を全て自分で準備しなくてはなりません。もし後遺障害診断書の記載内容に不備などがあったり、必要書類が不足しているといった状況では、適正な等級認定が受けられなくなる可能性が高くなります。申請には入念な準備をする必要があるのです。
交通事故における示談交渉とは
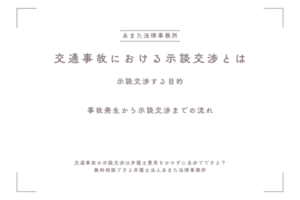
示談交渉とは、裁判を利用することなく、当事者間の話し合いによって法律上の紛争を解決する手続きのことです。交通事故にあった際には、加害者側と示談交渉することによってトラブルを解決していくことになります。
示談交渉する目的
加害者側と示談交渉することによって、損害賠償の金額を決定します。
交通事故で被害者に生じたさまざまな損害については、加害者に示談交渉で賠償請求することが可能です。
事故によって損害が発生したときは、まずは示談交渉を経て賠償金額を決めるのが一般的です。民事裁判よりも時間や費用がかからない手続き方法だからです。しかし交渉がまとまらなかったり、お互いの言い分が相容れなかったりした場合は、裁判に移行して決着をつけることになります。
事故発生から示談交渉までの流れ
人身事故が発生してから示談交渉までの流れについて解説します。
交通事故が発生したら、自身の身の安全を確保し、警察に通報してください。事故の当事者には警察への通報義務が課せられており、これに違反すると5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます(道路交通法第119条)。
事故後は自身が受けた怪我の治療に専念しましょう。
事故が発生した直後から通院を始めることが大切です。事故発生から初診までに期間が空いてしまうと、事故と治療の関係性が証明できなくなり、保険金を受け取れなくなる可能性があるからです。
また、怪我の治療は、医師が在籍している病院(整形外科など)で行ってください。医師の指示なく整骨院などで施術を受けると、医学上の治療行為とみなされずに保険金が受け取れなくなる可能性があります。
怪我の治療は、完治または「症状固定」によって終了します。症状固定とは、怪我の治療を継続しても症状の改善が見込めない状態のことを指し、医師が判断します。症状固定となると、保険会社から治療費などが支給されなくなります。

症状固定の後に「後遺障害」が残っている場合は、「後遺障害等級」の認定を受けましょう。
後遺障害等級は後遺障害の部位・程度などによって1〜14級に分類されており、等級によって後遺障害慰謝料の金額が異なります。適切な等級の認定を受けるためには、後遺障害の存在を証明する資料をきちんと揃えてから申請するように注意しましょう。
怪我の治療または後遺障害等級の認定が終わり次第、加害者側と示談交渉を開始します。当事者双方が示談の内容に納得すれば、示談書に捺印し示談が成立します。反対に、お互いが条件を譲らず、話し合いが進まず合意とならない状況が続けば、民事裁判などの次の段階の解決方法を検討することになります。
示談交渉を弁護士に依頼をせずに進めるポイント
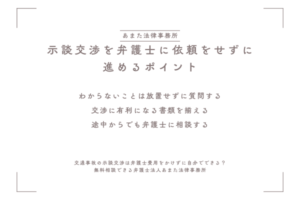
自分で示談交渉を進めるときには注意点がいくつかあります。被害者が押さえておきたい、示談交渉のポイントについて解説します。
わからないことは放置せずに質問する
話がわからないまま曖昧な返事をしていると、気づかないうちに交渉で不利になることがあります。
相手方の保険会社は示談交渉のテクニックを持っていますので、被害者に揺さぶりをかけて交渉を有利に進めようとします。例えば、あえて専門用語を多用して話を難しくしたり、十分な説明をせずに条件を提示したりすることがあります。

交渉に有利になる書類を揃える
交渉を有利に進めるためには、被害者側の主張を裏付ける証拠書類を用意する必要があります。診療報酬明細書や診断書があれば、適切な治療費を請求できます。休業損害を請求するときには、給与明細書や休業損害証明書が必要です。
また、賠償金の金額を決定するさいは、当事者にどのくらいの落ち度があるかを表した「過失割合」が問題になります。自分に過失がない交通事故であると証明するためには、ドライブレコーダーなどの映像を証拠として提出するのが良いでしょう。
途中からでも弁護士に相談する
自分一人で示談交渉を始めたものの、やはり一人では対応が難しいケースもあるでしょう。無理に自分で進めるよりも、弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士であれば、法律問題についてもわかりやすく説明してくれます。被害者側が有利になるような交渉術も持っているのもメリットです。
また、一般の人では対応しにくい損害賠償の費目のチェックや、金額の算定などもおこなってくれます。
示談金にはどのようなものが含まれる?
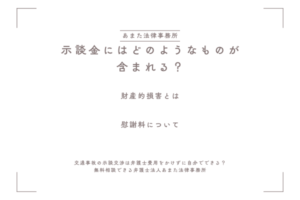
示談金には、大きく分けて「財産的損害」と「慰謝料」があります。示談交渉では、被害者に生じた全ての損害を示損賠賠償金として換算し、加害者側に請求できます。
示談金に含まれる損害賠償の項目について、財産的損害と慰謝料に分けて解説します。
財産的損害とは
被害者の財産に生じた損害のことを財産的損害といいます。財産的損害には、交通事故によって支出せざるを得なくなった「積極損害」と、受け取れるはずの収入が受け取れなくなった「消極損害」に分かれます。
積極損害に含まれる賠償項目
積極損害に分類される賠償項目を紹介します。
事故による怪我を治療する際に必要となる費用です。治療費には、診察費用、検査費用、入院費用、手術費用などが含まれます。
治療費は実費の全額を請求できるのが一般的ですが、「必要かつ相当な範囲」を超えた金額は請求できません。例えば、整骨院などで過剰診療していた分は、治療費として判断されないことがあります。
交通事故による怪我で身体の自由が効かなくなったとき、身の回りの世話をする付添い人にかかる費用です。一定の範囲で加害者に請求できます。ヘルパーなどの職業付添人を雇った場合はもちろん、近親者が被害者の付き添いをしたときでも、付添看護費用を請求できます。
入院中にかかる雑費のことです。たとえば、入院に必要な衣類や洗面具を購入した費用、外部の人と連絡を取るための通信費や切手代、栄養補給費(牛乳やヨーグルトなどの食費)などが対象となります。
通院のためにのかかった費用についても加害者に請求可能です。公共交通機関の交通費や自家用車での通院で発生したガソリン代などが適用となります。
消極損害に含まれる賠償項目
消極損害に含まれる賠償項目を紹介します。
交通事故による怪我で仕事を休んだために払われなかった収入のことを「休業損害」といい、加害者側に補填を要求できます。

交通事故にあわなければ将来得られたはずの収入を「逸失利益」といいます。後遺障害によって労働能力が低下したり、被害者が死亡したために、本来得られがはずの収入が得られなくなったケースがあたります。
慰謝料について
交通事故にあうと、怪我による苦痛や入通院の負担といった精神的苦痛を伴います。精神的損害を与えられたとして、被害者は加害者に対して慰謝料として請求できます。
慰謝料の算定基準とは
慰謝料の金額はどのように決まるのか、3つの慰謝料を計算する基準を紹介します。
自賠責保険が慰謝料の金額を算定するときに用いる基準です。自賠責保険は、原付を含む全ての車両に加入が義務付けられているため、人身事故の被害に遭った人は確実に自賠責保険の補償を受けられます。
ただし、自賠責基準で補償される慰謝料は極めて低い金額になっています。通常の人身事故では補償金額の上限が120万円と決まっており、超過したとしても賠償金は支払われません。
任意保険会社が慰謝料の金額を算定するときに用いる基準です。自賠責保険で支払いきれない賠償金は、相手方の任意保険会社から支払われるのが一般的です。金額は任意保険会社が独自の計算方法で慰謝料の金額を算定します。
任意保険基準は細かい計算方法が各保険会社で異なり、原則として公開はされていません。保険会社は営利企業ですから、保険金の支出は可能な限り抑えようとします。実際のところ、任意保険基準における慰謝料の金額は、自賠責基準よりもやや高い程度です。
過去の裁判例に基づいて設定された慰謝料の計算基準です。具体的な計算方法については、日弁連交通事故相談センター発行の「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」という書籍(赤本と呼ばれています)に掲載されています。
弁護士に依頼をせず示談交渉が進まないとどうなるか
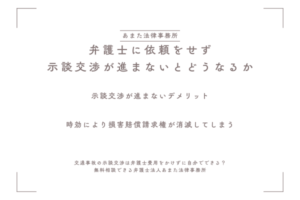
交通事故の示談交渉を自分ひとりですると、お互いの意見が食い違って交渉が難航することがあります。
示談の成立が遅れることによるデメリットと、交渉をスムーズに進めるための対策法について解説します。
示談交渉が進まないデメリット
交通事故の示談交渉が難航すると、慰謝料などの賠償金を受け取れないといったデメリットが生じます。
示談金を受け取れない
示談が成立しなければ、被害者は賠償金を受け取ることができません。賠償金が支払われるのは示談成立後になるため、交渉が終わるまでの間も賠償金は受け取れないのです。
賠償金が支払われるまでの間は、事故による損害を自分で負担することになります。一時的とはいえども、損害額が大きくなるほど、被害者の経済的負担も大きくなってしまいます。
時効により損害賠償請求権が消滅してしまう
交通事故で損害が発生すると、被害者は加害者に対する損害賠償請求権を獲得します。ただし、示談交渉が進まずに放置していた場合、「時効」によって加害者に対する損害賠償請求権が消滅してしまうおそれがあります。
時効が成立する期限は、交通事故の態様によって異なります。物損事故では、「事故発生日の翌日から3年」が経過した時点で時効が成立します。人身事故や死亡事故では、「事故発生日の翌日から5年」が経過した時点で時効が成立します。
また、ひき逃げや当て逃げなど、加害者がわからない場合は、事故が発生した翌日から20年経つまでは時効が成立しません。ただし、途中で加害者が判明したときは、加害者がわかった翌日から3年あるいは5年で時効が成立することになります。
示談交渉が進まないときの対策
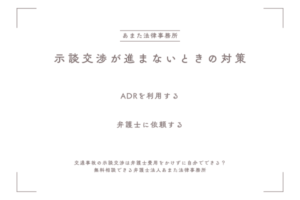
示談が難航しまとまらないときに、できる対策を解説します。
ADRを利用する
示談がまとまらないときは「ADR(Alternative Dispute Resolution)」を検討してみましょう。
「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」などに所属する第三者(センターの嘱託弁護士など)が当事者の間に入り、あっ旋や仲裁を行い法律上の紛争を解決していきます。
当事者のみで示談交渉すると、お互いの意見が衝突し合意に至らないことは多々あります。ADRを利用すれば、第三者から客観的な意見を聞くことができ、妥当な結論を導き出せる可能性が高くなります。
弁護士に依頼する
示談交渉は弁護士に任せるのがのおすすめです。事故後の面倒な手続きを一任できるため、被害者の負担を大きく減らせます。
示談交渉が難航していても、交通事故に関する法律に精通した弁護士が介入することで早期解決を目指せ安心です。また、加害者の態度が悪くて直接コンタクトを取りたくないときも、弁護士がすべて連絡してくれるので被害者側はストレスを感じずに済みます。
さらに弁護士が交渉を担当すると、慰謝料の金額を大幅に増額できるのは大きなメリットです。弁護士は慰謝料の金額を弁護士基準で算定するため、他の算定基準よりも慰謝料が高額になります。たとえ保険会社が弁護士基準による慰謝料の支払いを渋ったとしても、弁護士は民事裁判を提起できます。
裁判に進展すると保険会社が勝てる見込みはありません。相手方の保険会社は、交渉の段階で弁護士の増額請求を受け入れるのが一般的です。

慰謝料の増額を目指すなら弁護士への相談を
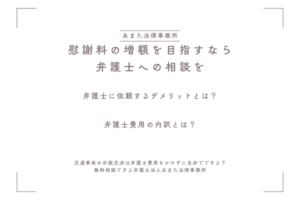
弁護士基準は自賠責基準や任意保険基準と比較すると、極めて高額になります。しかし、自分で相手方の保険会社に弁護士基準の慰謝料を請求し用途しても、相手にされないケースがほとんどです。
弁護士基準の賠償金を受け取る方法は、弁護士に依頼することです。弁護士であれば保険会社に弁護士基準での慰謝料を請求できます。たとえ保険会社が増額請求を断ったとしても、弁護士は民事裁判の提案ができます。保険会社は勝ち目がない裁判は嫌がるので、弁護士が提示する金額にしぶしぶでも応じると思われます。

弁護士に依頼するデメリットとは?
弁護士に依頼することで大きなデメリットは、弁護士費用を支払う必要があるということでしょう。
ただ、交通事故の場合は、相談料や着手金が無料、完全な成功報酬の事務所も多いのです。さらに、自動車保険などに付帯されている弁護士費用特約が利用できる場合には、基本的に弁護士費用の負担がかかることはありません。
弁護士費用の内訳とは?
交通事故の弁護士費用は、具体的なケースや弁護士事務所の料金体系によって異なる場合がありますが、一般的には、初回相談料、依頼費用、報酬金、実費、日当などが必要となります。
そのうち、事件を解決できた時に発生する報酬金は、経済的利益に応じて変わります。ほとんどの事務所で報酬額は「経済的利益の○%」などと設定しています。
示談交渉は自分でできるが難しい
交通事故の示談交渉は自分で行うことが可能です。しかし、法律に詳しくない被害者が一人で交渉に臨んでも、不利な条件で示談が成立してしまう危険性があり、自分だけで満足した結果を出すのは非常に難しいといえます。
示談交渉を自分でするのであれば、損害賠償の知識を熟知している必要があります。メリットとデメリットをよく考えながら、自分で交渉を進めるかを決めるようにしましょう。
示談交渉の途中からでも弁護士に依頼できます。不安になったり、交渉がうまく進まない状況になったら、泣き寝入りしないためにも交通事故の事案に強い弁護士への相談を検討してください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ