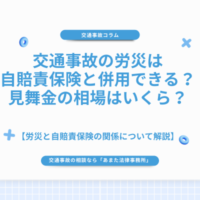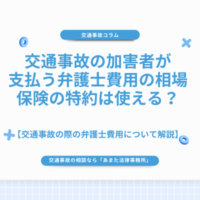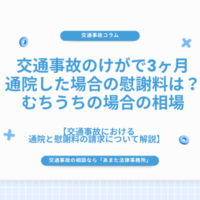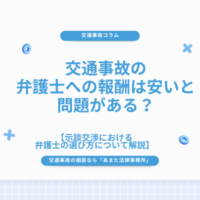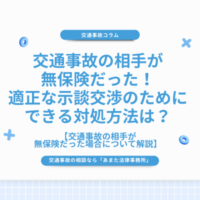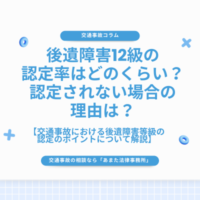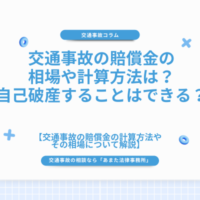交通事故の被害に遭ったとき、加害者に請求する損害賠償額を決める示談交渉は自分でやるより弁護士に依頼すると有利になります。とはいっても、費用がどのくらいかかるのか気になります。

この記事の目次
弁護士費用の内訳と金額の相場
弁護士に依頼する際の費用内訳には、相談料や着手金、成功報酬金などがあります。
実際に依頼したさいにかかる弁護士費用にはどのような項目があり、相場はいくらぐらいになるかを解説していきます。
相談料・30分 5000円~10000円
弁護士に法律相談するための費用です。相談したからといって必ず依頼しなければならないわけではなく、法律相談のみで終わるケースもあります。実際に顔を合わせ話をすることは弁護士との相性が分かるので、正式な依頼の前には一度相談に行くのが良いでしょう。

着手金・10万~20万円
着手金は初期費用とも呼ばれ、弁護士に正式な依頼を決めたら最初に払う費用です。成功するかどうかにかかわらず依頼すれば必ず支払わなくてはならない費用であり、案件の結果に関わらず通常は返金されません。金額は事務所によって異なりますが、交通事故は10万~20万円程度が相場です。
報酬金・経済的利益の10%~30%(+数万円)
報奨金は依頼が成功した場合に成功報酬として弁護士に支払う費用です。経済的利益とは得られた賠償金のうち、「弁護士への依頼で得られた利益」「弁護士によって増額できた利益」で、そのうのち10%~30%を報酬として支払います。
計算方法は事務所ごとに違い、獲得金額によって割合を変えているところもあります。金額の参考として2004年に廃止された日本弁護士連合会(日弁連)の報酬規程を掲載します。
| 経済的利益 | 報酬金の算定基準 |
|---|---|
| 300万円以下 | 16% |
| 300万円越え3000万円以下 | 10%+18万円 |
| 3000万円越え3億円以下 | 6%+138万円 |
| 3億円越え | 4%+738万円 |
弁護士報酬は現在自由化されていますが、多くの事務所では以前の規定に基づいて報酬を定めており目安としては有効と考えられます。ただ、事務所によっては成功報酬をとらず着手金のみにしているところもあります。
日当・数万~10万円
日当は出張など弁護士が事務所以外で業務を行ったときに必要となる費用で、移動距離や活動日数・時間の長さに応じて金額が決まります。1日かかる業務であれば5万~10万円、数時間であれば5万円以下が金額の目安です。

その他の実費
弁護士活動に必要な諸費用で、実際にかかった金額が請求されます。病院や警察署、関係機関、事故現場などに行く際の「交通費」や訴訟手続きで必要になる「収入印紙代」、相手保険会社などとの書類のやり取りで発生した郵便物の切手代といった「通信費」が含まれます。
消費税
弁護士費用にも通常の買い物と同じように金額の10%の消費税がかかります。見積りの時点で金額は税抜きなのか税込みなのか確認しておきましょう。
弁護士費用をそれぞれのケースで計算
示談交渉を弁護士に依頼するとき、実際にどれくらいのお金が必要になるか実例をもとに詳しく見ていきます。
料金体系は事務所ごとに変わりますが、ここでは目安として着手金ありとなしで損害賠償(経済的利益)が300万円と1000万円、30万円の場合に分けて解説します。
ケース① 損害賠償300万円のケース
着手金 10万円
成功報酬 48万円(300万円の16%)
弁護士費用の総額 1万円+10万円+48万円=59万円
旧報酬規程に従い成功報酬は賠償金の16%で計算しています。着手金ありだと弁護士費用は59万円となり、示談金から費用を引くと手元に残る金額は241万円になります。
着手金 0円
成功報酬 55万円(300万円の11%+22万円)
弁護士費用の総額 1万円+0円+55万円=56万円
着手金がない事務所では成功報酬が高めに設定されている場合が多いため、ここでは経済的利益の11%+22万円で計算しています。弁護士費用は56万円で被害者の手元に残る金額は244万円です。

ケース② 損害賠償1000万円のケース
着手金 20万円
成功報酬 118万円(1000万円の10%+18万円)
弁護士費用の総額 1万円+20万円+118万円=139万円
成功報酬の割合は旧報酬規程より10%+18万円で計算すると弁護士費用は139万円で、被害者が受け取る金額は861万円となります。
着手金 0円
成功報酬 132万円(1000万円の11%+22万円)
弁護士費用の総額 1万円+0円+132万円=133万円
着手金なしの弁護士報酬は133万円で被害者の手元に残る賠償金は867万円と、着手金ありの場合よりも多くなります。
ケース③ 損害賠償30万円のケース
着手金 10万円
成功報酬 4万8000円(30万円の16%)
弁護士費用の総額 1万円+10万円+4万8000円=15万8000円
軽症のケース
重傷ではないむちうちのような軽症の怪我だと損害賠償がそれほど高額になりにくく、着手金ありの弁護士費用は15万8000円と賠償金の半額を越えます。被害者が受け取る金額は14万2000円になります。
着手金 0円
成功報酬 25万3000円(30万円の11%+22万円)
弁護士費用の総額 1万円+0円+25万3000円=26万3000円
着手金なしの弁護士費用は26万3000円で手元に残る金額は3万7000円となります。
このように損害賠償が低額だと賠償金の半分以上を弁護士費用が占めるケースが出てきます。最終的に弁護士に示談交渉を依頼するメリットは少なく「費用倒れ」になる可能性があります。
交通事故の示談交渉とは
交通事故の被害に遭った被害者に加害者から支払われる慰謝料や治療費といった損害賠償の金額は、双方の話し合いによって決められます。これを「示談交渉」と呼んでいます。
示談とは
「示談」とは民事上の争いを裁判によらず、話し合いによる双方の合意によって事件を解決する方法です。成立すると加害者と被害者の間で「示談書」と呼ばれる書面を作成し、示談内容を遵守する約束を交わします。
示談書には法的効力があり、加害者は法律に従ってきちんと損害賠償を支払う必要があります。また、お金の支払いだけでなく、被害者が裁判を起こさないことや告訴を考えていれば取り下げることなども取り決められます。
基本的に決まった金額以上の損害賠償は請求できず一度成立すると覆すのが難しいという理由から、交通事故の示談交渉は非常に重要なものといえます。
示談交渉の流れ
交通事故の示談交渉は事故が起きてすぐに開始されるわけではなく、ケガの治療や後遺障害の認定などいくつかの段階を踏んで行います。

事故が発生したらすぐに警察へ通報してください。通報なしで済ませてしまうと物損事故扱いになり人身事故として処理されないため、被害者は不利になります。
事故後は医療機関へ入院または通院してケガの治療を行います。損害賠償として支払われる治療費や慰謝料はケガの程度によって変化するため、交通事故ではケガが完治するまで賠償金の正確な計算ができず交渉は始められません。
治療後も改善しない後遺症が残ったら担当医に診断書をもらい、専門機関に申請をして後遺障害等級の認定を受けます。後遺障害が認定されると後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できるようになり損害賠償額を大幅に増額できる可能性が高まります。
必要な治療が終わると損害賠償の計算ができるようになり、相手方との交渉がスタートします。被害者が亡くなる死亡事故では、葬儀と四十九日法要の費用を損害賠償に含められるため葬儀・四十九日法要を終えた段階ではじまります。
交通事故の交渉は基本的に相手の任意保険会社から提示される案をもとに行われます。被害者は提案内容を検討した上で納得できるまで増額の交渉等を行い、両者が合意すると成立となります。その後示談書または免責証書を取り交わします。
もし、主張が食い違い相手方と揉め決着がつかなければ、民事訴訟を起こして裁判所で決着をつける方法もあります。
相手の保険会社にいわれるまま応じていると、本来よりも低い金額で終了されてしまう可能性があるので注意しましょう。自分だけで挑むのは自信がない、感情的になってしまって冷静に話し合いができそうにない、といった時は弁護士に依頼することで有利に進められますし、トラブルにもなりにくいです。
弁護士に交通事故の示談交渉を依頼するメリット
交通事故の示談交渉を弁護士に行ってもらうメリットは多々あります。
1、示談交渉を一任できる
わずらわしい交渉をすべて弁護士に任せられるのは大きなメリットです。示談交渉が行われるのは平日の日中など仕事を休まなければならない時間帯が多いですし、金額に納得ができずに長引けばさらに大きな負担がかかります。
事故で怪我をした上、相手の保険会社との慣れない話し合いは精神的にも大きなストレスになるでしょう。
また、法的知識のない個人が相手では、保険会社が強引に話を進め被害者が不利になる条件で終了させようとするケースも考えられます。しかし弁護士が介入した場合はこじれると裁判に持ち込まれる可能性が高いため、保険会社も態度を軟化させ強引な態度は控えるようになると思われます。
2、慰謝料が増額する可能性が高い
弁護士に依頼すればより高額な損害賠償を請求できるようになります。交通事故の損害賠償には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算定基準があり、それぞれで請求できる賠償金の額が変わります。
このうち、最も高額な損害賠償を請求できるのは、弁護士に依頼すると適用される弁護士基準です。自賠責保険に基づく自賠責基準、相手が加入している任意保険会社による任意保険基準よりもはるかに高い賠償金が受け取れ、他の基準と比べると金額が2倍から3倍になるケースもあります。

3、被害状況に見合った賠償金を計算してくれる
弁護士がいると被害の状況に合った損害賠償をきっちり計算してもらえます。
交通事故で請求できる損害賠償は知識がないと分からないものが多くあり、個人での交渉は被害状況に見合った金額を請求できない状況に陥りやすいです。
事故のため仕事を休んだときの補償である「休業損害」や後遺障害が残ったときに将来得られるはずだった給与等の補償として受け取れる「後遺障害逸失利益」など、本来もらえるはずのお金を請求せずに終わらせてしまう危険性が出てきてしまいます。
弁護士に依頼すれば被害状況に見合った適切な損害賠償を計算してもらえ、請求漏れを防止できるようになります。
4、相手方へ法的主張が可能になる
相手方の保険会社に対して、法的根拠に基づいた十分な主張が可能になります。
相手の保険会社に不当な過失割合を主張されたときや途中で治療費の打ち切りを言い出されてたときなどは、法的な観点から反論や抗議を行う必要があります。また法的知識をもった弁護士が当たれば後遺障害等級の認定といった問題に対しても法的根拠に基づく主張が可能になります。

弁護士に交通事故の示談交渉を依頼するデメリット
示談交渉を弁護士に依頼するのはメリットが多いのですが、反対にデメリットが生じるリスクもあるのが注意点です。
1、依頼には費用がかかる
弁護士に示談交渉を依頼するには着手金や成功報酬など各種費用がかかります。弁護士に依頼すれば弁護士基準で損害賠償が計算できるようになりますが、弁護士費用は決して安いものではありません。事故の内容が複雑だったりするとさらに費用が必要になります。
なかには、請求できる損害賠償より弁護士費用のほうが上回り、コストに見合ったメリットが得られない「費用倒れ」になってしまうケースが出てきます。ただ、費用倒れは弁護士費用特約を活用すればほとんどが回避できるとも言えます。
2、依頼先の選定が難しい
どの弁護士に依頼するか、依頼先の選定が難しい面があります。交通事故では示談交渉の内容によって損害賠償が変わるため、どの弁護士に依頼するかは重要な問題になります。
すべての弁護士が交通事故の事案を専門にしているわけではなく、実績の少ない弁護士だと相談しても依頼を断られてしまったり、引き受けてくれても思うような内容にならないといったケースは考えられます。
3、弁護士を変更したいとき費用と手間がかかる
途中で弁護士を変更したいと思ったときに費用や手間がかかるのはデメリットです。弁護士も人間ですから依頼者と合う・合わないがあります。それに思ったほど頼りにならないと感じたなど、示談交渉を進めているうちに他の弁護士に変更したくなるケースはあり得ます。
弁護士への依頼は民法上の委任契約になるため原則として自由な解除が可能となっており、弁護士の変更自体は問題ありません。しかし、変更には新しく契約する弁護士を探す必要があり、信頼できる弁護士を見つけるには時間と手間がかかってしまうでしょう。
さらに費用面でも問題は発生します。現在の弁護士に支払った着手金は返金されないのが普通ですし、解除料やこれまでの必要経費、一定の成果を出している場合にはその報酬、手数料を請求される可能性が生じるデメリットがあります。

4、交渉を重ねるため時間がかかる
相手の保険会社と何度も話し合いを重ねなければならず、示談が成立するまでに時間がかかります。通常、交渉開始から成立までは2~3か月程度と言われていて、治療期間なども含めれば半年以上かかるケースも考えられます。
保険会社と何度も交渉を重ねると、弁護士は個人で交渉するケースと比較すれば時間がかかってしまうことが多くなります。交通事故の損害賠償は示談交渉が終わるまで受け取れないので、経済的に余裕のない被害者は弁護士よりも自身で対応したほうがよいと感じてしまうかもしれません。
しかし、弁護士はきちんと被害者の主張を相手の保険会社に認めさせ、適切な賠償金を請求するために時間をかけて交渉を行います。時間がかかりがちなのは仕方のない面があり、ある程度は許容しなければならないでしょう。
弁護士費用を抑える方法
弁護士に示談交渉をしてもらうメリットはいくつもありますが、かかる費用はなるべく安く抑えたいと考える方は多いでしょう。費用の負担を少しでも低くしたいのであれば、支出を抑える方法を実践してみてください。
無料法律相談を利用する
多くの事務所が実施している無料の法律相談を積極的に利用して、請求できる損害賠償の金額目安や見積もりを出してもらうようにしましょう。
ひとくちに交通事故の示談交渉といっても、請求できる損害賠償や必要になる弁護士費用は様々でホームページの情報だけではすべて分かりませんので、自分のケースではどうなるのかは実際に話を聞くのが有効です。事前に見積もりをもらっておけば費用面での不安は減りますし、費用倒れになりそうなら見積りを出した時点で注意してもらえることがほとんどです。

早めに弁護士に相談する
事故発生後はなるべく早く弁護士に相談するようにしてください。
交通事故の示談交渉はそれぞれのケースで対応すべき事柄や内容が大きく異なるのがポイントです。例えば、病院で治療する際に通院頻度が少ないと示談交渉時に慰謝料が減額される原因になることがあるのですが、後から弁護士に相談しても治療頻度は変えられません。
早いうちから弁護士に相談しておけば損害賠償をなるべく多く請求するための適切なアドバイスをもらえますし、後遺障害等級の認定手続きなどの相談にも乗ってもらえます。
弁護士費用特約を使う
交通事故の示談交渉において、強い味方になってくれるのが弁護士特約です。
特約が使えると自分自身で料金を負担する必要がなくなるので、金銭面を気にせず安心して示談交渉を任せられるようになります。
負担してもらえる金額には限度があり一般には法律相談料10万円、着手金・成功報酬・実費などは300万円が上限ですが、よほど損害賠償が高額になる場合を除いて交通事故の弁護士費用は300万円を超えることはまれです。実質的には全額を特約でまかなえます。
交通事故の被害者になったらぜひ弁護士特約の有無を調べてみてください。現在は自動付帯になっている自動車保険も多いのですが、使えることを理解しておらず損をしている方もいるようです。ちなみに、特約を使用しても保険の等級には影響しませんので、翌年の保険料が上がるといった心配はありません。
弁護士特約が使えなくてもまずは相談を
もし特約の利用ができなくても、弁護士に示談交渉について相談するのは有効です。交通事故では弁護士費用よりも回収金(示談金)のほうが高額になるケースがほとんどです。
交通事故では弁護士に示談交渉を依頼すると損害賠償の算定が高額の弁護士基準となり、訴訟を起こしたときと同水準の金額獲得が目指せます。そのため、個人で加害者側の保険会社と示談交渉する場合よりも、結果的に受け取る損害賠償を増額しやすくなります。

まとめ
弁護士に示談交渉を依頼すると相談料や着手金、報酬金などがかかり、費用面の心配が出てきてしまいます。しかし、弁護士特約を利用すればほとんど金銭的な負担をしなくても良くなります。特約がなくても弁護士に示談交渉してもらえば損害賠償が増額されるので、ほとんどのケースでは示談金が弁護士費用を上回ります。
負担を減らせる、交渉をスムーズに進められる、請求できる損害賠償が高額になるといった多くのメリットがありますので、結果的に交通事故の示談交渉では弁護士に依頼するメリットのほうが大きいといえます。交通事故の示談交渉に悩みがあるなら、無料相談を積極的に利用し弁護士への依頼を検討してみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ