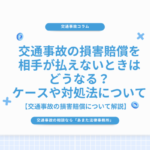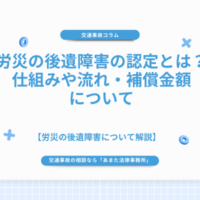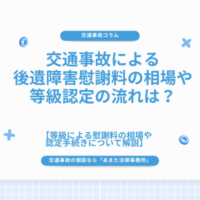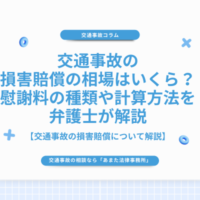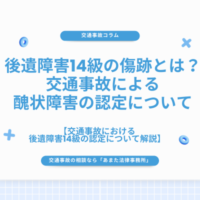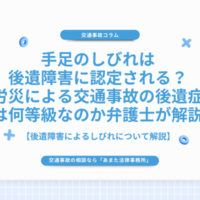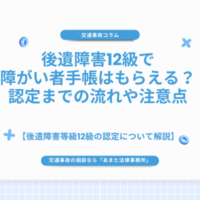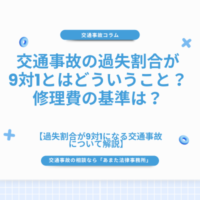交通事故で後遺症が残ると、後遺傷害慰謝料が請求できます。
後遺障害慰謝料の相場は後遺症の度合いにより違います。また、用いる計算基準でも変わってくるため注意が必要です。
慰謝料を獲得するためには、後遺障害に申請し等級認定を受けなければなりません。

この記事の目次
交通事故における後遺障害慰謝料とは
交通事故で後遺症残ると請求できるのが、「後遺障害慰謝料」です。
慰謝料は不法行為により感じた肉体的・精神的苦痛や苦痛を、お金に換算し支払われる補償です。交通事故では治療費やケガに対する「傷害慰謝料」が支払われますが、後遺症が残ったこと、今後の日常生活に支障が出ることの苦痛に対し、後遺障害慰謝料も別途請求できるようになります。
後遺症は病院で怪我や病気の治療を続けても完治する見込みがなく何らかの症状が残ってしまうことで、交通事故を原因とする後遺症は「後遺障害」と呼ばれます。
後遺障害と認めてもらい慰謝料を獲得するには、具体的に下記のような条件を満たしている必要があります。
- 受傷した傷害が治ったのに、身体に障害が残っている。
- 傷害の原因が交通事故にあることが医学的に証明されている。
- 労働能力の低下(もしくは喪失)が認められる。
- 傷害の程度が自賠責保険の等級に該当する。
1の条件にある「傷害が治った」とは、医師から「病状固定」の診断を受けた時を指します。「病状固定」は一定の治療を続けたもかかわらず、これ以上治療症状の改善が見込めないと判断された状態です。
病状固定の以降は、傷害慰謝料や治療費の算定期間ではなくなります。代わりに後遺障害慰謝料や後遺症により将来受け取れるはずだった給与などの利益が手に入らなくなったことへの補償である「後遺障害逸失利益」などを請求できるようになります。
逸失利益は会社員や自営業者だけでなく、無職の専業主婦(主夫)、学生なども対象です。
後遺障害等級の決まり方3つ
交通事故では2か所以上にケガを負ったり、何度か事故に遭い複数の後遺症が残るケースは存在します。このようなときは、3種類のルールを用いて後遺障害の等級や系列を決め、慰謝料の金額も算出することになります。
交通事故における後遺障害は1級~14級の等級と、部位や傷害の程度による140種類、35の系列の段階に細かく分類されています。後遺障害の各等級に認定される症状の条件は「後遺障害等級表」で確認できます。
例えば、同じ眼の障害でも視力障害や欠損など、どのような障害かで系列が異なります。また、同じグループのなかでも序列といわれる障害の上位、下位関係が決められています。
併合
等級および系統が異なる2つ以上の障害を残す際に、等級が繰り上がることを併合といいます。
- 5級以上の障害が2つ以上残った場合→重い方を3等級繰り上げ
- 8級以上の障害が2つ以上残った場合→重い方を2等級繰り上げ
- 13級以上の障害が2つ以上残った場合→重い方を1等級繰り上げ
- 14級の障害が複数残った場合→14級
| 重い方の等級→ ↓2番目に重い等級 | 1~5級 | 6~8級 | 9~13級 | 14級 |
|---|---|---|---|---|
| 1~5級 | 重い方の等級にプラス3級 | |||
| 6~8級 | 重い方の等級にプラス2級 | 重い方の等級にプラス2級 | ||
| 9~13級 | 重い方の等級にプラス1級 | 重い方の等級にプラス1級 | 重い方の等級にプラス1級 | |
| 14級 | 重い方の等級 | 重い方の等級 | 重い方の等級 | 14級 |
例えば、一番重い等級が5級でほかに6級の障害が残っていれば、重い方の等級にプラス2となり後遺障害等級の認定は3級となります。慰謝料も3級の相場が適用されます。
| 4級と5級→1級 | 8級と8級→6級 |
| 5級と5級→2級 | 8級と13級→7級 |
| 5級と6級→3級 | 13級と13級→12級 |
| 5級と8級→3級 | 13級と14級→14級 |
| 5級と13級→4級 | 14級と14級→14級 |
ただし、例外的なケースや併合ができないケースはあります。
・みなし系列……片方の腕と指の両方に障害が残るときのように、系列が異なる後遺障害でも、同じ箇所に残っていると同一の系列とみなされるケースがあります。
・組み合わせ等級……両腕を肘より上で喪失したケースのように、部位や系列が異なる後遺障害のなかにも例外的にまとめられる物があります。
併合の対象になる後遺症なのか、詳しい知識がない人が適切に判断するのは難しいです。迷ったら交通事故の案件に詳しい弁護士に相談してください。
加重
「加重障害」は過去の交通事故などが原因の後遺症が、再度の事故で度合いが重くなってしまった後遺症のことです。
加重障害では過去に受け取った慰謝料の金額を差し引いた差額のみが支払われます。もし障害が以前よりも重くなっていないと判断されれば、新たな慰謝料は受け取れません。
例えば、過去に14級と診断され慰謝料110万円をもらった人が新たに12級と認定された場合、支払われる慰謝料は12級の290万円から110万円を引いた80万円になります。12級の290万円がそのまま加算されると、勘違いしないようにしましょう。

準用
準用は相当とも呼ばれています。本来なら後遺障害に含まれない症状でも、各基準に「相当」していると考えられる程度であれば後遺障害に準ずる等級を適用しようという制度です。
交通事故の後遺障害は認定の基準として、後遺障害等級表によってどのような症状がどの等級に該当するかが細かく決められています。
しかし、後遺障害はケースバイケースです。誰もが同じ症状ではなく、事故により被害の内容や度合いは様々です。等級表だけですべての被害者をカバーするのは不可能に近いという現状があります。
たとえば、等級表では腕や足の機能障害や視覚、聴覚に関しては細かく分類されている一方、味覚や嗅覚などはほとんど規定されていません。味覚や嗅覚の障害は一般の方にとっては大きな支障はないかもしれませんが、料理人など職業によっては労働能力に関わり、被害者にとっては死活問題です。なのに、後遺症が認定されず、慰謝料ももらえないのはおかしいといえます。
このように、個人の事情を考慮して後遺障害認定を行い慰謝料を請求できるようにする措置が取られるのです。
自身の傷害が後遺障害に当たるのか、慰謝料を請求できるのか迷うときは、法律に詳しい弁護士に判断してもらうのが良いでしょう。
後遺障害慰謝料を算出する3つの計算基準
交通事故の後遺障害には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があります。それぞれの基準により相場は異なり、高額の後遺障害慰謝料を獲得できるのは弁護士基準となります。
自賠責基準
すべての車に加入が義務づけられている自賠責保険による算定基準です。事故に対する最低限の補償を目的としているため、3つのうち、もらえるお金の相場は極めて低額になります。
自賠責基準では、入通院慰謝料は1日あたり4300円が認められています。対象となる日数は、「治療の開始から終了までの期間」と「実入通院日数×2」を比較し少ない方になります。
自賠責保険には限度額が決まっており、十分な補償を受けれるとは言えません。上限を超えた分に関しては、加害者の加入している任意保険から支払いしてもらうことになります。もし加害者が任意保険に加入していないときは、弁護士に相談して対処してもらいましょう。
任意保険基準
加害者が加入している任意保険の保険会社が、独自に定めている慰謝料の算定基準です。計算方法は各社が自由に決められ、通常は外部に非公開とされているため詳細は不明です。任意保険基準では、通院期間よりも入院期間の方が高額な入通院慰謝料を設定しているケースが多いようです。
一般的には自賠責基準よりは高いとされていますが、実際には数十万程度の違いで大幅な差はありません。
弁護士基準
弁護士に依頼すると適用される算定基準で、3つの中では極めて高額な慰謝料を受け取れます。別名「裁判所基準」ともいわれ、交通事故で裁判を定期した際もこの基準が適用されますが、裁判をしなくても弁護士に依頼するだけでも構いません。
弁護士基準の慰謝料は、公益社団法人「日弁連交通事故相談センター」から発刊されている「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)や日弁連交通事故センター東京支部から刊行されている「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)などに記載されている基準を 参考に計算されます。
自賠責基準と比べると金額が2~3倍に増額されることもあり、弁護士基準こそが交通事故の被害者が本来受け取るべき適正な金額です。
デメリットとして弁護士費用がかかる点が上げられますが、後遺障害は慰謝料の金額も大きくなるので、弁護士費用が獲得できる金額を上回って赤字になる「費用倒れ」は起こりにくいといえます。

入通院慰謝料の早見表
「自賠責基準」と「弁護士基準」では、入通院慰謝料の金額はどのくらい違うのかをまとめました。
| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準(※軽傷の場合) |
|---|---|---|
| 1か月 | 12.9万円 | 28万円 (19万円) |
| 2か月 | 25.8万円 | 52万円 (36万円) |
| 3か月 | 38.7万円 | 73万円 (53万円) |
| 4か月 | 51.6万円 | 90万円 (67万円) |
| 5か月 | 64.5万円 | 105万円 (79万円) |
| 6か月 | 77.4万円 | 116万円 (89万円) |
このように、弁護士基準の入通院慰謝料は自賠責基準の約1.5倍~2倍程度の金額となっていることがわかります。
後遺障害慰謝料の相場はどれくらい?
実際にどれくらいの金額を後遺障害慰謝料としてもらえるのか、基準ごとの目安をまとめました。
任意保険基準は公表されておらず詳細が分からないため省略していますが、相場は自賠責基準プラス数十万円程度と考えると良いでしょう。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級(要介護) | 1650万円 | 2800万円 |
| 1級 | 1150万円 | 2800万円 |
| 2級(要介護) | 1203万円 | 2370万円 |
| 2級 | 998万円 | 2370万円 |
| 3級 | 861万円 | 1990万円 |
| 4級 | 737万円 | 1670万円 |
| 5級 | 618万円 | 1400万円 |
| 6級 | 512万円 | 1180万円 |
| 7級 | 419万円 | 1000万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
実際にもらえる慰謝料を比較
自賠責基準と弁護士基準で獲得できる慰謝料の表をもとに、具体的な後遺障害の事例と金額の目安を紹介します。
むちうちは追突や衝突の影響で頸部にダメージを受け、しびれや痛み、違和感、眩暈などの神経症状が出る後遺症です。
交通事故では比較的生じやすい後遺障害であり、等級は局部に神経障害が残った程度は14級、著しい神経障害が残ったものは12級が該当します。
- 14級 自賠責基準では32万円、弁護士基準では110万円
- 12級 自賠責基準では94万円、弁護士基準では290万円
いずれも弁護士基準では、自賠責基準の3倍以上の金額になっています。
ただ、むちうちは手指や足指の一部を失ったような目に見えた障害ではないため、軽症とみなされ認定の難易度が高くなってしまうのが注意点といえるでしょう。
骨折は人身事故ではよく生じる後遺障害です。どの部位を骨折し、どういった障害が残ったかで後遺障害の内容は多岐にわたり、ほぼすべての等級に該当する可能性があります。
今回は頭蓋骨骨折と足の骨折を取り上げます。
頭蓋骨骨折は非常に重い後遺症が残りやすく、極めて重症といえます。神経の機能に著しい障害が残り常に介護を必要とする状態になると、1級(要介護)が認定されます。
金額は自賠責基準1650万円、弁護士基準2800万円です。
足の骨折では片方の関節に偽関節が生じ著しい運動障害が残ると7級となります。
金額は、自賠責基準で419万円、弁護士基準で1000万円です。
事故によって眼を負傷したことによる視力の障害では、何よりも重い後遺症であるのが失明です。失明による等級認定と相場は以下のとおりになります。
・両目とも失明→1級……自賠責基準1150万円 弁護士基準2800万円
・両目とも視力0.02以下または片方が失明でもう一方の視力が0.02以下→2級……自賠責基準998万円 弁護士基準2370万円
・片方を失明し、もう一方の眼が視力0.06以下→3級……自賠責基準861万円 弁護士基準1990万円
後遺障害等級が上になり慰謝料の金額が大きくなると、弁護士基準では自賠責基準と比べて1000万円以上金額が異なるケースも出てきます。交通事故の後遺障害慰謝料では弁護士基準で算定すると、極めて多くの金額を受け取れるといえるでしょう。
慰謝料が相場より減額されるケース
慰謝料が減額されるケースはあります。
- 過失割合が被害者側にもある
交通事故などで、被害者自身にも過失があった場合、その割合に応じて金額が減額されることがある(過失相殺) - 被害者の責任割合が大きい
被害者が事故当時に交通ルールを守らなかったり、危険な行動をとった - 被害者の訴えに根拠がない
被害者が慰謝料を請求する根拠が乏しい - 請求額が高額すぎる
被害者が請求する金額額が、一般的な相場や法律の規定を超えている - 労災保険と重複する部分がある
労災保険で支払われた休業補償や治療費などが、損害賠償請求による慰謝料と重複している場合は相殺される
ただし、事情や交渉次第で少しの減額で済んだ実例はあります。上記の条件に該当するからと諦める前に、弁護士へ相談してみましょう。
死亡事故でもらえる慰謝料の相場を比較
被害者が命を落としてしまった死亡事故では、被害者の遺族は加害者に死亡慰謝料を請求できます。被害者本人と相続人となる遺族に対する慰謝料を合計した金額を受け取れます。
基本的に相続人は父、母、妻、子供が対象となりますが、以外の立場となる親族が請求できる可能性もあります。
自賠責基準と弁護士基準で計算した金額は、以下のようになります(任意保険基準は算定方法が明確でないため省略)。
自賠責基準
本人への慰謝料400万円と請求権者および被扶養者の数で決まります。
| 請求権者 | 慰謝料 |
|---|---|
| 1人 | 550万円 |
| 2人 | 650万円 |
| 3人 | 750万円 |
| 被扶養者 | 1人につき+200万円 |
例えば、父親が死亡しその妻と子ども1人に慰謝料が支払われる事故では、
本人(父親)の分400万円+遺族2人(妻と子ども)への分650万円+被扶養者1人(子ども)200万円=1250万円
が受け取る金額になります。
弁護士基準
弁護士基準では本人と遺族への慰謝料を合わせた額と決まっており、生前、家族内でどのような地位にあったかで金額が変わります。
| 一家の支柱になる人物(父親など) | 2800万~3600万円 |
|---|---|
| 一家の支柱に準ずる者(配偶者、母親など) | 2000万~3200万円 |
| 高齢者、子どもなど | 1800万~2600万円 |
上の例と同様、3人家族の父親が亡くなった場合、弁護士基準での金額は最大3600万円となり、自賠責基準と比べると約3倍の差があります。
後遺症の等級認定から慰謝料支払いまでの流れ
交通事故のあと後遺障害等級の認定を受けると「後遺障害慰謝料」を受け取れる可能性が高くなります。もし申請しても等級が認定されなければ、後遺症が残ったとしても補償は受けられません。
後遺障害等級は交通事故の被害者なら自動的に適用されるものではないため、定められた正しい手続きによる申請をして認定してもらうことが重要です。

1、申請を行うタイミングは病状固定後
後遺障害等級の認定を申請するには、医師から病状固定の診断を受ける必要があります。
事故後、これ以上治療をしても症状の改善が認められないと判断されたら、医師に「後遺障害診断書」を書いてもらいましょう。そして等級を判定している「損害保険料率算出機構」にある「自賠責損害調査事務所」という機関へ、後遺症の有無を証明できる書類と一緒に提出し申請します。
2、後遺障害の申請方法は2種類
後遺障害の申請方法には、加害者型の任意保険会社に仲介してもらう「事前認定」と手続きを被害者が自分で行う「被害者申請」の2通りがあります。
事前認定
事前認定は手続きを保険会社が一括して行ってくれます。被害者が用意するのは後遺障害診断書くらいで、それ以外の書類や資料を集める手間がかかりません。判定に必要となる資料や画像などを入手するための費用も保険会社が支払ってくれますし、金銭面の負担を減らせるのもメリットです。
ただし、自薦認定は場合によっては後遺症が認められない、十分な等級での認定を受けられないといった可能性はあります。
審査は損害保険料率算出機構が行いますので大きく不利になると一概にはいえません。しかし保険会社はなるべく支払う保険金を少なくしたいと考え、加害者側が不利になるような書類を故意に提出しなかったりするという理由があるからです。
さらに、事前認定は後遺障害慰謝料と他の損害賠償、慰謝料が一括して支払われるため、保険金の先払いはできなくなります。
被害者請求
被害者自身が書類を作成し、加害者の自賠責保険会社を仲介として申請を行う方法です。書類を作成する手間や費用はかかりますが、加害者との示談が成立する前でも自賠責保険の限度額までなら保険金受取が可能になるメリットがあります。
被害者請求による先払いは、自賠責保険の限度額120万円に達するまで何度でも利用できます。
また、被害者が有利になる書類を徹底的に集めての提出が可能となるため、後遺障害の等級が認定されやすい面もあります。ただ、被害者が1人で書類を取集するのは難しいでしょう。交通事故の事案に強い弁護士にやってもらうのがおすすめです。
3、申請にかかる期間の平均は2か月
後遺障害等級の認定結果は、通常、申請から1か月~2ヶ月で出ます。
もし2か月を超えても音沙汰がないようであれば、こちらから保険会社に問い合わせをしてください。
事前認定は時間がかかりがちでなかなか連絡が来ないことはあります。保険会社は同時に数十件の案件を抱えているので、処理が遅れたり連絡が滞ったりする状況になりやすいためです。
被害者請求は保険会社を挟まないので、基本的に手続きの時間が早くなる傾向がありますが、書類に不備が見つかったなど差し戻しになり時間がかかるケースは考えられます。

4、認定から慰謝料の支払いまで
後遺障害等級認定後は後遺障害慰謝料を含めた示談金を決めるため、相手方と示談交渉を行います。等級による慰謝料の相場はあくまで目安で、具体的な金額は交渉によって決定されます。
原則として双方が合意し示談が成立すると、通常は2週間程度で賠償金が支払われます。
もし、示談がまとまらず話し合いで解決しないときは、最終的な手段として民事訴訟等で決着をつけることになります。裁判になると半年や1年以上と長い期間がかかるケースもあり、示談と比べて支払いまでに時間を要します。
後遺障害逸失利益における補償額の算出方法
後遺症として認定されると、後遺障害慰謝料だけでなく「逸失利益」も請求できるようになります。逸失利益とは後遺症で労働能力が半分になるなど喪失してしまい、将来もらえるはずだった給与等の利益が手に入らなくなったことへの補償です。
後遺障害逸失利益の補償額は、次の3つの要素を基に算出されます。
- 収入の減少額:被害者の職種や年収、就業状況、障害程度などに応じて算出されます。
- 生活費の増加額:後遺障害によって、被害者が生活費などの必要経費に増加負担を強いられた場合、その増加額が補償されます。例えば、介護や通院、薬剤代、医療費などが該当します。
- 精神的な苦痛に対する補償:後遺障害によって、被害者が受けた悔しさ、苦痛、精神的な苦痛に対して、ある程度の補償が行われることがあります。この場合、被害者の人格、仕事、家族関係などの個人的要素によって、補償額が変わることがあります。
不安があれば弁護士に相談を
後遺障害の慰謝料に関して不安や悩みがあれば、自分で判断せず弁護士など法律の専門家へ相談することをおすすめします。一般の人は示談交渉の知識や対応の経験がないのが普通です。交渉に時間がかかったり、自分が納得できない賠償金しかもらえなくなるおそれがあります。
実績が豊富な弁護士なら後遺障害認定の手続きや交渉もスムーズに行えますし、慰謝料の算定も弁護士基準が適用されるため、受け取れる賠償金もしっかり増額できます。
弁護士費用がかかるのが難点ですが、現在は相談や着手金が無料になるサービスを実施している弁護士事務所は多々あります。また、加入している自動車保険などの任意保険に弁護士特約が付帯していれば、負担ゼロで弁護士に依頼することも可能です。料金が発生しなければ、気軽に利用できるでしょう。

まとめ
交通事故で後遺症が残ったとき、後遺障害等級の認定を受けると加害者に後遺障害慰謝料を請求できるようになります。慰謝料の相場は等級と、3つの算定方法のうちどれを使用するかで異なります。
後遺障害が残ると今後の生活にはとても大きな影響をもたらしますから、受け取る慰謝料は少しでも高額なほうが望ましいでしょう。弁護士に依頼すれば弁護士基準が使え慰謝料を増額できる可能性が高くなります。さらに後遺障害認定の手続き面でのサポートはもちろん、相手方との示談交渉も任せられます。
交通事故で後遺症が残り加害者への慰謝料請求を考えているなら、弁護士への相談を検討してください。相談はいつでも受付しています。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ