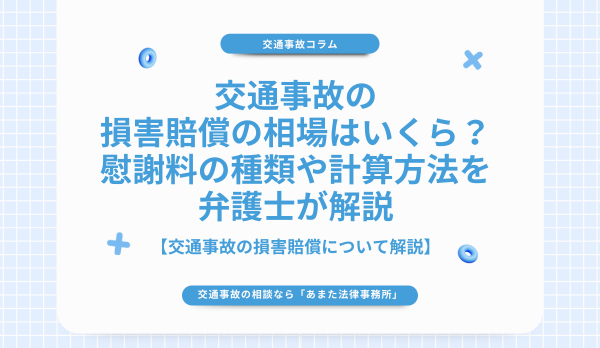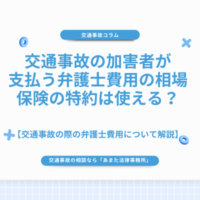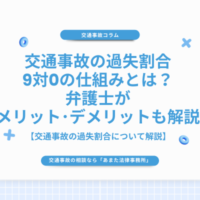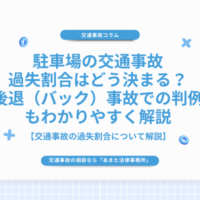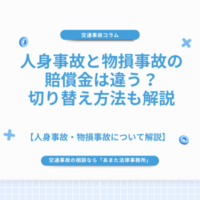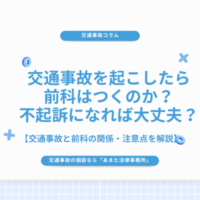交通事故の被害者は、加害者から損害賠償を受け取れます。
しかし相場はいくらでどんな種類があるのか知らないと、請求しそびれてしまったり、低い金額しか獲得できない危険性が高くなります。

執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
交通事故の損害賠償とは
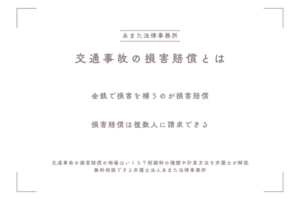
損害賠償とは、民法に定められている賠償金です。不法行為等により被害者に生じた損害を補償するものであり、交通事故ではケガの治療費や破損した車の修理代、慰謝料などが含まれます。
金銭で損害を補うのが損害賠償
責任を金銭によって支払うものが損害賠償です。民法709条では「故意または過失によって、他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、生じた損害を賠償する責任を負う」と定められています。
道路交通法70条には安全運転義務として、「車両等の運転者は、他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転しなければならない」とされています。交通事故で他人にケガをさせたり、物損を起こすことは上記義務の違反となります。
損害賠償は複数人に請求できる
複数の人間が関係する交通事故では、それぞれの加害者に損害賠償を請求できます。
何人もがかかわって発生する損害は、民法第719条で定められている「共同不法行為」にあたり、「各自が連帯して賠償責任を負う」とされています。
交通事故の状況によっては、車の使用者だけでなく運行供用者などの慰謝料も請求できます。運行供用者とは車の運行を支配し、利益を得ている者を指し、バス会社やタクシー会社などが代表的です。
またA、Bなど加害者が複数いる事故では、損害分すべてを1人に請求しても、2人以上に分けて請求してもかまいません。

請求できる損害賠償金の種類
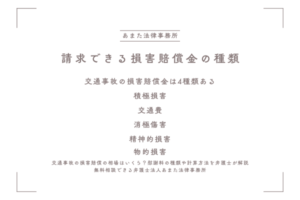
交通事故で相手方に請求できる損害賠償には、いくつもの種類が存在しています。実際に受け取れる項目について詳しく説明していきます。
交通事故の損害賠償金は4種類ある
交通事故で加害者に請求できる損害賠償の内訳は、
- 積極損害
- 消極損害
- 精神的損害
- 物的損害
主に上記の4種類に分けられます。
積極損害
被害者が事故のために出費しなければならなくなったお金で、事故がなければ不要だった費用です。
人身事故ではケガの「治療費」や病院へ通うための「交通費」、車椅子や義足、コルセットなどリハビリや介護に必要な「装具・器具の購入費」など付随する費用が含まれます。死亡事故では「葬儀費用」も対象です。
治療費(積極損害)
交通事故で発生したケガを治療するため、病院に入通院したときにかかる費用です。診療費や薬代、手術代、応急手当費、検査費用、リハビリ費用などが含まれます。
医師から完治または病状固定と診断されるまでほぼ全額請求でき、相手方が加入している保険から実費で支払われます。
しかし注意点となるのは、認められるのは医療行為として必要かつ適切と判断されるもののみであることです。
また、相手方の保険会社が治療費の打ち切りを提案してくることがありますが、医師がまだ治療の必要があると判断しているのであれば応じなくてもかまいません。治療は継続しましょう。
付添看護費
事故後の入院や通院の際に、付添看護が必要になったときの費用です。
原則として医師から付添が必要と判断されたときに請求できます。職業看護人は全額支払われるのが原則です。家族や近親者が付き添った場合は1日当たりの金額が決められており、自賠責保険基準では1日2,100円、弁護士基準(裁判基準)では1日3,300円が相場です。
交通費
ケガのため病院に入通院するときにかかった交通費です。
基本的に全額実費での請求が可能ですが、認められるのは必要性・妥当性があると判断されるものに限られます。
自家用車での通院は必要性・妥当性があるなら駐車場代やガソリン代、高速料金などが請求可能です。
タクシー代は注意が必要です。骨折により電車やバスといった公共交通機関に乗車できないなど、特別な事情や事由がない限りは認められない事例が多くなっています。やみくもにタクシーを使用するのは控えるのが良いでしょう。
入院雑費
入院中に必要になったお金です。
パジャマや寝具、ティッシュ、洗面用具、文房具といった日用品・消耗品のほか、公衆電話に使用するテレホンカードや手紙用の切手代といった通信費、新聞・雑誌、テレビカードを購入するための文化費などが該当します。
請求できる金額は定額化されており、入院1日当たり1100円~1500円程度が相場です。
器具・装具費
車椅子や義足、義手、義眼、リハビリ用の器具など、事故後、何らかの後遺症が残ってしまったときに発生するような費用です。
購入費やレンタル費用を実費として請求できますが、将来買い替えが必要になると見込まれる器具を計算に入れ、中間利息を差し引いた金額をプラスすることが可能です。
将来介護費用
事故で障害が残ったときなど、将来的に介護が必要となったときの費用です。
将来の介護費は高額になりやすく、示談では介護費用の金額がでもめるケースは少なくありません。
自宅改修費
事故後、バリアフリー化や手すりの設置など、自宅の改修が必要になった場合の費用です。
認められるのは介護に必要と判断できる部分のみです。利便性向上のためでは認めてもらいにくいでしょう。
車両の改造費
事故による後遺症のため通常の運転ができず、車を改造しなければならなくなったときの費用です。
認められるのは必要なものだけで、不必要な改造や設備の設置分は請求できません。
葬儀費用
不幸にも被害者が亡くなってしまった死亡事故では、葬儀にかかった費用を請求できます。
葬儀そのものの費用から、火葬・埋葬料金、読経・法名料、花代、お寺・僧侶へのお布施、食事代、仏壇などの購入費、遺族の交通費、四十九日法要費などが含まれます

損害賠償にかかる費用
損害賠償を請求するためにかかる費用です。
医師に作成してもらった診断書の費用や交通事故証明書、印鑑登録証明書を発行する費用、成年後見人を選ぶための手数料などが対象です。
弁護士費用
加害者との示談交渉を依頼した、弁護士に支払う費用です。
基本的に弁護士費用は被害者の負担ですが、裁判を行うと一部を加害者に請求できるようになります。
損害遅延金
金銭債務において支払いが遅れたとき、請求できるお金を「損害遅延金」といいます。
交通事故では事故直後すぐに損害賠償は支払われません。お金を受け取れるのは加害者との示談が成立してからです。
事故から賠償金の支払いまでのタイムラグが加害者による支払い遅延と位置付けられ、損害遅延金を請求できることがあります。ただ請求できるのは裁判所に訴えた場合に限られ、示談のみで支払われることはほぼありません。
消極傷害
交通事故に遭ったことで得られなくなった経済的利益に対する賠償金です。
事故でケガをしたため会社を休まなければならなくなったり、家事ができなくなってしまったり、後遺障害が残ったことで労働力が低下し仕事を続けられなくなったため発生した損害が含まれます。具体的には「休業損害」や「後遺障害逸失利益」などが当たります。
休業損害
事故で仕事を休んだことにより、収入が減少した分を加害者に請求できるのが休業損害です。
会社員は直近3カ月の給与明細(基礎収入)と休んだ期間により損害額が算出され、有給休暇の使用分も請求できます。事業主は1日当たりの収入から算出します。
また、専業主婦も「賃金センサス」という国の統計情報をもとにした平均賃金から、損害の計算が可能です。無職であっても失業中で近い将来就職する予定があれば、請求できる可能性があります。
後遺障害逸失利益
事故後に後遺症が残り将来的に減少した収入を補填する賠償金が、「後遺障害逸失利益」です。
休業損害がケガ治療中の収入減少を対象としているのに対し、後遺障害逸失利益は病状固定してからこの先に考えられる損害を補償対象としています。
金額は現在の収入をもとに計算され、会社員や自営業者のほか、給与所得のない主婦(主夫)でも請求できます。また、子供や学生も将来就職していたら得られるはずだった収入の補償として請求可能です。

死亡逸失利益
被害者が事故に遭わず死亡しなければ、将来働いて得られるはずだった給与などの収入の補填として請求できる賠償金です。
現在の収入や死亡時から定年までに働ける期間によって算出され、収入が高く、年齢が若いほど相場は高額になります。専業主婦(主夫)や子供、高齢者、失業中など収入がない人でも、平均賃金などをもとに請求可能です。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は傷害慰謝料とも呼ばれ、事故により病院へ入通院することで受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。
治療期間をもとに算出され、重症で入通院期間が長引いた場合ほど高額になりますが、軽い症状でも医療機関で治療を受ければ請求できます。捻挫や打撲、擦り傷程度の軽傷で、事故に遭った日に1日だけ病院に行っただけでも受け取れます。
精神的損害
交通事故によるケガ以外に、被害者や遺族が被った精神的な損害です。精神的損害に対する補償は、慰謝料と呼ばれています。
具体的なものには入院に対する「入通院慰謝料」、後遺症に対する「後遺障害慰謝料」があります。そして被害者が死亡した事故により、被害者自身の無念や残された遺族の悲しみに対し支払われる「死亡慰謝料」などがあります。

後遺障害慰謝料
事故で後遺症が残ったことで受けた、精神的苦痛に対する慰謝料です。
ただし、後遺症であればどんなものでも請求できるわけではありません。後遺障害等級を申請し認定を受ける必要があります。
交通事故の後遺障害は最も重度の1級~14級の等級に分かれており、重症になるほど慰謝料も高額になります。
医師に後遺障害診断書を書いてもらう→「損害料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」と呼ばれる専門機関に申請する→審査を受ける
以上が認定までの流れです。

死亡慰謝料
被害者が亡くなった事故で請求できる慰謝料です。被害者本人に対するものと遺族に対するものの2種類があります。
被害者本人への慰謝料は事故で「死に至らしめられた」という精神的苦痛への慰謝料です。本来は被害者自身に支払われるべきですが、すでに死亡しているため、両親、妻、子供などの「相続人」が受け取ります。被害者本人への慰謝料は、相続人の合意があれば自由に分配可能です。
遺族に対する慰謝料は「近しい人を失った」という精神的苦痛を補償するお金です。民法第711条では、他人の生命を侵害した者はその父親や母親、配偶者、子供にも損害を賠償しなければならないと定めています。
物的損害
交通事故で発生した物損に対する補償です。
車両の修理代や破れた衣服・壊れた手荷物の代金、車を修理する間の代車費用などが含まれます。
車両修理費
事故で破損した自動車の修理費用です。
請求範囲は事故による破損部分のみとなり、事故の前からついていた傷や壊れていた箇所、不要と判断される修理は対象外です。
修理代が車両の時価額を上回ってしまうと「経済的全損」となり、残念ながら修理費は支払ってもらえません。しかし、車両の時価と買い替えにかかった金額は請求できます。
代車使用料
事故で車が壊れて修理が終わるまでの間に、使用した代車の代金です。レンタカー代などが対象です。
代車費用を支払ってもらうには、公共交通機関やタクシーの利用では生活するうえで不十分であると認定される必要があります。また代車のグレードは、事故で破損した車両と同等でなければなりません。
評価損
「格落ち損」とも呼ばれます。事故車になり、価値が下がってしまった分の損害を相手側に支払ってもらうお金です。
評価損は車が修理不能になり性能的な低下を起こす技術的なものと、中古車市場での価格が下がってしまう取引上のものの2種類に分けられます。

休車損
営業車は事故がなければ稼働によって得られたであろう利益を、休車損として請求できます。
認められるのは修理や買い替えまでの期間のみで、代わりの車を保有していないことが条件になります。
その他の物的損害
事故との因果関係が認められる事案は、損害賠償として請求可能です。
事故車両の引き上げやレッカー移動にかかった費用、車に搭載していたカーナビやテレビの修理費用、積み荷の損害、同乗していたペットがケガをしたときの動物病院の治療費などがあります。
交通事故の損害賠償算定基準は3種類
交通事故では、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判)基準」3つの損害賠償の計算方法があります。適用する計算方法で受け取れる相場が大きく変わるのですが、金額が高額になる弁護基準を用いるのがおすすめです。
すべての車に加入が義務づけられている自賠責保険による算定基準です。
最低限の補償を目的としているため、3つの基準のなかで最も低額になっています。自賠責保険で補償される金額より損害賠償の金額が上限を超えると、加害者が加入している任意保険から支払いを受けることになります。
加害者が加入している自動車保険の算定基準です。
計算方法は保険会社が自由に設定しており一般的に外部には非公開とされています。そのため、詳細な金額を知りたくてもわからないのが現状です。
相場は自賠責基準より高額と言われますが、実際のところそれほど大きな違いはありません。
また保険会社はなるべく支払う保険金を安く済ませたいと考える傾向にあるため、示談金の金額を低めに提示してきます。そのため相手側が提示する条件そのまま応じてしまうと、本来よりも少ない賠償額で示談させられてしまう恐れがあります。
弁護士に依頼したときに適用される損害賠償の計算方法です。
3つの基準のなかでは最も高い相場となり、高額な賠償金を受け取れる可能性が高い計算方法です。
弁護士基準では公益社団法人「日弁連交通事故相談センター」から発刊されている「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)や日弁連交通事故センター東京支部から刊行されている「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)などをもとに計算されています。民事裁判に訴えたときにも使われるため、裁判基準とも呼ばれますが、弁護士に依頼すれば裁判を起こさなくてもこちらの基準が適用されます。
受け取れる金額は自賠責基準と比べると2倍~3倍になることもあり、弁護士基準は交通事故の被害者が本来受け取るべき適正な金額といえるでしょう。
交通事故の損害賠償はケガの治療費に充てるなど、今後の家計にも関わる非常に大切なお金です。獲得できる金額はなるべく高いほうが望ましいでしょう。弁護士基準を適用した損害賠償金を受け取れるよう、交通事故の被害者は弁護士への依頼を検討するのがおすすめです。
損害賠償金の相場を3つの基準で比較
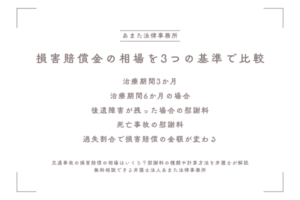
交通事故の損害賠償金を計算する3つの方法で、相場がどれくらい違うのか比較してみましょう。
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準では、治療日数や治療期間、後遺障害の重さなどの状況により慰謝料を計算する仕組みです。
ここでは慰謝料を例に、治療期間が3か月と6か月の場合、死亡事故の場合に分けて、実際に受け取れる金額をみていきます。
治療期間3か月
事故の怪我により、3か月医療機関に通院した場合の入通院慰謝料の目安です。
自賠責基準では、1日あたり支払われる金額が4300円と決められており、入院でも通院でも金額は変わりません。この金額をもとに下記2とおりの方法で計算を行い、金額の低いほうが実際にもらえる慰謝料になります。
①4300×通院期間
②4300×実通院日数×2
今回は治療期間3か月で1か月につき10日の頻度で通院したものとして計算します。
①4300×30日×3か月=38万7000円
②4300×(通院10日×3か月)×2=25万8000円
このうち金額が低い②の25万8000円が受け取る慰謝料になります。
任意保険基準は各保険会社によって計算方法が異なるうえ、非公開とされています。実際のところ、どのような方法で算定されているのか正確には分かりません。そこで、以前にすべての保険会社で共通の基準として利用されていた「旧任意保険支払基準」を参考に計算します。
任意保険基準では治療期間によって慰謝料が決まります。入院と通院で金額が違い、実通院日数は慰謝料に影響しません。
旧任意保険支払基準をもとにした入院および通院の慰謝料算定表
| 入院→ 通院↓ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 0 | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 128.5 |
| 1か月 | 12.6 | 37.8 | 63 | 85.7 | 104.6 | 121 | 134.8 |
| 2か月 | 25.2 | 50.4 | 73.1 | 94.5 | 112.2 | 127.3 | 141.1 |
| 3か月 | 37.8 | 60.5 | 81.9 | 102.1 | 118.5 | 133.6 | 146.1 |
| 4か月 | 47.9 | 69.3 | 89.5 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.1 |
| 5か月 | 56.7 | 76.9 | 95.8 | 114.7 | 129.8 | 143.6 | 154.9 |
| 6か月 | 64.3 | 83.2 | 102.1 | 119.7 | 134.8 | 147.4 | 157.4 |
単位:万円
上記の表を見ると、通院3か月の慰謝料は37万8000円となり、自賠責基準より高額になることがわかります。
弁護士基準の慰謝料は治療期間によって決まり、独自の算定表を使用し計算します。表は軽傷用と重傷用の2つが用意されており、ケガの種類や度合でどちらを使うかが決まります。
弁護士基準軽症用算定表
| 入院→ 通院↓ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 0 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 |
| 1か月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |
| 2か月 | 35 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |
| 3か月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |
| 4か月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |
| 5か月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |
| 6か月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |
単位:万円
弁護士基準重傷用算定表
| 入院→ 通院↓ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 0 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 |
| 1か月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |
| 2か月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |
| 3か月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |
| 4か月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |
| 5か月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |
| 6か月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |
単位:万円
今回は通院3か月なので、軽症用を使用しました。上記の表より弁護士基準での慰謝料は53万円となります。

治療期間6か月の場合
治療期間が6か月で2か月入院・4か月通院したケースで、獲得できる慰謝料はどれくらいか3つの基準でみていきます。
自賠責保険での1日あたりの支払い額は入院でも通院でも変わらず、計算式は3か月の場合と同じになります。
通院期間1か月につき10日として計算すると、
①4300×30日×6か月=77万4000円
②4300×(入院30日×2か月+通院10日×4か月)×2=86万円
となり、2つのうち金額が低い①の77万4000円が受け取れる慰謝料になります。
任意保険基準での慰謝料は上の表を参照すると、89万5000円が目安になります。自賠責基準よりは高額になっていますが、大きい違いが出るわけではなく十分とは言えないでしょう。
治療期間が6か月ですので、重症用の算定表を用いて計算します。
弁護士基準での慰謝料は165万円となり、自賠責基準の2倍以上で、他2つの基準よりも慰謝料は一桁多い額になります。
後遺障害が残った場合の慰謝料
入通院だけでケガの症状が完治せずなんらかの後遺症が残ってしまったら、後遺障害慰謝料を請求できます。交通事故ではむちうちなどの軽傷でも後遺症が残ることは多く、後遺障害慰謝料をもらえる可能性は高いでしょう。
後遺障害慰謝料は認定される後遺障害の等級によりもらえる金額が決まっており、算出する基準ごとに慰謝料額が変わります。各等級での自賠責基準・弁護士基準による慰謝料の相場は以下のようになります。

| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級(要介護) | 1650 | 2800 |
| 1級 | 1150 | 2800 |
| 2級(要介護) | 1203 | 2370 |
| 2級 | 998 | 2370 |
| 3級 | 861 | 1990 |
| 4級 | 737 | 1670 |
| 5級 | 618 | 1400 |
| 6級 | 512 | 1180 |
| 7級 | 419 | 1000 |
| 8級 | 331 | 830 |
| 9級 | 249 | 690 |
| 10級 | 190 | 550 |
| 11級 | 136 | 420 |
| 12級 | 94 | 290 |
| 13級 | 57 | 180 |
| 14級 | 32 | 110 |
単位:万円
後遺障害が残った場合の慰謝料も、弁護士基準は自賠責基準を大きく上回っています。等級によっては、1000万円以上の差になることもあります。
死亡事故の慰謝料
被害者が死亡した死亡事故では、加害者に死亡慰謝料を請求できます。3つの基準で計算してみましょう。
自賠責基準では、被害者本人への慰謝料は400万円と決まっています。遺族への慰謝料は、慰謝料請求権者の人数によって変わり、被扶養者がいる場合はさらに1人あたり200万円加算されます。
| 請求権者 | 遺族への慰謝料 |
|---|---|
| 1人 | 550万円 |
| 2人 | 650万円 |
| 3人 | 750万円 |
| 被扶養者 | 1人につき+200万円 |
例えば、事故で死亡したAさんは妻、子供の3人家族で、請求権者は妻と子の2名、被扶養者は子供1名だったとします。
400万円(本人への慰謝料)+650万円(遺族への慰謝料)+200万円(非扶養者)=1250万円となり、Aさんの事故のケースで得られる慰謝料は1250万円になります。
任意保険基準では死亡慰謝料の算定方法は非公開とされており、正確な相場は分かりません。ただ、家庭内での立場により金額が設定されており、一家の大黒柱である人物が死亡した事故の慰謝料は、1500万円~2000万円程度が目安とされています。
弁護士基準では本人への慰謝料と遺族への慰謝料を合計した金額が決められています。
弁護士基準での死亡慰謝料
| 一家の支柱である場合 | 2800万円 |
|---|---|
| 一家の支柱に準ずる者(母親、配偶者) | 2400万~2700万円 |
| その他(独身の男女、子供、高齢者など) | 2000万~2500万円 |
3人家族で夫が死亡した事故の慰謝料は2800万円となり、自賠責基準の2倍以上の金額になっています。
弁護士基準を適用することで大幅な増額が期待できるでしょう。
また休業損害や付添費、入院雑費などの項目に関しても、自賠責基準と弁護士基準で金額は異なります。交通事故の損害賠償請求では、弁護士に依頼すると全般的に受け取れる金額は高額になると言えます。
過失割合で損害賠償の金額が変わる
損害賠償金の相場はあくまでも目安であり、過失割合により金額が変わってきます。
過失割合は事故の責任を数字にしたもので、1:9や2:8などと表します。もし損害賠償金が100万円で過失割合が2:8だったとすると、被害者が受け取れるのは100万円から2割の20万円を差し引いた80万円となります。これを過失相殺といいます。
追突事故は0:10になりやすいですが、通常は被害者にも一定の過失があるとされています。実際には相場通りの金額をもらえるわけではないと思っておきましょう。詳細な計算は一般の人では難しいので、弁護士に相談し確認してもらうのがおすすめです。
損害賠償請求には時効がある
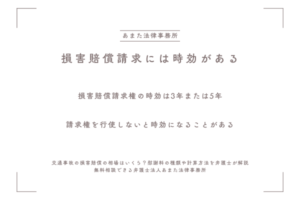
交通事故の損害賠償請求で注意しなければならないのが時効です。
事故から一定の期間が経過すると時効が成立して請求権が失われてしまい、損害賠償金を受け取れなくなってしまいます。
損害賠償請求権の時効は3年または5年
交通事故における損害賠償の時効は、基本的に被害者が事故の加害者および損害を知った翌日から3年または5年です。
時効は物損事故が3年(民法724条)、人身事故が5年(民法724条の2)です(民法が改正された2020年(令和2年)4月1日以降より)。ただ時効が発効されるのは加害者を知った日からとなっています。被害を受けたけれど加害者が分からないひき逃げなどでは、発生からすぐに時効がカウントされない事故もあります。
参考:法務省

請求権を行使しないと時効になることがある
民法724条2号では不法行為から20年間権利を行使しないときは、時効が成立して損害賠償請求権が消滅すると定められています。
ひき逃げのように加害者が分からない事故でも、時効がいつまでも来ないわけではありません。事故から20年経過すると時効になってしまう点には注意が必要です。
請求し忘れに気づいても時効を迎えていれば、受け取れず損をしてしまいます。
交通事故の損賠賠償は弁護士に相談しよう
交通事故の被害者は、加害者に慰謝料を含む損害賠償を請求できます。
交通事故の慰謝料を含めた損害賠償額は算定基準により相場には違いがあり、弁護士基準が最も高額な示談金を受け取れます。加えて、積極損害や消極損害、精神的損害など損害賠償の種類は多数ありますので、個人での対応は簡単ではありません。事前に用意をしていても、請求漏れを起こす可能性が高くなってしまいます。
すべての損害賠償金を高額請求するためにも、交通事故の事件に強い弁護士に相談してください。無料で法律相談をしている弁護士事務所であれば、気軽に利用できます。また、弁護士に依頼すると費用がかかりますが、弁護士特約サービスが使えれば無料で依頼することも可能です。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ