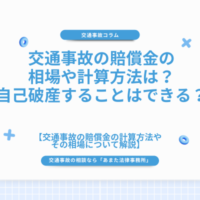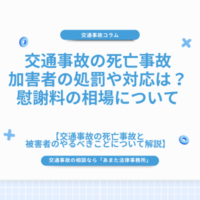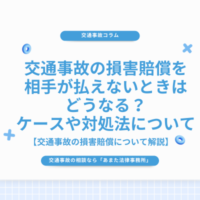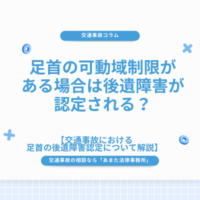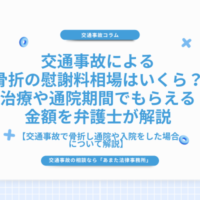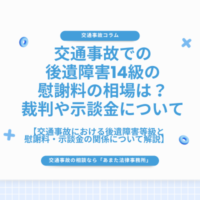後遺障害の併合は、一定のルールに基づき等級が繰り上がる制度です。
交通事故により複数の後遺症が残ったときに適用され、12級と12級の後遺障害は併合されると11級として扱われます。等級が上がると慰謝料などの賠償金が増額されますので、複数の後遺症があるなら併合への申請を考えるべきでしょう。

この記事の目次
後遺障害とは交通事故による後遺症
交通事故で負った傷害を治療したにもかかわらず、完治せず残った症状を「後遺症」といいます。さらに一定の要件を満たした後遺症は、「後遺障害」への申請が可能です。
後遺障害等級は1~14級に分けられる
後遺障害はケガの種類や部位、症状等により、1級〜14級の等級に分けられると自賠責施行令で定められています。1級に近づくほど重い後遺障害とみなされます。
例えば、重度の高次脳機能障害や脊髄損傷、遷延性意識障害では1級が認定される可能性が大きいです。一方、交通事故による後遺症の中でも多くみられるむちうちは、14級に認定される事例がほとんどです。
被害者が加害者に請求できる後遺障害の賠償金は、等級により金額が変わってきます。また後遺障害の等級認定を受けると、逸失利益なども請求でき、慰謝料を含む賠償金を増額できます。
等級認定手続きは、十分な金額を獲得するためにも非常に重要なものなのです。
「後遺障害」に当たるのは以下の条件に当てはまる後遺症です。
- 交通事故と障害との間に因果関係がある
- 後遺障害の存在が医学的に認められている
- 労働能力の低下(喪失)を伴う
- 自賠法施行令に定める後遺障害等級に該当する
一般的に「後遺症」と「後遺障害」は同じ意味で用いられることが多いのですが、厳密には定義が異なります。
後遺障害認定を受ける方法
後遺障害に関する損害賠償金を請求するためには、等級認定を受ける必要があります。後遺症が残ったからといって、自動的に後遺障害として認められるわけではない点に注意しましょう。
まず加害者側の自賠責保険に対し、後遺障害を申請します。自賠責保険会社が「損害保険料率算出機構」の「自賠責損害調査事務所」に申請書類を送付すると、等級認定の審査が行われ、後遺障害に該当するか、該当するなら何級相当なのかが決定されます。
併合11級のルール
一度の交通事故で2つ以上の後遺障害を残すときに、後遺障害等級が繰り上がる処理を「併合」といいます。
併合11級に当たる例や併合のルール、例外について解説します。
併合11級に当たる事例と賠償金の相場
併合11級に該当する事例を紹介します。
交通事故で頑固な神経症状を残し(12級13号)、加えて顔に大きな傷跡が残った(12級14号)後遺症は、等級が1つ繰り上がり併合11級が認められます。
12級に該当する後遺障害であれば、自賠責基準で算定すると約94万円、弁護士基準での算定だと約290万円の後遺障害慰謝料を請求できます(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。併合11級になると自賠責基準で計算すると136万円、弁護士基準では420万円の後遺障害を請求できるようになります。
比較すると併合により12級から11級に1級繰り上がるだけでも、獲得できる金額に大きな差がでることがわかります。そして、自賠責基準と弁護士基準で計算した金額を比較すると、大きな違いが出ることになります。
後遺障害慰謝料を請求するなら、損をしないためにも弁護士に相談し弁護士基準で計算できるようにするべきでしょう。
併合の原則
1つの事故で別の部位かつ別系列の後遺障害が認定されると、2つ合わせて併合〇級になります。
後遺障害の種類は、「眼」「耳」「鼻」「口」などの10の「部位」に区分され、さらに生理学的な観点から35の「系列」に分けられており、併合のルールにより繰り上がる等級が決定されます。
・8級以上の障害が2つ以上残ったときは、重い方の等級を2つ繰り上げる
・13級以上の障害が2つ以上残ったときは、重い方の等級を1つ繰り上げる
・14級以上の障害が2つ以上残ったときは、等級は繰り上がらない
たとえば、後遺障害の等級12級と13級に該当する事例では、重い方の等級である12級が1つ繰り上がり併合11級になります。
併合が適用されない例外がある
後遺障害の併合では、障害が発生した部位・系列が別であっても併合が適用されない例外が存在しています。
- みなし系列
- 組み合わせ等級
- 等級の序列を乱す場合
以上、3つの例外パターンがあります。
みなし系列
同部位に別系列の障害が複数残った事例では、同じ系列に障害が残ったものと判断されます。
これは「みなし系列」になり、併合は適用されません。
- 両眼球の視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害の各相互間
- 同一上肢の機能障害と手指の欠損または機能障害
- 同一下肢の機能障害と手指の欠損または機能障害
組み合わせ等級
部位と系列が異なったとしても、後遺障害等級表が規定する等級が認められるのが「組み合わせ等級」です。
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの(1級3号)
- 両手の手指の全部の用を廃したもの(4級6号)
- 両下肢の用を全廃したもの(1級6号)
- 両足をリスフラン関節以上で失ったもの(4級7号)
例えば、両足をリスフラン関節以上で欠損した後遺障害では、7級8号の「一足をリスフラン関節以上で失ったもの」を片足ずつで併合5級にはなりません。
結果、組み合わせ等級として4級7号になります。
等級の序列が乱れる場合
併合を適用すると後遺障害等級表の序列が乱れてしまうときは、通常の併合による等級よりも一つ下の等級になります。
例えば、右上肢を手関節以上で失い(5級4号)、左上肢をひじ関節以上で失った(4級4号)場合、本来ならば重い方の等級4級を3つ繰り上げて併合1級が認められると思われます。しかし、等級表では1級3号に「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」との規定があります。
実際は右上肢をひじ関節以上で失っていないため、1級3号を認めると等級の序列を乱すことになります。したがって、併合後の等級を1つ下げて併合2級になるのです。
併合が適用されない後遺障害もある
後遺障害には、そもそも併合が適用されないケースが存在しています。
併合できないのは、以下のような、例外的な事例です。
たとえば、右の大腿骨の変形(12級8号)と右の下肢が短縮(13級8号)の後遺障害は13級8号の症状が12級8号に含まれるとして、併合ではなく等級が上の12級8号が適用されます。
右の上腕に偽関節が残り(8級8号)同じ部位に神経症状も残っている(12級13号)ときは、1つの後遺障害に複数の症状が出現しているとして併合ではなく等級が上の8級8号になります。
さらに、要介護の1級、2級に併合は適用されません。併合は原則として介護が必要ない後遺障害を対象としているためです。
併合11級に申請するメリットとデメリット
後遺障害の併合11級に申請する行為自体に、大きなデメリットはありません。
ただし、「事前認定」と「被害者請求」どちらの申請方法を選ぶかにより、等級の認定で有利になったり不都合が生じる可能性があります。
事前認定のメリット・デメリット
・手間がかからない
・資料の収集などにかかる費用や時間を節約できる
・適切な等級が認定されにくい
・自賠責から保険金を先払いで受けられない
事前認定は加害者側の任意保険会社を介し、自賠責保険に書類を提出します。
被害者は医師に書いてもらった後遺障害診断書を相手方の任意保険会社に提出するだけでよく、資料の収集・提出といった後の手続きは相手方の任意保険会社が代わりに行ってくれます。
ほとんどの手続きを任意保険会社に一任できるため、被害者側に手間がかからないのが大きなメリットです。また、資料を集めるための費用も節約できます。
しかし事前認定は、適切な等級認定を受けにくいデメリットが生じてしまいます。
相手方任意保険会社は、被害者が有利になる資料を積極的に添付するとは考えられないためです。
保険会社は自社が支払う慰謝料といった示談金の総額を少しでも抑えようと考えます。結果、等級が上がるような証拠を意図的に提出しないような対応は珍しくなく、審査で不利になる恐れがあります。

被害者請求のメリット・デメリット
・手続きの透明性を確保できる
・適切な資料を提出でき適正な等級が認定されやすくなる
・示談成立前に自賠責から保険金を受け取れる
・手間や時間がかかる
・資料を集める際に費用がかかる
・後遺障害等級の認定に関する知識が必要になる
被害者請求は、被害者本人が必要書類を自賠責保険に直接提出する方法です。
事前認定とは異なり、被害者が必要となる書類・資料を全て収集しなければなりません。具体的に以下のような書類が必要になります。
・支払請求書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・印鑑証明書
・戸籍謄本
・休業損害の証明(事業主が発行する休業損害証明書や税務署・市区町村が発行する納税証明書、課税証明書など)
・通院交通費明細書
・レントゲン写真、MRI画像といった画像所見、および各種検査所見
被害者請求は後遺障害の等級認定のため、様々な書類を集めなければなりません。
取得場所を探すだけでも大変な労力になり、事前認定よりも多くの時間や手間がかかってしまいます。また、自賠責の等級認定基準を知らないと、どのような内容の書類が必要なのかが分からなく、不備が生じやすくなります。後遺障害に対する相応な知識は要求されるでしょう。
しかし、被害者が等級認定に有利な資料を選んで提出できるため、適切な等級が認定されやすいのがメリットです。
さらに、被害者請求が認められると、示談成立を待たずに自賠責保険から先払いで補償を受け取れます。ケガをすると入院や治療にお金がかかりますし、ケガのために仕事を休み収入が減るといった状況になることもあります。

併合11級に認定されるためのポイント
後遺障害に申請する前に知っておきたいのが、併合11級に認定されるためのポイントです。
後遺障害の等級審査は厳しく、簡単に認められるものではありません。認定されるための要点を押さえた適切な書類を提出する必要があります。
後遺障害の存在を客観的に説明する
適切な等級認定を受けるためには、客観的に後遺障害を説明できる資料を提示できるかがポイントです。
特にMRIやレントゲンなどの画像検査の結果は、誰が見ても症状がわかるため重要です。画像検査で異常所見が確認できると、適切な後遺障害等級の認定を得やすくなります。
代表的な神経学的検査は「スパーリングテスト」や「ジャクソンテスト」です。頭部を所定の方向に傾けたときに、放散痛が発生すれば陽性と判断できます。
レントゲンなどで後遺症がわかりにくいときは、医師に神経学的検査を実施してもらいましょう。
交通事故が原因で生じた障害であることを証明する
後遺障害の等級認定を受けるためには、交通事故と後遺症に因果関係があることを証明する必要があります。交通事故の以前から残存していた症状は、後遺障害として認められません。
関係があると証明するためには、事故直後に医師の診察を受けることが重要です。事故のすぐ後に生じている症状であれば、他の原因ではないと判断しやすいためです。
骨折や大きな傷がなく軽い症状と感じても、交通事故の被害にあったら怪我の程度にかかわらずすぐに病院を受診してください。
症状が一貫して続いていることを説明する
交通事故から治療を受けている間、症状が継続していなければ後遺障害の等級は認められません。
途中で通院をやめてしまうと、その期間は症状が出ていなかったと判断され等級認定を受けられなくなる可能性があります。
症状の常時性を訴える
後遺障害等級は常に症状があらわれていなければ認定されません。
例えば、「平常時は問題ないけど雨の日に痛みが出る」といった事例では、症状の常時性が否定され等級認定が受けられないおそれがあります。

併合11級が認定されないときの対処法「異議申し立て」
後遺障害を申請しても、併合11級に認定されないことはあり得ます。
認められなかったときの対応として異議申し立てがあります。自賠責保険に「異議申立て」を行い等級の再審査を求める方法です。
異議申立ての方法
異議申立ての申請方法は、事前認定と被害者請求の2通りがあります。
事前認定は自賠責保険から異議申立書を取り寄せ、必要事項を記入して加害者側の任意保険会社に提出します。あとは任意保険会社が申請手続きを行ってくれるため、手続き面の負担は軽いのが特徴です。

異議申立ては申請期限がなく回数の制限もありません。
どのタイミングで行っても良いとは言えるのですが、保険金や賠償金の請求権には時効期限があります。請求権がある期間内に異議申立てが通らなければ、慰謝料を含む賠償金を請求できない点に注意してください。
参考:国土交通省
異議申立てを成功させるポイント
異議申立てを成功させるためには、初回の申請で等級非該当になった原因をしっかり分析することが大切です。
併合11級が認められなかったのは何らかの理由があります。一度出た結果を覆すためには、当初の申請で不足していた資料を追加するなどの対策が必須です。
しかし、個人が1人で書類を完璧に準備するのは大変です。後遺障害について深い知識がないと書類の内容を精査するのは困難ですし、該当にならなかった問題を解決するのは無理に近いでしょう。
弁護士に相談し併合11級に認定された事例は多々あります。
まとめ
後遺障害の併合11級は、後遺症をしっかり証明できる書類を用意できないと認定されにくくなってしまいます。適切な等級認定を受けたいのであれば、自分で資料を集める被害者請求での申請が良いでしょう。
後遺障害への申請手続きで不安があれば、交通事故の事件に強い弁護士に相談するのがおすすめです。交通事故の事案に強い弁護士は併合11級の認定に必要な書類は何なのかをわかっていますので、認定される可能性が高めてくれます。
また、認定されなかったときも、弁護士のアドバイスを受けてください。豊富な実績により認定されなかった原因を見抜き、再審査に有利な方向へすすめてくれます。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ