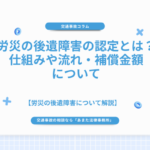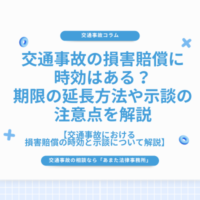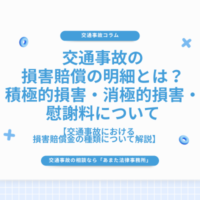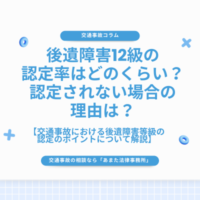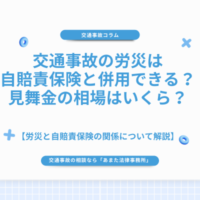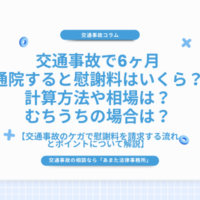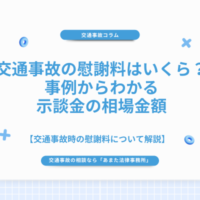勤務中や通勤中に遭った労災の交通事故により手指や足指に後遺障害が残った時は、損害賠償金を請求できます。ただ、指の切断や曲がる、しびれが残るなど、労災の認定要件を満たす症状が認めらないとなりません。

この記事の目次
交通事故による手指や足指の労災事故とは
「労災」は業務上の作業や通勤中の事故により、労働者が傷病を負ったり死亡してしまうことです。労災と略されることが多いですが、正確には「労働災害」と言います。
労災事故は仕事中の交通事故である労務災害だけでなく、通勤中の通勤災害も含まれ、労災保険はアルバイトやパートなど雇用形態に関係なく適用されます。
労災の交通事故による後遺障害は2種類に分けられる
労災による交通事故の怪我が治療しても完全に治り切らず何らかの症状が残ってしまうと、「後遺障害」の認定を受けられる可能性があります。
労災保険における後遺障害は症状の程度に応じて分類された後遺障害等級表に沿って認定されます。労災保険の後遺障害等級は1~14級に分かれており、数字が小さいほど症状が重くなり請求できる損害賠償の金額も高くなると定められています。
業務中ではない交通事故では自賠責保険に関する自賠責施行令(「自動車損害賠償保障法施行」)をもとに、後遺障害等級の認定審査が行われます。実は自賠責保険と労災保険では後遺障害認定の条件には違いがあり、一般的には労災のほうが高い等級(障害の程度が重い)での認定を受けられ、被害者に有利な結果が出る事例が多いと言われています。
労災の交通事故による手指や足指の後遺障害とは
手や足の指に後遺障害が残ると物を持つ、機械の操作、歩行といった通常の動作が制限されると思われます。仕事だけでなく日常生活にも支障が出る恐れがあり、後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高いといえます。
労災の交通事故による手指・足指の後遺障害は大きく2種類に分けられます。
欠損障害
手指・足指の「近位指節間関節」(指の関節のうち、根元に近い部分にある関節。人差し指、中指、薬指、小指では第二関節。親指には存在しないため中間の関節である「指節間関節」が適用される)が失われてしまう障害です。
| 手指 | 認定基準 |
|---|---|
| 3級5号 | 両手の指を全て失う。 |
| 6級7号 | 片手の5本の指、もしくは親指を含む4本の指を失う。 |
| 7級6号 | 片手の親指を含む3本の指、もしくは親指以外の4本の指を失う。 |
| 8級3号 | 片手の親指を含む2本、もしくは親指以外の3本の指を失う。 |
| 9級8号 | 片手の親指、もしくは親指以外の2本の指を失う |
| 11級6号 | 片手の人差し指、中指、薬指のどれかを失う。 |
| 12級8号の2 | 片手の小指を失う。 |
| 13級5号 | 片手の親指の指骨の一部を失う。 |
| 14級6号 | 片手の親指以外の指骨の一部を失う。 |
| 足指 | 認定基準 |
|---|---|
| 5級6号 | 両足の指を全て失う。 |
| 8級10号 | 片足の指を全て失う。 |
| 9級10号 | 片足の親指(第1の足指)を含む2本以上の指を失う。 |
| 10級8号 | 片足の親指、もしくは4本以上の指を失う。 |
| 12級11号 | 片足の人差し指(第2の足指)、もしくは人差し指を含む2本の指または中指以下の3本の指を失う。 |
| 13級9号 | 片足の中指(第3の足指)以下の1本の指、もしくは2本の指を失う。 |
機能障害
労災の交通事故により指の関節が動かしづらくなったり、可動に制限がかけられたりする障害です。欠損障害に当てはまらない部位を失った怪我も該当します。
(手指・足指の労災認定基準に出てくる「用を廃した状態」とは、次のいずれかに該当する場合を指します)
- 指の末節骨(指の第1関節より上にある指先の骨)の半分以上を失う。
- 「近位指節間関節(第2関節)」、「中手指節関節(第3関節)」に著しい運動障害が残っている状態(末節骨の2分の1以上を失った状態または第2・第3関節の可動域が健康な場合の半分以下の制限された状態)。
- 指先の腹、側面の表面もしくは深部感覚を完全に喪失した状態(感覚神経の検査により活動電位が検出されない場合に認定される)。
- 親指の末節骨の半分以上を失う。
- 足の親指以外を中節骨(足指の第1関節と第2関節の間の骨)または基節骨(足指の付け根の骨)で切断。
- 足の親指以外を「遠位指節間関節(第1関節)」もしくは「近位指節間関節(第2関節)」で切断。
- 親指の「指節間関節(第1関節)」もしくは「中足指節間関節(付け根の関節)」の可動域が半分以下に制限された状態。
- 親指以外の指で「近位指節間関節」もしくは「中足指節間関節」の可動域が半分以下に制限された状態。
| 手指 | 認定基準 |
|---|---|
| 4級6号 | 両手の全ての指が用を廃した状態。 |
| 7級7号 | 片手の全ての指、もしくは親指を含む4本の指で用を廃した状態。 |
| 8級4号 | 片手の親指を含む3本の指、もしくは親指以外の4本の指で用を廃した状態。 |
| 9級9号 | 片手の親指を含む2本の指、もしくは親指以外の3本の指で用を廃した状態。 |
| 10級6号 | 片手の親指、もしくは親指以外の2本の指で用を廃した状態。 |
| 12級9号 | 片手の人差し指、中指、薬指のどれかの指で用を廃した状態。 |
| 13級4号 | 片手の小指で用を廃した状態。 |
| 14級7号 | 片手の親指以外の手指で「遠位指節間関節」(指先に近いほうの関節)を上手く曲げられなくなった状態(関節が強直、もしくは損傷などが原因となって自動で屈伸しないかそれに近い状態)。 |
| 足指 | 認定基準 |
|---|---|
| 7級11号 | 両足の全ての指で用を廃した状態。 |
| 9級11号 | 片足の全ての指で用を廃した状態。 |
| 11級8号 | 片足の親指を含む2本以上の指で用を廃した状態。 |
| 12級11号 | 片足の親指、もしくは親指以外の4本の指で用を廃した状態。 |
| 13級10号 | 片足の人差し指、もしくは人差し指を含む2本の指、もしくは中指以下の3本の指で用を廃した状態。 |
| 14級8号 | 片足の中指以下の1本、もしくは2本の指で用を廃した状態。 |
参考:厚生労働省「労働者災害補償保険法施行規則/別表第一・障害等級表」
労災による指の後遺障害の認定要件
労災保険には「業務災害」と「通勤災害」があり、要件を満たすと労災と認められます。
労災による交通事故で指の機能を喪失したなどで後遺障害が残り労災保険を受けるためには、労災の認定を受けなければなりません。
労災保険は怪我をしたからといって自動的には受け取れないのですが、会社は社員が1人でもいれば労災保険に加入する義務があります。後遺障害が残れば労働基準監督署へ労災申請を実施し、労災と認められれば保険の適用を受けられます。
業務災害
事故の発生時に労働者が労働契約に基づき事業者の支配下にある状態で、業務と怪我の間に相当因果関係(社会通念上ある行為からその結果が生まれると認められる関係)があれば労災の業務災害と認められます。

通勤災害
被害者の住居と就業場所の間を移動するための合理的な経路上で発生した事故は、労災の通勤災害として認められます。
通常、対象になるのは朝、会社に行く途中や会社帰りなどの交通事故ですが、日用品の購入、病院での診察、保育園の送り迎えなど通勤途中に寄り道をした際の事故でも、一部は通勤の一環として認められることがあります。詳しくは交通事故や労災の事案に詳しい弁護士に相談してください。
指の後遺障害で受け取れる労災保険
労災による交通事故で指に後遺障害が発生すると、障害補償年金や療養補償、休業補償、傷病補償年金などの補償金を受け取ることができます。
障害補償給付
労災により後遺障害が残ると受けられる補償です。等級で内容が変わり、1~7級では「障害補償年金」として年金形式で毎年支給され、8~14級では「障害補償一時金」として一括支給されます。
給付金額は労災の発生3か月前の期間で賞与などを除き受け取っていた賃金の平均から求める、「給付基礎日額」をもとに各等級で支給日数が決まっています。
| 後遺障害等級 | 給付日数 |
|---|---|
| 1級 | 313日分 |
| 2級 | 277日分 |
| 3級 | 245日分 |
| 4級 | 213日分 |
| 5級 | 184日分 |
| 6級 | 156日分 |
| 7級 | 131日分 |
| 8級 | 503日分 |
| 9級 | 391日分 |
| 10級 | 302日分 |
| 11級 | 223日分 |
| 12級 | 156日分 |
| 13級 | 101日分 |
| 14級 | 56日分 |
例えば、給付基礎日額10,000円の人が片手の指2本を失い12級に認定されると、補償額は10,000×156=156万円になります。

| 後遺障害等級 | 支給額 |
|---|---|
| 1級 | 342万円 |
| 2級 | 320万円 |
| 3級 | 300万円 |
| 4級 | 264万円 |
| 5級 | 225万円 |
| 6級 | 192万円 |
| 7級 | 159万円 |
| 8級 | 65万円 |
| 9級 | 50万円 |
| 10級 | 39万円 |
| 11級 | 29万円 |
| 12級 | 20万円 |
| 13級 | 14万円 |
| 14級 | 8万円 |
療養補償給付
労災による病気や怪我の治療費に対する補償で、治療費や手術費用、薬代など給付範囲は幅広くなっています。労災指定の医療機関であれば窓口で支払いしなくてもよく無料での診療が可能です。
労災指定ではない病院での治療は窓口で一旦治療費を支払い、後日、労働基準監督署に申請すると治療費が還ってくる仕組みです。
休業保証給付
労災による怪我などで仕事を休んだ期間の給与・生活に対する補償です。支給は基礎給付日額の80%とされており、休業して4日目から給付を受けられます。つまり、もらえる金額は給与1日分の8割までで、休んでも最初の3日間は補償を受けられません。

傷病補償年金
療養補償給付を受けてから1年6か月を経過しても症状が治らないと継続して給付される補償です。労災の傷病補償年金には1~3級の等級があり、該当すると年金と合わせ特別支給金(「傷病特別支給金(一時金)」と「傷病特別年金」)を受け取れます。
| 等級 | 傷病補償年金(給付日数) | 傷病特別支給金 | 傷病特別年金* (給付日数) |
|---|---|---|---|
| 1級 | 313日分 | 114万円 | 313日分 |
| 2級 | 277日分 | 107万円 | 277日分 |
| 3級 | 245日分 | 100万円 | 245日分 |
*傷病特別年金の計算は算定基礎日額が使用されます。
算定基礎日額=算定基礎年額(労災に合う以前の1年間に支払われたボーナスなどの合計)÷365日
指の後遺障害で損害賠償を請求する方法
労災の交通事故による損害賠償金は、労災保険とは全く別であり労災の申請だけでは受け取れません。
交通事故の損害賠償金として代表的な慰謝料は、事故によって生じた精神的苦痛に対する補償として加害者や会社に対し請求するお金です。

業務災害
会社には従業員を安全な環境で労働させなければならない責任があります。監督していた会社側の法的義務違反を立証できれば、会社への損害賠償請求が可能になります。
通勤災害
通勤中の労災は事故が起きた原因が第三者の故意または過失にあれば、加害者に対し損害賠償金を請求できます。
通勤時に車と衝突した事故などは、事故の相手方に対する賠償請求できる可能性が高いです。バスやタクシーなど相手が業務中の車であれば、加害者側の会社に対して請求できます。個人では高い金額の賠償金を支払う能力が十分ではない可能性があるため、企業への請求も検討するのがおすすめです。
損害賠償は慰謝料をはじめ、次のようなお金を請求できます。
・治療費……医療機関での治療にかかったお金。
・入通院付添費用……入通院の際に付添が必要になった時のお金。
・交通費……病院に通うための交通費。
・入院雑費……怪我による入院で必要になった生活用品や通信費用などにかかったお金。
・休業損害……事故による怪我のために仕事を休んだ期間の給与に対する補償金。
・後遺障害逸失利益……後遺障害が残ったため将来得られるはずだった給与等が入らなくなったことを補償するお金。
・車の修理代など
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できるのは、後遺障害の認定を受けられた場合に限られます。しかし、入通院慰謝料や車の修理代などは後遺障害等級認定を受けられなくても請求できます。
指の後遺障害で請求できる損害賠償金の相場
労災による交通事故で手足の指に後遺障害が残った時、損害賠償の金額はどれくらいになるか慰謝料を例として金額の相場を見ていきましょう。
入通院慰謝料
交通事故の慰謝料は3つの算定基準が用意されています。
・自賠責基準……自賠責保険による慰謝料算定基準。事故に対する最低限の補償を目的としており、請求できる金額は3つのなかで最も低額になります。
・任意保険基準……事故の相手方が加入している任意保険会社で決められている慰謝料の算定基準。自賠責基準よりは高額とされますが、実際には金額に大きな差はありません。
・弁護士基準(裁判基準)……弁護士に依頼した場合に適用される算定基準。裁判を起こした時にも使われるため裁判基準とも言われています。請求できる金額は3つの基準のうちで最も高額になり、自賠責基準と比べると2~3倍になる事例は少なくありません。
交通事故により指の怪我で3か月通院(ひと月の通院日数12日)したケースで、それぞれの基準ごとに金額の目安を計算していきます。
自賠責基準
自賠責基準では怪我の大きさに関係なく1日あたりの金額が4,300円と決まっています。
①4,300×通院期間
②4,300×実通院日数×2
以上、2つの計算式で金額の低いほうが請求額になります。
通院3か月では
①4,300×90日(3か月)=38万7,000円
②4,300×36日(12日×3か月)×2=30万9,600円
となり、②の30万9,600円が適用されます。
任意保険基準
任意保険基準の請求額は保険会社によって異なり、外部から正確な金額は分からないのが現状です。以前に各社共通で使用されていた「旧任意保険支払基準」の算定表を参考に計算します。
旧任意保険支払基準をもとにした入院および通院の慰謝料算定表
| 入院→ 通院↓ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 |
|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 0 | 25.2 | 50.4 | 75.6 |
| 1か月 | 12.6 | 37.8 | 63 | 85.7 |
| 2か月 | 25.2 | 50.4 | 73.1 | 94.5 |
| 3か月 | 37.8 | 60.5 | 81.9 | 102.1 |
単位:万円
上の表をもとに、通院3か月の慰謝料は37万8,000円となります。
弁護士基準
弁護士基準では軽症用と重症用の2種類の算定表をもとに慰謝料を計算します。
参考:「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」
弁護士基準軽症用算定表
| 入院→ 通院↓ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 |
|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 0 | 35 | 66 | 92 |
| 1か月 | 19 | 52 | 83 | 106 |
| 2か月 | 36 | 69 | 97 | 118 |
| 3か月 | 53 | 83 | 109 | 128 |
単位:万円
弁護士基準重傷用算定表
| 入院→ 通院↓ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 |
|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 0 | 53 | 101 | 145 |
| 1か月 | 28 | 77 | 122 | 162 |
| 2か月 | 52 | 98 | 139 | 177 |
| 3か月 | 73 | 115 | 154 | 188 |
単位:万円
今回は通院のみのため軽症用を基準にします。請求額は53万円になり、自賠責基準と比較すると2倍近い差が生じます。
後遺障害慰謝料
後遺障害への補償である後遺障害慰謝料は、基準ごとに請求できる金額が決められています(任意保険基準については正確な金額が不明なため省略)。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級(要介護) | 1650 | 2800 |
| 1級 | 1150 | 2800 |
| 2級(要介護) | 1203 | 2370 |
| 2級 | 998 | 2370 |
| 3級 | 861 | 1990 |
| 4級 | 737 | 1670 |
| 5級 | 618 | 1400 |
| 6級 | 512 | 1180 |
| 7級 | 419 | 1000 |
| 8級 | 331 | 830 |
| 9級 | 249 | 690 |
| 10級 | 190 | 550 |
| 11級 | 136 | 420 |
| 12級 | 94 | 290 |
| 13級 | 57 | 180 |
| 14級 | 32 | 110 |
単位:万円
例えば、2本の手指に障害が残り10級の認定を受けると、請求できる慰謝料は自賠責基準なら190万円です。しかし、弁護士基準では550万円となり3倍近い差があります。

指の後遺障害で適切な等級に認定されるための注意点
適正な後遺障害等級に認定され、十分な補償を受けるために注意すべきポイント解説します。
適切に等級申請する
後遺障害等級の認定において申請内容は非常に重要です。不備があると認定されなかったり、低い等級に認定されてしまう可能性があります。認定を受けるには、自分の体に該当する症状が残っていると明らかにすることが大切です。それには、労災に関する専門的な知識が求められます。
申請に必要なのは医師が作成する後遺障害診断書ですが、医師は治療に関する知識はあれど労災について詳しいとは言い切れません。
企業への損害賠償請求は弁護士に相談を
自分が勤務する会社や加害者の勤めている会社など、交通事故の内容によっては企業を相手に損害賠償金を請求するケースが出てきます。会社に対する請求はまず会社と任意の交渉が行われます。決着しなければ労働者と事業主との紛争を解決する手段である、「労働審判」や訴訟などに移行します。
一連の交渉や手続きには高度な法的知識や交渉力が必要とされ、個人である被害者側は不利になってしまいがちです。会社の望む通りに交渉を進められ、不満の残る結果に終わらせないためにも、信頼できる弁護士に相談し対応してもらうのが安心です。

まとめ
仕事や通勤中に発生した交通事故による指の怪我は、後遺障害が認定されると労災保険から補償を受けられます。
また、後遺症に対する慰謝料や治療費、車の修理代などを含めた損害賠償金は、加害者側に請求できます。弁護士に依頼すれば、弁護士基準での請求が可能になり賠償金の増額が望めるでしょう。
労災の交通事故による損害賠償金を請求する際には、交通事故や後遺障害の解決経験が豊富な弁護士に一任するのがおすすめです。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ