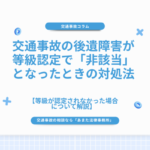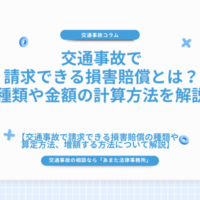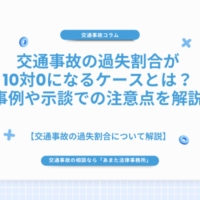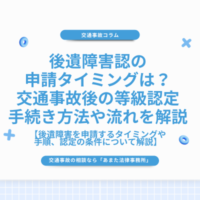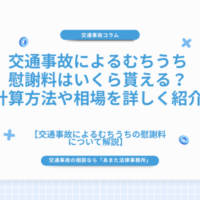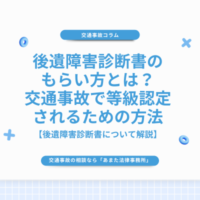交通事故でのケガが後遺障害等級非該当になってしまっても、慰謝料などの賠償金を受け取れる可能性はあります。

この記事の目次
交通事故による後遺障害とは
「後遺障害」は交通事故の被害に遭いケガの治療後も完全に回復せず何らかの症状が残ってしまった状態です。
後遺障害の定義
後遺障害は交通事故による症状に対してのみ用いられます。後遺障害に申請するためには以下の4つを全て満たしている必要があります。
2、後遺障害の存在が医学的に証明され、交通事故との間に相当の因果関係が認められる。
3、症状による労働能力の喪失・低下が認められる。
4、症状の程度が「自動車損害賠償保障法施行令」の定める後遺障害等級に該当している。
後遺障害は14の等級がある
後遺障害は1級~14級の等級に分類され、細かく当てはまる症状が決められています。等級の数字が小さくなるほど障害の程度が重くなっていき、1級が極めて症状が重く、補償が手厚くなり請求できる金額も大きくなります。後遺障害が認められると、賠償金として後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できるようになります。
「後遺障害慰謝料」……後遺症が残ってしまった精神的苦痛に対する慰謝料。
「後遺障害逸失利益」……障害が理由で働けなくなったり、職を変えなければならなくなったりしたことによる、得られるはずだった給料の減収に対する補償。
後遺障害の申請方法
後遺障害は交通事故でケガを負い、症状が残れば自動的に認められるわけではありません。所定の機関に申請を行い、認定をもらう必要があります。
後遺障害の認定は通常、「損害保険料率算出機構」の「自賠責損害調査事務所」で行われ、2種類の申請方法が用意されています。
「事前認定」
交通事故の加害者が加入している任意保険会社に依頼し申請してもらう方法。
| メリット | ・書類作成等の面倒な手続きをしなくて済む。 ・申請の際に、書類や画像資料等をもらうための費用が節約できる。 |
|---|---|
| デメリット | ・保険会社が手続きをしているため内容が不明瞭になりやすい。 ・保険会社は少しでも支払う金額を減らしたいと考えるため、受けられるはずの等級認定を受けられなかったり、本来よりも低い適切ではない等級での認定になってしまったりする可能性がある。 ・保険金の支払いが一括になるため、自賠責保険を申請して先払いを受ける方法が利用できなくなる。 |
「被害者請求」
被害者が加害者の加入している自賠責保険会社を通じて自分で申請手続きを行う方法。
| メリット | ・自分で全ての手続きするため透明性が高くなり、納得した申請が行える。 ・自賠責保険の先払い制度が利用でき、加害者との示談交渉が上手く行かなくても示談成立前に最低限の補償を受けられるようになる。 |
|---|---|
| デメリット | ・書類作成や資料請求などを全て自分で行う必要があり時間と手間、費用がかかる。 ・被害者自身が後遺障害の認定に慣れていないと不備が発生しやすく適正な等級認定を受けられない恐れがある。 |
事前認定と被害者請求にはそれぞれにメリット、デメリットがあります。どちらがより自分に適しているかをよく考え申請してください。
後遺障害の申請に関する知識がない、書類作成などの手間を省きたいというなら、事前認定を選択するのが良いと言えます。しかし、保険会社は被害者の側が有利になる書類や資料をきちんと集めて提出してくれる保証はありません。保険会社の申請に不安があるなら被害者請求のほうが望ましいでしょう。

後遺障害が非該当でも示談金はもらえる?
交通事故のケガで後遺症が残ったため後遺障害に申請したけれど、認定を得られなかったケースを「非該当」と言います。
示談金とは
「示談金」は交通事故における損害を全て現金に換算した損害賠償金です。被害者と加害者が「示談交渉」といわれる話し合いを行い双方が合意すると金額が決まります。
後遺障害が非該当になったときの示談金
示談金は後遺障害等級申請の結果に関係なく受け取れる可能性があります。
後遺障害が非該当になってしまうとお金がもらえないのではという心配が出てきますが、示談金は被害者と加害者双方が示談交渉で合意した金額です。そのため、示談交渉が実施され合意に達すれば、後遺障害の該当・非該当関係なく示談金は獲得できます。
非該当でも後遺障害慰謝料は受け取れるのか?
示談金のうち「後遺障害慰謝料」は、後遺障害が非該当なってしまうと基本的に受け取ることはできません。
慰謝料は不法行為による被害者の精神的苦痛に対して支払われる金銭であり、後遺障害慰謝料は後遺症が残ったという精神的苦痛に対して請求します。よって、後遺障害等級が非該当になってしまうと、後遺障害慰謝料の請求はできなくなります。
また、仕事を休業した分の収入を補償する「後遺障害逸失利益」の請求もできません。ただ、非該当だから絶対に無理とはいえず、場合によっては請求可能な場合も存在します。
後遺障害が非該当でも後遺障害慰謝料が受け取れるケース
後遺障害慰謝料は後遺障害に対して支払われる慰謝料のため、基本的に後遺障害の申請が非該当になってしまうと受け取れません。
しかし、例外的に後遺障害なしでもケガの状態や後遺症の程度など、被害者の性質から判断して慰謝料の支払いが認められるケースは存在します。

後遺障害の基準に満たないケース
体に残ったケガの痕が後遺障害として認定される基準を下回っている場合です。特に顔のケガや傷など顔面醜状や体の傷跡に対しては、比較的認められやすい傾向にあります。
傷跡が後遺障害として認定されるには手のひら大以上や10円玉以上などの基準が決まっています。ただ、基準以下の傷で認定を受けられなくても後遺障害慰謝料が認められる事例はあります。
被害者の事情を考慮するケース
年齢や職業など被害者個別の事情を考慮し、非該当でも慰謝料支払いが認められることがあります。
例えば、モデルやホステスなど容姿を重視する職業で顔など目立つ傷跡が残ってしまったケース、幼い子どもに傷跡が残り将来への影響が大きいと判断されるケースなどです。
仕事や生活への影響が大きいケース
後遺障害が非該当になったものの、後遺症が影響し仕事を続けられなくなったり、日常生活に支障が出るようになったりするケースです。
例えば、交通事故で多い「むちうち」は痛みや痺れ、めまいなどが残りやすいのですが、神経症状のため外見から分かりにくく非該当になりやすいです。しかし。仕事を退職しなければならなかったり、日常生活でこれまでできていた動作等が困難になったりと影響が大きいと思われるような状況です。

後遺障害が非該当になったときの慰謝料相場
後遺障害等級の認定が非該当になると後遺障害慰謝料の請求はできませんが、慰謝料が全くもらえないわけではありません。例えば、ケガで医療機関に通院したり、入院したりすれば、期間に応じて入通院慰謝料(傷害慰謝料)の請求が可能です。
交通事故における慰謝料は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類の算定基準があり、どれを適用するかで受けとれる金額が大きく変わるのが特徴です。
基本的に治療が長期間になるほどもらえる慰謝料が高額になる入通院慰謝料の相場を見ていきます。
自賠責基準
自動車を運転する上で加入が義務づけられている自賠責保険に基づく慰謝料算定基準です。全てのドライバーが加入しているため、どのような交通事故でも自賠責基準での慰謝料は受け取れます。
ただ、自賠責保険は事故の損害を最低限保証するのが目的のため、受け取れる慰謝料は3つの基準の中では低額になってしまいます。弁護士基準と比べると2~3倍の差が出るケースもあります。
自賠責保険には支払い限度額があります。傷害慰謝料の上限は120万円と定められていますので、超過分は加害者が加入している任意保険から支払いを受けることになります。自賠責基準ではケガの程度に関係なく、1日あたりの支払額は4,300円です。
実際にもらえるのは
①4,300×通院期間
②4,300×実通院日数×2
上記2通りの計算を実施し、金額が少ないほうの金額になります。
任意保険基準
加害者が加入している任意保険会社による慰謝料算定基準です。計算方法は各社が自由に決めてよいとされており、外部には非公開になっているため詳細は不明でなのが現状です。もらえる金額は保険会社ごとに異なりますが、自賠責基準を上回るものの実際の金額に大きな差はないと言われています。
任意保険基準の金額相場は、以前全ての保険会社で利用されていた「旧任意保険支払基準」の算定表を参考に計算できます。
旧任意保険支払基準をもとにした入院および通院の慰謝料算定表
| 入院→ 通院↓ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 0 | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 128.5 |
| 1か月 | 12.6 | 37.8 | 63 | 85.7 | 104.6 | 121 | 134.8 |
| 2か月 | 25.2 | 50.4 | 73.1 | 94.5 | 112.2 | 127.3 | 141.1 |
| 3か月 | 37.8 | 60.5 | 81.9 | 102.1 | 118.5 | 133.6 | 146.1 |
| 4か月 | 47.9 | 69.3 | 89.5 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.1 |
| 5か月 | 56.7 | 76.9 | 95.8 | 114.7 | 129.8 | 143.6 | 154.9 |
| 6か月 | 64.3 | 83.2 | 102.1 | 119.7 | 134.8 | 147.4 | 157.4 |
単位:万円

弁護士基準
弁護士に依頼すると適用される算定基準で、裁判を起こした場合にも使われるため「裁判所基準」とも言われています。弁護士基準は3つの基準中では一番高額請求が可能になり、裁判を起こさなくても弁護士に依頼すれば適用できます。
弁護士基準では公益社団法人「日弁連交通事故相談センター」が発刊している「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)や、「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)などを参考に慰謝料算定を実行します。金額は治療期間によって決まり、軽症用と重症用2種類の計算表に分かれています。
弁護士基準軽症用算定表
| 入院→ 通院↓ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 0 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 |
| 1か月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |
| 2か月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |
| 3か月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |
| 4か月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |
| 5か月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |
| 6か月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |
単位:万円
弁護士基準重傷用算定表
| 入院→ 通院↓ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 0 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 |
| 1か月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |
| 2か月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |
| 3か月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |
| 4か月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |
| 5か月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |
| 6か月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |
単位:万円
3つの基準における実際の慰謝料相場
実際の事故の事例を見ながら、それぞれの基準で慰謝料相場がいくらになるか比較していきます。
事例①
Aさんは車を運転して信号待ちをしていたところ、後ろから加害者の車に追突され、腕や背中、腰などを打撲するケガを負いました。入院する必要はなかったものの、3か月通院(通院日数月12日)しました。
①4,300円×3か月(90日)=38万7,000円
②4,300円×(通院3か月×12日)×2=30万9,600円
実際の請求額は②の30万9,600円になります。
「旧任意保険支払基準」の算定表による通院3か月の慰謝料額は37万8,000円です。
軽症用の算定表をもとにすると、慰謝料額は53万円になります。
任意保険基準は自賠責基準より高いものの金額の差はほとんどありませんが、弁護士基準と自賠責基準では2倍近い差があることが分かります。
事例②
Bさんは信号のない横断歩道を渡っている最中、車に衝突され完治までに入院4か月と通院6か月(通院日数月10日)を要する大ケガを負いました。
①4,300円×10か月(300日)=129万円
②4,300円×(入院4か月×30日+通院6か月×10日)×2=154万8,000円
請求額は①の129万円になります。
算定表による慰謝料額は134万8,000円です。
重症用の算定表にる慰謝料額は239万円です。
弁護士基準と自賠責基準では約100万円もの差が出てしまいます。
事例③
Cさんは車を運転中前方の道路が渋滞していたため停車したところ、後続車に追突されました。事故により頸椎捻挫のケガを負い症状固定までに通院6か月(通院日数月12日)を要しました。
さらに、治療が済んでからも首の痛みやしびれなどいわゆる「むちうち」の症状が残り、後遺障害等級の14級に認定されました。
※任意保険基準後遺障害慰謝料の詳しい金額が不明のため省略しています。
①4,300×6か月(180日)=77万4,000円
②4,300×(通院6か月×12日)×2=61万9,200円
実際の請求額は②の61万9,200円になります。
さらに、この事例ではむちうちによる後遺障害慰謝料も請求できます。後遺障害慰謝料は等級ごとに金額が決まっており、むちうちで認定されることが多い12級と14級の慰謝料額は自賠責基準では
- 12級・94万円
- 14級・32万円
14級の認定を得ていれば慰謝料額は32万円です。入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を合計すると、受け取れる金額は61万9,200円+32万円=93万9,200円です。
軽症用の算定表によると入通院慰謝料は89万円です。
さらに、後遺障害慰謝料は
- 12級・290万円
- 14級・110万円
になります。
14級ですと後遺障害慰謝料は110万円ですので、合計金額は89万円+110万円=199万円です。
自賠責基準と比較すると2倍以上の金額を受け取れる可能性があります。
後遺障害が非該当の慰謝料請求で気を付けること
後遺障害が非該当と判断されると、該当したときと比べると正規祐できる慰謝料の金額は少なくなるのが普通です。そのため、注意点を踏まえ、慰謝料を請求するのがおすすめです。
1、自分で交渉せず弁護士に依頼する
交通事故の慰謝料は適用される算定基準により金額が大きく異なります。弁護士基準を適用すると示談金の大幅な増額が期待できますので、弁護士に依頼し弁護士基準での支払いを受けられるようにしましょう。

2、保険会社からの治療費打ち切り提案は受け入れない
事故後、ある程度の治療期間になると加害者の保険会社から、「そろそろ治療は終わりにしましょう」と治療費の打ち切りを打診されることはよくあります。しかし、このような提案は簡単に受け入れないようにしてください。
3、治療期間を保つ
入通院慰謝料の金額は治療期間によって変わるため、ある程度の期間がないと受け取る慰謝料が少なくなってしまいます。また、治療期間が短いと「後遺症が残るほどの大きなケガでないのでは?」「もっと治療すればきちんと治ったのでは?」などと思われてしまい、慰謝料を減額されてしまう恐れがあります。むちうちだと3ヶ月くらいの通院期間が目安と言えるでしょう。
さらに、通院期間が長い割に治療日数が少なくても慰謝料が低くなる可能性があります。通院日数は医師と相談しながら、週に2~3日が目安です。
4、自宅療養期間を治療期間に含める
自宅療養期間は自宅で怪我の治療をしていた期間です。例えば、事故で骨折し入院はしていないものの、ギプスを付けての生活を余儀なくされていたケースなどが該当します。自宅療養期間を治療期間として慰謝料の算定期間に含めることができると、慰謝料の金額を増額できる可能性が高くなります。
5、無断で整骨院には通院しない
治療を受けている医療機関の以外に、無断で整骨院・接骨院などに通うのは控えてください。整骨院での治療は通院期間に含めてもらえない可能性が高いです。
整骨院・接骨院での治療が慰謝料の算定期間に含まれるには条件があります。医師から施術に対する許可をもらい、実際に施術の効果が認められなければならないのです。整骨院などへの通院を希望するなら、無断で通うのはやめ医師に伝え許可をもらう必要があります。
後遺障害等級の非該当が納得できないときの対処法
後遺障害等級の申請が認められず非該当になってしまい不服があるときは、「異議申立て」が可能です。異議申立ての方法は保険会社に任せる「事前認定」と自分自身で手続きをする「被害者請求」の2種類があります。
どちらを選ぶかは自由であり、回数の制限もありません。1度目の申請を事前認定で2度目は被害者請求への切り替えといった手段も可能です。ただ、異議申立ては審査が厳しく、損害保険料率算出機構によると成功率は約15%と決して高くないのが現状です。非該当という結果を覆すには、最初の申請時に不足していた画像や検査結果など資料を追加するといった改善が大切になります。

まとめ
交通事故の後遺障害等級申請で非該当になっても、慰謝料等の示談金を受け取ることはできます。後遺障害慰謝料は基本的に請求できませんが、目立つ傷痕や日常生活に影響があると判断されれば請求できる可能性もありますので、諦めず請求することが重要になります。
また、入通院慰謝料は後遺障害の有無にかかわらず請求可能です。高い金額の時短金を受け取るためには弁護士に依頼し弁護士基準で請求するのおすすめです。後遺障害の認定や慰謝料に関する不安や疑問は、交通事故の事件に強い弁護士に相談し解決してください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ