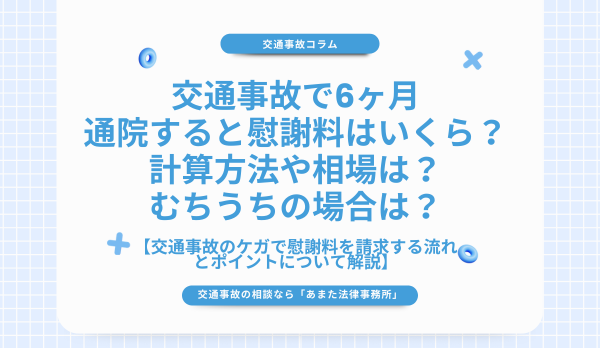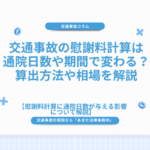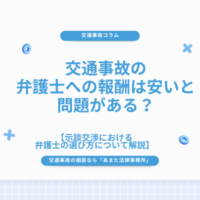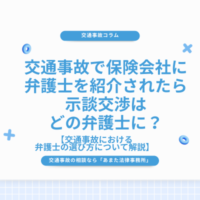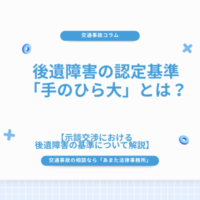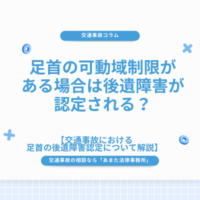交通事故で6ヶ月通院してもらえる慰謝料は、89万円か116万が目安です。
しかし交通事故の状況はさまざまです。入院期間の有無や、後遺症が残ったりすると、金額が変わってきます。また計算方法によっても異なります。

この記事では交通事故で多く見られるむちうちの例を出しつつ、6ヶ月通院で、もらえる慰謝料の種類や相場、計算方法などを解説します。
また慰謝料を請求する流れや請求するためのポイントもわかります。
執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
交通事故で通院したときの慰謝料とはどんなもの?
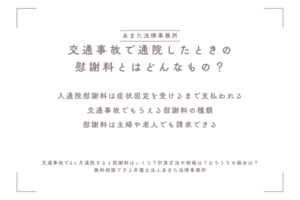
6ヶ月の通院が必要となるケガは重症といえ、基本的には誰でも慰謝料を請求できます。
入通院慰謝料のほか、後遺障害慰謝料も請求できる可能性が出てきます。
入通院慰謝料は症状固定を受けるまで支払われる
通院・入院の慰謝料や治療費は、交通事故のケガを治療・リハビリを継続している間は保険会社に請求できます。しかし、症状固定の判断を受けると賠償期間が確定し、支払いは終了してしまいます。
症状固定とは、ケガの治療やリハビリをしても、これ以上の改善が期待できない状態を意味します。
交通事故で重傷と言われるケガは、6ヶ月経過した時点で「症状固定」となるのが一般的です。
むちうちは3ヶ月程度で完治することも多いですが、重度になると症状固定まで6ヶ月程度かかることがあります。
骨折も6ヶ月が目安ですが、プレートを入れるといった大きな手術をしたときは1年程度かかることもあります。
また、高次脳機能障害など重症度が高いケガでは、症状固定はリハビリの効果が確認できてからということになります。最低でも1年はかかると見て良いでしょう。
交通事故でもらえる慰謝料の種類
交通事故でもらえる慰謝料は、大きく分けて「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。
むちうちで6ヶ月通院した分の負担は入通院慰謝料として損害賠償を請求できます。
また、後遺症が残ってしまった場合は、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求できます。
入通院慰謝料
交通事故によって入院や通院を余儀なくされた負担に対して請求できる慰謝料です。入院や通院しなければならない傷害を負っていることから「傷害慰謝料」ともいいます。
慰謝料の金額は通院日数または通院期間によって決定します。1日以上の通院で請求できますので、1度も通院していなければ請求できません。
後遺障害慰謝料
交通事故で負ったケガに対し、後遺障害(後遺症)が認められると請求できる慰謝料です。
後遺障害(後遺症)とは、外傷を治療した後も完治しない機能障害、運動障害、神経症状などをいいます。
後遺障害慰謝料を受け取るには、審査を受けて後遺障害等級に認定されなければなりません。後遺障害等級は、後遺障害の程度によって1〜14等級に分類されており、重度の後遺症ほど高い金額を請求できます。
等級ごとに請求できる慰謝料の金額の相場は決まっていますが、どのようはケースでも規定の金額が支払われるとは限らない点に注意してください。
後遺障害の等級認定では怪我の治療経過が考慮されるため、通院日数により獲得できる金額が異なることがあります。また、示談交渉次第では、慰謝料を増額することも可能です。
慰謝料は主婦や老人でも請求できる
交通事故の慰謝料は、収入がない専業主婦(主夫)や老人、子供でも請求できます。しかも、もらえる慰謝料は所得があるサラリーマン等と同額になります
慰謝料は交通事故の被害者になったという精神的苦痛に対して支払われるお金です。そのため慰謝料は性別や年齢、収入の有無や収入の金額に関係なく請求できるのです。
また慰謝料以外にもらえる入通院の治療費や交通費なども、誰でも実費を請求できます。無職でも年収が1億円あろうとも同額です。
ただし、休業損害や逸失利益は収入により違ってきます。
休業損害
事故によって働けなくなった期間に発生する予定であった収入を、休業損害として加害者側に請求できます。
例えば、事故で入院を余儀なくされると、入院している間は働けません。交通事故の被害者になったことで本来は得られるはずの収入が入ってこないような消極損害の分を補償してもらえます。
治療のためであれば、有給休暇の分も支払いの対象です。
金額は仕事を休んだ期間や通院日数などにより変わってきます。
また休業損害は専業主婦(主夫)でも請求できますが、収入が高いサラリーマンや事業主と比較すると獲得できる金額は少なくなってしまいます。
逸失利益
逸失利益とは、交通事故がなければ得られたはずの将来の収入のことです。
後遺障害逸失利益と死亡事故が対象になる死亡逸失利益があります。
交通事故で後遺障害が残ると、労働能力が低下し将来得られるはずの収入は減少することになります。
例えば収入が労働能力低下によって70%に減少してしまった場合、減った30%の「労働能力喪失率」は逸失利益として相手に支払ってもらえます。
一般的に労働能力喪失率は後遺障害の等級が高くなるほど大きくなり、逸失利益の金額も上がります。
ただ後遺障害に認定されたとしても、収入が減っていなければ逸失利益は対象になりません。

6ヶ月通院した慰謝料の計算方法を解説
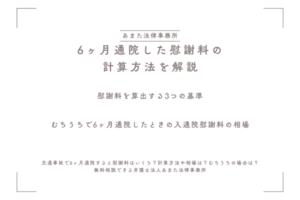
交通事故で多いむちうちの事例で、6ヶ月間通院したときの慰謝料を計算する方法と相場を解説します。
慰謝料を算出する3つの基準
交通事故の慰謝料は、自賠責基準、自賠責基準、弁護士基準と3つのうちいずれかの方法を使用し算出します。
自賠責基準
自動車損害補償法に基づく自賠責保険での支払基準です。
自賠責保険は原動機付自転車(原付)を含むあらゆる自動車を購入した際に義務付けられている強制保険です。自賠責保険に未加入の車両を運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
自賠責保険は人身事故の被害者へ、最低限の補償を目的としています。
補償額は任意保険基準や弁護士基準よりも低くなっています。なお、自賠責保険で支払われる賠償額の上限は法律で120万円と決まっており、上限を超えた分は任意保険基準でまかないのが普通です。
任意保険基準
保険会社が交通事故の慰謝料の金額を算定する基準です。
保険会社が示談交渉で提示する慰謝料を含めた損害賠償金の内容は、任意保険基準で計算された金額です。任意保険基準での支払額は、保険会社が独自に設定していますので一定ではありません。また、任意保険基準は非公開であるため、具体的な計算方法は知り得ないのが現状です。
支払われる金額は自賠責基準よりも若干高い程度であり、高額な慰謝料を受け取れるとは言えません。
各保険会社は自社の利益を考慮し、慰謝料を含む賠償額をできるだけ低額で済ませようとするためです。交渉次第で増額できることはありますが、個人の主張に保険会社が応じる可能性は低いです。弁護士なしで解決するのは難しいでしょう。
弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準は裁判所や弁護士が用いる基準であり、3つの算定基準の中で最も高額の慰謝料が支払われますのでメリットが大きいです。
弁護士基準は日弁連交通事故相談センターが毎年発行している「損害賠償額算定基準(通称:赤本)」が掲載している計算基準です。
赤本は東京地方裁判所での裁判例に基づき交通事故による損害賠償額の算定基準や、参考になる裁判の判例が記載されています。赤本の基準は、裁判実務でも用いられているため「裁判基準」とも呼ばれています。
できるだけ高い慰謝料を請求したいと考えるのであれば、弁護士に依頼し示談交渉を進めるのがおすすめです。
むちうちで6ヶ月通院したときの入通院慰謝料の相場
むちうちで6ヶ月通院したときの入通院慰謝料の相場を、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準でそれぞれ算出してみます。
自賠責基準での計算
自賠責基準では「対象日数×4,300円(2020年3月31日以前は4,200円)」の計算式で金額を計算します。
対象日数は「通院期間(事故発生日から完治または症状固定するまでの全日数)」と「実通院日数×2(入院日数と通院日数を合計した日数)」のうち、少ない方が対象となります。
むちうちで1ヶ月間(30日)入院し、通院期間が6ヶ月間(180日)の例にて、実際の通院日数が多いケースと少ないケースの慰謝料を例として計算してみましょう。
1ヶ月間(30日)入院した後に100日間通院していた場合、実通院日数(30日+100日)は130日になります。130を2倍すると230ですので、通院期間の180日の方が少なくなります。したがって、このケースでの対象日数は180日になります。
自賠責基準の計算式は「対象日数×4,300円」ですので、150日に4300円をかけます。結果、実際の通院日数が100日間のケースでもらえる入通院慰謝料は774,000円です。
1ヶ月(30日)入院した後に20日間通院していた場合、実通院日数(30日+20日)は50日になります。40を2倍すると100ですので、通院期間の180日よりも少なくなります。したがって、このケースでの対象日数は100日になります。
100日に4300円をかけて金額を算出すると、実際の通院日数が10日間のケースでは、入通院慰謝料430,000円になります。

任意保険基準での計算
任意保険基準の計算方法は各保険会社が個別で設定しています。また、計算方法が公開されていないため、外部の人には正確な金額がわかりません。
ただし、平成11年6月30日以前はすべての任意保険会社は「旧任意保険基準」という統一基準で慰謝料を算定していました。現在、この統一基準は撤廃されていますが、今も旧任意保険基準を採用している保険会社は一定数存在します。そのため、6ヶ月通院したときの慰謝料の相場を知る目安にはなります。
旧任意保険基準(単位:万円)
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 128.6 | |
| 1月 | 12.6 | 37.8 | 63 | 85.6 | 104.7 | 120.9 | 134.9 |
| 2月 | 25.2 | 50.4 | 73 | 94.6 | 112.2 | 127.2 | 141.2 |
| 3月 | 37.8 | 60.4 | 82 | 102.2 | 118.5 | 133.5 | 146.3 |
| 4月 | 47.8 | 69.4 | 89.4 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.3 |
| 5月 | 56.8 | 76.8 | 95.8 | 114.6 | 129.9 | 143.6 | 155.1 |
| 6月 | 64.2 | 83.2 | 102 | 119.8 | 134.9 | 147.4 | 157.6 |
上記の表では、入院期間と通院期間の長さによって金額を計算します。
横軸を入院期間、縦軸を通院期間とし、それぞれが交わる箇所に記載されている数字が慰謝料の金額になります。
例えば、むちうちで1ヶ月間入院し6ヶ月間通院したケースでは、832,000円の慰謝料が支払われます。自賠責基準では、通院日数が多いケースでも約75万円でしたので、それよりも若干高額の慰謝料を受け取れることがわかります。

弁護士基準での計算
損害賠償額算定基準に記載されている「入通院慰謝料算定表」を使用して計算します。
表には骨折や脱臼などがある重症と、むちうちなどの軽症用の2種類があります。
むちうちでも脱臼があれば重症用の表を用いますが、通常は軽症用の表をもとに慰謝料を計算します。
入通院慰謝料算定表:重症の怪我用(単位:万円)
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 |
| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 |
| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 |
| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | |
| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | ||
| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | |||
| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 |
入通院慰謝料算定表:むちうちなどの軽症用(単位:万円)
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | |
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 |
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 |
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 |
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 |
| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 |
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 |
| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 |
| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 |
| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | |
| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | ||
| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | |||
| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 |
横軸を入院期間、縦軸を通院期間とし、それぞれが交わる箇所に記載されている数字が慰謝料の金額になります。
通常のむちうちが対象となる軽症用の表を使用すると、入院期間が1ヶ月で通院期間が6ヶ月だと113万円の慰謝料が支払われることになります。
後遺障害慰謝料の相場|むちうちのケース
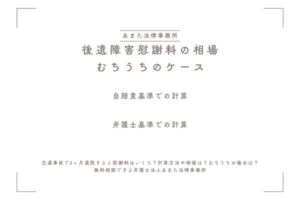
交通事故よるむちうちで後遺症が残ると、後遺障害では14級9号に認定される可能性が高くなります。
14級9号は「局部に神経症状を残すもの」と規定しています。むちうちでは首や腰という特定の部位(局部)に神経症状を残すため14級9号となります(ただし必ず該当するとは限りません)。
後遺障害が認定されると、等級に応じて後遺障害慰謝料と逸失利益(後遺症による労働能力喪失がなければ得られたはずの収入)を請求できるようになります。

自賠責基準での計算
自賠責基準でもらえる後遺障害慰謝料の金額は、「自動車損害賠償保障施行令別表」で定められています。
別表は第1と第2に分かれており、後遺症の程度が極めて重篤で介護を要するものは別表第1、それ以外は別表第2を参照します。
加えて交通事故で怪我を負うと、慰謝料の他にも逸失利益を含む保険金が支払われます。
後遺障害慰謝料別表による慰謝料の金額と保険金総額は以下のとおりです。
後遺障害慰謝料別表第1
| 等級 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 第1級 | 1650万円(4000万円) |
| 第2級 | 1203万円(3000万円) |
後遺障害慰謝料別表第2
| 等級 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 第1級 | 1150万円(3000万円) |
| 第2級 | 998万円(2590万円) |
| 第3級 | 861万円(2219万円) |
| 第4級 | 737万円(1889万円) |
| 第5級 | 618万円(1574万円) |
| 第6級 | 512万円(1296万円) |
| 第7級 | 419万円(1051万円) |
| 第8級 | 331万円(819万円) |
| 第9級 | 249万円(616万円) |
| 第10級 | 190万円(461万円) |
| 第11級 | 136万円(331万円) |
| 第12級 | 94万円(224万円) |
| 第13級 | 57万円(139万円) |
| 第14級 | 32万円(75万円) |
()内は保険金総額
むちうちは原則として別表第2の14級にあたります。したがって、むちうちが後遺症と認定されると、自賠責基準では32万円の後遺障害慰謝料が支払われます。
弁護士基準での計算
交通事故損害額算定基準で後遺症慰謝料を請求します。
自賠責基準では1級と2級の後遺症のうち要介護のものは表を分けていましたが、弁護士基準では同一の表を使用します。
弁護士基準で請求できる後遺障害慰謝料をまとめた表は以下の通りです。
| 等級 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 第1級 | 2800万円 |
| 第2級 | 2370万円 |
| 第3級 | 1990万円 |
| 第4級 | 1670万円 |
| 第5級 | 1400万円 |
| 第6級 | 1180万円 |
| 第7級 | 1000万円 |
| 第8級 | 830万円 |
| 第9級 | 690万円 |
| 第10級 | 550万円 |
| 第11級 | 420万円 |
| 第12級 | 290万円 |
| 第13級 | 180万円 |
| 第14級 | 110万円 |
むちうちの等級は第14級ですので、弁護士基準では110万円が慰謝料として支払われます。

交通事故のケガで慰謝料を請求する流れとポイント
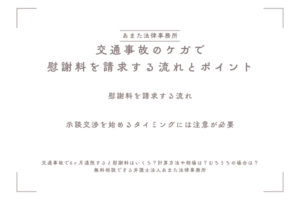
交通事故のケガで慰謝料を請求する流れを紹介します。また、できるだけ高額の慰謝料を獲得するためにも、請求するときに注意したいポイントを知っておきましょう。
慰謝料を請求する流れ
交通事故後はすぐに病院で診察を受けて検査を行い、医師の指示にしたがって治療を始めます。
直後は軽傷で異常はないと思っても、打撲などがあればのちに痛みや違和感が出てくることはあります。交通事故に遭ったら、医療機関への受診は必須です。
交通事故にあったらまずは警察に連絡しましょう。
交通事故の報告は道路交通法上の義務ですので、怠ると懲役3ヵ月以下または5万円以下の罰金が科されます(道路交通法72条1項)。
また、警察に届け出をしないと、損害賠償請求や保険金請求するのに必要な「交通事故証明書」を発行してもらえません。警察に届け出る際は、ケガをしているのであれば人身事故として届け出を提出しましょう。
交通事故でケガをすると保険金を受け取れますので、自分が加入している保険会社に連絡しましょう。
交通事故発生時の状況、加害者の情報、ケガの有無や症状などの詳細を、保険会社に説明します。
正しい情報を保険会社に伝えていないと、十分な金額の保険金が支払われない可能性が出てくるのが注意点です。事故が発生してから状況が落ち着き次第、忘れずに連絡してください。
もし加害者が任意保険に加入していないと、保険金がすぐに支払われません。いったん、被害者自身が治療費を支払っておく必要があります。自由診療では治療費が高額になりますので、治療費を1〜3割に抑えられる健康保険適用の治療を受けるのがおすすめです(ケガであればほとんどは保険適用診療になると思われます)。
交通事故によるむちうちの重傷や骨折は、6ヶ月で症状固定と判断さるのが普通です。
症状固定後に後遺症が残ってしまったら、後遺障害を申請しましょう。後遺障害の等級が認定されると、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
ケガが完治もしくは症状固定となったタイミングで、示談交渉を開始します。事故の当事者同士で慰謝料を含む賠償金について取り決めます。
示談交渉を始めるタイミングには注意が必要
後遺症が残るかもしれない時点で示談交渉を始めてしまうと、本来であれば請求できたはずの損害賠償金が請求できなくなる可能性があります。
相手方の保険会社は交通事故の示談交渉を急ぎたいがために、6ヶ月より前に「そろそろ症状固定を」と提示してくることがあります。しかし、固定症状を待たずに示談交渉に入ると、後遺障害慰謝料の請求ができなくなるため、症状固定または完治してから始めてください。
むちうちの慰謝料請求で気を付けるべき点
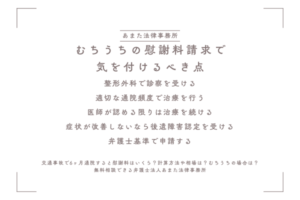
むちうちで慰謝料を請求する際は、適正な金額を請求するために気を付けるべきポイントがいくつかあります。知らないと慰謝料を減額されてしまうことがあるので、注意してください。
整形外科で診察を受ける
適正な後遺障害慰謝料を受け取るには、整形外科で診察してもらいましょう。
むちうちの治療は整形外科だけでなく整骨院(接骨院)でも行えます。ただし、整骨院には医師がいませんので、後遺障害等級の認定に必要な後遺障害診断書などの書類を作成してもらえません。
POINT
適切な通院頻度で治療を行う
むちうちを治療してもらう際には、適切な通院頻度で治療しなければなりません。
適正な慰謝料を受け取るためには、正しいペースで通院することが重要です。通院頻度が少なすぎると症状が軽いと判断され、支払われる慰謝料が減額されるおそれがあります。また、整骨院で毎日治療していたようなケースでは、過剰診療と判断され保険会社から支払われる治療費が打ち切られる可能性があります。

医師が認める限りは治療を続ける
治療を続けていると保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。一般的にむちうちは3ヶ月で完治するため、多くの保険会社は交通事故から3ヶ月経過した時点で治療費の打ち切りを打診してきます。
ただし、交通事故による怪我の重さは人それぞれであり、医師が必要性を認める限りは治療をやめるべきではありません。
一方的に治療費を打ち切る保険会社もあるのですが、治療をやめてしまうのは心身に悪い影響を与えてしまいます。完治または症状固定という主治医の所見があるまでは、自身の健康保険を使って治療を継続しましょう。
症状が改善しないなら後遺障害認定を受ける
症状固定後にも後遺症が残っていれば、後遺障害申請をします。
6ヶ月程度の通院期間があれば、むちうちでも後遺障害に認定される可能性が出てきます。認定されれば、後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害への申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。
事前認定は保険会社に等級認定の申請を一任するため手軽に利用できます。しかし、被害者側が有利になる書類が提出されないといった理由から、適正な等級の認定が受けられない可能性が大きくなります。
一方で、被害者請求は被害者本人が書類を提出しますが、自身が有利になる資料をしっかり提出できるのがメリットです。

弁護士基準で申請する
交通事故の慰謝料は弁護士基準で請求するのが良いでしょう。
むちうちで6ヶ月通院した場合、自賠責基準や任意保険基準よりも高い慰謝料を請求できるためです。
ただし、個人が弁護士基準で請求しても、保険会社が素直に応じてくれることはないと思って良いでしょう。弁護士に示談交渉を任せ、弁護士基準で慰謝料を請求してもらう得策です。
弁護士に依頼するデメリットは、弁護士費用がかかることです。
弁護士基準で慰謝料を増額できても、弁護士費用の方が高くなってしまうと損してしまいます。弁護士に依頼する前に、自分の交通事故のケースではどのくらいの弁護士費用になるか、どのくらいの慰謝料を貰えるのかをあらかじめ確認しておきましょう。
ただ、自身や家族が加入している自動車などの任意保険に弁護士特約が付いていれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。特約を活用すれば、費用を心配せずに弁護士のアドバイスを受けられます。
弁護士に交通事故の示談交渉を代理してもらえば、任意保険会社に弁護士基準での慰謝料請求が可能になります。任意保険会社は、弁護士の要求を断れば訴訟に発展してしまうリスクがあると承知しています。法律の専門家である弁護士と張り合っても勝ち目は少ないため、ほとんどは弁護士基準による慰謝料請求を受け入れます。
弁護士のサポートがあれば、交通事故の示談交渉を有利に進められます。困ったときは法律事務所に所属している弁護士に対応をお願いするのがおすすめです。
慰謝料請求についてまとめ
交通事故のケガで6ヶ月通院すると、加害者に対し入通院慰謝料を獲得でき、後遺症が残ると後遺障害慰謝料も請求できます。
慰謝料の金額は計算基準により違うため、損をしないためにはぜひ弁護士基準を使用してください。
弁護士に依頼することで慰謝料を増額できますし、面倒な示談交渉や後遺障害への申請手続きなども任せられるため、納得できる結果になるでしょう。
現在は相談や着手金は無料としている弁護士事務所もあり、弁護士へは気軽に依頼しやすくなっています。交通事故によるケガで6ヶ月通院して慰謝料を請求したいのであれば、弁護士への相談を検討してください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ