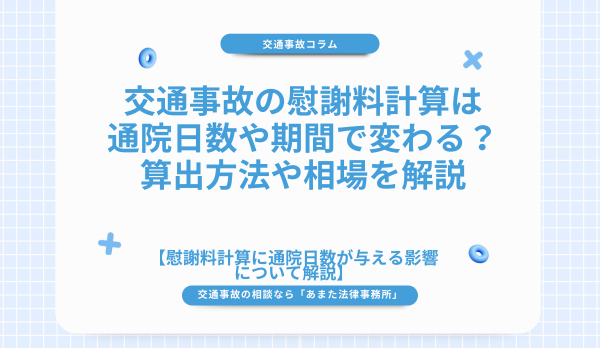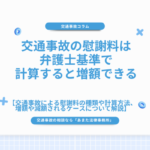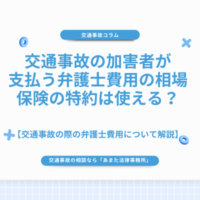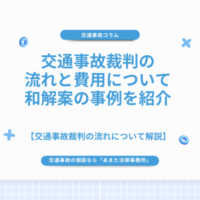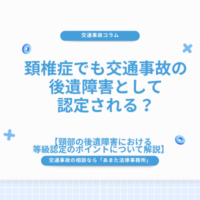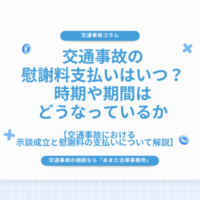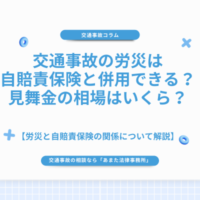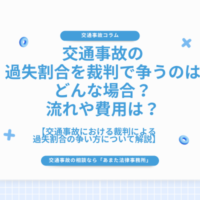交通事故で被害を受け、ケガで入通院をしたり、後遺症が残ったときは加害者への慰謝料請求ができます。
慰謝料を計算するさいに、重要なのが医療機関への通院日数。どれだけ治療を受けたかで慰謝料額が変わります。

この記事の目次
交通事故で慰謝料は請求できる
交通事故に遭い、ケガをして医療機関で治療が必要になったときや後遺障害が残ってしまった場合には、相手方に対して慰謝料を請求することが可能です。
しかし物損事故では慰謝料の請求ができない交通事故もあります。また計算方法や通院日数により金額は変わってきます。
交通事故の慰謝料は通院日数で変わる
交通事故の慰謝料請求では医療機関への通院日数で、もらえる金額が変わってきます。
交通事故における身体的・精神的苦痛とは、主にケガをして病院に入院・通院することの負担に対する賠償です。苦痛の度合いは個人差がありますし、数値化するのは難しいものです。そのためどれだけ病院に通ったか、どのくらいの期間治療したのかによって、慰謝料の金額が計算されています。
通院の期間自体は同じでも、通院日数が少ないと慰謝料金額が減らされることもあります。交通事故では慰謝料の計算方法がいくつかあるのですが、いずれの方法でも慰謝料をいくらもらえるかは通院日数が左右しているのです。
慰謝料とは身体的・精神的苦痛に対して支払うもの
民法に定められた民事責任の1つで、不法行為に対する損害賠償のうち、身体的苦痛や精神的苦痛に対するものを慰謝料と呼びます。
身体的苦痛や精神的苦痛は本来数値化できるものではなく計算するのは難しいのですが、法律上では慰謝料として金銭で支払うこととしています。
民法709条では、故意または過失によって他人の権利や利益を害した場合には、その損害を賠償する責任を負うと定められており、710条では他人の身体や自由を侵害した場合にも損害を賠償することが求められています。
この規定により、交通事故で負傷した被害者は加害者に対して慰謝料を請求することができます。
物損事故では慰謝料がもらえない
同じ交通事故でも、ケガ人のいない物損のみの事故では慰謝料を請求することはできません。慰謝料は身体的・精神的苦痛に対する補償ですから、物に対する精神的苦痛というものは認められないのです。

交通事故の慰謝料は計算方法により金額が変わる
交通事故の被害者が相手方に慰謝料を請求するときに欠かせないことが、慰謝料の計算方法です。実は、交通事故の場合、ひとくちに慰謝料といっても計算方法が複数あり、どの方法を採るかによってもらえる金額が変わってきます。
事故が起きると相手が加入している保険会社が慰謝料を提示してくることが多いのですが、保険会社は基本的に支払う保険金の額をなるべく少なくしたいと考えるものです。そのため、保険会社が提示する慰謝料の金額は適正とされる金額よりも低額である可能性が非常に高くなっています。
交通事故で慰謝料を請求するときは、適正な金額を支払ってもらうため相手の保険会社と交渉が必要なのですが、一般の方が保険会社と対等に交渉することは難しいです。慰謝料請求では弁護士に依頼するのがおすすめです。
交通事故の慰謝料は3つの種類がある
交通事故でもらえる慰謝料には、以下3つの種類があります。
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
交通事故の慰謝料、それぞれの種類を解説していきます。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
交通事故により、医療機関への入院や通院が必要になったことに対する肉体的・精神的苦痛への慰謝料です。傷害慰謝料ともいわれます。
精神的苦痛は目に見えるものではないので、基本的には、入院・通院日数によって計算されます。そのため、病院に通っていた日数が金額に大きく関係し、治療期間にくわえて、どのくらいの頻度で病院に通っていたかも重要になります。

後遺障害慰謝料
交通事故でむちうちなどの後遺症が残ってしまった場合に請求できる慰謝料です。どんな後遺症でも認められるわけではなく、請求するには、後遺障害認定を受ける必要があります。
後遺障害認定には、1級から14級までの等級があります。1級が何よりも重く、2級、3級と数字が大きくなるほど軽傷になっていきます。いくつかの等級に同時に当てはまっているケースもあり、その場合は重い方の等級を繰り上げる併合といわれる制度が適用されます。
死亡慰謝料
交通事故で被害者が死亡した場合に、家族等に対して支払われる慰謝料です。死亡慰謝料の場合、上2つと異なり、入通院日数は慰謝料額の計算には影響を与えません。
死亡慰謝料は、被害者の家族内での地位や役割、扶養の有無によって決まり、被害者が生前に家計のほとんどを支える大黒柱であった場合などは慰謝料も高額になります。
被害者が死亡した場合でも、それまでに病院に入院していた期間などがあれば、死亡慰謝料とは別に入通院慰謝料も請求できます。
交通事故による通院日数・治療期間の数え方
交通事故で慰謝料を算定するときの通院日数および治療期間の数え方についてです。
通院日数と治療期間の違い、計算するうえでの注意点を確認しておきましょう。
通院日数と治療期間の違い
通院日数と治療期間、2つの違いから説明します。
事故のため医療機関に通うことになった日数を表すもので、例えば、1か月のうち、週3回のペースで通院した場合は3日×4週間で通院日数は12日になります。
対して、治療期間は治療をはじめてから完治するまでにかかった期間です。入院した場合は、入院期間と通院期間を合わせたものです。
起算日となる治療開始日から完治・症状固定日までのすべての日数が治療期間として計算されます。病状固定とは、一般的な治療方法ではこれ以上症状の改善が見込めない状態をいいます。
例えば、9月1日に事故に遭って完治したのが11月30日だったとすると、治療期間は3か月となります。通院日数と異なり、この3か月の間に、何日通院していたかは治療期間の計算には影響を与えません。
通院日数・治療期間計算上の注意点
通院日数と治療期間を数えるときに分かりにくい点や注意すべきポイントを紹介します。
・慰謝料は1日から請求することができ、通院1日、入院1日であっても支払いの対象になる
・事故後、後遺症が残ってしまった場合、リハビリ目的での通院も期間の中に含まれる
・交通事故が発生した当日中に病院に行った場合も期間や日数の中に含まれる
・1日に複数回病院に行った日があっても、同じ日であれば計算上は1日でカウントされる
慰謝料計算に入院していない期間が含まれることもある
入院前・退院後の療養期間も通院日数・治療期間としてカウントされることがあります。やむを得ない事情で早期に退院せざるを得ない状況や、入院ができなかった場合でも、慰謝料を請求できる可能性はあります。
・幼い子をもつ母親が育児のため退院時期を早めた
・どうしても仕事を休むことができないので退院時期を早めてもらった
・病院側の都合で早めに退院してほしいと言われた
・病院が満床で入院までに待機期間があった
このようなケースでは、実際に入院していなくても入院を要する状態にあったと判断されるため、慰謝料計算に含まれることがあります。
交通事故で通院したときの慰謝料を計算する方法
交通事故で通院したときの慰謝料は、3つの計算方法があります。、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つのなかから、いずれかを選択することになります。
どの方法にするかで金額が大きく変わるのが交通事故の慰謝料の特徴で、自賠責基準では安く、反対に弁護士基準では高額となります。以下にそれぞれの詳しい計算方法を紹介します。
自賠責基準
すべてのドライバーに加入が義務付けられている自賠責保険に基づく算定方法です。交通事故の慰謝料では何よりも安い計算方法になります。
自動車を運転する人なら誰でも自賠責保険に加入しているため、交通事故の被害者になれば絶対に自賠責からの損害賠償を受け取ることができます。しかし交通事故の被害者に対して損害を最低限賠償することを目的としており、補償の限度額が法律で規定されているためもらえる金額は低くなってしまいます。
ただし慰謝料の金額が自賠責の限度を越えてしまった場合には、相手や相手の家族が加入している任意保険から超過分を支払ってもらうことも可能です。
任意保険基準
相手方が加入している民間保険会社の任意保険による慰謝料の算定基準です。算定方法は保険会社が自由に決めることができ、通常、計算方法は非公開とされていますが、自賠責基準よりは金額が高くなるのが普通です。
民間企業の保険会社は会社の利益を上げるため、保険金の支払い額をなるべく抑えたいと考えています。結果、任意保険基準では、最初から慰謝料の金額が安くなるような計算方法を設定していることが多くなっているのです。
自賠責基準より高いとはいっても、次に説明する弁護士基準と比べれば、かなり安くなると思っておきましょう。
弁護士基準(裁判所基準)
弁護士基準は、交通事故の慰謝料計算方法の中で非常に高い金額を請求できる算定基準です。裁判所基準ともいわれ、弁護士に依頼するか、裁判を起こした場合に適用されます。計算法は公益社団法人「日弁連交通事故相談センター」が発刊している「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)や「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)などを参考にしています。
自賠責基準や任意保険基準よりも高い慰謝料をもらうことができ、弁護士基準による金額こそ被害者が本来受け取るべき慰謝料額といえます。
裁判を起こすのは知識がない素人には大変ですが、弁護士に依頼すれば裁判と同じ慰謝料を受け取ることができます。交通事故の慰謝料は、ぜひ弁護士基準で請求すべきといえますが、弁護士に依頼するには当然弁護士費用がかかります。
弁護士への依頼では、はじめに着手金を支払う必要があるところもあるので、金銭的な負担が大きいと感じる方もいるかもしれません。

また加入している自動車保険や医療保険などに弁護士特約が付いていれば、負担金ゼロ円で弁護士基準による慰謝料を請求できる可能性があります。ご自身や家族の任意保険の内容を確認しておくと良いでしょう。
慰謝料の金額を3つの計算方法で比較
同じ期間、同じ通院日数の場合、3つの計算方法でどれくらい交通事故の慰謝料は金額が変わるのでしょうか。今回は3ヶ月の治療期間(入院期間なし)で月に12日通院したケースで比較しました。
自賠責基準
自賠責では1日4300円として、治療期間と通院日数の双方で計算を行います。適用されるのは低い方の金額です。
①治療期間での計算 4300×治療期間
4300円×90日=38万7000円
②通院日数で計算 4300円×実通院日数×2
4300円×36日(12日×3か月)×2=30万9600円
低い方が請求できる金額になるので、自賠責基準での慰謝料請求額は30万9600円になります。
任意保険基準
任意保険基準は自賠責基準より高いとはいわれているものの、実際にはほとんど同じか、少し高いくらいの金額になります。
各保険会社は計算方法を公開していないため、詳細な金額はわかりませんが、以前にすべての保険会社で使用されていた「旧任意保険支払基準」が参考になります。現在も多くの保険会社がこれをもとに基準を決めているといわれ、実際の慰謝料と大きな違いはないと考えられます。
| 通院↓ 入院→ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 |
|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 0 | 25.2 | 50.4 | 75.6 |
| 1か月 | 12.6 | 37.8 | 63 | 85.7 |
| 2か月 | 25.2 | 50.4 | 73.1 | 94.5 |
| 3か月 | 37.8 | 60.5 | 81.9 | 102.1 |
(単位:万円)
これを見ると、通院3か月の慰謝料は37万8000円、もし入院であれば75万6000円になります。ただ、保険会社はなるべく支払う保険料を低く抑えたいと考えるものなので、実際にはこれより低い金額で済まそうと交渉してくることも考えられます。
弁護士基準
3つのなかで極めて慰謝料が高額になるのが弁護士基準は、任意保険と同じように目安となる算定表が存在します。軽症用と重症用に分かれていますが、基本的に算定には重症用の表を使うようにします。
| 通院↓ 入院→ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 |
|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 0 | 53 | 101 | 145 |
| 1か月 | 28 | 77 | 122 | 162 |
| 2か月 | 52 | 98 | 139 | 177 |
| 3か月 | 73 | 115 | 154 | 188 |
(単位:万円)
| 通院↓ 入院→ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 |
|---|---|---|---|---|
| 0か月 | 0 | 35 | 66 | 92 |
| 1か月 | 19 | 52 | 83 | 106 |
| 2か月 | 36 | 69 | 97 | 118 |
| 3か月 | 53 | 83 | 109 | 136 |
(単位:万円)
交通事故で通院3か月の場合、重症なら73万円、軽症でも53万円になります。自賠責基準や任意保険基準を大幅に上回る金額になっているのがわかるでしょう。
もし入院であれば、骨折などの重症であれば145万円と慰謝料は100万円を超えますし、軽症でも92万円と100万円近い金額になります。弁護士基準を適用することで、慰謝料請求額が文字通り桁1つ大きくなることもあります。

慰謝料と通院日数の関係
交通事故の慰謝料を計算するにあたり、影響するのが通院日数です。通院日数はどのように関係しているのか、慰謝料の種類別・基準別に解説します。
慰謝料の種類別
交通事故の慰謝料には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、3種類があります。それぞれの慰謝料と通院日数の関係を見ていきます。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、通院日数との関係が大きくなります。身体的・精神的な苦痛がどのくらいなのかの判断は難しいため、実際に通院した日数や治療した期間により慰謝料が計算されるためです。
治療期間が基準として計算した場合、通院日数は直接関係ないように思われます。しかし、治療期間に対して病院に行っている日が極端に少ないと「本当は症状が軽いのでは?」「本当は治療の必要がないのでは?」などと判断され慰謝料計算で不利になる可能性が出てきます。
弁護士基準では、30日(1か月)で最低10日間は通院しているのが望ましいとされています。一定の通院日数を確保しておかないと慰謝料が減額されることはあるのです。
逆に通院日数が多ければ慰謝料の金額が増えることはありません。必要もないのに無闇に病院通いを続けても、合理性や必要性をもたない「過剰治療」と判断されてしまいます。
後遺障害慰謝料
交通事故の後遺障害慰謝料では後遺症の等級によって金額が決められるので、通院日数は直接影響をおよぼしません。
しかし、後遺障害の等級の判断においては通院日数が判断材料になることがあり、あまりにも回数が少ないと後遺症を訴えても認定してもらえないケースもあります。間接的に通院日数が関係しているといえるでしょう。
死亡慰謝料
交通事故の死亡慰謝料は被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料ですから、病院に行った回数によって左右されることはありません。
しかし、死亡する以前に入院したり、病院に行っていた期間がある場合は、入通院慰謝料を請求できるため、ここでは入通院日数が計算の基準になります。
慰謝料の基準別
3つの基準のなかで、通院日数が直接影響を与えるのは自賠責基準のみになります。任意保険基準と弁護士基準は、基本的に通院日数は関係していません。
自賠責基準
自賠責基準では1日あたり4300円という金額が慰謝料算定に使われるため、もらえる金額に通院日数が直接影響するといえます。ただ、必要がないのに病院に通い続けても過剰治療と思われる可能性が高いので、治療は適切なペースで行うことが望ましいでしょう。
任意保険基準
任意保険基準では一般的に通院日数よりも治療期間を目安に計算しています。原則として、通院の回数で受け取る金額が変わることはありません。しかし、期間の割に実際に病院に行った日が少ないと、「実際は症状が軽いのでは?」と疑われ、相場よりも低い金額を提示される可能性があります。

弁護士基準
弁護士基準でも算定に使われるのは主に治療期間のため、原則として病院に行った回数は関係がないといえます。ただ、通院日数が少なすぎる場合、通院日数の3.5倍を治療期間として計算する「3.5倍ルール」といわれるものが存在しているため注意が必要です。
ここでも任意保険基準同様、通院日数が極端に少ないと慰謝料の算定で不利になることがあります。医師の診断のもと、適切な治療を受けるようにしてください。
慰謝料以外の損害項目との関係
交通事故では慰謝料以外の損害賠償金のなかにも、入通院日数によってもらえる金額が変わるものがあります。付添看護費と入院雑費、交通費の3つです。交通事故の被害者になると、自動車の修理費や入院にかかる経費、交通費なども請求することができます。
付添看護費
付添看護費とは、交通事故による入通院にかかる付添人の費用です。看護師や介護福祉士などプロの付添人に対するものと家族など近親者の付添に支払われるものの2種類があります。
看護師等の費用は実費ですが、近親者に関するものは1日につき入院なら6500円、通院なら3300円で計算され支払われます。近親者による付添看護費の金額には、入通院日数が影響しているのです。
入院雑費
交通事故の入院雑費は、入院中にかかる様々な費用のことです。病院の売店で文房具やティッシュ、洗面具などの必要品や飲み物など購入する費用や公衆電話から家に電話をかけるときの費用、新聞など、テレビカードの購入費用などが当てはまります。
入院雑費は、日用品雑貨費、通信費、文化費の3つに分けられます。入院1日に月1500円を請求でき、入院期間が長くなるほど金額も多くなるため、入院日数が請求金額に影響します。
交通費
交通事故の通院にかかる本人分の交通費を損害請求することができます。支払いは原則実費で計算されますが、入院日数が増えれば請求金額は多くなると思われます。
交通事故の慰謝料が増額・減額されるケース
交通事故の慰謝料は、増額・減額されるケースがあります。慰謝料は入通院日数によって影響を受けるものなのですが、回数が多ければ金額が高くなり、少ないと金額が低くなるといった単純なものではありません。交通事故の慰謝料は様々な条件を総合的に判断して決定されています。
入通院日数が長いと慰謝料は増額される
原則として、入通院期間は長いほうがより多くの慰謝料をもらえるといえます。ただ、長ければ長いほどいい、というものでもありません。
なかには、慰謝料増額を目当てに必要以上に通院を続ける方もいますが、通院回数が多すぎる場合は過剰治療と判断され、慰謝料増額に結びつかないこともあります。ほかに、あえて高額な治療法を選択するケースも同様です。
このような場合には、適切な治療と認められずに慰謝料が増額されないばかりか、「無意味な治療を続けていたのではないか?」と疑われて、相手方が慰謝料支払いを渋る可能性もあります。
後遺障害認定の等級が高いと増額される
後遺障害認定には1級~14級があり、数字が小さいほど後遺症の程度が高く慰謝料も高額になります。後遺障害の申請には、手続きを相手方の保険会社に任せる「事前認定」と被害者自身が手続きを行う「被害者請求」の2種類があります。
事前認定は保険会社がすべてやってくれるぶん楽ですが、後遺障害の等級を下げられてしまうなど不利になる可能性はあります。できる限り自分でやるのが望ましいといえます。
被害者請求は手続きの手間がかかるうえ、医師から後遺障害診断書など必要書類をもらうときは実費になります。

交通事故の後遺障害認定の際、通院日数が極端に少ないと等級が下がったり、後遺症を認めてもらえないことがあります。適切な頻度での通院することが大切になります。
加害者側に過失が大きいほど増額される
居眠り運転やスピード違反、ひき逃げなど加害者側の過失割合が大きいほど、慰謝料が増額されやすくなります。
また、被害者に謝罪をしなかったり、警察の取り調べに対する態度が悪い、証拠の隠蔽、無理な主張をするなど、事故後、不誠実な態度をとった場合にも慰謝料増額の可能性があります。
事故による被害が大きいほど増額される
交通事故のために被害者自身や近親者の生活や人生に重大な被害をおよぼした場合にも、慰謝料が増額される可能性があります。
- ケガをして会社を辞めざるをえなかった
- ケガで通学が難しくなり、学校を退学することになった
- 事故のショックで近親者が精神疾患を患った
- 配偶者と離婚することになった
- 子どもを中絶することになった
などが該当します。
被害者が死亡した場合、子どもがいたり、新婚であったりすると、遺族の無念さが大きなものになると判断され、慰謝料が増額され計算されることがあります。
軽傷は慰謝料減額されやすい
軽傷で入院もせず、通院日数も少ない場合には慰謝料が減額されることもあります。ただ、たとえ金額が少なくてもきちんと慰謝料は請求するようにしてください。
擦り傷など病院に行く必要もないほど軽症の場合、医療機関にかからずに済ませてしまう人もいます。しかし時間が経ってから痛みなどが出てくることもあるので、必ず医師の診断を受けましょう。

通院日数が少ないと慰謝料は減額されやすい
通院日数が極端に少ない場合も慰謝料減額につながる可能性があります。通院日数が少ないと、適切な治療を受けられない危険性もあります。週2~3日のペースで必要な日数をきちんと通うようにしてください。
やむを得ない事情により通院回数を減らす場合などは考慮してもらえます。
素因減額
交通事故による損害が被害者自身の素因(要因)によって引き起こされたと判断される場合には、素因減額が適用され、慰謝料が減額される可能性があります。素因には以下の2種類があります。
・心因的素因……イライラしやすい、怪我から回復しようという意欲に乏しいなど被害者の性格に関するもの。
・体質的素因……事故前から被害者がもっていた既往症が事故に影響した場合は減額の対象に。ただし、年齢による老化現象は素因減額にならないことが多い。
素因減額は保険会社が支払い金額を減らす材料として用いることがあります。素因による減額が適用されると言われても、簡単に鵜呑みにして従うことのないようにしましょう。

まとめ
交通事故に遭ったとき、医療機関への入通院日数は直接・間接的に交通事故の慰謝料計算に影響を与えることがあります。そ極端に通院日数が少ないと慰謝料金額で不利になることは考えられます。しかし、必要以上に病院に通えば良いわけではありません。
大切なのはきちんとした治療を受けることです。医師と相談して適切な頻度での通院を行い、ケガの完治を目指しましょう。その上で、妥当な通院日数で慰謝料請求を行います。
交通事故の慰謝料は弁護士基準が望ましいため、請求にあたっては弁護士など法律を担当する者に相談するようにしてみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ