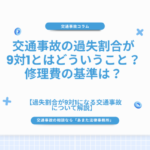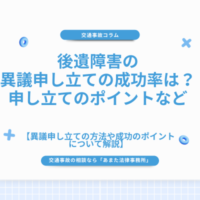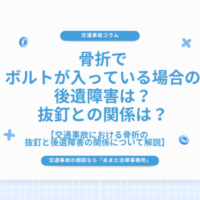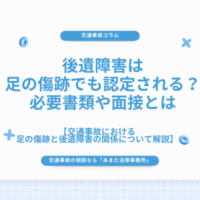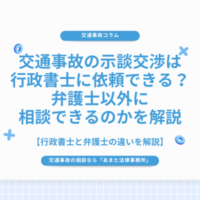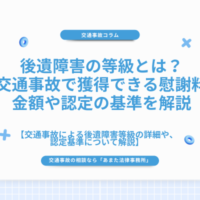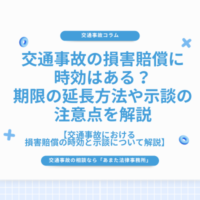交通事故の過失割合は、スピード違反などの個々の事情を考慮しながら過去の裁判例を参考にしつつ決定します。しかし双方の意見が食い違いやすく過失割合の算定はもめることが多いのが現状です。

この記事の目次
過失割合とは何?交通事故でもめるのは何故?
交通事故において当事者双方の過失(責任)がそれぞれにどれくらいあったかを割合で示したものを過失割合といいます。
ほとんどの交通事故では加害者と被害者の双方に過失が存在しています。当事者双方の落ち度の程度を「80:20」「70:30」といった過失割合で表します。加害者のみに責任があるケースは追突事故など一部に限られます。
過失割合や示談金の受け取り金額は示談交渉で取り決めていきますが、証拠の不確かさや法的基準の解釈の違い、利益や責任の関心の違いなどから、当事者同士が不満を持ち交渉がまとまらずもめるケースは少なくありません。
過失割合は示談金に影響する
過失割合の大小は示談金の受け取り金額に影響します。交通事故で発生した損害は当事者双方の責任に応じて負担しなければならないためです。
例えば、被害者に過失が一切なく加害者のみに責任があれば、過失割合は100:0となり被害者に生じた損害を全て加害者が支払うことになります。一方、過失割合が70:30の事例では、本来被害者が獲得できる賠償金のうち30%が減額されてしまい受け取れるのは70%の金額です。
上記のように過失割合に応じて受け取る賠償額が差し引かれる処理を「過失相殺」といいます。
過失割合を決めるのは誰?
過失割合は当事者同士が話し合う示談交渉で決まります。当事者には事故を起こした本人のほか任意保険会社や弁護士などの代理人も含まれ、一般的には相手方の保険会社が事故状況に合わせた過失割合を提示してきます。
警察が実況見分をした上で過失割合が決まるわけではない点は間違わないよう注意しましょう。警察には「民事不介入の原則」があるため、示談交渉など民事上の手続きには関与できないのです。
過失割合の決まり方
過失割合は加害者側の保険会社が提示してくるのが一般的ですが、算定は過去の裁判例を参考に行っています。
判例タイムス社が出版している「別冊判例タイムズ民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍には、過去の判例や類型がまとめて掲載されており過失割合を算定する際の参考資料にされています。
「別冊判例タイムズ」で過去に発生した類似事件を参照すれば、裁判所が認定した具体的な過失割合を知ることができます。

過失割合には修正要素がある
過去の裁判例を基にし事故のパターン別でまとめた過失割合を「基本過失割合」といいます。ただし、さまざまな状況がありますから、全ての類似事件で必ずしも基本過失割合が当てはまるとは限りません。安全運転義務に違反する行為は過失割合の「修正要素」として扱われます。
過去の判例で過失割合が70:30と認定された事例でも、相手側が著しいスピード違反をしているようなときは加害者の過失割合は高くなる可能性があります。
過失割合の修正要素にはどのようなものがあるのか、具体的にいくつか紹介します。
著しい過失とは事故態様ごとに通常想定されている程度を超える不注意のことを指します。原則として著しい過失の修正割合は10%になっており、脇見運転などの著しい前方不注意、酒気帯び運転、時速15キロ以上30キロ未満の速度違反、著しく不適切なハンドル・ブレーキ操作などが該当します。
故意と同視し得る不注意のことを重過失といいます。原則として修正割合は20%です。酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、時速30キロ以上の速度違反、信号無視などが当たります。
大型車は危険が大きく普通車よりも高い運転技術が課せられるため、5%程度の過失割合が加算されるケースがあります。ただすべてに適用されるわけではなく、大型車を理由とする修正要素が適用されない事例もあります。
ウインカーの点滅を怠り生じた事故には過失割合が20%加算されます。運転者が進路変更する時は交差点の30m手前もしくは進路変更の3秒前に「指示器による合図(ウインカーの点滅)」をしなければならないと決められているためです。
既に右折している車両と衝突した時は、直進車に過失割合が10%加算されます。右折車が右折を完了しているにもかかわらず、直進車が無理に交差点に進入すると接触する危険が高くなるという理由からです。
道路交通法50条違反の直進によって事故を起こすと、直進車の過失割合が10%加算されます。通常、交差点では直進車が優先されます。しかし直進車が交差点内で停止し他の車両の通行妨害になったようなときは、直進車の進入は禁止されています(道路交通法50条1項)。
交差点中心の直近の内側を進行せず早い段階で右折することを早回り右折といい、原則、修正割合は5%になっています。早回り右折は他の車両から見てその車が右折するとは予測し難く、右折先の対向車と衝突してしまうおそれがあります。
あらかじめ道路の中央に寄らずに右折する大回り右折では、原則5%の修正割合になります。他の車両は道路の中央に寄っていない車両の右折は予測が難しく、対応できなくなるリスクがあります。
対向直進車が停止線を越えて交差点に進入しているにもかかわらず右折を開始することを直近右折といいます。直近右折をすると、直進車が衝突を回避しにくくなります。原則として、直近右折の修正割合は5%になっています。
過失割合でもめることが多い原因
交通事故の当事者は示談交渉で過失割合や示談金の受け取り金額を取り決めますが、「自分は安全運転を怠らなかった」「相手の方が過失の程度が大きい」など、当事者同士の言い分が食い違い交渉がまとまらず進まないケースは多く見られます。

過失割合は被害者と加害者の話し合いで決める
交通事故の示談交渉は被害者と加害者で行われ公平な第三者が存在しておらず、法的に正しい過失割合を算定するのは困難であると言われています。
過失割合は裁判でも決定でき、裁判官が法的に適正な割合を算出し判決を下してくれます。しかし実際に裁判を利用すると膨大な時間や費用がかかるため、当事者による話し合いのみで解決するのが一般的です。また、過失割合の決定に警察は介入できません。警察が関与するのは刑事事件のみで過失割合の算定は民事事件になるため、干渉するのは「民事不介入の原則」に反するからです。示談交渉は裁判所や警察のような第三者の力を借りることなく、自分たちの力で解決しなければならないと言えるでしょう。
とはいっても、法律に関する詳しい知識がない個人が交渉を進めても適切な過失割合の算出は非常に困難です。お互いが自分の主張をぶつけ合い感情的になってしまい、冷静な話し合いができなくなることもあります。

過失割合はお金の問題に直結する
損害賠償の金額は過失割合の大小によって大きく異なるため、当事者がお互い「相手の方が悪い」ともめる要因になります。
例えば、被害者に1,000万円の損害が生じる事故で過失割合が100:0であれば、被害者に発生した損害を全て加害者に請求できます。もし過失割合が70:30であれば、相手に請求できるのは700万円で残りの300万円は請求できません。
過失割合でもめる3つの事例
過失割合の決定でもめてトラブルになる事例は少なくありません。過失割合の決定で特にもめやすい3つの事例を紹介します。
客観的な証拠がない
事故状況を裏付ける証拠がない事例では当事者の証言のみを頼りにして交渉を進めるしかなくもめやすくなります。双方の証言が食い違うと、合意に至るまでにかなりの時間を費やしてしまいます。
交通事故の証拠として役立つのは以下のものです。
- ドライブレコーダーの記録
- 防犯カメラの映像
- 目撃者の証言
- 事故直後に事故現場や車を撮影した写真や映像
- 警察が作成する実況見分調書
中でもドライブレコーダーの記録が最も強力な証拠になります。しかし、2020年に国土交通省が実施したモニターアンケートではドライブレコーダーの普及率は53.3%と約半数の車両にしか搭載されていないのが実情です。
損害額が大きい事故
損害額が高額な交通事故では過失割合による賠償金の増減幅が大きくなります。例えば、損害額が10万円で過失割合が80:20であれば減額される賠償金は2万円です。被害者にとっては2万円程度のであれば妥協できるかもしれません。
しかし、損害額が1000万円になれば過失割合が同じ80:20であっても、減額される賠償金は200万円になります。被害者側にすれば賠償金が200万円も減額されるのはたまったものではなく譲歩したくないと感じるでしょう。加害者側としても減額される金額が大きいほど自らの過失割合は低いことを主張し、支払額を減らしたいと考えるのは普通です。
駐車場内の事故
駐車場内が事故現場でも基本的には公道での交通事故と同様の対応がなされます。しかし、駐車場内の事故は事故状況によって過失割合が大きく異なります。
事例① 駐車場内の通路で出合い頭に起きた事故
は基本的に50:50になります。交差点を直進する場合でも、右折または左折する場合でも変わりません。
ただし、どちらかの通路が明らかに広ければ狭い通路を走行していた車両の過失割合が10%加算されます。また、一時停止の表示を無視した、通行方向表示に違反していたりしていれば、その車両の過失割合が10%〜20%加算されることがあります。
事例② 通路を進行する車両(進行車)と駐車スペースに進入する車両(進入車)の事故
進行車の過失割合が80%、進入車の過失割合が20%になります。駐車場は駐車するための場所であるため、駐車スペースに進入する車両が優先されるという考えがあります。

事例③ 通路を進行する車両(進行車)と駐車スペースから退出する車両(退出者)の事故
進行車が30%、退出車が70%になります。駐車スペースから通路部分への退出はお店や住宅などの私有地から公道へ出るシーンと類似しています。
道路交通法25条の2第1項では、車両は、他の車両等の交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の場所に出るための横断等が禁止されています。よって、駐車スペースから退出するケースにおいても退出車に大きな過失があるとみなされます。
交通事故の過失割合でもめたときの対処法
過失割合でもめてしまうとと示談が長引いてしまい、賠償金が支払われる時期が遅くなり被害者の負担が増えてしまいます。示談交渉でもめたときはどうすれば良いのか、対応策について紹介します。
相手方の過失割合の根拠を書面で提出してもらう
提示された過失割合がおかしいと感じたときは、相手方の保険会社に対してどのような根拠でを算定しているか書面で説明してもらいましょう。
保険会社としては被害者に支払う保険金はできるだけ抑えたいと考える傾向があります。そのため、被害者に不利な条件を提示するケースは少なくありません。個々の修正要素を考慮せずに算定していることも多いことから、書面で根拠の提出を求めることは有効な対処法になります。

片側賠償で妥協する
中には「90:0」や「80:0」など、特殊な過失割合で示談を成立させる手法がとられます。「90:0」や「80:0」などの例外的な数値で損害賠償することを「片側賠償」といいます。
通常、過失割合は「90:10」や「80:20」など、合計が100%になるのが基本です。90:10の過失割合では被害者10%、加害者90%で発生した損害を賠償しなければなりません。ところが90:0にすると、被害者が支払う損害賠償金はゼロで示談を成立させることができます。

片側賠償のメリット
片側賠償を提案すると示談が成立しやすくなります。被害者が「自らに過失は一切ない」と100:0を主張したとしても、加害者が「過失割合は90:10である」と言い張って譲らければ交渉がまとまらず長期化するおそれがあります。
そこで過失割合を90:0にすると相手方の合意を得られる可能性が出てきます。被害者は損害額の90%しか賠償請求できませんが、加害者に発生した損害を負担する必要がなくなります。一方、加害者としても被害者に対して支払う賠償金を10%減らせるため納得しやすい結果になります。
片側賠償のデメリット
被害者に過失がなければ本来は相手に対して損害額の100%を請求できます。しかし、片側賠償で90:0の過失割合を提案すると、損害額の10%は請求できません。
もめていた示談が完了すれば交渉のストレスから直ちに解放されますし、裁判に発展して余計な費用や時間をかける必要がなくなり、片側賠償は被害者が得するように見えます。
交通事故ADRを利用する
交通事故ADRとは、「Alternative Dispute Resolution」の頭文字をとった略語であり、裁判外で紛争を解決する手法を意味します。
ADR機関では「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」などが有名です。ADRを利用すると、ADR機関に所属している経験豊富な弁護士が間に入り、客観的かつ実務的な立場から示談交渉を仲介してもらえます。
ADRはありがたいことに基本的に無料で利用できますし、手続きが簡便・迅速なのも特徴で早ければ3ヶ月程度で和解することが可能です。通院や入院などケガの治療費を支払い費用がかさんでいる、できるだけ早く慰謝料を含む賠償金を受け取りたいという交通事故の被害者には心強い存在になるでしょう。

ADRでの調停を検討するのは有効です。
訴訟で解決する
示談交渉やADRでも過失割合が決まらなければ、訴訟を提起し民事での解決方法を検討することになります。裁判であれば示談交渉で解決できなかったトラブルでも、確実に決着させられます。
裁判は裁判所に訴状を提出することで開始します。訴状を提出したら、約1ヶ月半後に第一回口頭弁論が開かれ当事者双方が主張・反論を行うことになります。双方の意見や証拠が出尽くし争点が整理されると、ほとんどのケースで裁判所が和解を勧めてきます。お互いに納得すれば和解成立となり、合意した内容で過失割合が決まります。和解が成立しなければ裁判官の判決によって過失割合が決定します。
なお、判決に言い渡されるまでには通常1年〜1年半程度の期間がかかります。訴訟費用などもかかるため、基本的には示談交渉で過失割合を決めるのがおすすめになります。裁判を起こすのはもめてどうしようもないときの最終手段と考えるのが良いでしょう。
弁護士に依頼する
弁護士は法律問題のエキスパートであり交通事故の事件についても問題なく相談できます。難航していた示談交渉でも弁護士に任せることでスムーズに解決できた例も少なくありません。
弁護士は過去の判例を参考にするだけでなく、個々の修正要素も加味し正しく過失割合を算定してくれます。また、客観的な証拠(警察の実況見分調書やドライブレコーダーの映像など)をしっかり揃えてから過失割合を主張してくれるため、相手方が交渉に慣れている任意保険会社であっても有利に進められます。
さらに、弁護士への依頼は慰謝料の増額が期待できるというメリットも生じます。任意保険会社は「任意保険基準」と呼ばれる計算方法で慰謝料の金額を算出しますが、弁護士は「弁護士基準」と呼ばれる計算方法で慰謝料を算出できます。弁護士基準の慰謝料は、任意保険基準の金額をはるかに上回ります。
弁護士に依頼すれば正しい過失割合を算出してもらえるだけでなく、弁護士基準で慰謝料請求でき損害賠償の金額を大きく増やせる可能性が高くなります。

まとめ
交通事故の示談金を決定する上で過失割合は重要な要素になります。しかし、過失割合はお金の問題に直接かかわるため、示談交渉でお互いの折り合いがつかずもめてしまうケースは少なくありません。特に、客観的な証拠がなかったり損害額が大きいケースでは過失割合でトラブルに発展しやすくなってしまいます。
過失割合でもめたときの対処法はいくつかありますが、弁護士に相談するのが一番有効になります。過失割合に少しでも納得できない部分があるなら弁護士に相談してみましょう。無料で法律相談をしている弁護士事務所は増えていますし、加入している自動車保険などに弁護士特約が付帯していれば費用の負担なく気軽に弁護士を利用することが可能です。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ