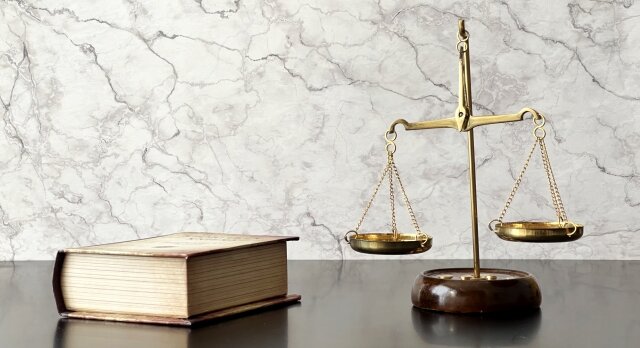交通事故の問題を解決するために、弁護士は必要かは迷うところです。弁護士に相談すると手厚いサポートが受けられますが、弁護士費用が気になり自分で対応しようとするケースもあります。

交通事故の慰謝料は示談交渉で決まる
交通事故の被害者は加害者に慰謝料を請求できます。慰謝料の金額を決めるのが示談交渉です。
慰謝料は精神的苦痛を補償するお金
「慰謝料」は、被害者が受けた精神的苦痛を補償する賠償金です。
交通事故に遭った被害者は事故の恐怖やケガによる苦痛を味わい、肉体的にも精神的にもダメージを負います。また死亡事故になると、遺族は大きな精神的ショックを受けてしまいます。
交通事故に遭い被った精神的な苦痛を償うために、加害者が支払うのが慰謝料ということになります。
交通事故では「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」と、主に3つの慰謝料を受け取れます。
交通事故による怪我の治療を行うために、入院や通院した際に支払われる慰謝料です。入院や通院にかかる負担に対する金銭ですので、入通院期間が長くなればなるほど金額は増額します。
交通事故で負った怪我の一部が完治せず、後遺症として残った場合に請求できる慰謝料です。
後遺障害は症状によって等級が1〜14級に分類されており、等級認定の審査に通ることで初めて後遺障害慰謝料を請求できます。等級が重症度の高い1に近づくほど高額の慰謝料が支払われます。交通事故による後遺障害の代表例であるむちうちは、軽症とされる14級に該当するケースが多いです。
交通事故の被害者が亡くなってしまった死亡事故で、遺族が加害者に請求できる慰謝料です。
死亡慰謝料を請求できるのは、①死亡者本人と②死亡者の遺族(父親、母親、子供などの家族)になります。
- 死亡者本人は死亡事故を引き起こした加害者に慰謝料請求権を持ちます。しかし、死亡していれば本人が直接請求することはできません。そこで、相続人に当てはまる近親者が代わりに請求することになります。
- 死亡者の遺族について、被害者を亡くした精神ショックを償わせるために、加害者に対して死亡慰謝料を請求できます。
示談交渉で賠償金の金額を決める
「示談交渉」は被害者と加害者が損害賠償の金額や支払い期日などについて取り決める話し合いのことです。
交通事故トラブルの解決方法には、民事裁判で決着をつける方法もあります。しかし、裁判は長期間に及ぶため迅速な事件解決は望めません。また、裁判費用などのコストがかかりますので、基本的には示談交渉でトラブルを解決することになります。
基本的に被害者は加害側の保険会社と交渉することになります。ここで問題となるのが弁護士は必要かという点です。被害者本人が交渉の席に着くことはできすが、弁護士に代行してもらうことはできます。知識がない個人が行うよりも交通事故の事案に精通している弁護士に依頼したほうが、有利に進めることができます。
示談交渉は双方の合意の上で損害賠償の金額を決定します。どちらかが条件に納得できないと示談は成立しません。
また、一度示談が成立すると示談書に記載された内容の撤回は不可能です。一度解決したトラブルの蒸し返しを防ぐためなので、交渉は慎重におこないましょう。

交通事故で弁護士に依頼するメリット
事故後の手続きは、弁護士に任せるのが有効です。メリットが多く、被害者の負担を軽減できます。
示談交渉を一任できる
弁護士に依頼すると、示談交渉といった事故対応にかかる手間やストレスを大幅に軽減できます。
事故直後は事故のショックにより、ナーバスになっている時期です。しかし加害者や加害者側の保険会社と何回も連絡を取らなければならず、相手とうまく意思疎通を取れないことは多いです。
慰謝料を増額できやすい
弁護士に依頼すれば慰謝料を増額できる可能性が高くなります。少しでも高い慰謝料を請求するには、弁護士は必要ということになるでしょう。
慰謝料の計算方法の種類
慰謝料の計算方法には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3種類の基準があります。弁護士に依頼すると、高額請求が可能となる弁護士基準を使用できます。
「自賠責保険」が定める慰謝料の算定基準です。自賠責は交通事故による被害者を救済するために、原付を含む全ての自動車に加入が義務付けられている保険のことです。
被害者が受けた損害を迅速に補償してくれるのは大きいメリットですが、最低限の金額しか保証されないのがデメリットです。3つの算定基準の中で最も慰謝料が低額になってしまいます。
任意保険会社が設定している慰謝料の算定基準です。各保険会社が個別に基準を設定しているため、保険会社ごとに計算方法や算出される金額は異なります。
慰謝料の金額は自賠責基準よりも若干高くなる傾向にありますが、弁護士基準と比較すると相場はかなり低い額になります。
弁護士が相手方と示談交渉する際に用いる慰謝料の算定基準です。裁判実務でもこの基準が適用されるので「裁判基準」ともいいます。
3つの基準の中で慰謝料の金額が最も高額になるのがメリットですが、弁護士への依頼が必要です。
慰謝料が増額する理由
弁護士に依頼すると、弁護士基準で慰謝料を請求できるようになります。弁護士なしだと自賠責基準か任意保険基準の金額になってしまいますから、一人で示談交渉に臨むときよりも慰謝料が増額することになります。
一般的に示談交渉は相手方の保険会社と行います。慰謝料は任意保険基準で算定した金額が提示されますが、最低限の補償である自賠責基準と大差なく低い金額しか獲得できないとえるでしょう。
賠償金を支払う立場である保険会社は、できる限り賠償金の金額を抑えようとします。

そこで、弁護士への依頼が必要になります。弁護士なら高額となる、弁護士基準で算出した金額を加害者側に請求できます。
弁護士基準は裁判所でも適用されており、法的に正しい算出基準と言えます。仮に任意保険会社が弁護士基準による請求を断っても、弁護士は民事裁判を提起して増額請求を求めるでしょう。
したがって、通常は示談交渉の段階で、保険会社は弁護士基準による支払いを受け入れてくれるのです。
被害状況に合った賠償金を計算してくれる
弁護士は保険会社に提示された示談金額と損害賠償項目を精査し、適正な賠償金を計算してくれます。
損害賠償金には代表的な治療費や慰謝料、車の修理費の他にもさまざまな項目があります。
例えば、後遺障害によって労働能力が低下し将来の収入が減少した分は「逸失利益」によって補償されます。逸失利益は高額になるケースが多いですが、保険会社が提示する逸失利益の金額は基本的に低めです。そのまま応じてしまえば、損をする可能性が高いでしょう。
被害者の方が全ての項目をチェックし、賠償金額が正しいか判断するのは困難な作業です。弁護士なら保険会社が提示してきた損害賠償項目と賠償金額の内訳が妥当であるかを、すぐに判断してくれます。

交通事故で弁護士に依頼するデメリット
弁護士への依頼はメリットが多数ありますが、デメリットもあるのが注意点です。
依頼には費用がかかる
弁護士に依頼する際には費用が必要になります。
弁護士への依頼料や相談費用である「弁護士費用」が高すぎると、費用倒れが発生するリスクがあります。
入通院を要する重症事故や死亡事故なら、賠償金が高額になるので費用倒れする心配はほぼないでしょう。しかし、物の破損に留まった物損事故や些細な軽傷事故であれば、支払われる賠償金は低額になります。

ただ、初回無料で法律相談を実施している法律事務所はいくつもあります。初回相談の時点で示談金額をタダで見積もってくれ、この費用倒れになるかを指摘してくれます。費用が不安ならば、無料で法律相談を行っている弁護士事務所を使うのがよいでしょう。
弁護士の選定が難しい
適切な賠償金を獲得するためには、弁護士の選び方が重要になります。
弁護士は全国にたくさんいますので、自身にあった弁護士を見つけるのは簡単ではありません。なかには交通事故の案件を扱っていない弁護士もおり、せっかく相談しても依頼を断られる場合があります。また、交通事故が得意分野ではない弁護士だと、期待する結果を得られないリスクもあります。
さらに弁護士とは連絡を取り合う機会が増えます。コミュニケーションが取りにくい弁護士を選ぶと、十分な説明を受けられない可能性もあります。疑問を解決できず、心理的な負担が増えてしまうのが注意点です。
弁護士の変更に費用と手間がかかる
弁護士への依頼は委任契約ですので、今の弁護士を解任して別の弁護士への変更は可能です。
しかし、一度弁護士に依頼した段階で、着手金など弁護士費用の一部を支払っています。キャンセルすると支払い済みのお金は返還されません。
また、別の弁護士を探すとなると、余計な労力が必要になります。
こちら側の話を聞いてくれなかったり対応が遅かったりするなど不信感があったら弁護士の変更を検討するのは必要ですが、費用と手間がかかってしまう点に注意しましょう。
デメリットありでも弁護士に依頼すべきケース
弁護士に依頼するときはデメリットもありますが、それを考慮しても弁護士を必要としたほうが良いいケースはあります。
治療費を打ち切られた
相手の保険会社はこれ以上治療の必要性がないと判断し、突然治療費の打ち切りを打診してくることがあります。
交通事故による怪我の治療費は、相手方の任意保険会社が補償してくれます。しかし、保険会社としては治療費をいつまでも支払い続けるわけにはいかないという考え方をします。一般的に打撲は1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月が「症状固定」の目安になり、保険会社はそのタイミングで治療費の打ち切りを打診してくることが多いです。
ただ、怪我の治癒状況や痛みの感じ方は人それぞれで、症状固定のタイミングも人によって違います。そして、症状固定を判断するのは保険会社ではなく医師です。治療を必要とする診断であれば、症状固定の目安となる時期を過ぎても治療を止めるべきではありません。
保険会社は被害者の怪我に必要な治療費を支払う義務があり、一方的に支払いの終了を宣告されても治療を継続する必要があれば治療費を再請求できます。その際は弁護士に依頼し、適切な補償が受けられるように交渉を進めてもらうのが良いでしょう。

入通院の期間が3ヶ月以上になっている
3ヶ月以上の入通院を要する重傷を負ったケースでは、賠償金額が高額になりやすく弁護士の介入による増額幅も大きくなります。
入通院慰謝料の金額は入通院期間の影響を受け、長ければ長いほど高額の慰謝料を請求できます。そのため、入通院期間が3ヶ月以上と長引いていれば弁護士に依頼するのがおすすめです。
また、入通院慰謝料を受け取るには、適切なペースでの通院は非常に大切です。通院ペースが著しく少なかったり、必要がないにもかかわらず毎日整骨院などに通っていたりしていると、入通院慰謝料が減額されるおそれがあります。
後遺障害が残った
後遺障害が残ったときや残る可能性が高ければ、迷わずに弁護士に相談しましょう。
後遺障害の等級が認定されると治療費、休業損害、入通院慰謝料といった後遺障害慰謝料を請求できます。
また、後遺障害によって身体の自由が制限されると、将来の労働、仕事にも悪影響が及びます。後遺障害によって労働能力が低下すれば、将来的な収入減少を免れることはできません。このとき、逸失利益によって、この先に得られるはずだった利益を賠償してもらえます。
後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、後遺障害の等級認定を受ける必要があり、医師のカルテや診断書、MRIといった検査の画像の準備など入念な対策をしての申請が必須です。
交通事故に詳しい弁護士に依頼することで、後遺症義の等級認定に必要な資料の収集や書類の作成を手伝ってくれたり、医学的根拠に基づいた申請書を提出してくれたりします。

被害者側に過失が一切ない
交通事故の原因について、被害者側の過失が全くないケースは弁護士に依頼するべきといえます。
交通事故には過失割合というものがあり、事故の責任を2:8や1:9などと数字で表します。被害者0、加害者10になるのは、追突事故などの「もらい事故」が当てはまります。
実は、一切過失がないと被害者が加入する自動車保険の「示談代行サービス」は利用できない決まりがあります。
示談代行サービスを利用するには、保険会社の示談交渉への参加について「利害関係」を持っている必要があります。
被害者側に過失がない事例では被害者に賠償責任が発生せず、保険会社は事故の相手方に保険金を支払わなくて済みます。つまり、保険会社が示談交渉に参加することに利害関係が生じないのです。
弁護士法72条は弁護士以外で金銭的に利害関係を持たない者が、報酬を得る目的で法律事務を行うこと(非弁行為)を禁止しています。したがって、被害者側に過失が一切ないケースでは、示談代行サービスを利用できません。
事故発生の要因が100%加害者側にあるときは、保険会社ではなく弁護士の力が必要になります。
参考:電子政府の総合窓口(e-Gov)
弁護士特約に加入している
自動車保険に「弁護士特約」が付帯しているなら、弁護士は積極的に利用してください。
弁護士特約は交通事故の解決を弁護士に依頼したときに、保険会社が代わりに弁護士費用を支払ってくれるサービスです。年間保険料を追加で2,000円前後支払えば、任意で弁護士特約をつけられます。
弁護士特約は保険会社が弁護士費用をひとり当たり300万円を限度として負担してくれます。
特に役立つのは、物損事故や軽傷事故のように賠償額が低額になる事故です。
被害者側の損害が小さいと受け取れる賠償金よりも弁護士費用の方が高額になり、費用倒れを起こすリスクが高まります。ところが、特約を利用すれば弁護士費用を自己負担せずに済むため、費用倒れを気にせず気軽に相談できるでしょう。弁護士費用が300万円を超えるケースもほぼありません。

弁護士へ依頼するべきか見極めるポイント
弁護士が必要な状況であるかの判断ポイントを解説します。自身にとって不都合が生じることがないように気を付けましょう。
費用倒れにならないか
弁護士が必要かは、【弁護士による示談金の増額分>弁護士費用】になるかで判断しましょう。
弁護士への成功報酬は成果に対する割合で設定されいます。もらえる示談金が少ないと、支出である弁護士費用の方が高くなってしまい費用倒れが生じます。
もし費用倒れになるリスクがあるときは、見積もりの段階で指摘してもらえます。金銭面で損すると本末転倒ですので、後悔しないためにも相談段階で費用倒れにならないか、きちんと確認してください。
タイミングが遅すぎないか
弁護士への依頼が、手遅れになってしまうことはあります。依頼のタイミングを逸してしまうと、解決は難しくなってしまいます。
弁護士へ相談するタイミングは早ければ早いほど良いと言われていますが、相談のタイミングが手遅れになっている事例について2つ紹介します。
すでに示談が成立している
示談が既に成立してしまうと、弁護士に依頼しても取り返しがつきません。
当事者がお互いに納得し解決したトラブルを蒸し返すのは好ましくないとされており、示談が成立したあとは弁護士に相談しても示談内容を撤回することはできません。
ただし、示談成立後に内容の撤回・再交渉が認められる例外はあります。
例を挙げると、示談成立後に後遺障害など当時予測し得なかった事情が生じた場合は、示談の撤回・再交渉が認められる可能性があります。
原則として示談のやり直しは認められませんが、後から予期しないトラブルが発生する可能性はあります。困ったときは、示談成立後でも遠慮なく弁護士に相談してください。
損害賠償請求の時効が成立している
交通事故の損害賠償請求権はいつまでも行使できるわけではありません。民法には時効制度が定められており、時効が成立することで損害賠償請求権が消滅してしまいます。
損害賠償請求権の時効は、被害者が加害者及び損害を認知した日の翌日からカウントされます。
物損事故は3年、人身事故は5年で時効を迎えます。ひき逃げ事故のように加害者がわからない事故では、事故発生日から20年が経過すると時効を迎えます。
ただし、時効を迎えたからといって、直ちに損害賠償請求権はなくなりません。時効の成立には期間を経過した後に、債務者(賠償金を支払う者)が時効制度を利用して時効の効果を得ようとする意思表示である「時効の援用」をする必要があるためです。
弁護士に相談する前に知っておきたい注意点
弁護士に相談する際に気をつけるべきポイントを解説します。
相談しやすい雰囲気の弁護士を選ぶ
気兼ねなく報告や相談できそうな弁護士を選ぶようにしましょう。
弁護士も一人の人間ですので、性格は人それぞれ異なるのが現状です。中には、気難しい人や態度が悪い人もいます。事件を依頼した後は連絡を取り合う頻度も増えますので、相性が合わない弁護士に依頼してしまうと、後々のコミュニケーションに支障をきたすおそれがあります。

事実をありのままに伝える
事実関係を正確に把握していなければ、弁護士は的確なアドバイスができません。
自分に不都合な事実が知られると「争いで不利になるのでは」と感じるかもしれませんが、逆に後から不利な事実がバレて悪い状況に追い込まれた事例はあります。自分にとって不都合な事実があっても包み隠さずしっかり伝えましょう。
まとめ
交通事故で弁護士が必要になってくる場面はあります。慰謝料を含む賠償金の増額や被害者の負担軽減などは、大きなメリットと言えます。
費用倒れにならないのであれば、悩んでいるよりも早めに弁護士に相談するのが良いでしょう。
高額な賠償金を獲得できる事故や、弁護士特約が利用できる状況なら、弁護士に依頼するのがおすすめです。
- すべて弁護士にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ