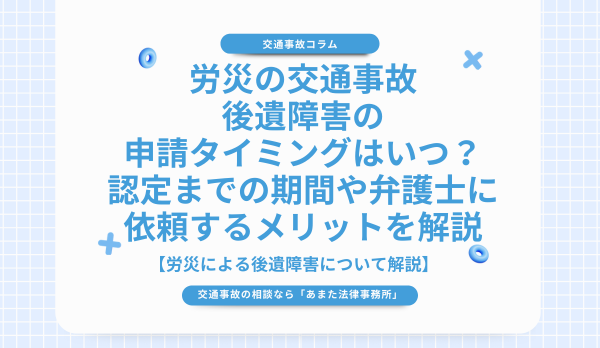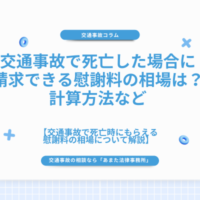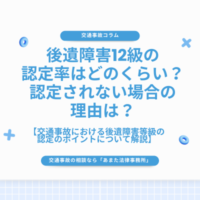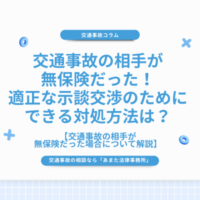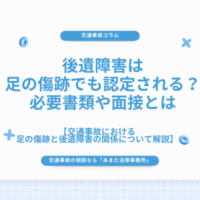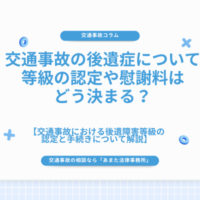労災で後遺障害が残ったとき支給されるのが障害補償給付です。ただし、障害補償給付は自動的に支払われるものではなく、後遺障害の等級認定を受けなければなりません。


2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 ▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
この記事の目次
労災による後遺障害は2種類ある
業務や通勤中の交通事故は労災になりますが、後遺障害が残ると労働者は労災保険から後遺障害に関するお金を受け取れます。
労災(労働災害)は労働者が業務中や通勤中に発生した災害(負傷・病気・障害または死亡)のことです。労災が認定されれば、雇用形態にかかわらず保険の給付を受けられます。
労災は一般的に「業務災害」と「通勤災害」の2つの種類に分類されます。
業務災害
労働者が業務中に生じた負傷・病気・障害または死亡のことです。業務中に怪我したときなどが当たります。
業務災害と認められるためには、
- ①労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある(業務遂行性)こと
- ②業務がきっかけで災害が発生したという因果関係がある(業務起因性)こと
が必要になります。

通勤災害
労働者が通勤中に生じた負傷・病気・障害または死亡のことです。例えば、朝の通勤で車を運転していた労働者が事故に遭ってむちうちを発症したときは通勤災害にあたります。
通勤災害における「通勤」とは、
- ①住居と勤務先との間の往復
- ②勤務先から他の勤務先への移動
- ③単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
上記のうち、合理的な経路及び方法によって行うことをいいます。
合理的な経路を逸脱すれば「通勤」にはならないのですが、コンビニでの買い物など、日常生活で必要と認められる最小限度であれば合理的な経路を逸脱したことにはなりません。
労災による後遺障害で受け取れるお金
交通事故などで負ったケガや病気を治療したものの完治せず、残ってしまった機能障害や神経症状が後遺障害です。業務中や通勤中に発生した交通事故で後遺障害が残ったら「後遺障害等級」に認定されると労災保険から後遺障害に関する保険金が支払われます。
後遺障害等級は1級から14級まであり、障害の程度が重い1級に近づくほど補償の内容が手厚くなります。
労災による後遺障害に等級が認定されると、労災保険から障害補償給付が支払われます。障害補償給付は、後遺障害の程度によって年金と一時金に分かれています。
参考:厚生労働省徳島局
労災により残った障害の程度が重く介護が必要なケースでは介護給付を受け取れます。1級は全ての障害、2級は精神神経・胸腹部臓器の障害が残ると介護給付が支給されます。
労災によるケガや病気を治療するため通院したときにかかった治療費や交通費などに対する療養補償給付を受け取れます。
労災によるケガや病気を治療するために仕事を休んだときは、働けなかった機関について休業補償給付を受け取れます。
障害補償給付の請求方法
障害補償給付を受け取るには休業補償給付や療養補償給付とは別に改めて請求するなどの対応が必要になるため、請求方法や注意点を知っておきましょう。
労災申請の必要書類
労災保険は所定の様式で作成した給付請求書と、必要な添付書類を提出して請求します。障害補償給付を受けるために必要となる書類は以下の通りです。
・後遺障害診断書
・レントゲン画像といった検査の結果
障害補償給付支給請求書と診断書は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。診断書は担当医に自覚症状を丁寧に説明し、記載漏れがないよう書いてもらってください。
障害補償給付の請求方法
請求書や診断書、レントゲン写真といった資料を労働基準監督署に提出し障害補償給付を申請します。労働者が属している会社が労災認定するわけではないため注意しましょう。
その後、労働基準監督署が必要な調査を行い、顧問医が申請者と直接面談した上で後遺障害の等級認定を判断します。労災と認定されれば、障害補償給付が支払われます。
障害補償給付の請求には時効がある
労災申請の注意点となるのが時効期限です。時効期限を過ぎると、以降は労災保険を請求できなくなります。
時効期限は労災保険の内容で異なります。障害補償給付の時効は5年となり、傷病が治癒(症状固定)した日の翌日から時効のカウントが進みます。

労災による後遺障害の申請タイミングはいつ?
労災による後遺障害の程度は症状固定の後に評価されます。そのため、後遺障害の申請タイミングは症状固定後になります。
障害が残ったことを症状固定という
症状固定はケガや病気の治療を継続しているにもかかわらず症状の一部が改善せず、これ以上治療を継続してもその効果が期待できない状態を意味します。症状固定の判断は医師がケガの様子をみて行います。交通事故で多い後遺障害であるよるむち打ち症は、3ヶ月〜6ヶ月の経過観察を経た上で症状固定になるケースが一般的です。
症状固定になると治療は終了したものとして扱われます。治療中は労災保険から療養補償給付や休業補償給付が支払われますが、症状固定以降は支払いがストップします。

症状固定と判断されるタイミング
症状固定と判断される時期は、大きく分けて2つのタイミングがあります。
- 医学上妥当と認められる期間を待ってから
- 症状固定の見込みが6か月以内の期間においても認められないものは療養の終了時
①の「医学上妥当と認められる期間」は、6ヶ月以内を意味します。例えば、指の欠損など器質的な障害は基本的に元に戻ることはないと考えられるため、6ヶ月を経過しなくても症状固定と判断できます。
一方、痛みや痺れといった神経症状や関節の可動域制限といった機能障害は、一定期間治療を継続すれば回復する可能性があります。そのため、まずは6か月間様子を見て、完治しなければそれ以降の妥当な時期を症状固定日と考えるのが②のケースです。
後遺障害等級が認定されるまでの流れ
事故発生から後遺障害の等級が認定されるまでの流れを解説します。
1、ケガや病気の治療を受ける
労災事故に遭ったらまずはケガを治療しましょう。今後も治療を継続したとしても改善の見込みがない症状固定と主治医に診断された時点で治療は終了したものと考えられ、労災関係の書類では「治ゆ」と表記されます。

2、必要書類を提出する
症状固定と診断されたら、必要な書類を取り寄せ労災保険を請求する準備をしましょう。障害補償給付支給請求書、後遺障害診断書、レントゲン写真などが用意できたら、労働基準監督署に提出し申請します。
3、労働基準監督署による審査
所轄の労働基準監督署に必要書類を提出すると、労働基準監督署で後遺障害の等級を認定する審査が行われます。労災の等級認定審査では、原則として地方労災医員という医師が申請者と面談を行い等級認定を判断します。
4、支給決定通知が届く
労働基準監督署で後遺障害の審査が完了し等級が認定されると、厚生労働省から支給決定通知と支払振込通知が一体となったハガキにより連絡が来ます。通知が送付されるタイミングの前後に、支払振込通知記載の等級に応じた障害補償給付年金又は一時金が振込指定先の口座に振り込まれます。
後遺障害診断書の記載内容が重要
労災の後遺障害等級は申請しても100%認められるわけではありません。審査は厳しいと言えますので、適切な等級が認定されるためのポイントを押さえておくことが大切です。まず、後遺障害等級の認定にあたり、非常に重要になるのが労働基準監督署に送付する後遺障害診断書の内容です。
労災保険を利用する際には労災指定の診断書の書式を入手し、担当医に後遺症の内容を記載してもらいます。記載内容が不十分であると正しい等級が認定されないおそれがあるため、日常で感じる痛みや痺れがあれば、日頃から医師に丁寧に説明するようにしましょう。
結果に納得いかないときは不服申立てする
想定よりも低い等級が認定されたり、等級不該当で不支給決定になる事例はあります。納得できない結果が出たときは、所定の行政庁に不服申立てができます。
審査請求
行政庁が違法または不当な処分をしたときに、労働基準監督署を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に行う不服申立てです。審査請求は後遺障害の認定結果を知ったときから3ヶ月以内に、口頭・書面・電子申請で行います。
審査請求が認容されれば行政庁の処分(労災保険の不支給決定)が取消されます。
再審査請求
審査請求が棄却となったり3ヶ月が経過しても結果が出なかったときは、労働保険審査会に「再審査請求」ができます。再審査請求は、審査請求の決定書送付の翌日から2か月以内に申請します。
また、再審査請求は審査請求とは異なっており、口頭ではできず書面で提出しなければなりません。
後遺障害認定されても慰謝料はもらえない
労災で後遺障害等級が認定されても慰謝料は受け取れません。慰謝料は労災保険の給付内容に含まれていないためです。会社や第三者から慰謝料を含む賠償金を受け取るためには、労災保険請求とは別に損害賠償請求する必要があります。
会社への請求
労働者を雇う会社は労働者の生命や身体に損害が生じないために、労働環境を整える配慮しなければなりません(安全配慮義務)。
例えば、問題がある設備をそのままにしていたり、長時間労働を強いたりしたことで業務災害が発生したのであれば、会社側が安全配慮義務をしていないことになります。

第三者への請求
労災が第三者の故意や過失によって引き起こされた場合は、相手方に不法行為に基づく損害賠償請求ができます。通勤途中に生じた交通事故の加害者からは、慰謝料を受け取れる可能性があります。
適切な補償を獲得するために弁護士に相談しよう
労災は初めてという個人が、ケガや病気があり万全でない状態で労災関係の手続きを全て自分でなすのは困難といえるでしょう。スムーズに後遺障害を申請し補償を受けるためには、交通事故や労災問題の事案に強い弁護士への相談を検討するのがおすすめです。
弁護士に依頼するメリットはいくつもあります。
メリット① 適切な等級が認定されるようサポートしてくれる
労災認定を受けるためには労働基準監督署に送付する申請書類の内容が重要になります。しかし、医師は医療の分野には詳しいですが、後遺障害認定に関しては専門ではありません。等級が認定される基準を必ずしも熟知しているわけではなく、診断書の内容が不十分なケースがあります。
弁護士は等級認定に必要なポイントを押さえているので、適切な診断書の書き方についてアドバイスしてもらえます。

メリット② 会社や第三者に損害賠償請求してくれる
労災保険は慰謝料の補償がありません。慰謝料は災害の原因となった会社や第三者に別途請求する必要があります。しかし、法律に詳しくない一般の人が会社や第三者に慰謝料請求しても不備が起きやすく、適切な賠償金を獲得するのは難しいでしょう。
メリット③ 弁護士特約を利用できる
労災の交通事故でも本人や家族が加入している自動車保険などに付帯する「弁護士特約」を利用できます。
交通事故で500万円の損害賠償請求を弁護士に依頼すると、通常は100万円以上の弁護士費用がかかります。しかし特約があれば費用の負担を気にしなくても良いため、安心して弁護士に相談できるようになります。
加入している任意保険に弁護士特約が付帯するのかわからないときは、弁護士に確認してもらうことも可能です。

労災に当たる交通事故についてまとめ
労災に当たる交通事故で後遺障害が残ったときは、労災保険から障害補償給付を受け取れます。ただし、後遺障害等級が認定されなければ、障害補償給付は支払われません。
交通事故のケガは誰もが見てわかるような器質的な障害は受傷から6ヶ月を待たなくてもよいですが、障害痛みや痺れが生じたときの後遺障害等級の申請タイミングは受傷してから6か月以上経過した後になります。
労災認定や後遺障害の分野は法律知識が求められるため、不安や悩みがあれば弁護士に相談し解決するのが良いでしょう。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ