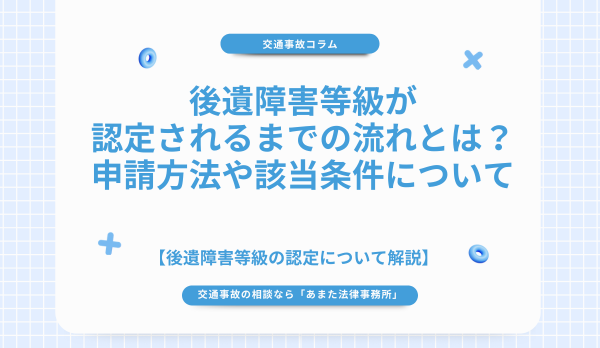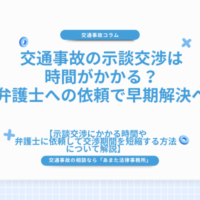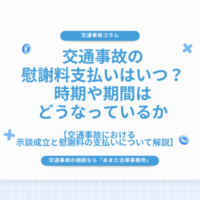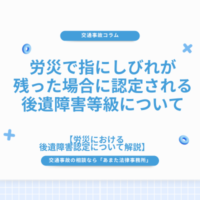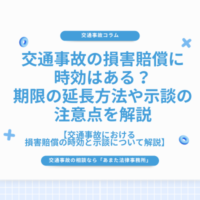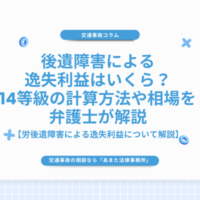交通事故の被害者が後遺障害の補償を受けるには、専門機関に申請し認定を受ける必要があります。

この記事の目次
交通事故による後遺障害とは何か
交通事故で負ったケガを治療したものの完全に治りきらず何らかの症状が残ってしまった状態を「後遺障害」といいます。一般的に、治療後に機能障害や神経症状などが残るケースは「後遺症」と呼びますが、後遺症と後遺障害は少し意味が異なります。後遺障害は後遺症のうち、交通事故が原因のもの限定で使われる用語です。
後遺障害には定義があり、認定を受けるには次の4つの要件を満たす必要があります。
- 交通事故による怪我を治療しても何らかの症状が残存しており、将来的にも回復が難しいと見込まれる。
- 症状と交通事故との間に相当な因果関係(社会通念上、原因と結果の関係性があると認められること)があると医学的に証明されている。
- 残存する症状のために、労働力の低下や喪失が生じている。
- 症状が「自動車損害賠償保障法施行令」に規定されている1級~14級までの「後遺障害等級」のいずれかに該当している。
交通事故で後遺症が残ったとしても、自動的に「後遺障害」が認められて損害賠償が請求できるわけではありません。後遺障害は所定の手続きをして後遺障害等級を認定してもらう必要があります。
後遺障害等級への認定には申請が必要
後遺障害等級の認定は、交通事故の後遺障害を担当する専門機関に「申請」し、自賠責施行令に定められている等級に該当すると認めてもらうことです。後遺障害に対する損害賠償を請求するためには、後遺障害等級の認定が必須になります。
申請は書面で行います。申請書のほかに医師が作成する「後遺障害診断書」やCT、MRIの画像等を証拠資料として添付し、事故の相手方が加入している自賠責保険会社に提出します。
後遺障害等級へ認定される流れ
実際に後遺障害等級の申請を行う際のタイミングや申請先、手続きの流れやかかる時間などをみていきましょう。
後遺障害認定を申請するタイミング
後遺障害等級に申請するのは、医師から「症状固定(治癒)」の診断を受けたタイミングが一般的です。症状固定は交通事故によるケガがこれ以上治療を行っても、症状が改善しないと判断される状態を指します。
交通事故の損害は症状固定を境にして傷害分と後遺障害分に分かれており、請求できる損害賠償の項目が異なっています。
後遺障害認定を申請する機関
後遺障害は事故の相手方が加入している自賠責保険会社を通じて、「損害保険料率算出機構」の「自賠責損害調査事務所」へ申請します。
自賠責損害調査事務所では申請書類に基づき公正な視点から、事故の状況や後遺障害の内容、損害賠償の妥当性、損害額の算出などを行います。そして、認定の可否が判断されます。
後遺障害認定の申請手続きは2種類
後遺障害等級の申請は、「事前認定」と「被害者請求」の2通りの方法があります。
事前認定
加害者の加入している任意保険会社を通じ申請する方法です。診断書など必要書類を送れば、後の手続きはすべて保険会社がやってくれます。
・書類作りや資料集めといった複雑な申請手続きをしなくても良く、時間や手間がかからず被害者の負担が少ない。
・初めての申請でミスが起きないか不安があれば、保険会社に頼むほうが安心できる。
・申請に必要な資料を用意するためにかかる費用を保険会社に支払ってもらえる。
・保険会社はなるべく支払う保険金を低く抑えたいと考える傾向にあるため、被害者に有利となる書類を提出してくれるとは限らない。結果、非該当になってしまったり、納得のいく等級での認定を受けられない可能性がある。
・保険料の支払いが一括で行われ、自賠責保険分だけを先に受け取る制度が利用できなくなる。経済的に余裕のない方は注意が必要。
被害者請求
加害者の加入している自賠責保険会社に必要書類を収集し、被害者自身が申請する方法です。
・保険金のうち自賠責保険分の先払い制度が利用可能で、加害者との間で示談が成立する前でもお金を受け取れるようになる。
・申請書類等は全て自分で用意する必要があり時間と手間がかかる。
・後遺障害への知識がないと不備が起きやすい。
・診断書や画像資料を発行してもらうための手数料等は被害者自身が負担する必要がある。
後遺障害認定にかかる期間
後遺障害等級の認定にかかる期間の目安は、早ければ1か月、遅ければ2~3か月ほどです。2020年度の統計では全体のうち72.7%が30日以内となっており、7割以上が1か月以内に結果が出ています。
ただ、所要日数は後遺障害の種類によっても異なります。61~90日は7.1%、90日越が7.4%となっており、全体の14%程度は2~3か月の期間を要している点には注意が必要です。1か月以上かかるケースもあるとは考えておくのが良いでしょう。

参考「2021年度 自動車保険の概況」
後遺障害認定の流れ
事故が起きてから後遺障害等級の認定を受けるまでの流れを見ていきましょう。
後遺障害の申請は事故発生後に治療を受け、医師に「症状固定」と診断された時点です。申請時には必要書類の1つとして医師の診断書を用意する必要があるため、症状固定の診断をもらうまでは申請できません。
申請に必要な書類を準備します。後遺障害等級の認定には医師による「後遺障害診断書」が必須で、診断書には決められた書式があります。

また、レントゲンやCT、MRIなどの画像資料、ジャクソンテストやスパークリングテストをはじめとした神経学的検査などの結果、後遺症が今後の生活や仕事に与える影響に関して医師の所見を記した「意見書」などを用意できると有利です。
必要な書類等が揃えたら、加害者側の保険会社に提出し申請します。提出先は申請方法により異なります。
- 事前認定→加害者側の任意保険会社
- 被害者請求→加害者側の自賠責保険会社
申請方法によって必要になる書類も異なります。事前認定は後遺障害診断書等を提出するだけですが、被害者請求は自分で申請書等の書類一式を準備する必要があります。
保険会社から申請書類が損害保険料算出機構の自賠責保険調査事務所に送付されると、審査が開始されます。後遺障害認定の審査は基本的に書類のみで済みますが、顔の傷など外見から分かるような後遺症では面談を実施するケースもあります。
審査後、事前認定は保険会社へ、被害者請求は被害者本人(弁護士に依頼した場合は弁護士)に対し結果の通知が行われます。
後遺障害等級へ実際に申請したケース
実際に後遺障害等級に認定を申請した2つの事例を紹介します。
1、被害者請求で申請したAさんのケース
Aさんはバイクを運転していたところ、交差点で自動車と衝突する事故を起こし腕を骨折するケガをしました。
治療により骨折自体は治ったものの首から背中にかけての痛みが残ったため、後遺障害の申請を行うと決めました。事前認定と被害者請求の2つの方法があることを知ったAさんは、どちらにするか悩みましたが、自分で納得できるやり方が良いと考え自身で手続きを進めることにしました。
2、異議申立てで認定を受けられたBさんのケース
Bさんは車を運転中に信号待ちをしていたところ、後ろから来た車に追突される事故に遭い治療後もむちうちによる痛みの症状が残りました。
1度目は任意保険会社を通じた事前認定で申請しましたが、後遺障害に当たらないとして非該当の結果になってしまいました。納得できなかったBさんは弁護士に相談し、アドバイスに従い病院のカルテなど資料をしっかり集め、被害者請求による異議申立てを行いました。
後遺障害が認定されると受け取れるお金
後遺障害が認定されると、慰謝料を含む賠償金を受け取れるようになります。
後遺障害の認定後に請求できる賠償金
後遺障害等級に認定されると後遺症によって生じる損害への賠償請求が可能になり、加害者からもらえる損害賠償額が大きく変わってきます。
「後遺障害慰謝料」……後遺症が残ったために生じる精神的苦痛に対する慰謝料。
「後遺障害逸失利益」……後遺症のために仕事が続けられなくなるなど将来的に得られる収入への影響に対する補償。
後遺障害が認定されれば、保険会社は賠償金を含めた金額での示談金を提示してくるようになります。

自賠責保険の先取り
被害者請求で後遺障害が認められると、損害賠償の自賠責保険分を先取りで受け取れるようになります。後遺障害が残るほどのケガは仕事や生活にも影響をおよぼし、経済的な負担は大きくなると考えられます。
しかし、通常、交通事故の損害賠償が支払われるのは、加害者との示談が成立してからです。一部とはいえ、先にお金を受け取れるのは、被害者にとっては大きなメリットと考えられます。
ただ、自賠責保険の先取り金額には上限が決められており、後遺障害で請求できるのは4,000万円までです。
| 傷害分 | 120万円 |
|---|---|
| 後遺障害分 | 75万~4,000万円 |
| 死亡分 | 3,000万円 |
被害者自身が加入している保険
後遺障害に認定されると、被害者自身が加入している保険からも保険金を受け取れるケースがあります。もし、自身の契約している保険に以下のようなプランがあれば保険金を請求できる可能性がありますので、保険会社へ確認してください。
・搭乗者傷害保険……運転手を含め、契約車に乗っている人がケガをした事故に支払われる保険。
・人身傷害補償保険……契約者とその家族が自動車事故で死傷した場合に損害を補償する保険。
後遺障害へ認定されるための条件を確認
交通事故による後遺障害は、認定条件に該当している必要があります。
1、交通事故が原因で生じた症状である
後遺障害の認定を受けるためには、症状と交通事故との因果関係が認められなければなりません。交通事故の前からあった症状は、当然ですが認められません。また、事故が起きてから病院で診察を受けるまでに期間が開いていたり、途中で通院をやめてしまったりするとのは、事故との関連性を疑われる原因になります。

2、症状の存在を医学的に証明できる
後遺障害で認定を受けられる症状は本人の訴えだけでは不十分で、きちんと医学的な証明がなければなりません。被害者がいくら痛みや違和感があると伝えても、医学的に問題がないと診断されると後遺障害に認定される可能性は低くなってしまいます。
身体の傷跡や欠損など外見やレントゲン画像等から一目で分かる症状であれば、疑われる可能性は低くなります。しかし、むちうちのような本人にしか分からない症状は、医学的証明が難しくなるのが注意点です。
そのため、むちうちの症状は医師や弁護士と相談の上、神経学的検査などの結果を添付して申請するのが良いでしょう。
3、症状が一貫して続いている
訴えている症状に一貫性や連続性がないと、後遺障害の認定を受けるのは難しくなってしまいます。後遺障害は事故後に治療を行ったものの、治りきらずに残存してしまった症状に対して認められるためです。
途中から訴える症状が変わったり、一度は治ったのにまた症状が出たと言って病院に来たりすると、一貫性がないと判断されてしまう可能性があります。
4、治療期間が短かすぎない
後遺障害は医師による適切な治療が行われた上で回復せずに残ってしまった症状に対し認定されるため、一定の治療期間がないと認めてもらうのは難しくなります。あまりに治療期間が短すぎると「もう少し治療すれば完治するのではないか」と思われて認定されない可能性があります。
一般的に後遺障害認定に必要な治療期間は6か月程度といわれていますが、明確な規定があるわけではなく1つの目安です。身体の一部が欠損したケースのように外見から判断できるような障害なら、6か月未満でも認定される事例はあります。長く治療したからといって必ず認定してもらえるものではありません。

後遺障害が認定されないときの対処法
交通事故で後遺障害等級の認定を受けられるのは全体の5%程度とされています。申請しても非該当になることは想定しておくことは大切でしょう。もし後遺障害が認定してもらえなかったときの対処法を紹介します。
参考:損害保険料率算出機構
異議申立てをする
保険会社を通じて自賠責調査事務所に異議申立てを行い、等級認定の再審査を求める方法です。異議申立てに費用はかからず、回数制限がなく何度でも利用可能です。
異議申立ての方法には事前認定と被害者請求の2通りがあります。最初の申請を事前認定で行っても、異議申立ての際には被害者請求へ切り替えることも可能です。ただ、前回と同じ申請内容では、一度非該当になった結果を覆すのは難しいと考えられます。新たな書類や資料を揃えてから、異議申し立てをしてください。
後遺障害診断書の再発行は5,000~1万円ほど費用がかかり、他の検査を受ける場合にも追加費用が必要になります。異議申立てそのものは無料ですが、ある程度の出費は覚悟しなければなりません。また、異議申立ての結果が出るまでには、数か月~半年程度の期間がかかることも頭に入れておきましょう。
異議申立てを成功させたいなら弁護士へ相談を
交通事故における後遺障害の異議申立て成功率は15%程度です。初回の申請よりは高い数字ではあるものの、狭き門には違いありません。
非該当には何らかの理由が存在しています。認定を受けるには単に異議申立てをするだけでなく、初回で不十分だった点についての改善が求められるのです。通常、後遺障害の結果通知書に非該当になった理由は書かれていますが、内容が一般的・表面的であり詳細はよくわからないのが現状です。
そのため、申請のどこが悪かったのかは自分で検討する必要があります。しかし、後遺障害は専門的な知識が求められるため、異議申立てでどのように対応すればいいのか分からず困る方が多いです。
そこで、異議申立てを考えるなら、交通事故の事件を得意とする弁護士への相談をおすすめします。弁護士は申請内容のどこが悪かったのか、どういった書類等を準備すれば良いのかといった適切なアドバイスをしてくれるため、異議申立ての成功率アップが期待できます。

まとめ
交通事故で負ったケガが後遺障害と認められば、慰謝料や逸失利益など損害賠償請求が可能になります。
後遺障害は事前認定と被害者認定のどちらかで申請しますが、審査は厳しく認定率は決して高くはありません。あらかじめしっかり準備してから、申請する必要があります。
後遺障害への申請に不安がある、認定率をアップさせたい、非該当だったため異議申立てをした、賠償金を増額させたいなどのお悩みを解決したいなら、経験豊富な弁護士に相談してください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ