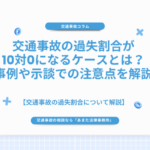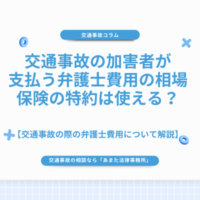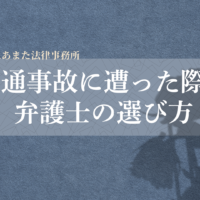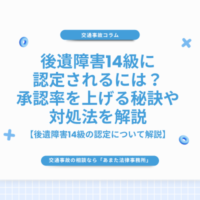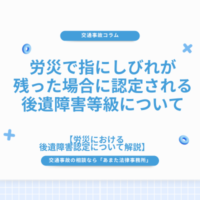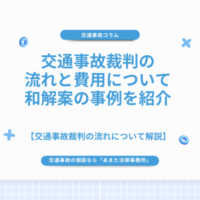交通事故では、当事者それぞれの責任を表した過失割合により請求できる損害賠償・慰謝料が決まります。10対0は被害者の過失が全くない事故ですが、どのような場合にこの割合が適用されるのでしょうか。

執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
交通事故の過失割合とは?
「過失割合」は交通事故において、どちらにどれだけの責任があるかを0~10までで表したものです。交通事故で、片方のみ責任がある事故は少なく、多くの場合は程度の差はあるものの、両者に何らかの責任があると判断されます。
過失割合は事故ごとに決められ、通常は10対0や9対1、8対2など、双方の数字を合計すると10になり、数字の大きい側を「加害者」、小さい側を「被害者」と呼びます。
過失割合の決定方法
交通事故の過失割合は「示談交渉」によって決められます。法律上の紛争を当事者同士の話し合いによって解決する方法を「示談」といい、示談を成立させるための交渉は「示談交渉」と呼ばれます。
交通事故では、示談交渉によって相手方に請求する損害賠償の内容や金額などが決定され、過失割合もここでの話し合いによって決められます。交通事故の示談交渉は、通常、本人ではなく、加入している任意自動車保険の担当者が代理で行い、過去に起こった類似の事故での裁判例をもとに、個別の事情を加味して修正を加えていくのが一般的です。
もし話し合いで揉めてしまい、示談交渉だけで決着がつかなかった場合は、裁判に訴えるのも可能で、裁判官によって決定される場合もあります。保険を通じた交渉や手続きを活用することで、当事者は負担を軽減し、よりスムーズに解決を図ることができます。
過失割合はいつ決まるか
過失割合は以下のような流れで決定されます。
相手方の保険会社からお互いの過失割合や損害賠償額などの条件が書かれた「示談案」が贈られてきます。
保険会社が提示してきた割合を確認し、問題がなければそのまま示談を行い、納得できない部分があれば根拠となる「修正要素」を提示して変更を求めます。
お互いに納得できる内容が決まれば、相手方の保険会社から示談条件を記した「示談書」が送付されてきます。
示談書に署名・捺印して返信すると、正式に示談が成立し、このタイミングで過失割合も確定します。「示談金」は「示談成立」から2週間ほどで支払われます。
過失割合の影響
過失割合は相手に請求できる損害賠償の金額に影響を与えます。交通事故では、お互いの過失に応じて賠償金を減額する「過失相殺」が行われるため、割合が大きくなるほど、受けとる示談金の額も減ってしまいます。
例えば、過失割合が8対2なら、10対0の場合と比べて8割分の賠償金しか請求できません。1割や2割くらいならたいしたことはないだろうと思う方もいるかもしれませんが、本来の賠償金が1000万円とすると、8対2なら請求できるのは800万円となり、200万円も減額されてしまいます。
交通事故で過失割合が10対0になる事例
交通事故において過失割合がもつ影響について解説してきましたが、ここからは10対0になるのはどのようなケースか、実際の事例をみていきましょう。
10対0は「もらい事故」といわれ、被害者は事故の原因に対しての責任が全くないケースです。100%相手が悪いと判断されるため、割合が10対0の場合、損害賠償が減額される心配はありません。
過失割合が10対0になる四輪車同士の交通事故
事例①:背後からの一方的な衝突事故
停車している車両Aに後方から車両Bが突っ込んできたケースです。「おかまをほられた」といわれる事故で、自動車同士で10対0になる典型的な事例といえます。
事例②:相手の信号無視
交差点などで、被害者である車両Aが青信号で入ってきたのに対して、加害者の車両Bが赤信号を無視したために起きた事故です。通常の信号だけでなく、進行方向を表す青矢印でも同様に10対0になります。
事例③:相手車両が中央線を越えたため起きた正面衝突
対向車線を走っていた車両がセンターラインを越えたことから、正面衝突を起こしたケースです。車同士の事故では、停車していた場合を除き、被害者にも何らかの責任が認められるケースがほとんどで、片方がゼロになる事例は限られています。

過失割合が10対0になる自動車対自転車の交通事故
事例①:自転車追い越し後の曲がろうとした際の事故
信号のない交差点で先行していた自転車を追い越した車が、その後、曲がるときにぶつかった事故で、自動車が10になります。ただ、自動車が先行だった場合には、自転車にも責任が認められるケースもあります。
過失割合が10対0になる自転車同士の事故
自転車同士の以下のような事故では割合が10対0になります。
・並走時の接触事故……自転車Aが先を走っていた自転車Bを追い抜こうとして並走状態になった際に相手に接触してしまった事故。(後続車Aが10割)
・信号無視……青信号で走行していた自転車Aに赤信号を無視してきた自転車Bがぶつかった事故。(信号無視した側が10)
・追い抜き後の接触事故……自転車Aが先行する自転車Bを追い越した後、Bの進路上に出た際に接触してしまった事故。(後続車Aが10割)
過失割合が10対0になる自動車対歩行者の交通事故
事例①:横断歩道の歩行者と信号無視の車の事故
信号のある交差点で青のときに横断歩道を渡っていたAさんに信号の車両Bがぶつかった事故で、車に一方的な過失があると判断されます。横断歩道は歩行者優先のルールがあり、歩行者側の信号が途中で黄色や赤になっていた場合でも、渡りはじめたときに青なら、歩行者の過失は0になります。
事例②:歩道上での歩行者と自動車の事故
道路脇の店舗や駐車場などに入ろうと路外に出て歩道に進入して車と歩いていた歩行者との事故です。法律上、歩道は歩行者のものであり、車は車道を通らなければならないとされているため、歩道上で事故を起こしたケースでは、車に全ての責任があると判断されます。
事例③:歩道がない道路で右側通行の歩行者と自動車の事故
歩道と車道が区別されていない道路で右側通行をしていた歩行者と車がぶつかった事故で、正面・後方のどちらからでも車が一方的に悪いと判断されます。

事例⑨:横断歩道の歩行者と右左折車の事故
青信号で横断歩道を渡っている歩行者と右折または左折の車がぶつかった事故です。このケースでも直進と同様、信号が青のときはもちろんですが、途中で黄色・赤になっていたとしても車のほうが一方的に悪くなります。
交通事故で過失割合が9対1になる事例
続いては、他の割合になるのはどのような事故なのかについても解説していきます。まずは、被害者であるにもかかわらず、一定の責任があると判断される9対1の事例からみていきましょう。どのような点に被害者の過失があると判断されるかにも注意してみてください。
過失割合が9対1になる四輪車同士の交通事故
事例①:交差点での優先車と劣後車の事故
信号機が設置されていない交差点で片方が優先道路になっている場合に、優先道路を走行してきた車両Aと優先でない道路から来た車両Bの出会い頭の事故です。
優先でない道路を走る劣後車には徐行義務がありますが、優先道路を走る優先車には見通しが効かない交差点であっても義務がなく、責任の大部分はB車にあるとみなされます。しかし、A車にも注意義務は存在するため、1割の過失が認められます。
事例②:道路外に出ようとする右折車との事故
直進していた車両Aに、道路脇の店舗や駐車場などに入るため、右折しようとした反対車線の車両Bが衝突した事故です。路外に出ようとする車には原則や合図などの義務があり、事故を起こした場合は責任が大きいと判断されます。
A車が走ってきたとき、すでにB車が右折していたケースではA車の割合が高くなり、反対に幹線道路での右折や徐行・合図をしていなかったケースはB車の割合が高くなります。
事例③:一時停止の規制がある交差点での事故
一方に一時停止のラインがある交差点で、規制がない道路から進入してきた車両Aと一時停止のある道路から来た車両Bがぶつかった事故です。減速していたA車に対し、B車が減速していなかった場合は、B車の責任が大きいとみなされ、9対1になります。
過失割合が9対1になる自動車対自転車の交通事故
事例①:黄色信号の自転車と赤信号の自動車の事故
信号機が設置されている交差点で、信号が黄色のときに進入してきた自転車と赤で信号無視してきた車との衝突事故です。赤で進入してきた車が悪いのはもちろんですが、自転車も黄色なら基本的には停止する必要があります。
事例②:一時停止規制がない自転車と規制がある自動車の事故
信号機が設けられていない交差点で、一時停止の規制がない道路から進入してきた自転車と規制がある道路から来た車の出会い頭事故です。このような事故では、自転車は一般的に車よりもスピードが遅いのが前提とされるため、過失割合も車9:自転車1に設定されています。
過失割合が9対1になる自動車対歩行者の交通事故
事例①:黄色信号で横断歩道を渡る歩行者と赤信号の自動車の事故
信号機が設置されている交差点において、黄色の段階で渡りはじめた歩行者と赤信号で進入してきた車との事故です。基本的には信号無視している車のほうが悪いのですが、歩行者も黄色なら横断すべきではないため、責任があるとみなされます。

事例②:信号がない交差点での事故
信号機が設けられていない交差点付近で起きた歩行者と車の事故は、直進・右左折など車の進路に関係なく、多くのケースでは車9:歩行者1の過失割合になります。
交通事故で過失割合が8対2になる事例
続いては、さらに被害者の責任が大きくなる8対2の事例です。
過失割合が8対2になる四輪車同士の交通事故
事例①:交差点での直進車と右折車の事故
信号機が設置されていない交差点において、直進で入ってきた車両Aと対向車線から右折してきた車両Bとぶつかった事故です。8対2の典型的なケースで、基本的にルールとしては直進優先のため、B車の責任が重いとみなされます。
事例②:お互い青信号で交差点に進入した自動車同士の事故
信号の設置されている交差点で、お互い青信号で進入してきた対向車同士で、一方が直進しもう一方が右折した場合などに起こった衝突事故で、右折車の責任が大きいとみなされます。

事例③:信号のない交差点での事故
信号の設置されていない交差点で、左方から進入してきた車両Aと右方から来た車両Bが起こした事故です。信号のない交差点では左方車が優先となるため、Aが減速してBが減速しなかったケースではBの過失が8割となります。右方車が一時停止を怠った場合も同様の割合になります。
過失割合が8対2になる自動車対自転車の交通事故
事例①:自転車と自動車の衝突事故
以下のような自転車と車の事故では割合は8対2です。
・道幅が同じくらいの交差点で起きた自転車と車の衝突事故。
・右側通行をしている自転車と直進してきた対向車との事故。
自転車に乗っていたのが子どもや高齢者だった場合は自転車に有利に修正され、逆に夜間や自転車がふらふら走行の場合は車に有利になります。
過失割合が8対2になる自動車対歩行者の交通事故
事例①:道路を横断している歩行者と自動車の事故
交差点から10メートル以上離れた場所で横断歩道以外のところを渡っている歩行者と直進してきた車が起こした事故です。交差点の少ない地方の道路などで起きやすい事故で、基本的には車の責任が重く、車8:歩行者2となります。
事例②:歩行者とバックしている自動車の事故
後ろの見通しが十分でない状況で、徐行かそれに近い速度でバックしていた車が、すぐ後ろを横断していた歩行者とぶつかった事故です。
事例③:横断歩道での自転車と歩行者の事故
信号の設置されている交差点の横断歩道で、青で横断をはじめたものの、途中に信号が黄色から赤へと変化したにもかかわらず横断を続けていた歩行者と青信号で直進してきた自転車の事故です。

過失割合に納得できない!割合を有利に変更できる?
実際の事故の事例で見てきたように、類似の事故も状況が少し違うと過失割合が変わる場合があり、賠償金にも影響を与えます。そのため、示談交渉では納得できない過失割合には容易に応じないようにする必要があります。
過失割合に納得いかないとき有利に変更できる?
もし相手方の保険会社が提示してきた過失割合に納得がいかない場合、示談が成立する前であれば、交渉によって修正できる可能性があります。
最初に提示される過失割合は相手方の保険会社が一方的に認定したもので、弁護士などからみると誤った割合であるケースも存在します。しかし、一般の方が過去の判例や法律をもとに保険会社と交渉するのも難しいといえます。
過失割合を9対0などにする場合も
交渉を行っても相手方がなかなか割合の変更に応じてくれず、話し合いがこじれるケースでは、過失割合を9対0や8対0などにすることも検討しましょう。こうした片側が0で合計しても10にならない割合は、通常の計算からは出てこない数字です。
これは片側賠償(片賠)と呼ばれ、被害者は過失がないことを主張しながら一定の割合については妥協し、加害者は自分の損害賠償請求権を放棄し、お互いの譲歩により成立します。
被害者は請求できる賠償金が本来より低くなりますが、加害者が請求権を放棄しているため、過失相殺による減額の心配がありません。結果、9対1や8対2の場合より、受け取る示談金の額は大きくなります。

過失割合に納得できないなら早めに弁護士に相談を
示談交渉で提示された交通事故の過失割合に納得できないときは、早めに弁護士に相談するようにしましょう。早くから相談するほうが過失割合を修正できる可能性が高くなります。
割合を有利に修正できた事例
弁護士に依頼して割合を有利に修正できた事例を紹介しますので、依頼を検討される際の参考にしてみてください。
事例①:過失割合を8対2から9対1に変更
車を運転していたAさんは信号が設置されていない交差点に進入したところ、左方から来た車両と衝突事故を起こしました。示談交渉で保険会社が提示してきた過失割合は8対2。しかし、Aさんは「むちうち」の後遺症が残り、この割合には納得できませんでした。
Aさんは過失割合の変更について弁護士に相談。弁護士が警察から捜査資料を取り寄せて精査したところ、加害者の運転には、保険会社が気づいていない過失があった可能性があると判明しました。これをもとに交渉を進めた結果、過失割合を9対1に変更して示談が成立しました。
事例②:過失割合を9対1から10対0に変更
車を運転中のBさんは、信号が設置されていない交差点に進入したところ、別の道路から来た車両とぶつかる事故を起こしました。Bさんの走っていた方が優先道路だったため、過失割合は9対1になりましたが、自分に過失はなかったと思っていたBさんは納得がいかず、弁護士に相談しました。
事故当時の状況を精査したところ、相手の車両に速度超過の可能性があったことがわかりました。また、事故の目撃者も見つかり、聞き取りを行った内容をもとに保険会社と交渉したところ、過失0での示談が成立しました。
また、弁護士に依頼すると、他にもメリットがあります。
1つ目は、弁護士基準で損害賠償が請求できるようになることです。交通事故の賠償金計算にはいくつかの算定方法が存在します。弁護士基準はその中で極めて高額になる算定基準で、保険会社の提示する金額に比べて2倍~3倍になる場合もあります。
交通事故で損害賠償はケガの治療など、事故によって受けた損害の補填に使用する大切なお金ですので、請求の際は、出来る限り弁護士に依頼して弁護士基準が適用されるようにしましょう。
2つ目は、後遺障害が残った場合にも適切な対応をしてもらえることです。交通事故で後遺症が残った場合は、慰謝料などを増額できますが、そのためには、決められた手続きにより、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
弁護士なら、認定手続きはもちろん、後遺障害によって将来受ける損害の補填である逸失利益の請求など、適切な損害賠償項目を漏れなく請求してもらえるようになります。

過失割合の事例や変更方法まとめ
交通事故の過失割合は、双方がどれだけ事故に対する責任をもつかで決められ、過失の大きさによって請求できる損害賠償に影響を与えます。10対0なら被害者には一切過失がないとみなされるため、賠償金は本来の金額を全て請求可能になりますが、他の過失割合の場合は、過失相殺によって示談金が減額されてしまいます。
過失割合に納得できない場合、弁護士が交渉にあたれば有利に修正できる可能性があります。相手方の保険会社が提示する過失割合に不満やおかしいと思う部分があれば、弁護士への相談を検討してみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ