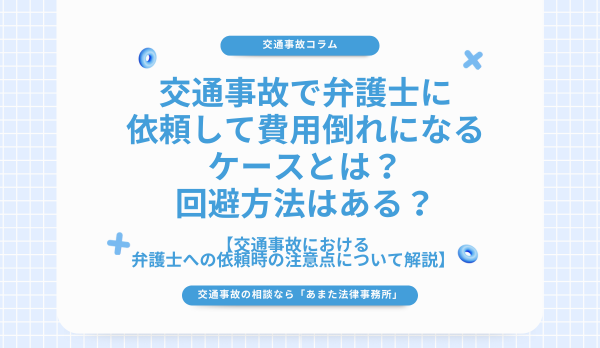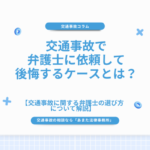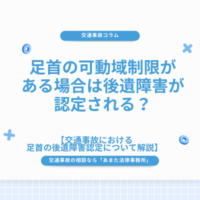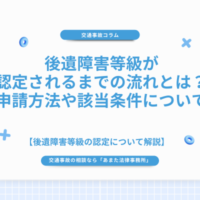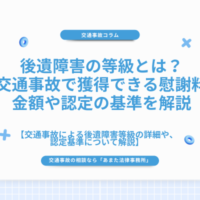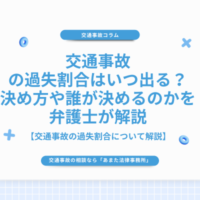交通事故で弁護士に依頼すると、費用倒れが起きるのではないかという懸念があります。
慰謝料の増額や示談交渉を代行してもらえるなど、弁護士のサポートを受けると多くのメリットが生じます。しかし、弁護士費用が受け取る賠償金を越えて費用倒れになるケースが、まったくないとは言えません。

執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
弁護士に依頼することで起きる費用倒れとは
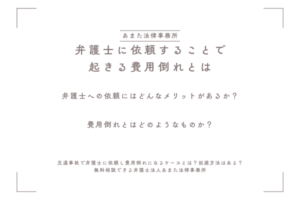
費用倒れは、せっかく費用をかけて弁護士に依頼したにもかかわらず、見合った価値を得られなかったり、逆に被害者にとってマイナスになってしまったりするケースです。
交通事故の処理を弁護士に依頼するメリットはいくつもあるのですが、費用倒れには注意しなければなりません。
弁護士への依頼にはどんなメリットがあるか?
交通事故の被害者は加害者に慰謝料を請求するといった事後処理があります。手続きを弁護士に依頼するともらえる慰謝料などの賠償金が増額されたり、被害者に代わって示談交渉してもらえるなどのメリットが生じます。
慰謝料が増額される
交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算定基準があります。
中でも弁護士基準は最も高額の慰謝料を受け取れます。
弁護士基準は裁判基準とも言われ、弁護士に依頼したり、訴訟を起こしたときに適用され、自賠責や任意保険基準よりも相場が高額になっています。弁護士に示談交渉を頼めば弁護士基準で計算されるため、慰謝料の増額が見込めるのです。
示談交渉を代わりに行ってもらえる
弁護士が相手方との示談交渉を行ってくれますので、被害者自身の負担を減らせます。
交通事故の示談交渉は保険会社がやってくれるものというイメージがありますが、被害者に全く責任がない事故では適用されません。被害者の保険会社に保険金支払いの必要がない「もらい事故」では非弁行為に当たるため、保険会社は示談交渉ができないという決まりがあるためです。
被害者自身が示談交渉に臨むことはできます。しかし、交通事故や法律の知識に乏しく、さらに事故によりケガなど肉体的・精神的にダメージを受けている被害者が相手方の保険会社との交渉は不安ですし多大なストレスになるでしょう。
保険会社の言いなりで合意してしまい、納得した慰謝料を受け取れない事態に陥るという結果を招くことにもつながります。

交通死亡事故での対応
被害者自身が死亡してしまった死亡事故では、慰謝料請求などの手続きを遺族が行わなければなりません。
遺族は身近な人を亡くして精神的なショックを受けています。また死亡事故では被害を受けた本人が証言できないため、目撃者がいないと遺族側が不利になるケースもあります。
弁護士に相談すると各種手続きを代行してくれるため、遺族側の負担が減ります。さらに遺族が納得できる結果になるように示談交渉を進めてくれます。
費用倒れとはどのようなものか?
費用倒れは獲得できた慰謝料をよりも、弁護士費用のほうが大きくなってしまう状態です。コストに見合った結果が出なかったともいえるでしょう。
相手方の保険会社から提示された金額は10万円。
いくらなんでも安すぎると思い、弁護士に依頼。
結果、倍となる20万円の保険金の受取に成功。
しかし、弁護士費用は15万円だといわれた。
せっかく増額され手も手元に残ったのは5万円で、もらえたお金は最初の半分。
最終的には、弁護士が介入したことで損をしてしまった。
上記は弁護士費用がかかったおかげで、当初よりも手元に残る金額が少なくなったケースですが、弁護費用が賠償額を越えてしまい、被害者が赤字になってしまう状況もあり得ます。

弁護士への依頼で費用倒れが起こる理由
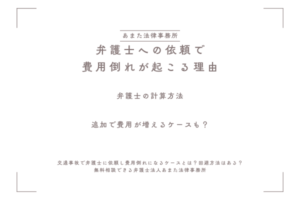
費用倒れが起きる一番の原因は、弁護士費用が高額になるためです。
弁護士費用はどのような結果になったとしても弁護士を利用すると決められた料金が発生するため、高額になりやすいシステムです。
弁護士の計算方法
弁護士費用の計算方法は、大きく分けると「着手金・成功報酬方式」と「時間報酬方式(タイムチャージ方式)」という2種類があります。
時間報酬方式は1時間あたりの料金が決まっており、案件の処理にかかった時間に対して請求されます。主に契約書の作成や法律相談などに用いられています。
着手金・成功報酬方式は、弁護士に依頼する時点で着手金を支払い、案件が解決したら成功報酬を払う形式です。
交通事故での一般的な弁護士費用の相場を表にまとめました。
| 相談料 | 弁護士に法律相談を行う費用。 正式に依頼する前に行うもので、相談だけで正式な依頼にはならないこともある。 初回無料などのサービスをしている事務所もある。 | 30分あたり5000円~10000円程度。 |
|---|---|---|
| 着手金 | 弁護士に依頼する際に支払う費用。 事務所により、着手金0円で成功報酬のみのところもある。 | 10万円~ |
| 成功報酬 | 依頼が成功した際に支払う費用。 事務所により、成功報酬をもらわず着手金のみのところもある。 | 獲得した示談金の10~30%(+数万円) |
| その他 | 弁護士の出張時などに発生する日当や交通費、郵便物の切手代など | 実費 |
法律相談は時間報酬方式ですが、実際に弁護士に依頼すると着手金・成功報酬方式が適用されます。
着手金・成功報酬方式は弁護士への固定料金であり、費用倒れを起こしやすいお金です。
着手金は示談の結果に関係なく、必ず支払わなければなりません。
成功報酬は獲得した示談金(経済的利益)に応じて額が決まるシステムです。そのため、もらえるお金が増額されるほど、弁護士に払う費用は増えることになります。
追加で費用が増えるケースも?
追加で着手金や成功報酬が必要となり、さらなる弁護士費用が発生するケースがあります。
以下のような法的手続き等は、追加で弁護士費用が発生しやすくなります。
- 後遺障害等級の認定を行う。
- 後遺障害等級の認定で異議申し立てを行う。
- 示談が上手くいかず裁判を起こす。
- 調停(裁判によらない話し合いによる紛争解決手段)を行ったり、ADR(代替的紛争解決手段)機関を利用する。
- 事故の内容が複雑で通常の案件よりも手間がかかる。
追加の成功報酬は弁護士事務所ごとに異なりますが、最初の着手金+10万から40万円くらいが目安です。
着手金0円の事務所でも追加費用が必要になったり、成功報酬が割り増しされる可能性があるのは注意点でしょう。
弁護士に依頼しても費用倒れにならない金額の目安
弁護士の費用倒れを起こさないための目安として、いくつかの料金体系を例に賠償金のボーダーラインをみていきましょう。
交通事故の慰謝料額が最低20万円程度とれるものとして計算しています。
| 料金体系 | ボーダーライン金額 | |
|---|---|---|
| 料金体系① | 着手金0円 + 成功報酬 取得した賠償金の11%+22万円 | 約25万円 |
| 料金体系② | 着手金10万円 + 成功報酬 取得した賠償金の16% | 約14万円 |
| 料金体系③ | 着手金0円 +成功報酬 取得した賠償金の11%+16万5000円 | 約19万円 |
料金体系は弁護士事務所により大きな違いはありますが、弁護士に依頼すると最低でも10万から20万円程度の費用はかかると考えておきましょう。
ただ、実際には着手金や成功報酬のほかに日当や諸費用が加算されますので、さらに数万円ほどは余分に用意しておく必要があります。なので、ボーダーラインの目安は30万円程度になると考えられます。
交通事故の中でも費用倒れになりやすいケース
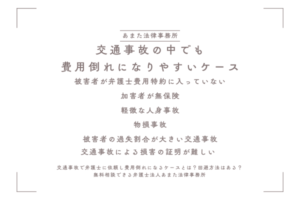
弁護士を利用すると、費用倒れを起こしやすい交通事故の例を紹介します。
被害者が弁護士費用特約に入っていない
弁護士費用特約は交通事故の被害者になった際、弁護士への依頼費用を保険会社が負担してくれるサービスです。
自動車保険など任意の自動車保険に付帯しており、一般的には相談料10万円・依頼費用300万円を上限に補償してもらえます。だいたい5~7割の保険に付いているといわれています。
弁護士特約が付いていれば、弁護士費用が0円になることもあります。弁護士特約を活用することで被害者は費用を気にせず弁護士に依頼でき、費用倒れのリスクもほぼゼロになります。

家族でも適用される弁護士特約もあります。自身の保険だけでなく、家族が加入している保険に付帯していないか確認してください。ちなみに、弁護士特約を使用しても保険の等級には影響を及ぼしません。
加害者が無保険
交通事故の加害者が任意保険に加入していないと、もらえる賠償金額は少なくなります。獲得できる金額が低くなれば、費用倒れになるリスクは大きくなります。
任意保険に未加入の場合は、保険金は自賠責保険のみから支払われます。自賠責保険では事故の内容によって受け取れる賠償金の上限が決まっていますが、任意保険基準や弁護士基準に比べると低くなってしまいます。
| 慰謝料の種類 | 損害賠償の上限金額 |
|---|---|
| 傷害慰謝料 | 120万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害の等級に応じて75万円~4000万円 |
| 死亡慰謝料 | 3000万円 |
本来、上限を超えた分の金額は任意保険からの受け取りが可能なのですが、無保険だと自賠責保険のみでの補償となってしまいます。
加害者は賠償金の支払いの義務がなくなるわけではなく、自賠責保険だけで払えない分は裁判所に強制執行を申し立てることにより、加害者自身に請求できます。しかし、相手に金銭的な余力がなければ、支払いが滞りまともに受け取れなくならう可能性はあるでしょう。
軽微な人身事故
怪我の程度が軽微で治療の期間が短い人身事故では、そもそもの損害賠償がボーダーラインに近い低額になる傾向があります。そのため弁護士に依頼すると費用倒れとなる可能性が高くなります。
むちうちなどの軽症で1か月通院(実通院日数12日)したときの傷害慰謝料を、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準で計算したときを見てみましょう。
| 算定基準 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 10万3200円 |
| 任意保険基準 | 12万6000円 |
| 弁護士基準 | 19万円 |
自賠責基準では10万3200円、弁護士基準では19万円です。弁護士を利用しても上乗せできるのは9万円程度であり、弁護士費用が10万円を超えると費用倒れになってしまいます。
重篤な障害が残るケースや死亡事故など慰謝料が高額になる事故では、弁護士を利用しても費用倒れが起きるケースはほとんど見られません。しかし弁護士基準にしてもその他の基準と慰謝料額があまり変わらないケースでは、費用倒れに注意が必要です。
物損事故
物損事故は費用倒れが起こりやすい事故の1つです。
人身事故は慰謝料や休業補償、逸失利益など様々な損害賠償が請求でき、金額は相手方との交渉次第で大きく増額できる可能性があります。
しかし、物損事故では弁護士の交渉による増額の余地があまりありません。車の修理代や事故で破損した物の価値などから、実際にどれくらいの損害が生じたかにより、客観的に損害賠償額を計算します。

被害者の過失割合が大きい交通事故
被害者の過失割合が大きな事故では、費用倒れの可能性があります。
慰謝料の増額幅が少なかったり、被害者側からも相手に補償をしなければならないケースがあるためです。
過失割合は、交通事故の原因となった責任がどちらにどれだけあるかという割合を数値化したものです。「8:2」「7:3」などで表されます。
原則、過失割合は過去の事故事例や裁判判決などをもとに、双方の保険会社による話し合いで決定されます。追突事故など明らかに被害者に非のないようなもらい事故を除き、被害者側にもいくらかの割合で責任が生じる場合が多いです。
自身の過失割合が高いときは、弁護士に相談して慰謝料がどれくらい減額されるか聞いてから依頼するかを決めるのが良いでしょう。また過失割合は変わらないことが多いのですが、交渉により割合が変わる可能性はないかも確認してください。
交通事故による損害の証明が難しい
損害賠償を請求するための証拠が不足していると賠償金の増額が難しくなり、費用倒れになる恐れがあります。
例えば、病院の診断書がないと本当に事故によるケガなのか立証ができません。事故の直後、警察に届けなかったため交通事故証明書がなければ、事故そのものがなかった扱いにされることがあり得ます。
示談で事故による損害を証明する客観的な証拠が提示できないと、経験豊富な弁護士といえども交渉を有利に進めるのは難しくなります。結果、慰謝料の大きな増額がかなわず、弁護士費用だけがかかり費用倒れになってしまうワケです。
弁護士の費用倒れを防ぐ方法
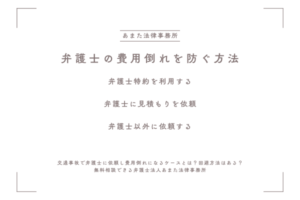
弁護士の費用倒れを回避する方法を実践すれば、後悔しない結果を得られやすくなります。
弁護士特約を利用する
加入している保険に弁護士特約があれば、費用倒れはほぼ回避できます。
弁護士特約は300万円を限度とし、保険会社に弁護士費用を補償してもらえます。
弁護士費用が300万円を超えるのは、だいたい賠償金が約2000万円の事故です。費用を特約ですべてまかなえるケースがほとんどでしょう。たとえ上限の300万円を超え残りを自腹で払ったとしても、費用倒れになる可能性は低いといえます。
例えば、高次脳機能障害など後遺障害等級1級に認定されるような大事故や死亡事故では、弁護士基準による慰謝料は2800万円程度とされています。弁護士費用が330万円(着手金0円、成功報酬11%+22万円で計算)としても、特約から300万円が支払われれば残額30万円を自腹で出しても手元には十分な額の慰謝料が残ります。
弁護士に見積もりを依頼
料金体系は弁護士事務所によって様々です。事前に見積もりをもらい、慰謝料はどれくらいになりそうか、費用はいくらくらいかかるか、費用倒れのリスクはないかなど、きちんと説明を聞いておくことが大切です。
また、弁護士にはそれぞれ得意分野があり、交通事故の事件に精通した弁護士が交渉に当たることで、損害賠償の大きな増額が期待できます。同じ事故でも交通事故の事件に強い弁護士を選ぶとより多くの賠償金が受け取れ、費用倒れになるリスクを減らせます。
最近では初回相談無料の事務所は増えています。相談したら契約しなければならないという決まりはありませんし、無料であれば気軽に利用できるでしょう。いくつかの事務所で見積もりをして、条件を比較するようにしてください。

弁護士以外に依頼する
司法書士、行政書士など弁護士以外の法律の専門家に依頼するのも1つの方法です。一般的に司法書士や行政書士は費用が安いメリットがあります。
しかし、司法書士や行政書士といった資格では、弁護士と同じ法律業務を扱うことはできません。
司法書士は民事に関する示談交渉を代理できますが、請求額が140万円以下のものに限られています。行政書士ができるのは、保険会社への書類提出や後遺障害の申請や認定のサポートなど限られた法律業務のみです。
最初は司法書士や行政書士に依頼しても、途中で弁護士に切り替えるケースもあります。
交通事故における弁護士費用についてまとめ
交通事故の被害者が弁護士を利用しても、費用倒れになるケースはあまりありません。
弁護士に依頼すると示談交渉を代行してくれ、賠償金を増額できるといった大きなメリットがあります。しかし賠償金が低い事故などでは、費用倒れになってしまう可能性はあります。
せっかく高額な賠償金を受けとれると思ったのに、弁護士費用で損をしてしまう事態は避けたいものです。
交通事故に強い弁護士を選ぶ、きちんと見積もりをとる、弁護士特約を利用するといった対策を実施しつつ、弁護士の力を借りるようにしてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ