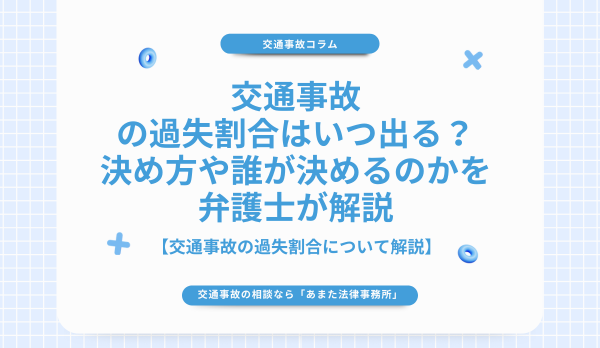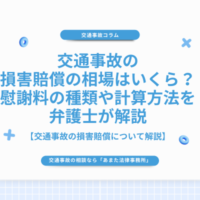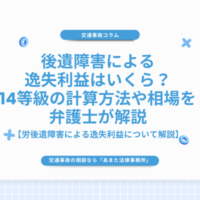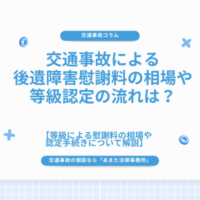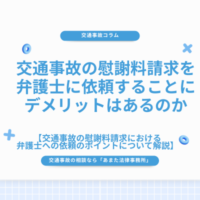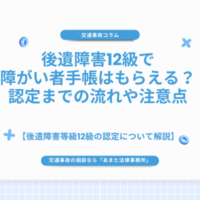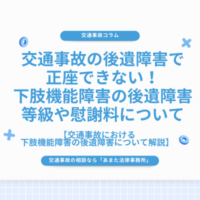交通事故の過失割合はいつ出るのかは示談や裁判などの決め方により異なりますし、事故の状況などでも変わってきます。

執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
交通事故の過失割合とは何か
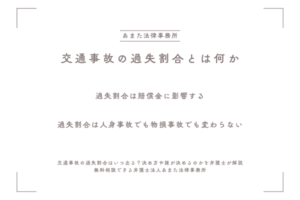
過失割合とは交通事故の損害において、当事者それぞれの責任がどれくらいあるのかを表した割合です。損害賠償額の比率をわかりやすくするために、お互いの落ち度を80:20や70:30などの数値で表します。
交通事故の態様はそれぞれ千差万別であり、個々の事情を考慮に入れて過失割合を決定しなければなりません。
例えば、青信号の交差点で直進車と右折車が衝突した事故では、優先されるのは直進車なので右折車に大きな非があると言えます。しかし、直進車が優先されるといっても、直進車の不注意がなければ右折車との衝突は避けられたはずでありどちらにも多かれ少なかれ責任があると判断されます。
このように交通事故ではどちらか一方が全ての責任を負うケースは追突くらいであり、実際のところ滅多にありません。被害者にも不注意があったにもかかわらず加害者が全ての責任を負うのは不公平ですから具体的に過失割合を決めることで、被害者と加害者の責任の割合を明確にできます。
過失割合は賠償金に影響する
過失割合は被害者が受け取る損害賠償の金額に影響します。双方の不注意で交通事故が発生したのであれば、加害者のみが全ての賠償責任を負担するのは妥当ではありません。損害賠償の公平性という観点により被害者の過失割合に応じて加害者が負担する損害賠償額を減額するべきと考えられています。
被害者の損害額が1,000万円で過失割合が70:30のパターンであれば、被害者が受け取れる賠償金は70%の700万円ということになります。

過失割合は人身事故でも物損事故でも変わらない
交通事故は主に「人身事故」と「物損事故」に分類されます。人身事故は他人の生命・身体に損害を与えた事故が該当し、物損事故は生命・身体への被害はないものの自動車や建物といった他人の物を壊してしまった事故のことを指します。
過失割合は人身事故でも物損事故でも同様の扱いを受けます。人身事故と物損事故で過失割合が異なることはありません。
ただし、物損事故として処理されると被害者は他の点で不利益を被ることになる点には注意が必要です。なぜかと言うと物損事故では加害者に対して慰謝料や治療費などを請求できませんし、加害者には刑事罰が適用されず免許の違反点数も加算されないためです。
過失割合の決定はいつ出る?決まる時期とは
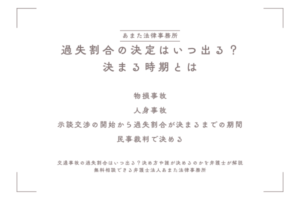
最終的な過失割合は示談成立後や判決確定後に決まります。一般的に示談であれば半年〜1年程度、裁判になると1年〜2年程度かかると言われています。
過失割合を決めるためには、被害者に発生した損害額が確定していなければなりません。物損事故と人身事故では損害額が確定するまでにかかる期間が異なります。それぞれのケースで損害額が確定するまでの流れを解説します。
物損事故
事故によって車両が壊れたときは、加害者に対し修理費や買い替え費用などを請求できます。損害額を確定させるためには、修理を依頼した工場に修理費用の見積もりを出してもらう必要があります。
修理費用が時価(現在の市場価格)よりも安ければ、加害者に対して修理費用を請求することになります。修理費用が時価よりも高いのであれば、買い替え費用を請求することになります。車両の時価は「オートガイド社発行のレッドブック(正式名称:オートガイド自動車価格月報)」を参考にしてください。

人身事故
人身事故で怪我を負ったらまずは病院で治療しなければならず、損害額が確定するのは治療が終了したタイミングになります。ケガの症状や程度は事故の規模や人によって異なりますが、軽傷であれば2週間〜1ヶ月程度での完治が見込めますが重傷であれば1ヶ月以上の治療を強いられるケースも見られます。
ただ、全ての怪我が無事に完治するとは限らず、怪我が完治せずに後遺障害として残る場合があります。後遺障害が残ったときは後遺障害等級に申請し認められることで、加害者に対し後遺障害慰謝料などを請求できるようになります。
示談交渉の開始から過失割合が決まるまでの期間
被害者の損害が確定に至れば示談交渉に移ります。最終的な過失割合が決まるのはお互いが納得し合意となった時点です。軽症の人身事故や物損事故であれば、ほとんどが示談交渉を開始してから2〜3ヶ月で示談が成立しています。
一方、双方が主張を譲らずに話し合いがもつれると、示談成立までに半年〜1年ほどかかることがあります。被害者が重症を負い損害額が高額になると過失割合によって示談金の額が大きく異なるため、交渉が難航することが予想されます。被害者は受け取るお金は減額させたくないですし、加害者は支払うお金を少しでも減らしたい考えるため、両者が納得せずに折り合いがつきにくいのです。
民事裁判で決める
お互いが主張を譲らずに示談交渉がまとまらず決裂すると、最終手段として民事裁判で決着をつけることになります。民事裁判は裁判を起こす者(原告)が、請求の趣旨などを記載した「訴状」を裁判所に提出し開始します。
訴状の提出から約1ヶ月後に第1回口頭弁論が開かれます。その後1〜2ヶ月に1回ほどのペースで裁判が進行し、事故の証拠を提出しながら争点整理を行うことになります。当事者の主張が明らかになると裁判所から和解勧告をされることがあり、両者が和解案に合意すればこの時点で事件は終結します。
和解が成立しなかったときは証人や当事者による尋問が行われ裁判官から判決が言い渡されます。もし判決に不服がああるなら、控訴すれば上級裁判所に新たな判決を求められます。
過失割合は当事者が決める
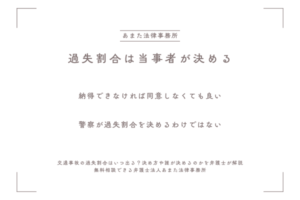
過失割合を決めるのは事故の当事者です。この当事者には事故を起こした本人だけでなく、保険会社や弁護士などの代理人も含まれます。基本的に被害者と加害者側の任意保険会社と交渉することで過失割合は決まります。相手方保険会社は過去の裁判例を参考に過失割合を算出し、「示談案」という形で被害者側に提示します。

納得できなければ同意しなくても良い
保険会社が提示する過失割合に納得いかないと感じたときは、相手方の提案を断ることは可能です。
保険会社が算出した過失割合は必ずしも正しいわけではないので気を付けてください。被害者に保険金を支払いする立場である保険会社は自社の支出を低くしたいため、あえて被害者が不利になる過失割合を示すケースは少なくありません。相手方の提案を一度受け入れてしまうと後から変更できなくなる可能性があるため、安易に了承しないようにしましょう。
警察が過失割合を決めるわけではない
過失割合を決めるのは警察ではないことは注意点です。事故の報告を受けた警察官は現場に駆けつけ当事者や目撃者から事故状況の調査を行います。警察官が調査結果をまとめ作成した「実況見分調書」は過失割合を算定する際の重要な資料になります。
過失割合には修正要素がある
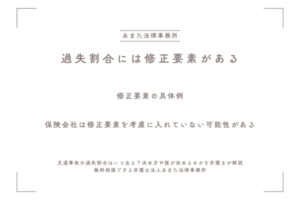
任意保険会社や弁護士は過去の裁判例を参考にしつつ、今回の事故状況と照らし合わせて過失割合を算出します。
ただ個々の事故状況を考慮して基本となる過失割合が修正されることがあります。当事者の過失割合が加算・減算される要因を過失割合の「修正要素」と呼びます
たとえば事故の態様は多種多様であるため、過去の判決が全ての事例に当てはまるわけではありません。加害者に著しいスピード違反が見受けられたような事故では、ベースとなる過失割合に加害者側の過失が加算されます。
修正要素の具体例
過失割合の修正要素にはどのような例があるのか、具体的にいくつか紹介します。
事故態様ごとに通常想定されている程度を超える不注意を著しい過失といいます。脇見運転などの著しい前方不注意、酒気帯び運転、時速15キロ以上30キロ未満の速度違反、著しく不適切なハンドル・ブレーキ操作などが該当します。
著しい過失よりも過失の程度が大きく故意と同視し得る不注意を重過失といいます。酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、時速30キロ以上の速度違反などが当てはまります。
大型車が事故を起こすと過失割合が加算される場合があります。これは、普通車よりも大型車は走行時の危険が大きく、高い運転技術が課せられるという理由からです。
運転者が進路変更するときは交差点の30m手前もしくは進路変更の3秒前に「指示器による合図(ウインカーの点滅)」をしなければなりません。ウインカーを点滅させないことで事故が発生すると、その車両に過失割合が加算されます。
通常、交差点では直進車が優先されます。ただし、直進車が交差点内で停止してしまい他の車両の通行妨害になる状況であれば、直進車は交差点に進入してはいけません(道路交通法50条1項)。例えば渋滞時などに交差点に進入し、交差点内で停止して事故が起きると直進車に過失割合が加算されます。
保険会社は修正要素を考慮に入れていない可能性がある
示談交渉では相手方の任意保険会社が過失割合を算出し、被害者側に提示するのが一般的です。保険会社は過去の裁判例を参考にして過失割合を計算しますが、中には修正要素が考慮されていないケースが多く見受けられます。
修正要素を適用するかしないかの判断は高度な専門知識が要求されますので、法律の専門家でない保険会社では全ての修正要素を正しく適用するのは難しいでしょう。また、保険会社は自社の支出を抑えたいと考えるため、意図的に修正要素を適用せず被害者に不利な過失割合を提示することがあります。
交通事故の過失割合に納得できないときの対処法
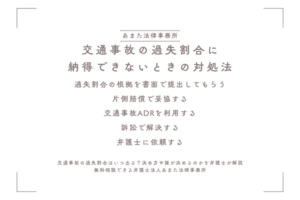
過失割合によって損害賠償の金額が大きく変わるため、当事者が言い争い交渉が難航する事例は少なくありません。過失割合に納得できずにもめたときの対処法を紹介します。
過失割合の根拠を書面で提出してもらう
任意保険会社が提示した過失割合に納得できないなら、どのような根拠で過失割合を算定したか書面で説明してもらいましょう。事故の状況が正しく反映されているか、修正要素が考慮されず過失割合が算定されていないかなどを書類で確認してください
片側賠償で妥協する
過失割合は「80:20」や「70:30」のように割合の合計が100%になるのが原則です。しかし、「90:0」や「80:0」など例外的な割合で示談を成立させることもできます。
一般的には被害者側にも過失があれば損害の一部を賠償する義務があります。例えば、過失割合が80:20で加害者の損害が100万円の事故ですと、被害者は加害者に対して20万円支払わなければなりません。しかし片側賠償が適用されると、被害者の過失割合が0になるため、加害者に対する損害賠償義務がなくなります。

片側賠償のメリット
片側賠償を利用する主なメリットは、相手方の合意を得やすくなることです。
本来は過失割合が100:0の事故を片側賠償で90:0に譲歩すると相手方が支払う賠償金額が10%減るため、加害者の同意を得られやすくなります。被害者自身の過失割合は0%のままなので相手方に賠償金を支払う必要はなくなり問題はないように感じます。
片側賠償のデメリット
片側賠償は根気よく交渉を続ければ100%の金額を受け取れたのに、90%や80%の金額の賠償金しか受け取れなくなります。あくまでも加害者の合意を得やすくするための妥協案に過ぎないと思ったほうがよいでしょう。
示談交渉の手続きから解放されるなど精神的な負担は軽くなります。しかし、本来ならば受け取れるはずの金額が減ってしまうのは損をすることになりますし、片側賠償には大きなデメリットがあるといえます。
交通事故ADRを利用する
ADRは「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」などの機関が当事者を仲介し紛争の解決を目指す方法です。「Alternative Dispute Resolution」の頭文字をとった略語であり裁判外で紛争を解決する手続きを意味しています。
ADR機関に登録されている弁護士を通じてあっ旋・調停・仲裁などの手続きが利用できます。
あっ旋とは「あっ旋人」と呼ばれる第三者が当事者の話し合いに参加し、当事者間による主体的な紛争解決を促す手法です。あっ旋人として選ばれるのは弁護士などの専門的知見を有する専門家になります。そのため法的な観点から客観的な意見を聞くことができます。
調停は調停委員が合議を開催し当事者に紛争解決を働きかける手法です。あっ旋と違い単に協議を促すだけでなく、当事者に調停案を示し受諾を勧告できます。またあっ旋人は原則として1人ですが調停は3名の委員によって運営されます。

仲裁は仲裁人が「仲裁判断」を下し紛争を解決する手法です。仲裁を使うにはあらかじめ当事者たちが仲裁判断に従う旨を約束する「仲裁合意」が必要です。仲裁判断には判決と同様の効力が生じるため、仲裁判断の是非を裁判所に判断してもらうことはできません。
もし相手方が仲裁判断の内容を履行しなければ強制執行により財産の差し押さえるができます。
交通事故ADRのメリット
訴訟手続きと比べるとADRは簡易・迅速に結果が出るためコストや時間を節約できます。また、ADRは非公開で手続きが進行するため外部に紛争の内容を知られる心配はありません。
交通事故ADRのデメリット
ADRはあくまで当事者双方の合意の上に成り立つ制度です。どちらかが紛争解決に消極的であるとADRによる解決は期待できません。
訴訟で解決する
相手方との交渉が決裂しどうにもならないときは、最終的に裁判所に訴訟を提起することになります。
訴訟のメリットは裁判所が判決を言い渡すため当事者がどれだけもめていたとしても確実に解決に至ることです。また、示談交渉では受け取れない利息や弁護士費用の一部を請求できます。
まずは話し合って示談で解決を目指すのが一般的ですが折り合いがつかなければ訴訟に発展します。訴訟には豊富な法律知識が求められるため、弁護士などの専門家に対応してもらうのがおすすめです。
弁護士に依頼する
示談交渉を弁護士に代理してもらうと、確実に過失割合を決められます。弁護士に任せるのはメリットが多々あります。
正しい過失割合を算出してくれる
過失割合は交通事故の中でも専門性が高い分野であり、保険会社でも誤った過失割合を算定する場合があります。しかし、交通事故に詳しい弁護士は過去の判例や修正要素について十分に熟知しています。

受け取る慰謝料を増額できる
人身事故の被害者は精神的苦痛に対する賠償金、いわゆる「慰謝料」を請求できます。具体的な慰謝料の金額は過失割合などと同様に、相手方の保険会社が算定して被害者側に提示してきます。
ただし、任意保険会社は「任意保険基準」という低額の算定基準が適用するため、被害者の精神的苦痛を十分に補償する賠償金は得られません。
一方、弁護士は「弁護士基準」という計算方法で慰謝料を算出します。裁判で認められる金額と同額であるため、精神的苦痛を補償するために十分な慰謝料を加害者に請求できます。
弁護士特約があれば実質タダで弁護士に依頼できる
被害者が加入している自動車保険に「弁護士特約」というオプションがついていることがあります。弁護士特約は交通事故の問題を弁護士に依頼したとき、被害者が加入している保険会社が代わりに弁護士費用を支払ってくれるサービスです。
弁護士特約は1回の事件につき1名ごとに300万円まで弁護士費用を負担してくれます。交通事故において弁護士費用の相場は10万円〜20万円である場合がほとんどで300万円を超えるケースは滅多にないため、特約があれば実質タダになり気軽に弁護士に依頼できるようになります。
交通事故の過失割合についてまとめ
交通事故の過失割合は示談交渉開始から2~3か月程度で決まります。ただ事故の態様によって決まる時期が異なり、物損事故では比較的すぐに決まりますが人身事故では交渉が進まず1年くらいかかることもあります。
また裁判に持ち込むことになると6ヶ月~2年程度、ときには3年以上と過失割合が出るまで長期間かかってしまいます。
過失割合を早く決めたいなら示談をスムーズに進める必要がありますが、もめそうなときは実績のある弁護士への依頼が有効です。弁護士は素早く適正な過失割合を算定し、被害者に有利な方向へと交渉を進めてくれます。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ