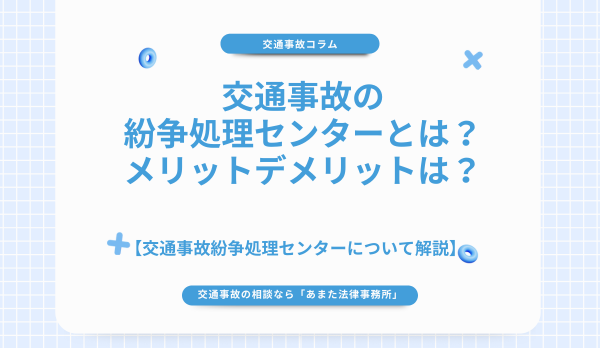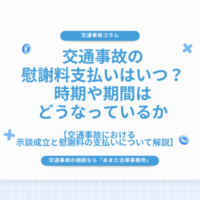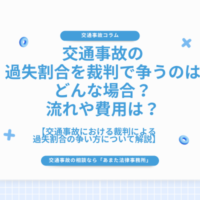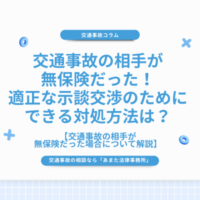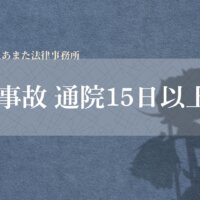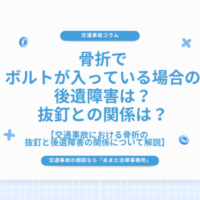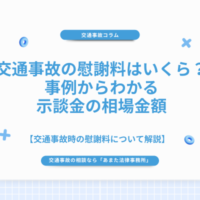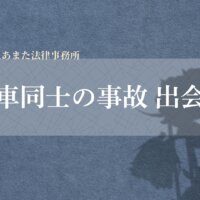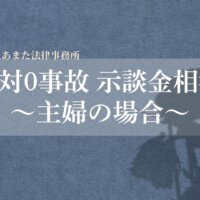交通事故の被害者なのに、慰謝料金額が低かったり加害者の保険会社から過失責任を主張されたりして、思ったよりも損害賠償金額が少ないなどのトラブルは本当に多いです。
専業である保険会社に対して法律知識のない一般人が交渉したところで、うまくいく可能性は非常に少ないと言えるでしょう。
そのようなトラブルのときに利用できるのが交通事故紛争処理センター。


2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 ▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
この記事の目次
交通事故の紛争処理センターとは?
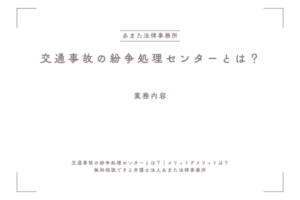
示談によって和解が成立しない場合、両者間の紛争は訴訟に発展します。
しかし、訴訟手続きによらず解決する手段があります。それがADRという手段です。
「Alternative(代替的)」「Dispute(紛争)」「Resolution(解決)」の頭文字を取ったもので、翻訳すると裁判外紛争解決手続。つまり裁判(訴訟)をせずに両者間の紛争を解決する手段というものになります。
法務大臣の認証を受けた公益財団法人交通事故紛争処理センターという団体が運営する機関です。
1974年に交通事故裁定委員会として発足してから組織を拡充し、1978年には組織を拡充し、中立公正な立場を強化するため「財団法人交通事故紛争処理センター」と発展し、2012年には、公益財団法人となっています。
拠点は「東京・名古屋・札幌・福岡・広島・大阪・高松・仙台・さいたま・金沢・静岡」の全国11都市に置かれています。
業務内容
センターではどのようなサービスを受けることができるのでしょうか?
相談の受付
処理センターでは、経験や知識が豊富な弁護士が相談に乗ってくれます。
斡旋
加害者側と被害者側の協議や、損害保険会社との協議が難航している場合、両者の間に入り、双方の言い分を聞き、中立の立場で和解案を提示し斡旋を行います。
和解へ向けた双方の協議回数は、人身事故の場合は3回~5回程度、物損事故の場合は1~2回程度行われます。何度協議をを行った後、仲裁の弁護士から斡旋案が示されます。これに応じる場合でも応じない場合でも斡旋は終了します。
審査
和解の斡旋を行っても両者が合意に達することができなかった場合、上位組織である審査会に対して審査を申し立てることができます。
審査前に、斡旋を担当していた弁護士から審査会に対して、双方の主張や事案の争点などが説明されて、審査会の日程を決定します。
審査会では、審査委員が双方の主張を聞いて裁定を下します。
結果が出てから14日以内に、裁定に同意か不同意かの回答を行わなければなりませんが、期限内に回答を行わない場合は不同意と見なされます。
申立人は、裁定に対して拘束されることはありませんので、裁定が不服であるのならば不同意の回答を出すことができます、また紛争の相手が加害者自身ならば、加害者も拘束されることはありませんので、不同意の回答を出すことができます。
しかし、相手が保険会社のときは、裁定を尊重することが決められていますので、申立人が同意した場合には和解が成立します(物損の審査において、審査会が必要と認める一定の条件に同意し審査会が審査、裁定を行う場合は、申立人と相手方双方の所有者が裁定に拘束されることになります。)。

交通事故紛争処理センターのメリットとデメリット
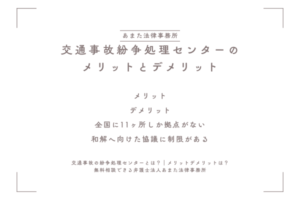
処理センターを利用した時ににはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
メリット
1.相談や斡旋の費用がかからない
交通事故によって生じたトラブルなどの相談、加害者や保険会社との和解へ向けた協議などは、交通事故関連の経験が多い担当弁護士が行ってくれますが、相談費用や協議費用は無料で行っています。

2.中立的な立場で適正な解決手段を提供してくれる
交通事故処理センターでは、申立人の担当として弁護士がつきますが、弁護士は被害者の利益を優先するのではなく、あくまでも申立人と加害者や保険会社の間に立ち、双方にとって中立的な立場で話を聞き、和解案を作成します。
保険会社によっては、被害者に対して過失責任を強調し、損害賠償金の割合を不当に下げてくることなどがありますが、紛争処理センターの弁護士が適正な過失割合を当てはめて再計算してくれるので、損害賠償金が不当に低いという申し出の場合、相手側から支払われる金額が上がる可能性が高いです。
3.迅速な解決が期待できる
双方が和解できず、両者の紛争の解決を裁判に委ねた場合、解決までの期間はかなり長くなることが予想されます。長期にわたって裁判で争うことは金銭的にも肉体や精神的にも大きな負担となってしまいます。裁判に比べると解決までの時間は早くなります。
センターでの解決は、双方の主張を聞いた上での和解を目指します。前述したように和解に要するのは数回程度ですから、平均すると訴訟によっての解決の約半分の期間、3ヵ月~1年くらいで解決することも可能です。
デメリット
1.担当弁護士は中立な立場であること
弁護士に依頼して訴訟を起こした場合、依頼された弁護士は依頼者の利益獲得を最優先に考えて動いてくれますが、無料で利用できる紛争処理センターで選出された弁護士は、あくまでも両者の間で中立的な立場で和解をすすめます。
また、担当になる弁護士については申立人が選ぶことはできないため、相性が悪かったり、弁護士が力量不足の場合、思ったような結果が得られない可能性があります。
全国に11ヶ所しか拠点がない
交通事故紛争処理センターは全国に11ヶ所しか拠点がありません。相談や和解の斡旋をおこなってもらうためには、申立人本人がセンターへ赴く必要があるため、拠点のない都市の場合、センターまで遠く不便になる可能性があります。
無料で相談や和解へ向けた協議をおこなってもらえるものの、和解が成立するまでは何度もセンターへ赴く必要があるため、遠方からの利用の場合、多額の交通費がかかることもあります。
和解へ向けた協議に制限がある
交通事故後に後遺症が残った場合などは、症状が固定されて損害賠償の金額が確定した状態でなければ申立てを行うことができません。また、和解の相手が任意保険に加入していない場合も斡旋の申し立てはできません。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ
交通事故紛争処理センターが利用できないケース
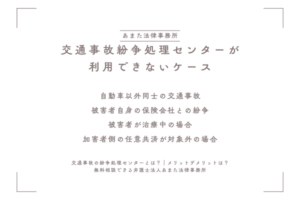
無料で利用できること、法律の知識が全くなくても担当弁護士がついてくれるので申立てを行うことが可能なことなどメリットは多いですが、全ての交通事故に対して相談や和解へ向けた協議をおこなってくれるわけではありません。
自動車以外同士の交通事故
最近では、自転車と歩行者の交通事故の増加が問題になっており、法改正が行われたり自転車での交通事故に備えた任意保険も増えていますが、センターでは、被害者もしくは加害者のどちらかが自動車でなければ、相談や和解の斡旋などを行うことができません。自転車同士の事故、自転車と歩行者の交通事故などは対象外となります。
被害者自身の保険会社との紛争
和解へ向けた協議が行われるのは、被害者と加害者もしくは、被害者と加害者の保険会社になります。被害者が加入している保険会社との紛争については関与することができません。
被害者が治療中の場合
前述したように、和解へ向けた協議が行えるのは損害賠償額が確定してからになるため、被害者が治療中でこの先どのくらい治療費がかかるのか見通しが立たず、損害賠償の金額が確定していないものや、後遺症が発生して認定の手続き中のため、等級が確定していない場合などは取り扱うことができません。
加害者側の任意共済が対象外の場合
対象になる任意共済は、JA共済、全労済、交協連、全自交、日火連になります。これ以外の任意共済の場合は取り扱うことが原則的にできませんが、加害者が和解へ向けた協議を行うことについて同意した場合は申し立てを受けてくれる可能性があります。
解決できない事案はどうすればいいか?
以上のようなケースに当て嵌まり、取り扱ってもらえないのであれば、弁護士に依頼して和解を目指す方法があります。
弁護士に依頼する場合は費用がかかりますが、交通事故紛争処理センターとは違い、住んでいる地域や仕事をしている地域の弁護士事務所に依頼することにより、交通事故紛争処理センターが近くにない場合は交通費などを考えると、それほど依頼費用と変わらなくなることもあります。
弁護士事務所では、交通事故での加害者や保険会社とのトラブルなどによる無料相談を行っていますので、今までの経験から和解した場合の損害賠償金額などがどのくらいになるかなどアドバイスを受けることができますので、弁護士費用とのバランスを考えて依頼するかどうか判断することができます。

交通事故の紛争処理センターの利用についてまとめ
双方の主張の隔たりがそれほど大きいものではないならば、交通事故紛争処理センターで和解へ向けた協議を行ってもらうことにより、和解が成立し解決に至る可能性が高いですが、主張に大きく隔たりがあるのであれば、和解へ向けた協議をしてもらっても和解が成立せずに、審査そして訴訟にまで発展してしまう可能性があります。
和解ができる可能性はどれだけあるのか?


2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ