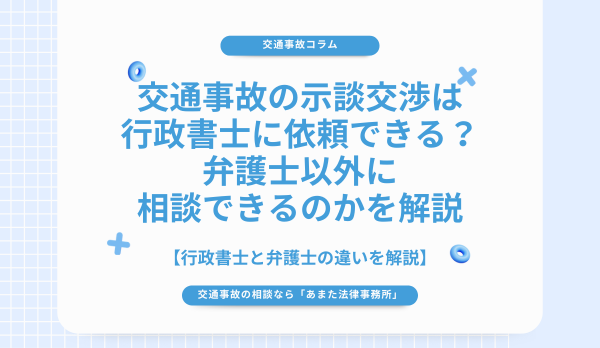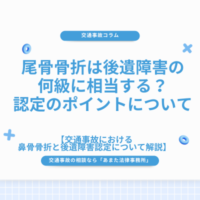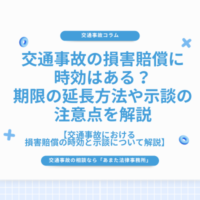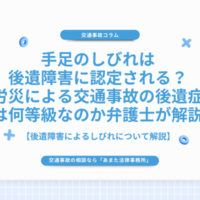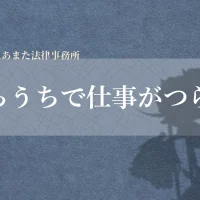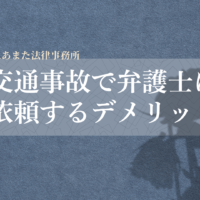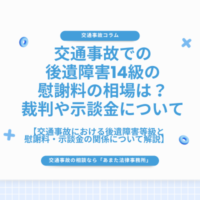「行政書士と弁護士の違いって?」
「交通事故の示談交渉は誰に相談すれば良い?」
こんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、交通事故の示談交渉を行えるのは弁護士だけです。
行政書士は、依頼に応じて交通事故に関する書類や示談書の作成を行うことはできますが、 交渉そのものはできません 。

執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
【結論】示談交渉は行政書士に相談できない
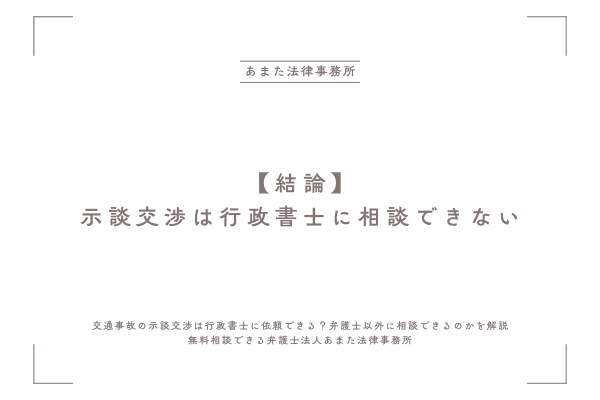
行政書士は、示談交渉を代理することが法律で禁止されています。
行政書士は、官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類の作成を主な業務としています。しかし、依頼者の代理人として相手方と交渉することはできません。
たとえば、交通事故の損害賠償交渉や離婚に伴う慰謝料請求など、当事者間で争いがある場合の交渉は、弁護士の業務範囲となります。
行政書士がこれらの交渉を行うと、非弁行為として処罰の対象となる可能性があります。
ただし、行政書士は示談書の作成自体は行うことができます。依頼者から聞き取った内容を基に、合意内容を文書化することは可能です。
行政書士と弁護士の違いとは?
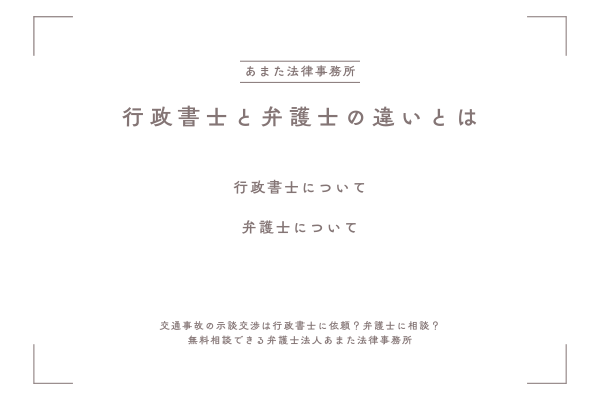
行政書士と弁護士の違いを知らない方も多いのではないでしょうか。
行政書士と弁護士はどちらも法律問題に携わる職業ですが、仕事内容は全く異なります。
まずはじめに、行政書士と弁護士の違いについて解説します。
行政書士について
行政書士は、「行政書士法」に基づいて国家資格を取得した専門職のこと。
主に、役所などの行政機関に提出する書類を作成する仕事を担っています。
言い換えれば、行政書士は「国民と行政をつなぐパイプ役」といえる存在です。
行政書士の仕事は大きく分けて以下の3つ。
行政書士の主な仕事は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、警察署など)に提出する書類の作成です。そのほとんどは「許認可」に関する書類であり、行政書士にしかできないものも数多くあります。
- 建設業を始める際に提出する「建設業許可書」
- お金の貸し借りを明記した「消費貸借契約書」
- 遺産分割について取り決めた「遺産分割協議書」
- 社内の会議内容を記録した「取締役会議事録」など
行政書士は単に書類を作成するだけでなく、その書類を依頼者の代理人として官公署に書類を提出することができます。
例えば、「飲食店を開業したいけれど、営業許可の申請手続きが複雑で不安」と言った場合、行政書士に依頼すれば、必要な書類の準備から提出までを一括して任せることができます。
また、行政機関の判断に対して不服がある場合には、「審査請求」や「再調査の請求」など、不服申し立ての手続きを代理することもできます。
交通事故などで必要になる書類の作成については、行政書士に相談することができます。
行政書士が対応できるのは、役所に提出する書類や、権利・義務、事実の証明に関する書類。
たとえば、内容証明郵便や示談書といった書類は、行政書士か弁護士しか作成できません。
ただし、弁護士は示談交渉や裁判などの対応も含まれるため費用が高くなる傾向があります。
一方、行政書士は書類作成に特化しているため、比較的費用を抑えて相談できるのが特徴。

弁護士について
弁護士は法律のエキスパートであり、司法試験に合格し、弁護士資格を得た者だけが就任できます。
裁判の代理、示談交渉、法律文書の作成など、幅広い法的業務を担っています。
では、具体的にどのような仕事をしているのか見ていきましょう。
弁護士は、依頼人の訴訟代理人として裁判で主張や立証を行います。
民事裁判では、交通事故、借金問題、離婚、相続などのトラブルに対応。
刑事裁判では、起訴された被告人の弁護を担当し、無罪を主張したり、刑を軽くするように働きかけます。
弁護士に示談交渉を任せることで、交渉を有利に進められます。
「示談」とは、当事者同士の話し合いによって紛争を解決すること。
刑事事件や交通事故で利用されることが多く、事件の被害者と加害者は、裁判することなく自主的に損害賠償の金額などを取り決めます。
示談交渉は本人でも行えますが、弁護士に依頼することで、法律的な根拠に基づいた交渉が可能。
経験のある弁護士に任せることで、交渉を有利に進められるだけでなく、加害者側とのやりとりも全て任せられるため、精神的な負担を大きく減らすことができます。
弁護士は、法的な効力を持つ文書を正しく作成することができます。
内容証明郵便や示談書など、トラブル解決に必要な文書には法律的な形式や内容が求められるため、一般の人がミスなく作るのは難しい場合も。
弁護士に依頼すれば、そうした書類を専門的な知識に基づいて正確に作成してもらえ、後々のトラブルを防ぐことにもつながります。
つまり、重要な書類の作成は、弁護士に任せることで安全かつ確実です。

弁護士に相談すれば、法律トラブルの内容を法的に分析し、適切なアドバイスを受けることができます。
依頼者が抱える問題を整理し、どのように対応すべきかを法律の視点からわかりやすく説明してくれるの弁護士の法律相談。
例えば交通事故に遭った場合、相手の保険会社が提示する損害賠償の内容が妥当かどうかを確認してもらえます。
さらに、適正な慰謝料を受け取るにはどう通院すればよいか、治療や証拠の残し方など、今後の対応についてもアドバイスを受けられます。
なお、2006年の法改正により、認定司法書士も140万円以下の民事トラブルに限って、法律相談や交渉、簡易裁判所での代理ができるようになっています。
交通事故で行政書士に依頼できることは?
行政書士は「代書屋」とも呼ばれる職業なので、書類作成が苦手な方には心強い存在といえます。交通事故においても、行政書士に面倒な書類の作成を依頼することができます。
では、交通事故にあった際に、行政書士に作成を依頼できる書類はどのようなものでしょうか。交通事故で必要となる書類を一部紹介します。
どのような内容の文書を、誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明してくれる文書です。
相手方が任意保険に入っていない場合などでは、連絡を入れても無視されるケースがあります。このとき、内容証明郵便を送ることで、「郵送物なんて送られてきてない」としらを切られるのを防ぐことができます。
自賠責保険に被害者請求するときは、被害者本人が必要書類を作成しなければなりません。
具体的には、「支払請求書兼支払指図書」「事故発生状況報告書」「診断書・診断報酬明細書」などの書類を用意する必要があります。行政書士に依頼すれば、これらの書類を代わりに作成してもらうことができます。
交通事故で後遺障害が残った場合、審査機関から後遺障害等級の認定を受けることで、加害者に後遺障害慰謝料などを請求できます。
後遺障害慰謝料の金額は等級によって異なるため、適切な等級が認定されることが非常に重要です。しかし、等級認定の申請をする際には、後遺障害の存在を裏付ける証拠書類を収集・作成しなければなりません。

このように、交通事故に関する書類の作成で困っている方は、行政書士に相談するのも一つの手です。文書作成に関することであれば、その範囲でアドバイスを受けても弁護士法違反にはなりません。
ただし、行政書士の職務範囲には制限があるため、示談交渉や裁判代理を依頼できない点には注意しましょう。
交通事故で弁護士に依頼できることは?
弁護士であれば、交通事故にかかわる全てのトラブルを依頼可能です。
特に、示談交渉や裁判代理などは行政書士で担当できないため、はじめから弁護士に依頼した方が二度手間にならなくて済みます。
また、弁護士に依頼すると、慰謝料の金額を増額させることができます。これは、相手方の保険会社と弁護士では、慰謝料の計算方法が異なるからです。
保険会社が用いる慰謝料の計算基準は「任意保険基準」と呼ばれますが、この基準で算出した金額は、裁判で認められる相場を大きく下回ります。一方で、弁護士が用いる「弁護士基準」は、過去の判例を基に設定された慰謝料の計算基準であり、任意保険基準の金額と比較すると倍以上になることもあります。
交通事故で行政書士と弁護士ができること・できないこと
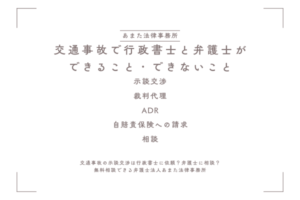
行政書士と弁護士では職務権限の範囲に違いがあります。
交通事故で行政書士と弁護士ができること・できないことを以下の表にまとめました。
| 行政書士 | 弁護士 | |
|---|---|---|
| 示談交渉 | × | ◯ |
| 裁判代理 | × | ◯ |
| ADR | × | ◯ |
| 自賠責保険への請求 | △ | ◯ |
| 相談 | △ | ◯ |
表からわかるように、弁護士は全ての法律事務を扱えますが、行政書士にはさまざまな制限があります。
交通事故において、行政書士にはできないことがいくつかありますが、弁護士には制限がありません。
ここからは、表の各項目について詳しく解説します。
示談交渉とは?
「示談交渉」とは、交通事故の当事者が、損害賠償の金額、すなわち示談金額を決定するための話し合いです。弁護士は、弁護士法第3条により、すべての法律に関する事務をおこなうことが認められています。したがって、弁護士は、被害者に代わって示談交渉に参加することも可能です。
一方で、行政書士は示談交渉を代理することはできません。なぜなら、弁護士法72条は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、弁護士のみに認められている法律行為をおこなうのを禁じているからです。
裁判代理とは?
示談交渉で当事者双方が合意に至らなかった場合、民事裁判を提起することで紛争の解決を目指します。このとき、交通事故の当事者は、本人の意思によって訴訟代理人を選任できます。依頼を受けて訴訟活動をおこなう弁護士は訴訟代理人にあたるため、弁護士は裁判代理が認められます。
一方で、行政書士による裁判代理は、弁護士法が禁止する非弁行為にあたります。したがって、行政書士は本人に代わって裁判を代理することはできません。
ADRとは?
「ADR(Alternative Dispute Resolution)」とは、裁判外で、第三者が間に入ることで紛争を解決する手法です。日本語では、「代替的紛争解決手続き」や「裁判外紛争解決手続」と訳されます。

あっ旋とは?
ADR機関のあっ旋人が当事者の間に入り、当事者たちの自主的な紛争の解決を促す方法です。あっ旋人が解決案を提示する場合がありますが、法的な拘束力はなく、あっ旋人による提案を拒否することができます。
調停とは?
3人の調停委員による合議を開催し、委員会が紛争解決に向けて働きかける手法です。あっ旋と同様に、当事者たちは調停委員による解決案を拒否することもできます。
仲裁とは?
裁判を受ける権利を放棄し、仲裁委員に紛争解決の判断を委ねる手法です。仲裁判断には、裁判と同様の効力が生じます。
自賠責保険への請求とは?
交通事故の被害者は、自賠責保険に保険金を請求できます。自賠責保険とは、原付を含む車両を所有する者に加入が義務付けられている強制保険であり、交通事故の被害者救済を目的としています。

加害者請求とは?
加害者又は加害者が加入する任意保険会社が自賠責保険に請求する方法です。保険金を支払うのは加害者側の保険会社になるため、本来は加害者請求によって保険金が支給されることになります。
加害者請求では、加害者側の任意保険会社が書類を用意してくれるため、被害者に手間や面倒がかかりません。ただし、加害者側に手続きを任せる以上、手続きが不透明になるといったデメリットもあります。
被害者請求とは?
事故の被害者が、加害者側の自賠責保険に直接請求する方法です。本来は加害者請求によって自賠責保険に保険金を請求しますが、加害者が任意保険に入っていないケースなどでは、被害者請求を利用した方がいい場合があります。
被害者請求では、被害者自身が必要書類を収集・提出しなければなりません。一方で、自らが提出書類の内容を確認できるため、手続きの透明性が確保されます。
相談
行政書士は、行政書士が作成できる書類に関する書類についての相談に応じることができます。交通事故にあった際には、後遺障害等級認定の申請書や示談書に関する相談を受けることが可能です。
反対に、行政書士が作成できない書類や、その他の法律に関する相談に応じることはできません。例えば、行政書士が、示談交渉の進め方や訴訟についてのアドバイスをすると、弁護士法の「非弁行為」に該当するため、法律違反となります。
弁護士であれば、全ての法律問題に対応できるため、どのような内容でも相談することが可能です。書類作成に関するアドバイスだけでなく、示談交渉の流れや獲得できる賠償金の見積もりなどの相談にも応じてくれます。

まとめ:示談交渉は行政書士に依頼できない!
行政書士は文書作成の専門家ですが、職務範囲の都合上、取り扱えない業務もあります。特に、交通事故の分野では、示談交渉や裁判の代理権が認められていないため、行政書士に依頼しても断られるおそれがあります。
この点、弁護士ならば、交通事故に関連する全ての手続きを一任できます。また、弁護士に依頼すれば、示談交渉で慰謝料の金額を増額してくれます。
このように、交通事故では弁護士に相談するメリットの方が大きいため、行政書士よりも弁護士に相談するのがおすすめです。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ