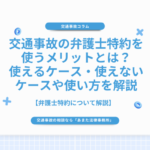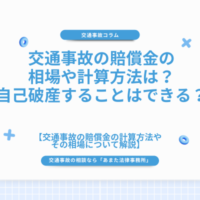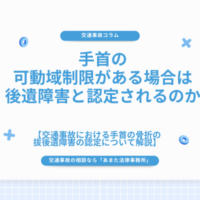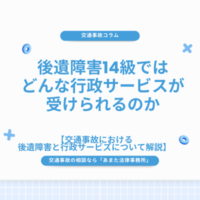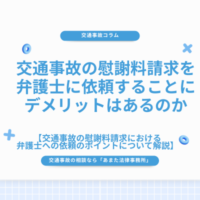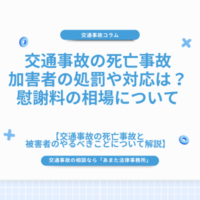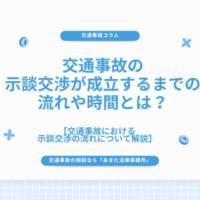交通事故に遭ったら、弁護士特約はぜひとも活用したいサービスです。しかし、事故の内容によっては、使えないケースもあります。

この記事の目次
弁護士特約とは?
弁護士特約は交通事故や日常生活における事故で被害者になったときに、「弁護士費用」を保険会社が負担してくれるサービスです。
自動車保険をはじめ、火災保険や死亡保険といった任意保険やクレジットカードなどの特約として付帯しており、不慮の事故に備えて任意でつけることが可能です。
弁護士特約を契約していれば、実質タダで弁護士に相談できるのがメリットです。
弁護士特約が使える費用
弁護士特約でカバーされるのは、以下のような弁護士費用です。
弁護士への依頼が決定した時点で、請求されるお金です。
結果に関係なく支払いますので、もし問題が解決できなくても返還されません。
事件の解決に成功したら、弁護士に改めて支払うお金です。
交通事故では慰謝料などの賠償金を増額できたときに発生します。
成功には一部成功も含まれ、割合に応じて報酬金を支払います。なお、裁判を起こしたものの全面敗訴したり、示談金を全く増額できなかったようなケースで支払う必要性はありません。
弁護士が問題を解決するために、実際にかかった代金です。
裁判を起こすときに納める収入印紙代や、相手方に郵送物を送るときに必要になる切手代などが含まれます。

弁護士の拘束のための費用として、支払われるのが日当です。
弁護士が事務所を離れて仕事をすると、基本的に他の案件を処理できなくなるという理由で発生します。
依頼者が弁護士に相談したときに発生する費用です。
どのような事件でも弁護士にいきなり問題解決を依頼するのではなく、相談から始めるのが原則です。
弁護士特約のメリット
弁護士特約の大きなメリットは、弁護士費用を節約できる点です。また、弁護士が介すると慰謝料を含む賠償金を増額でき、よりお得な結果を得られる可能性が高くなります。
費用をかけずに弁護士に依頼できる
弁護士特約における一番のメリットは、費用をかけずに弁護士に依頼できる点です。
弁護士への報酬は獲得した賠償額に応じて支払うことになります。交通事故では怪我の程度が大きかったり後遺障害の等級が高いと受け取る賠償金も増え、弁護士に支払う金額も大きくなります。弁護士費用が100万円以上かかる場合もあり、出費を抑えるために自分だけで解決しようと考える方も一定数いるのは事実です。
しかし弁護士特約があれば、保険会社がこれらの費用を支払ってくれます。気軽に弁護士を使用できるといえるでしょう。
弁護士特約が使えないと、弁護士費用を全額自己で負担しなければなりません。特に、受け取れる賠償金が少額になる軽症の人身事故では、弁護士費用の方が高くなるケースが増えます。弁護士に依頼すると費用倒れになってしまい、損をすることもあるのです。
自動車保険に弁護士特約をつけると、通常の保険料に特約分のコストが上乗せされるのはデメリットです。ただ、弁護士特約は月々100〜300円程に設定されており、年間で換算しても1500円ほどの負担で済みます。いつどこで交通事故が起きるかわかりませんので、特約として契約しておくと安心です。

受け取る示談金額を増額できる
弁護士特約を利用して弁護士に依頼すれば、示談金額を大きく増額できます。「弁護士基準」で慰謝料を請求できるためです。
交通事故における慰謝料の計算基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。この中で最も高額な賠償金が得られるのは弁護士基準です。反対に最も低額なのは自賠責基準になります。任意保険基準は自賠責基準より若干高くはなりますが、弁護士基準の金額と比べるとかなり低額になってしまいます。
通常、慰謝料を含む賠償金は被害者と加害者が加入している保険会社と話し合いをする示談交渉で決定されますが、相手の保険会社が提示するのは「任意保険基準」とで算定した金額です。安易に保険会社側の条件を了承してしまうと、少ない賠償金しか受け取れません。
被害者が個人で弁護士基準の金額を請求しても、主張を聞き入れる保険会社はほぼないと言えます。ところが、弁護士が交渉に参加すれば話が変わります。
弁護士がいれば、弁護士基準で算出した慰謝料を請求できるようになります。
弁護士の請求を拒否すると、保険会社は民事裁判になることを知っています。裁判所では弁護士基準を適用して慰謝料を算出しますので、弁護士に訴訟を起こされるとほとんど勝ち目がありません。手間がかかる裁判を起こされる上に訴訟費用を払うのは避けたいと考えるため、たいていは示談交渉の時点で弁護士の増額請求を受け入れるのです。
実質無料で被害者の負担を減らせる
弁護士特約があると実質無料で交通事故に関する煩わしい手続きを一任でき、被害者の精神的な負担を大きく減らせるのもメリットです。
交通事故の被害に遭うと、被害者の方はさまざまな手続きをおこわなければなりません。加害者や加害者が加入している保険会社とやりとりするのはもちろんのこと、休業損害の申請や労災保険への給付金請求などの手続きも必要になります。
また、事故によって後遺症が残ると、後遺障害慰謝料を請求するため後遺障害の等級認定を申請しなければなりません。
交通事故の分野に精通している弁護士であれば、後遺障害等級認定をはじめとしたさまざまな手続きを適切に行ってくれます。

示談代行サービスが使えないときに役立つ
弁護士特約は示談代行サービスが使えない交通事故でも、対象になるのがメリットです。
被害者が加入している保険会社の担当者が代理で示談交渉をしてくれるのが、示談交渉サービスです。多くの自動車保険に付いていますが、被害者側の過失割合がゼロである追突事故のようないわゆる「もらい事故」では使えないので気をつけてください。
過失がないと被害者側に損害賠償義務が発生しません。
被害者側にも過失があれば、被害者が支払うべき賠償金を被害者側の保険会社が負担します。保険会社は賠償金額を決定するための示談交渉に参加することは、利害関係を持つことになります。しかし被害者側の過失割合がゼロであると、保険会社は賠償金を支払う必要が発生せず示談交渉への参加は利害関係を持ちません。
利害関係がないにもかかわらず弁護士以外の者が金銭に関する交渉を行う事態は、「非弁行為」という法律違反行為に当たってしまいます。したがって、被害者側に過失なしの事故では、保険会社が提供している示談代行サービスを使いたくても使えないのです。
弁護士特約が使えないケースはある
弁護士特約には利用できない条件が存在しています。
事故内容によっては、弁護士特約が使えない可能性があるのは注意点でしょう。
被害者の過失が大きいケース
事故発生について被害者の過失が大きいケースでは、弁護士特約を使えない可能性があります。
弁護士特約の約款には弁護士特約が使える前提条件として「もらい事故などで損害を受けたとき」と記載されています。「被害者に故意・重過失がある場合は適用されない」と書いてあることも多く、被害者の不注意が事故発生の原因に大きく関わっていると弁護士特約は使えません。
例えば、以下のようなケースでは弁護士特約が使えないおそれがあります。
- 飲酒運転
- 無免許運転
- 薬物を摂取して正常な運転ができない状態
- 煽り運転など、運転中に不適切な行為があった
- 被害者が所有または管理している物の欠陥や摩耗によって生じた損害
被害者に重大な過失や不適切行為が認められた交通事故では、弁護士特約は使えないと思っておきましょう。
自転車事故のケース
交通事故といっても自転車同士の事故や自転車にぶつかられた事故では、弁護士特約は使えません。
自動車保険に付帯する弁護士特約が適用されるのは、「自動車が引き起こした交通事故」に限られています。
自動車には通常の車両だけでなくトラックやタンクローリーなどの大型車、原付といっのバイクも含まれます。しかし、自転車は軽車両で自動車とは見なされないのです。そのため、自転車同士または歩行者と自転車の衝突事故では、弁護士特約の適用範囲外になります。
自転車事故にも弁護士特約を適用させたいときは、「自動車事故と日常生活のトラブルを補償してくれるコース」を選ぶか、「自転車保険」に加入する必要があります。もしくは、医療保険や個人賠償責任保険などの弁護士特約では、自転車事故を含む日常事故にも対応しやすくなります。
その他のケース
弁護士特約は、以下のような事例でも使えない点に注意してください。
- 天変地異や自然災害(地震・噴火・津波・台風・洪水)によって発生した損害
- 損害賠償の請求先が被害者の身内(配偶者・父母・子ども)または自動車の所有者である
- 事業用車両が事故にあった(保険会社によっては事業用車両でも適応あり)
弁護士特約が適用される範囲
弁護士特約は家族が加入している保険でも適用されるものがあります。
実は被害者が弁護士特約をつけていることを失念して、利用しないケースはたくさん存在しています。また、事故にあった本人だけではなく家族が加入する保険の弁護士特約が該当になる点を知らない方は多くいます。
- 契約者の配偶者
- 契約者と同居する同居の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)
- 契約者と別居する未婚の子

保険会社が弁護士特約を使わせたくないケース
弁護士の必要性が低い内容の事故では、弁護士特約の利用を嫌がる保険会社があります。
弁護士特約を利用されると、保険会社が弁護士費用を負担ししなければなりません。そのため、保険会社側はできれば使ってほしくないと、消極的な態度を示すことがあるのです。
しかし必要であれば積極的に特約の利用を検討すべきです。契約者は保険料を支払っているのですから、使えないと言われるのはおかしな話です。遠慮せずに特約を利用する意思表示をしましょう。
示談交渉が順調に進んでいる
示談交渉が特に争いがなく進んでいる状況では、弁護士特約を使って欲しくないと考える保険会社はあります。交渉で揉めていないのに、わざわざ弁護士に依頼する必要性はないと考えるためです。
しかし、弁護士は示談交渉以外にも、さまざまな対応をしてくれます。被害者にとって弁護士は気軽に相談できたり、アドバイスをくれたりする心強い存在です。
物損事故や軽微な人身事故
物の破損に留まった物損事故や、むちうちなど比較的軽微な症状のケガを負った人身事故では、保険会社は弁護士特約の利用を渋る傾向にあります。
物損事故や軽傷の人身事故では損害賠償額がそれほど高くなく、弁護士に依頼してもが大きく増額される可能性は低いためです。つまり弁護士に依頼する必要性が低いと予想され、弁護士特約を使ってまでの対応は不要というわけなのです。
ですが、弁護士特約は損害額が小さい交通事故だからと、使えないサービスではありません。少額だとしても賠償金が増額するのであれば、弁護士に依頼するべきといえます。

弁護士特約は過失ゼロの事故には使えない?
弁護士特約は被害者に過失が認められる事故でも、使えないことはありません。
交通事故は被害者側にも少なからず過失がある判断されることがほとんどです。そのため、被害者側に過失があるからといって、直ちに弁護士特約が使えないとはならなのです。
一般的には被害者の過失が50%を超える交通事故になると、弁護士特約の利用に影響してくると言われています。ただ、中には50%を超える過失割合でも利用できた事例はあります。飲酒運転や無免許運転など、被害者に重大な過失があると弁護士特約は適用されませんが、こちら側に過失があったとしても諦めずに弁護士特約を利用できるか保険会社に連絡してみましょう。
弁護士特約で補償される金額の上限
弁護士特約で補償される金額は上限があります。
相談は10万円まで、弁護士費用は300万円までが基本です。300万の上限を超えた分は被害者の実費となりますが、弁護士特約を使うメリットは大きいでしょう。
弁護士費用が300万円以上かかるケース
弁護士費用の総額が300万円を超えるケースでは、すべてを弁護士特約で賄うことはできません。
弁護士特約のほとんどは1件の交通事故につき、一人当たり300万円を上限としています。一人当たり300万円まで弁護士費用を補償してくれることになり、一台の車に3人の家族が乗車していれば最大900万円まで弁護士費用の補償を受けられます。
事故による被害の程度が大きく弁護士により示談金を大きく増額できたときなどは、弁護士費用が300万円を超えるケースがあります。
弁護士報酬に含まれる着手金や成功報酬金は、弁護士が賠償金を増額させた経済的利益の割合に応じて支払います。2004年までの日弁連の弁護士報酬規定では、弁護士費用を以下のように定めていました。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8%(下限は10万円) | 16% |
| 300万円超3,000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3,000万円超3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
現在ではこの統一の報酬基準は廃止され、各法律事務所が自由に弁護士費用を設定できるようになりました。ですが、旧報酬規定を参考にして弁護士費用の相場を定めている法律事務所は多いです。
この表を参考にすると、弁護士が賠償金を1,800万円以上増額させれば、日当、実費などの他の弁護士費用と合わせて300万円以上になることが想定されます。ただし、実際のところ死亡事故や重篤な後遺障害が残ったなど、限られた交通事故でしか1600万円以上の増額は見込めません。300万円までは弁護士特約で補償を受けられますので、弁護士費用が高額になっても大部分は保険会社が負担してくれることになります。

相談費用が10万円以上かかるケース
依頼前の法律相談料は、弁護士特約では一人当たり10万円の補償限度が一般的です。
法律相談料はそれぞれの法律事務所によって異なりますが、初回は無料~30分につき5,000円程度と手ごろな金額で対応している法律事務所が目立ちます。しかし二回目以降は30分につき10,000円〜25,000円ほどと、一気に料金が跳ね上がることは少なくありません。
事件の内容が複雑だったり何回も法律相談を受けたいときは、すぐに10万円を超えてしまうでしょう。法律相談料が高めの弁護士であれば、数回で相談費用が10万円を超えることもあり得ます。
弁護士への相談費用が10万円を超えると、弁護士特約だけでは賄いきれません。限度額を超えた分は自己負担になりますが、交通事故について10万円まではじっくり相談できると考えれば、弁護士特約は積極的に活用すべきです。

弁護士特約がなくても弁護士に相談すべき
交通事故の被害者は、弁護士特約が使えなくても弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば示談金を大きく増額できます。特約がついていなければ、最終的には依頼者が獲得した利益から弁護士費用が差し引かれますが、手取りがプラスになる場合がほとんどです。特約がついていなくても弁護士に相談する意味は大いにあります。
したがって、弁護士特約なしの状況でも、交通事故に遭ったら弁護士に相談するのがおすすめです。
まとめ
交通事故のさいに弁護士特約が使えないケースはほとんどありません。
被害者の過失があまりにも大きいときなど一部使えないケースはあるといえ、被害者に過失があった交通事故でも利用対象になります。
保険会社が弁護士特約を使わせたくないケースは存在していますが、弁護士特約は保険料を支払い付けているオプションです。弁護士に依頼することで慰謝料などの賠償金を増額できる、示談交渉の負担を軽減できるといったメリットが少しでもあるなら、大いに利用すべきです。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ