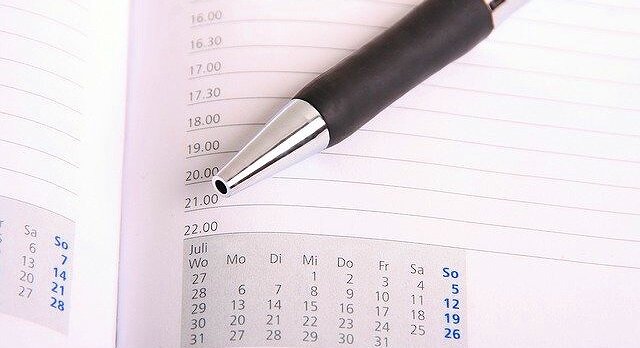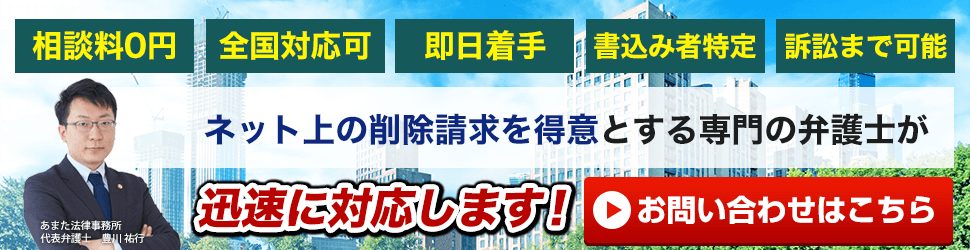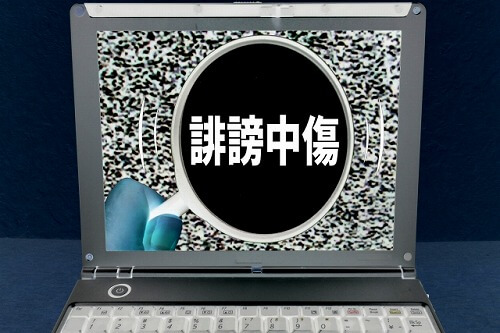2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら

執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
発信者情報開示請求の仮処分とはどんな状態か
インターネット上で誹謗中傷などの被害に遭った者が発信者情報開示請求して発令される仮処分は、正式な裁判の前に民事保全法に基づき裁判所が決定する暫定的な処置です。つまり、裁判で勝訴した時と同じような状態です。
仮処分を用いると悪質な書き込みが行われたインターネット掲示板やSNSなどのサイト運営者等へ情報開示請求や、加害者が契約、利用している経由プロバイダ(ISP[携帯のキャリアなど])に対しアクセス記録の削除の禁止が可能になります。
仮処分を求める理由とは
仮処分は通常だと2週間から2か月程度と、数か月以上は軽くかかる判決より迅速に対処できるのが特徴です。
通常の民事訴訟でもインターネット掲示板などのサイト運営者等に情報開示請求はできますが、訴訟手続きはそれなりの時間を要します。判決が出ても経由プロバイダ(ISP[携帯のキャリアなど])に請求する頃には、発信者の情報は既に消されており請求できなくなる事態があり得ます。
そのため、ウェブサイトの運営者等に対し、ログなどの情報を消去しないようにする仮処分の手続きを取ることが一般的です。
また、経由プロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟を提起しても、判決までに通常は6か月~1年程度かかります。経由プロバイダが保有するログの保存期間は約3~6か月て程度であることが多く、情報開示を認める判決が出てもログが消えていれば判決は無意味になってしまいます。

仮処分の効力
発信者情報開示請求による仮処分命令は裁判所の決定に基づくものであり、法的な効力を持っています。しかし、仮処分はあくまで仮の決定ですから、本訴では結果が覆る可能性はあります。発信者情報消去禁止の仮処分が認められても、情報開示が認められなければ投稿者の情報を知ることはできません。
しかし、プロバイダが裁判を起こし訴訟になる事例はほとんどありません。仮処分が認められたら本訴しないのが普通だからです。
仮処分が認められる2つの要件
発信者情報開示請求の仮処分が認められるためには、以下2つの要件を満たす必要があります。
- 被保全権利の存在
- 保全の必要性
被保全権利の存在
被保全権利はプロバイダ責任制限法4条に規定されている発信者情報開示請求権で、発信者情報開示請求権が存在することの主張を行います。
開示請求する人が利権を侵害されたと主張するだけでなく、投稿者の利権侵害が明らかであると証明しなければなりません。
名誉毀損ではその人の社会的評価を低下させている、真実ではない内容である、公共性や公益性を充足していないなどの明確な理由を要します。
プライバシー侵害ははっきりとした定義がなく判断が難しい面があります。心理的な不安や負担を与えると認められることなどがあげられますが、個人の感じ方にも違いがあります。ただ、住所や氏名、電話番号、メールアドレス、病歴、犯罪歴などを勝手に晒す行為は、誰に対してでもプライバシー侵害に当たると言えます。
保全の必要性
早急に決定が出ないと回復できない損害が生じると裁判所に伝えるための要件です。
ログの保存期間が3カ月~6カ月程度と短いため、早急にIPアドレスやタイムスタンプを開示してもらえないと情報が消えてしまい書き込みを行った人物の特定ができなくなることをコンテンツプロバイダに対し指摘します。
保全の必要性が認められIPアドレスやタイムスタンプなどのログを仮処分で開示した後、アクセスプロバイダ(接続プロバイダ)に訴訟を起こす形になります。
仮処分が発令された後の流れ
仮処分が発令されると、開示請求した側が訴訟に入るのが一般的です。された側は仮処分の命令や訴訟の判決に従うことになります。
発信者情報開示請求した側の流れ
発信者情報開示請求の後に仮処分が発令されたら、次の段階としてコンテンツプロバイダなどの債権者に訴訟の提起を行うのが一般的な流れです。仮処分の決定をもとに決定正本の写しを提示し、プロバイダに情報の開示を求めます。サイト管理者が開示に応じれば、投稿者のIPアドレスが判明するのでこれを基に特定した経由プロバイダ(ISP[携帯のキャリアなど])に対する情報開示請求を実施します。
ただし、経由プロバイダには投稿者の情報開示やアクセスログの保存を求めても、任意の開示請求には応じてもらえないことがほとんどです。仮処分は裁判を前提とした手続きですし、否が応でも裁判に進む必要があるでしょう。裁判で勝訴となれば、仮処分で認められた保全の権利により発信者情報開示が行われます。
また、仮処分申立時に申立人が支払った担保金といった費用を取り戻すためにも、裁判を起こす必要があると言えます。
請求された側の流れ
法務局で供託書を裁判所に提出すると仮処分が発令され、裁判所は相手方に決定正本を送達します。仮処分後の対処法を請求された側の流れをプロバイダと投稿者に分けて解説します。
債権者(プロバイダ)側の流れ
請求された側の債権者は、仮処分や訴訟の結果に従いアクセスログの保全や情報の開示を実施します。
ただ、仮処分の後に申立人が提訴をしないと、「起訴命令申立」という方法を取ることができます。起訴命令申立は裁判所が債権者に訴訟の提起を命じるものです。もし命令を無視して訴訟に進まなければ、仮処分命令は取り消されてしまうという注意点があります。

投稿者側の流れ
仮処分はプロバイダなどが対象になるため、開示請求の対象になる書き込みをした側に直接的な影響はありません。
ただし、結果的には個人情報が開示される可能性が高いです。後に損害賠償請求されたり、名誉毀損に該当するなど悪質な書き込みでは逮捕・起訴などの刑事の事件に発展するおそれもあります。
プロバイダから投稿者に開示に同意するかどうか確認するための意見照会書が送付されます。拒否すればプロバイダが勝手に個人情報を開示することはありませんが、誹謗中傷の被害者は開示のため訴訟手続きを起こす可能性が高いと考えられます。
判決で請求が認められると、原則としてプロバイダは控訴せず一審の判決に従います。投稿者の氏名・住所といった個人情報が相手に開示されることになります。
発信者情報開示請求の仮処分まとめ
発信者情報開示請求により仮処分命令が発令されると、IPアドレスの開示やアクセス記録の保全を行うことができます。
しかし、その後すぐに氏名や住所といった相手の情報が開示できるわけではなく、情報を提供してもらうには本訴で勝訴判決を要します。
仮処分だけで目的を達成したとはいえませんが、より確実に発信者の情報を取得するためのステップと言えるでしょう。
仮処分後の訴訟を個人だけでスムーズに進めるのは困難なのが現状です。インターネット上のトラブル事案に強い弁護士に対応してもらうのがおすすめです。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら