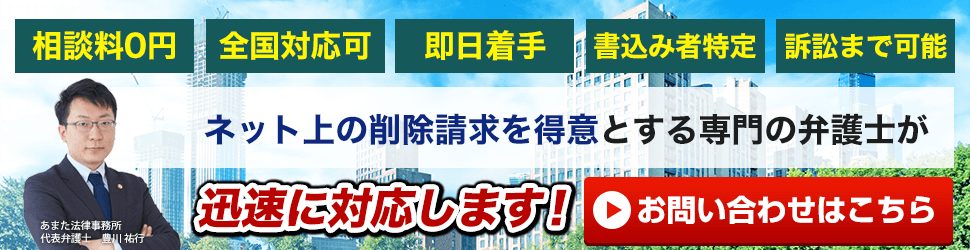2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
SNSや掲示板などネット上で誹謗中傷されたら、刑事や民事上の時効内に対応する必要があります。また、匿名の加害者を特定する手続きにも期限があるのは注意点です。


2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 ▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
この記事の目次
名誉毀損はどのような罪なのか
名誉毀損罪は3つの要件を満たすと成立し、刑法上の罰則を受けることになります。
インターネット上で他人を攻撃したり、悪口を言う行為は一般的に「誹謗中傷」と呼ばれていますが、名誉毀損に該当します。「誹謗中傷」は正式な法律用語ではありません。
名誉毀損は刑法230条に定められた法律上の犯罪で相手の社会的な評価を落とす行為を指します。ネット上での書き込みだけでなく日常生活での発言や文章、ビラなど、相手の名誉を傷つける行為はすべて名誉毀損と認められます。
名誉毀損になる3つの要件
名誉毀損に3つの要件が定められています。
公然とは書き込みや発言が不特定多数の目に触れたり聞いたりできる状態を指します。
SNSや掲示板といったネットに書き込まれた誹謗中傷は誰でも閲覧できますから、公然に当てはまります。いっぽう、周囲に誰もおらず相手と1対1の状況でも発言やDMの内容などは公然性があるとは判断されず、名誉毀損に該当しない可能性があります。
事実を摘示とは具体的な事柄を示すことであり、何らかの具体的な内容に基づいて相手を中傷することです。「不倫している」「破産したことがある」などが当てはまります。

名誉毀損は外部的名誉を毀損するのが要件となり、社会的な評価を低下させるような行為が該当します。個人だけでなく、会社や企業など法人も対象です。
名誉毀損で科される罰則
名誉毀損罪は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられます。また、刑事罰のほかに被害者から民事上の責任を問われ慰謝料を請求されるケースがあります。

名誉毀損には時効が設けられている
ネット上の名誉毀損には時効があり、相手を訴えるなら迅速に行動する必要があります。
時効とは
時効は一定の時間経過により権利を主張できなくなったり、犯罪として処罰できなくなる制度です。
時効が存在する理由は時間が経過すると事実関係の立証が困難になる点、法律関係の安定のため現在の状態を保護する必要が生じる点などが上げられます。

名誉毀損の告訴期間
名誉毀損の告訴期間は「犯人を知った日」から6か月以内と定められています。
名誉毀損は「親告罪」の1つで、被害者が訴えない限り警察が捜査したり犯人を逮捕することはありません。そのため、被害に遭ったときは告訴期間内に自分から警察に加害者を捜査してもらえるよう申し出る必要があります。
決められた告訴期間を過ぎてしまうと、警察は動いてくれません。告訴期間の時間制限は名誉毀損における時効の1つと言えるでしょう。
告訴期間の時間制限
犯罪行為が終了したときから6か月が告訴期間の時間制限になります。
名誉毀損の時効がスタートするタイミングは、被害に遭ったときではなく「犯人を知った日」からというのがポイントです。「犯人を知った日」の定義ですが、過去の判例を見ると「犯人が誰なのか知ることのできる状態」になります。加害者の氏名や住所を知る必要はないとされているため、ネット上のトラブルでは投稿者のアカウントが分かった時点と考えられるでしょう。
もし、相手からの誹謗中傷が続いている状況であれば、告訴期間の時間制限はスタートしません。
公訴時効
名誉毀損は刑事上では告訴期間に制限があるほか、公訴時効と呼ばれるものがあります。
公訴とは検察官が犯罪事件の被疑者を刑事裁判で訴えることで、時効が成立すると加害者を裁くことはできなくなります。

民事上の時効
名誉毀損は民事上では加害者に対し損害賠償・慰謝料を請求でき、以下2つの消滅時効が存在しています。
- 被害者が損害および加害者を知ったときから3年間、訴訟の提起などの権利行使をしない場合
- 不法行為が行われてから20年が権利を行使しないとき
民事事件では被害に遭ったことを知ったときから3年間、知らなければ20年経過すると、加害者へ慰謝料を含む損害賠償の請求はできなくなります。
名誉毀損の書き込みに対する時効
ネット上にある名誉毀損に対する匿名での投稿者を特定する手続き、投稿の削除といった工程にも、時効は存在しています。悪質な書き込みを見つけたら、迅速に対応することが大切です。
投稿者の特定ができる期間
投稿者を特定できる期間に法律上の時効はありません。しかし、問題になるのはプロバイダによるアクセス記録の保存期間です。
アクセス記録は投稿者がいつ、どのサイトに接続を行ったかを記録したデータで消去されると証拠がなくなり、名誉毀損の書き込みをしたと証明するのが難しくなります。
プロバイダの保存期間は半年から1年程度が多くなっていますが、なかには3カ月ほどの会社もあります。
投稿者の特定は情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)により、書き込みのあったサイトの運営会社や管理者(コンテンツプロバイダ)に問い合わせ投稿者の情報開示をして行います。そして、明らかになったipアドレスの情報をもとに加害者が利用している接続プロバイダに住所や氏名といった個人情報の開示を請求します。
サイトやプロバイダはプライバシー保護の観点から開示請求があっても利用者の個人情報をすんなりと開示することは少なく、それぞれに裁判に訴え開示仮処分と開示請求することになります。
一般的にコンテンツプロバイダから開示を受けるのに2~4週間、接続プロバイダからの開示には10日から1か月半程度が必要とされています。無駄に時間がかかると裁判に勝ってもデータがなくなり、結局開示を受けられないリスクが生じます。半年以上経過した書き込みだと犯人の特定は難しいと思って良いでしょう。名誉毀損で訴えるためにはタイムリミットがあると認識した早めの行動が求められます。
投稿の削除を依頼できる期間
ネット上にある問題の投稿を削除するさいは、時効と呼べるものはありません。
削除の請求はサイトやSNSの問い合わせフォームなどから被害者が直接削除を依頼できます。投稿内容が違法であることやサイトのポリシーに反していると証明できれば、特にタイムリミットは存在しません。

参考:総務省・インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)
名誉毀損の時効を迎える前の対処法
時効を迎える前に名誉を毀損されたという証拠を残しておきます。そして、弁護士に相談しながら対処するのがおすすめです。
証拠を保全しておく
名誉を毀損している投稿を証拠として残しておきます。
ネット上にある対象の書き込みがある画面をプリントアウトしておくのがおすすめです。書き込まれているサイトのURL、書き込みされたアカウント名、日時などもわかるようにしておきましょう。もし、プリンターがないなど印刷できない環境であれば、スマホのスクリーンショットでもかまいません。
ネットでは投稿者が自身で書き込みを削除すると閲覧できなくなってしまい、名誉毀損だと訴えても証拠がなく何も対処できなくなります。忘れずに証拠を残すようにしてください。
弁護士に相談する
ネット上で名誉毀損の被害に遭っているなら、迅速に弁護士への相談を検討するのがよいでしょう。
名誉毀損には刑事、民事どちらにも法律上の時効が存在します。警察の捜査には被害者の刑事告訴が不可欠ですが、放置していると時効を迎え加害者を取り締まってもらえなくなります。また、投稿者の特定にもタイムリミットがあり、スピーディーな行動が求められます。
そのため、少しでも迅速な対処が重要なのですが、法律の知識がない一般の方適切な手続きを踏むのは難しいのが現状です。
特にネットでの誹謗中傷といったトラブルに強い弁護士は、時効を考慮しながら対応してくれますので安心です。

名誉毀損まとめ
インターネット上の名誉毀損には刑事上、民事上それぞれに時効が設けられています。また、プロバイダのアクセスログ記録の保存期間を過ぎると加害者の個人情報を開示できなくなりますので、被害に遭ったときはなるべく早く対応する必要があります。
もし、名誉毀損を受けている可能性があるなら、弁護士に相談し時効を迎える前に悩みを解決してください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら