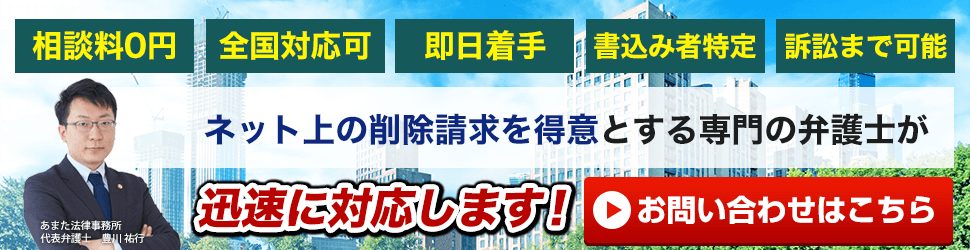2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら

この記事の目次
匿名のアカウントでも誰なのか特定できる
インターネット上のSNSや掲示板などは匿名で書き込みできますが、書き込みをしたのが誰なのかアカウントを特定することは可能です。匿名であれば身元はバレず何を投稿しても問題ないと考えている人は多いのですが、誹謗中傷など法的に問題のある投稿をした犯人はアカウントを特定され民事や刑事の責任を問われるリスクがあります。
最近は特定の動きが活発に
近年はネット上での誹謗中傷問題が社会的に注目を受けるようになりました。合わせて、投稿者のアカウント特定の動きが多く見られるようになっています。有名人や芸能人が加害者と戦う事例が増えており、2020年5月に起きた女子プロレスラー木村花さんがネットで受けた誹謗中傷が原因で亡くなった事件は、世間の注目を大いに集めました。この事件では花さんの母親が、情報開示によりX(旧Twitter)で中傷する投稿をしていた男性を特定し、損害賠償を請求する訴訟を起こしています。
また、2018年にはプロ野球・横浜DeNAベイスターズの井納翔一選手がネット上で妻に対し誹謗中傷していた女性を情報開示によって特定し、損害賠償や開示費用を含めて約190万円を求める訴訟を提起しています。
当時はまだネットでの誹謗中傷被害に対する訴訟は一般的ではなかったため、井納選手の行動は周囲を驚かせました。そして同時に、同じくネットで誹謗中傷の被害を受けている有名人たちを勇気づけたと言われています。
さらに、2020年7月には俳優の春名風花さんがネットで自身や家族を中傷していた男性を特定し、民事で訴訟を起こした後に315万円で示談しています。

匿名ならバレないは大間違い
匿名アカウントは誰が書き込みしたかわからないため、過激な内容を投稿する人はいます。誹謗中傷や攻撃的な書き込み用の捨てアカウントを、わざわざ作成するケースも存在しています。
しかし、発信者情報開示という法律に基づいた方法を使えば、たとえ匿名のアカウントでも本名や住所といった個人情報の特定はできます。
ネットの書き込みは一度投稿すると、拡散されてしまい削除するのが難しいという特徴があります。誹謗中傷など問題のある発言がデジタルタトゥーになり、日常生活に影響を及ぼす可能性もあります。安易に誰かを攻撃するような発言はしないようにしましょう。
誹謗中傷のアカウントを特定するための準備
誹謗中傷の被害を受けたとき、投稿したアカウントを特定するために大切なのは証拠を残しておくことです。
証拠を残す
相手のアカウントと特定するために、誹謗中傷を受けたという証拠を残すことが大切です。対象の投稿をURL付きでプリントアウトしてください。もしプリンターがないなど印刷できない状況であれば、スクリーンショットやスマホのカメラで撮影しても構いません。
書き込みに違法性があるかを確認
アカウントの特定には書き込みされた内容の違法性が必要になります。投稿者の情報を開示するにはいくつかの要件があり、その1つに明確な権利侵害があります。よって、違法性がなければアカウント特定は不可能になってしまいます。
通常、誹謗中傷の書き込みは名誉毀損罪や侮辱罪など刑法上の犯罪行為に該当し、罪が成立する要件を満たしているかが違法性の基準になります。
名誉毀損成立する要件
- 他の多くの人の目に触れる書き込みだったか (公然性)
- 名誉を傷つ社会的な評価を下げる内容だったか
- 何らかの事実を持ち出して攻撃する内容だったか (事実の摘示)
以上3つの条件を満たさなければ違法性がないと判断されます。
単に「バカ」「アホ」といった悪口であれば、侮辱罪になります。

発信者情報開示請求の手順
誹謗中傷しているアカウントの特定は、プロバイダ責任制限法第4条で定められている発信者情報開示請求を利用します。開示されれば、投稿者の氏名や住所、メールアドレス、IPアドレスといった識別番号を知ることができます。
発信者情報開示請求では、段階を踏みながらアカウントを特定する必要があります。
1:投稿者のIPアドレスとタイムスタンプ開示
誹謗中傷のコメントが掲載されているサイトやSNSの管理者や運営者(コンテンツプロバイダ)に、アカウントを識別するためのIPアドレスと投稿日時を証明するタイムスタンプの開示を求めます。
しかし、任意では開示する可能性は低く、多くは開示の仮処分を求める裁判が必要です。
仮処分は民事保全法に基づき行われる暫定的措置で、2週間~2か月と通常の裁判よりも結果が早く出るのがポイントです。
2:投稿者のプロバイダを特定
IPアドレス等が分かれば、相手がインターネットを接続しているプロバイダを特定できます。ネット上にあるIPを入力するとプロバイダが分かるサイトから、投稿者のプロバイダを割り出し情報開示を行います。
ただ、本人の同意なく、接続プロバイダが利用者の情報を教えることはありません。
3:接続プロバイダへの情報開示請求の訴訟を起こす
接続プロバイダに投稿者の情報開示を求める訴訟で、仮処分ではなく正式な裁判になります。裁判は結果が出るまで6ヵ月~1年ほどかかるのが一般的です。
注意点はプロバイダが保有している発信者のアクセス記録には保存期間があり、通常は平均3~6か月ほどで削除されることです。そのため、裁判に時間がかかりそうであれば、開示請求と同時にアクセスログの削除禁止の仮処分を求めます。
裁判の結果、書き込みの違法性などが認められれば、相手の氏名や住所が開示され、アカウントの特定は完了します。
海外のサイトやサーバーの場合
FacebookやX(旧Twitter)など海外の企業が運営しているサイトやサーバーでも、日本向けの事業があれば日本の裁判所で開示請求はできます。
ただ、日本法人が存在する企業でも、多くは訴訟の権限をもっていません。海外にある本社に対しての手続きが必要になるため、開示請求は日本企業への請求より時間と手間がかかります。
海外の登記簿にあたる資格証明書の取得や英文を翻訳する必要があり、管轄は請求する側の居住地域ではなく東京地方裁判所になります。手続きなどに時間がかかってしまうと、結論が早く出る仮処分のメリットが薄れてしまうと言えるでしょう。

法改正でアカウント特定がしやすくなっている
2021年(令和3年)4月21日改正プロバイダ責任制限法が参院本会議で可決・成立し、2022年10月から「発信者情報開示命令」の制度が施行されています。ネット上での誹謗中傷被害の深刻化を受け、匿名アカウントをより特定しやすくなる内容に改正されました。
また、2025年4月には「情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)」が施行され、誹謗中傷など問題のある投稿は削除されやすくなるなど、被害者が有利になるよう法律は改正され続けています。
今後さらに、悪質な書き込みをしている匿名アカウントは特定しやすくなると予想されます。
参考:総務省・情報流通プラットフォーム対処法の省令及びガイドラインに関する考え方
アカウント特定後にできること
誹謗中傷しているアカウントが誰か特定できたら、事件化して相手に責任を問うことができます。
特定した相手の法的責任を追及
アカウントが特定できたら、民事訴訟を提起し慰謝料を含む損害賠償の請求が可能になります。また、刑事告訴すれば、相手を名誉毀損罪や侮辱罪などの罪に問うことができます。相手を警察に逮捕してもらったり、刑事裁判に持ち込むことも可能です。
民事、刑事、両方での責任追及もできます。
弁護士に相談を
誹謗中傷しているアカウントの特定や相手の責任を問うには、インターネットに関するな知識やノウハウが必要です。ネットで誹謗中傷の被害に遭っても個人では対応できないケースが多いのが現状ですので、法律に詳しい弁護士に依頼しアドバイスをもらってください。
インターネットでのトラブル事案を扱う弁護士は、心強くスムーズな解決が望めます。初回の相談無料サービスを実施している弁護士事務所なら、弁護士費用を気にせずに悩みを聞いてもらえます。
まとめ
ネットの匿名アカウントは、発信者情報を開示するの手続きにより誰かを特定できます。
法改正によりアカウントを特定する手続きは簡略化されており、特定後は相手に民事や刑事で責任を問うこともできます。
誹謗中傷の被害に遭っているなら、泣き寝入りする必要はありません。ただ、個人で解決するのは難しい面がありますので、法律に精通した弁護士の力を借り対処するのがおすすめです。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら