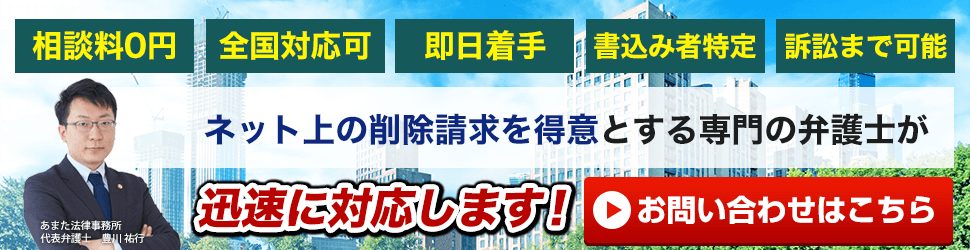発信者情報開示請求をするとき、警察に相談した場合、問題解決につながるのでしょうか。

執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
誹謗中傷問題を警察に相談するデメリットは?
オンラインでの誹謗中傷に直面した際、多くの人が解決策として警察に相談を考えるかもしれません。一見、これは自然な対応に思えますが、実際には予期せぬ困難やデメリットが伴うことがあります。本記事では、発信者情報開示請求を警察を通じて行う際に遭遇する可能性のある具体的な問題点を深掘りし、なぜ警察が常に最適な解決策とは限らないのかを探ります。
まずは警察に相談するデメリットからみていきましょう。警察に相談することで得られるメリットがある一方で、技術的障壁やプライバシー保護の厳格化、事件性の評価による捜査の限界など、多くのデメリットも存在します。これらの要因がどのようにして対応の遅延を引き起こし、結果的に被害者の苦痛を延長させるのかを明らかにします。
事件性がなければ動いてくれない
誹謗中傷問題に関して警察に相談するデメリットの1つ目は、警察は事件性がないと判断すれば、相談しても捜査に動いてくれないことです。
警察に行けば、相談には乗ってくれますし、話も聞いてくれるでしょう。ですが、それ以上の捜査となると、一般的に、事件性がなければ警察を動かすのは難しいとされています。

民事事件は捜査してくれない
警察には民事不介入の原則があるため、悪質なものを除いて、民事事件に関して積極的に動いてくれることはありません。そのため、警察に解決してもらうためには、刑事告訴を行い、問題を刑事事件にする必要があります。
ですが、書き込みが犯罪にあたるかどうかの判断は難しい場合も少なくありません。憲法には表現の自由が保障されているため、警察もそう簡単に「これが犯罪である」と断定することはできないのです。
さらに、被害者のなかには、「そこまで大事にしたくない」「相手の情報が開示されてから対応を決めたい」「民事で慰謝料や損害賠償を支払ってもらえればそれでいい」と考える方もいるでしょう。そういった方にとっては、警察に相談することが自分の望む解決に結びつくとは限らないといえます。
刑事告訴すれば犯罪が公になる可能性も
警察に捜査してもらうには、告訴状を出して相手を刑事告訴し、問題を刑事事件化する必要があります。
しかし、誹謗中傷で多くのケースに当てはまる名誉毀損や侮辱罪などは親告罪となっています。親告罪とは、被害者が告訴しなければ、警察も事件として捜査を行うことがない犯罪です。
なぜこうした罪が親告罪になっているのでしょうか。それは、事件が公にされることで、被害者自身も不利益を被るケースがあるからです。
警察対応の遅延に影響する技術的障壁とプライバシー問題
オンラインでの誹謗中傷事件における警察の発信者情報開示請求の遅延は、デジタル証拠の複雑な取り扱いと厳格な個人情報保護の必要性によるものが多いです。デジタルデータは伝統的な証拠と異なり、その保存、分析、そして法的な提示が困難なため、これらを処理する際には特有の技術的障壁が存在します。特に、個人情報の保護を規定する法的要件が捜査プロセスを複雑化し、警察の対応速度に影響を与えています。
この背景により、発信者情報の開示が遅れると、被害者は長引く精神的ストレスにさらされ、法的解決への道が遅れることが一般的です。その結果、被害の拡大を防ぎきれず、解決までの全体的な時間が長くなります。このため、デジタルデータの迅速かつ適切な処理と個人情報の保護は、効率的な捜査と被害者支援のバランスを取る上で重要です。
警察に相談するメリットはあるのか?
それでは、逆に誹謗中傷問題について警察に相談するメリットにはどのようなものがあるでしょうか。
警察は事件性がなければ動いてくれないものの、もし動いてくれた場合には、高い捜査能力に加えて、ネット犯罪を専門とする部署ももっていることから、個人で動く場合よりも情報の開示や事件解決がはるかにスムーズになります。
高い捜査能力で解決してくれる
ネットでの書き込みの中でも、明らかに名誉毀損など事件性があるとみられるケースで証拠なども揃っている場合は警察が捜査を開始してくれることがあります。
この場合の最も大きなメリットは、警察のもっている高い捜査能力が発揮されることです。
個人で行う発信者情報開示請求の場合、プロバイダの情報開示はプロバイダ責任制限法4条2項に基づくものになるため、請求を受けたプロバイダは相手に情報開示を許可するかどうかを尋ねることになります。この時、相手側が拒否すれば、基本的にプロバイダが情報を開示することはありません。
ネット犯罪の捜査を専門にしている部署がある
近年では、警察でもネット上でのハイテク犯罪に対応するべく、ネット犯罪に対応するための専門の部署が設けられています。
ひと昔前は、ネット上での書き込みなどでは、非常に悪質なものを除けば、警察はなかなか動いてくれないケースも見受けられましたが、現在ではこうした状況も変わってきたといえます。

相手が分からなくても刑事告訴できる
警察への刑事告訴は、個人で行う発信者情報開示請求や民事訴訟と異なり、相手の氏名などがわからない場合でも告訴を行うことが可能です。
通常、プロバイダへの発信者情報開示請求を行い、相手が拒否する意思を示した場合、次は裁判手続きにより情報の開示を求めることになります。そして、相手の氏名や住所が明らかになった後で損害賠償などの民事訴訟手続きに入ります。
民事訴訟では相手の氏名や住所の入った訴状を裁判所に提出する必要があるため、どうしても情報開示により相手の個人情報を知る必要があるのです。
しかし、刑事告訴は、特定の犯人に対するものではなく、犯罪行為に対して行うことができます。そのため、相手が情報開示を拒否している場合でも刑事告訴は可能となりますし、その後の警察の捜査で犯人が明らかになることもあります。
警察に相談しても捜査してくれないことも多い
警察に相談しても事件性がないとみられて動いてくれないことも多いです。警察としてもネット上のすべての誹謗中傷事件を一から捜査する余裕はないというのが実情です。
事件化したい場合でも、被害者側で証拠集めなど事前に準備を行ってから告訴する必要があります。
このプロセスには、スクリーンショットや通信記録、目撃者の証言など、具体的な証拠が必要とされます。さらに、警察が介入しにくい場合には、民事訴訟や弁護士を通じた発信者情報開示請求などの法的手段が有効です。
また、警察が捜査を行わない具体的な理由には、誹謗中傷が直接的な物理的危害につながらないと判断される場合や、具体的な犯罪行為としての証拠が不足している場合があります。警察のリソースも限られているため、緊急性や重大性が高い案件を優先する傾向にあります。このため、被害者は自身でできる予防策や対策を講じることが重要です。例えば、オンラインでのプライバシー設定を見直したり、デジタルフットプリントを管理することが挙げられます。
法律専門家や元警察官からのアドバイスも貴重で、彼らは警察が誹謗中傷事件にどのように対応するか、また被害者が取るべき適切な行動について具体的なアドバイスを提供することができます。これにより、読者は自分自身の問題に対してより具体的かつ効果的な対応を計画することが可能になります。
発信者情報開示請求は警察よりも弁護士に相談を
弁護士であれば、発信者情報開示請求の方法から開示を拒否された場合の訴訟手続きまで、それぞれのケースに応じて詳しく相談に乗ってもらうことができます。
こちらのほうが、民事での訴訟からから刑事告訴までとれる選択肢も増えますし、よりきめ細やかに対応してもらうことができます。
被告訴人不詳のまま刑事告訴を行う場合でも、事前に弁護士と相談して準備を整えておかないと、対応してもらえない可能性も出てきます。誹謗中傷問題は警察に相談するよりも、弁護士など法律の専門家に相談するようにするといいでしょう。

誹謗中傷問題を警察に相談するデメリットまとめ
ネットでの誹謗中傷問題について発信者情報開示請求をする前に警察に相談をしても、すぐに捜査してくれないなど徒労に終わる可能性のほうが高いと考えられるため、あまりおすすめできません。
誹謗中傷問題への対応を考えている方は、まずは弁護士など法律の専門家に相談することを検討してみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら