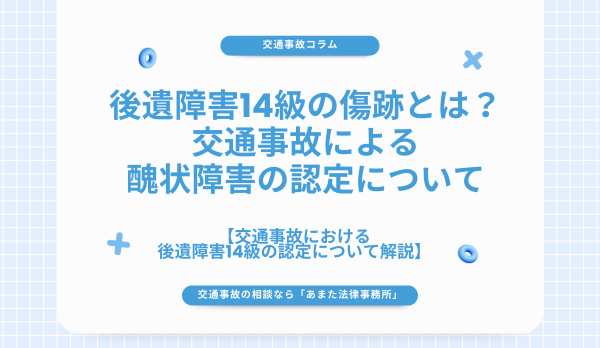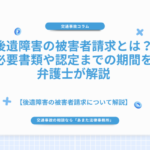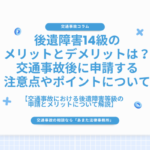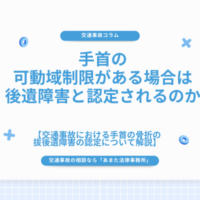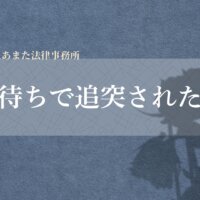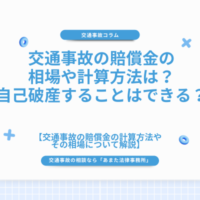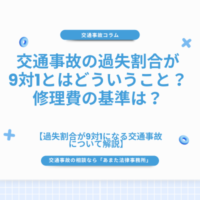交通事故でケガを負い傷跡が残ると、後遺障害等級が認定される可能性があります。特に、顔や首などの見た目に関わる部位に傷跡が残ったケースでは、「外貌醜状」として後遺障害14級に該当することが多いです。

交通事故後に傷痕が残ってしまった方や、後遺障害認定を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
後遺障害の14級になる傷跡とは?
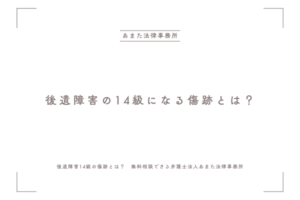
交通事故でケガをして、顔や体に傷跡が残った場合は「後遺障害14級」に認定される可能性があります。傷跡の場所や大きさによっては、将来にわたって見た目に影響が残るため、しっかり補償を受けることが大切です。
自賠責保険では傷跡(瘢痕)を「醜状障害(しゅうじょうしょうがい)」として後遺障害の1つに分類しており、14級として認定されることが多いです。
交通事故により、目立つ傷跡が残ると、醜状障害として
ただし、傷がどのくらい目立つか、どの部位にあるかによって、認定されるかどうかは変わってきます。
たとえば、事故によって顔に切り傷を負い、治療後もくっきりとした傷跡が残ったケースでは、「見た目に明らかに残る傷」として14級に認定された例があります。一方で、目立ちにくい場所や、日常生活でほとんど気づかれないような傷だと、後遺障害と判断されないこともあります。

傷跡に関する後遺障害14級の認定基準
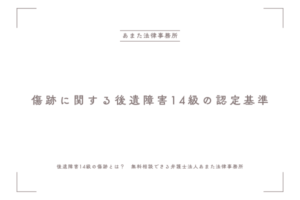
交通事故で傷跡が残った場合でも、すべてが後遺障害14級として認定されるわけではありません。
等級認定を受けるには、傷の部位や見た目の程度が、後遺障害等級表に定められた条件を満たしている必要があります。
傷跡に関する等級表では、対象となる部位を次の2つに分類しています。
・外貌……頭・顔・首。頭から首にかけて、日常生活で露出している部位。
・露出面……手・足。肩の関節から手の先までと足の付け根から足の甲までに当たる部位。
このうち、後遺障害14級に該当する可能性があるのは、主に「露出面」や、同等と判断される「胴体の一部」などの部位に残る傷跡です。たとえば、腕や脚に残った明らかな傷痕がこれに該当することがあります。
傷跡が後遺障害に該当するケース
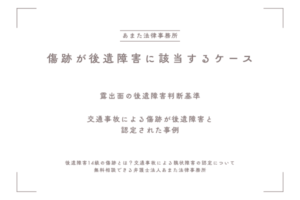
交通事故の傷跡が後遺障害の何級に該当するかの基準となるのが露出面です。14級と認定された傷跡の症例をチェックしていきましょう。
交通事故による傷跡が後遺障害14級と認定された事例
ここでは、実際に後遺障害14級またはそれ以上の等級が認定された傷跡の事例を3つ紹介します。
Aさんは横断歩道を渡っている最中に車にはねられ、左大腿骨を骨折し、右太ももに複数の傷跡が残るケガを負いました。治療後も明らかに目立つ瘢痕が残ったため、後遺障害等級の申請を実施。
審査の結果、右太ももの「手のひら大」の瘢痕が露出面に該当すると判断され、後遺障害14級5号が認定されました。
Bさんは、横断歩道を歩いていたところ、車に衝突される事故に遭ってしまいました。特に右足のケガは酷く、骨折のほか、いくつもの傷があり、皮膚移植が必要になるほどでした。1ヶ月近い入院に加えて1年ほどリハビリが続き、治療は終了。歩けるようにはなったものの、膝から下には線状の傷が、また太腿には移植による傷跡が残ってしまいました。
露出面の傷跡による後遺障害の認定では傷の大きさが問題になります。手のひらと同じくらいの大きさなら14級ですが3倍なら12級相当となり、受けられる補償が大きく変わってくるのです。Bさんの場合は、移植が必要なほど大きなケガだったため、最終的に12級相当が認められました。
Cさんは交通事故の現場近くを歩いていた際、事故車両に巻き込まれ、腕に火傷を負いました。火傷の治療後も皮膚に明らかな痕跡が残ったため、症状固定後に後遺障害等級の申請を行いました。
審査の結果、「人目に触れる部位(腕)」に火傷痕が残っていたことから、14級4号が認定されました。Cさんは直接車と衝突したわけではありませんが、事故によって受けた間接的な傷でも、等級が認定されるケースがあることがわかります。
露出面の後遺障害判断基準
後遺障害として認められる傷跡の露出面は、上肢(肩から手の先)と下肢(足の付け根から足の甲まで)に関するものに分かれています。そして日常生活で露出しない部分でも、相当として障害が認められる場合があります。
- 上肢の露出面に手のひら大の酷い傷跡が残った場合。
→14級4号 - 下肢の露出面に手のひら大の酷い傷跡が残った場合。
→14級5号 - 上肢または下肢の露出面に手のひら大の3倍以上の傷跡が残った場合。
→12級相当 - 胸、腹の全面積または背中、お尻の全面積に2分の1以上の傷跡が残った場合。
→12級相当 - 胸、腹の全面積に2分の1以上、または背中、お尻の全面積に4分の1以上の傷跡が残った場合。
→14級相当
後遺障害の外貌醜状とは?
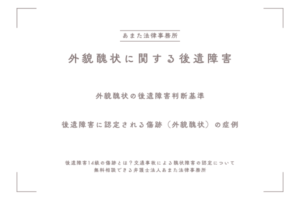
14級以上の後遺障害と認められるのが、「外貌醜状」です。外貌醜状は頭や顔、頸部などに火傷の傷跡といった「一定の瘢痕」または「線状痕(線状の傷跡)」を醜いあとを残すケースをいいます。
事故による傷跡だけでなく、その後の手術等によって生じた傷も後遺障害の対象に含まれます。
外貌醜状の後遺障害判断基準
外貌醜状の程度にはいくつかの種類があり、それぞれ等級も異なります。
著しい醜状 7級12号
- 頭部に手のひら大以上の傷跡または手のひら大以上の頭蓋骨欠損が生じた場合。
- 顔に鶏卵大以上の傷跡または10円玉大以上の陥没が生じた場合。
- 首に手のひら大以上の傷が生じた場合。
相当程度の醜状 9級16号
- 顔に5cm以上の線状痕が残った場合。
外貌の醜状 12級14号
- 頭に鶏卵大以上の傷跡または頭蓋骨に鶏卵大以上の欠損が生じた場合。
- 顔面に10円玉大以上の欠損または3cm以上の長さとなる線状痕が生じた場合。
- 首に鶏卵大以上の傷跡を残す場合。
手のひら大は被害者の手のひらの大きさを基準にしており、タテは薬指の付け根から手首の上端、ヨコは親指の先から手のひらの側端となります。手の全面から指を除いた大きさと言えば、わかりやすいでしょうか。手の大きさは個人差がありますから、後遺障害として認められる面積は人によって違ってきます。
また、鶏卵大は鶏の卵ほどの大きさを指し、タテ5cm×ヨコ3cmの15㎠ほどの面積が目安です。
後遺障害に認定される傷跡(外貌醜状)の症例
交通事故で顔に傷が残ってしまった場合、その傷が「外貌醜状」として後遺障害に認定されることがあります。
具体的には、次のようなケースがあります。
- 交通事故による顔面挫傷で1年間の通院後に症状固定となったが、眉間から左の目にかけて5cmを越える傷跡が残ってしまった。
→相当程度の醜状:9級16号 - 事故を原因とするケガで額に斑点上の瘢痕(鶏卵大以上の面積)が残ってしまった。
→著しい外貌醜状:7級12号 - 事故のため、左眉に3cmほどの擦れたような傷が残り、その部分は眉毛も生えなくなってしまった。また、傷跡の部位はケロイドのようになり、ひきつれた感覚も残っている。
→外貌の醜状:12級14号
このように、傷の位置や大きさ、残り方によって認定される等級が変わってきます。
顔に残る傷は、見た目だけでなく、気持ちや対人関係にも関わる重要な問題。事故後に傷跡が残った場合は、きちんと後遺障害の申請を行い、正当な補償を受けることが大切です。
傷跡で後遺障害等級が認定されるまでの流れ
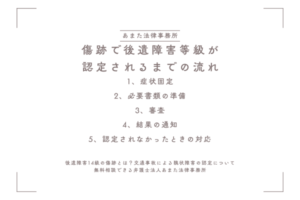
交通事故のケガによる傷跡で、後遺障害の等級認定を申請する流れを解説します。たとえ後遺症が残っていたとしても、申請が通らなければ障害補償給付は受けられないので気を付けましょう。

1、症状固定
後遺障害の申請は「症状固定(治癒)」後に行います。症状固定とは、これ以上治療を継続しても、傷跡が改善しない状態を指します。医師から症状固定の診断をもらうまでは診断書の作成も行ってもらえないため、後遺障害の申請も行えません。
2、必要書類の準備
後遺障害の申請に必要なのは、「後遺障害診断書」などの書類です。
障害を証明できる画像も有効ですので用意しておきましょう。
労災では請求書も必要になります。請求書は厚生労働省のホームページからダウンロードできるので、必要事項を記入してください。業務災害の場合は「障害補償給付支給請求書(様式第10号)」を、通勤中に起きた事故の場合は通勤災害用の「障害給付支給請求書(様式第16号の7)」を使用します。
また、必要書類のほかに今後の生活への影響など、治療をした病院の医師が所見を記載した「意見書」も添付すると効果的です。
3、審査
後遺障害診断書などの書類を自賠責保険会社に提出すると、審査が行われます。
申請方法は被害者が自分で行う被害者請求と加害者側が加入していた保険会社が代行する事前認定があります。
審査は書類で行われるのが基本ですが、醜状障害では面接が行われることもあります。後遺障害14級に該当する程度なのか、人の目で確認するためです。ただ、全ケースで行われるわけではなく、省略されることも増えています。
4、結果の通知
審査から1か月~2か月で結果が通知されます。
被害者請求では自賠責保険会社から自賠責保険金が支払われ、事前認定では保険会社から賠償金が一括で支払いされます。
5、認定されなかったときの対応
申請をしたけれど認定されなかったときは、3つの方法で対応することになります。
異議申し立て
まず、利用したいのが異議申し立てです。異議申し立ては何度でも可能ですが、書類の不備など不満足な結果となった理由を精査しないと結果は覆りにくいので気を付けてください。
紛争処理制度
紛争処理制度は、後遺障害認定の結果が出たあとか、異議申し立ての結果が出たあとに行います。1度しか利用できませんので、安易な利用はしないようにしましょう。確実に成功するためには、後遺障害や法律に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。
訴訟を起こす
訴訟は異議申し立てや紛争処理制度を利用しても、結果に納得できないときに選択します。14級の後遺障害にも該当しないとされた傷跡でも、裁判所が独自の等級を判断しますので、当初とは違った結果になる可能性はあります。

後遺障害等級認定で気を付けたいポイント
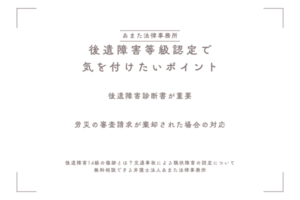
後遺障害の認定を受けようとしても、必ず認められるわけではありません。傷跡の後遺障害が認められるだけでは、慰謝料が受け取れるわけではないため注意が必要です。慰謝料を受け取るには、相手方に対し損害賠償金を請求する必要があります。
そこで、後遺障害の申請を行う際のポイントをおさえておきましょう。

後遺障害診断書が重要
後遺障害等級の認定で重要になるのが、事故と障害の医学的な因果関係を証明するための後遺障害診断書です。後遺障害診断書は医師しか作成できないため、担当医にしっかりと記載してもらう必要があるのです。
しかし、なかには診断書の重要性をよく理解していない医師もいるのが現状です。また、稀なケースではあるものの、診断書を書いてくれない医師も存在します。「本当にこの後遺障害診断書でいいのか」「診断書をきちんと書いてもらえない」といった不安があれば、交通事故に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。
労災の審査請求が棄却された場合の対応
労災の後遺障害認定では審査請求も棄却されてしまった(または3か月以内に審査請求の結果が出ない場合)ときは、「再審査請求」か「行政訴訟」が可能です。
・再審査請求……裁判における2審に相当するものです。審査請求を棄却する決裁の通知書が送付された日の翌日から2か月以内に、労災保険や雇用保険の給付処分に対する不服審査を実施している「労働保険審査会」に対して再審査請求を行います。
審査会では、3名の審査員による審理が実施され、再審査請求が妥当と判断された場合は原処分(最初の後遺障害申請に対する不支給決定)の一部または全部の取消を行い、逆の場合は再審査請求が棄却されます。
ただ、再審査請求の判断基準も審査請求と基本的には同じであるため、新しい証拠などを提出しない限り、審査請求と異なる結果が出る可能性は低いと考えられます。
・取消訴訟……裁判所に対して原処分や審査請求・再審査請求の決裁に対する取り消しを求めて訴訟を提起する方法です。訴訟は各審査の結果を知ってから6か月以内に実施する必要があります。
裁判所ではこれまでの申請や審査請求では認められなかった結論が出される可能性があります。訴訟は個人での対応が難しくなるため、弁護士などに相談するようにしましょう。
傷跡による後遺障害の認定は弁護士に相談
後遺障害の認定手続きは書類を揃えるなど、複雑で簡単ではありません。適切な等級を受けるためには、弁護士に相談するのが良いでしょう。
交通事故に詳しい弁護士がいれば、ケースに合ったアドバイスをしてもらえます。書類に記載漏れはないかなどの不備も確認してくれます。さらには認定されなかったときの対応や慰謝料の請求など、多方面にわたるサポートが受けられます。
弁護士に依頼すると費用が気になるところです。目安は以下のようになります。
・着手金……10万円~。弁護士に正式な依頼をすると発生する費用。
・成功報酬……経済的利益(弁護士の介入により得られた利益)の10~30%(+数万円)。弁護士への依頼内容が成功した場合に支払う費用。
・その他の費用……弁護士の交通費や通信費、事務所外で活動した場合の日当など。基本的に実費で請求される。
弁護士は心強い味方になってもらえるものの、依頼すれば最低でも十数万円の費用がかかってきます。お金の問題が気になって、弁護士に相談したくてもなかなかできないと思っているケースもあるでしょう。
ただ、弁護士費用を節約する方法はあります。
相談は無料とする法律事務所であれば、気軽に利用できるでしょう。また「弁護士費用特約」の利用を検討するのも賢いやり方です。
弁護士費用特約(弁護士特約)は、任意で加入する自動車保険に付いてくるオプションの1つです。事故の際、弁護士への相談・依頼の費用を補償してもらえるサービスです。
補償金額は原則として弁護士費用なら300万円、相談費用なら10万円までとなっており、よほど大きな事故でなければ弁護士費用の負担が0円で済むと思って良いでしょう。
弁護士特約を使えば、費用面を気にすることなく弁護士へ相談・依頼ができます。弁護士特約は家族の加入している保険でも適用されることがありますし、クレジットカードや火災保険等にも付帯していることがあります。ぜひ使えるものがないか確認してみてください。
後遺障害の14級の傷跡についてまとめ
交通事故による傷跡が上肢や下肢、腹部にあれば、後遺障害14級に該当する可能性があります。きちんと申請を行い、後遺障害等級の認定を獲得しましょう
ただ、後遺障害は申請すれば必ず認められるわけではなく、不支給になる可能性も高くなっています。後遺障害の申請方法がわからない、申請したけど審査結果に納得できないといった疑問や悩みを解決したいなら、弁護士に相談してください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ