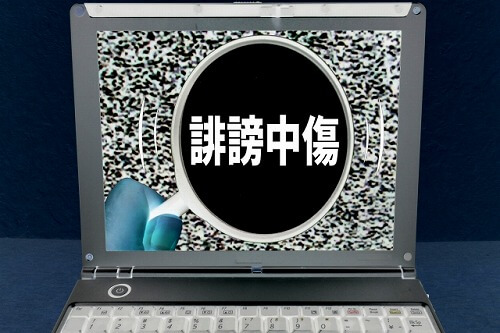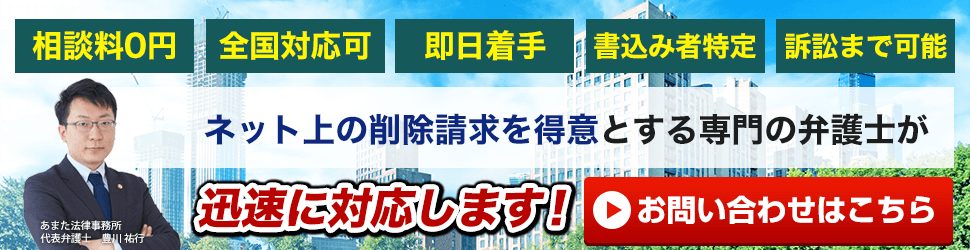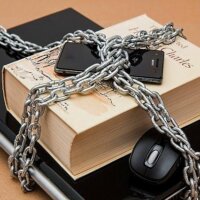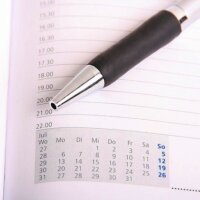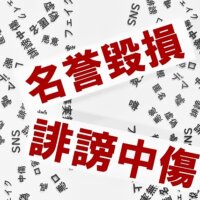インターネット上で誹謗中傷はなぜ起きやすいのか、それは、匿名性が高いという特徴が大きな理由になっています。
SNSや掲示板への投稿は実名ではなく匿名のため、誰が発信しているのかわかりにくく、悪意のある文言も言いやすいという特徴があります。

この記事の目次
誹謗中傷を助長するインターネット世界の特徴
インターネットで誹謗中傷が生まれやすい理由は、主に匿名性、集団心理、正義感の3つが影響していると考えられています。
匿名性の保障
インターネット世界の特徴に「匿名性」の保障があげられます。匿名性とは発言した人の身元が分からないシステムです。
Facebookなど実名を載せるSNSもありますが、X(旧Twitter)を含めたほとんどのSNSは匿名で書き込みをするのが一般的ですし、匿名掲示板も多くあります。
匿名は投稿者の個人情報が流出しにくいメリットがありますが、責任の所在が曖昧になってしまうデメリットが生じます。匿名の世界では発信者の特定は困難であり、身元がバレないなら何を言っても責任がなく許されると誤解しがちです。

集団心理の発生
インターネットは「みんなが誹謗中傷しているなら自分も許されるのではないか?」という「集団心理」が生まれやすい世界です。
ネット社会には誹謗中傷を書き込む人が多数いるのが現状です。他人を批判し貶めることで快楽を得ようとする人も中には一定数存在しており、「赤信号みんなで渡れば怖くない」という同調に便乗し誹謗中傷するケースも多々見られます。
正義感の強要
SNSや匿名掲示板などに攻撃的な書き込みをしている人の大多数は、自分は正しく相手が間違っていると考えています。
「許せない、失望した」といった感覚をベースに、「悪い事をした人は報いを受けるべきだ」「人に迷惑をかけた人間を徹底的に罰しなければいけない」という感情が生まれ、行き過ぎた正義感を持ってしまい相手を攻撃し始めます。
例えば、コロナウイルスに罹患した事を隠し高速バスに乗車した女性に対し、インターネット上で誹謗中傷が集中しました。実名や顔写真、SNSアカウント等が晒されるという事件が起きています。
誹謗中傷を行った人たちの心情は未知のウイルスに対する恐怖のほか、「相手に落ち度があるのだから叩かれて当然だ」という正義感が働いていたと想像できます。
誹謗中傷はなぜ起こる?なくならない理由
なぜ誹謗中傷はなくならないのかですが、本人は知らずに誹謗中傷しているという理由もありますが、法制度の問題も指摘されています。
誹謗中傷している自覚がない
誹謗中傷がなくならない理由として大きいのは、発信者自身が「誹謗中傷している自覚がない」点です。自分が誹謗中傷したと自覚があった人は2割程度しかなかったという調査もあります。
自分が持っている正しさや常識に反する価値観を持った人に攻撃的になってしまう人はたくさんいます。
たとえば、親が未婚の子どもに対し「結婚できないのはクズ人間」などひどい言葉を投げつけることがあります。結婚することが常識と考える親にとっては、子どもが未婚であることが許せないという理由から発せられた言葉です。人格否定された子どもが傷ついたとしても攻撃的な発言をした本人には悪いことを言ったという自覚はなく、むしろ「正しいことをしている」と勘違いしているケースがあります。

法制度の問題
ネット上で誹謗中傷した加害者を特定する法制度にはまだ課題が多いと言えます。
加害者を取り締まるには、加害者の身元特定が必須になります。現行法では、発信者情報開示請求で加害者を特定することが可能です。
しかし、情報開示請求の制度は複数の裁判手続きを踏む必要があります。多くの時間と費用を要してしまうことから、被害者の全てがこの制度を有効に利用できるとは限りません。
加害者の視点からすると、被害者が「わざわざお金と時間をかけて法的措置は取ってこないだろう」と考えるのが普通です。また、そもそも犯人を特定する制度を知らず、匿名なら法的に罰せられることはないと思っているケースもあります。こういった理由から、法律はあれど誹謗中傷の減少につながっていないと言えるでしょう。
誹謗中傷を減らす方法
誹謗中傷を減らすには一人ひとりの心構えや、社会の動きが必要になります。
自分が誹謗中傷されたときを考えてみる
SNSや掲示板に書き込みする前に、自分が言われると嫌な気持ちにならないか、相手へのリスペクトが欠けていないか一度振り返ってみましょう。
感情的にならず相手への尊重を忘れなければ、誹謗中傷を書き込むような行動はしません。怒りを覚えた時や自分が正しいと思った時は、投稿する前に一呼吸置くことが重要です。

法律の改正を期待する
現在、政府は誹謗中傷の加害者を特定しやすくする法整備をおこなっています。現行法でも誹謗中傷の被害を受けた際は、発信者情報開示請求によって発信者を特定することで訴えを提起することができます。
発信者情報開示請求はプロバイダ責任制限法によって規定されている制度です。IPアドレス・タイムスタンプの開示請求をした後に氏名・住所などの開示請求を行うことで、発信者の身元の特定が可能になります。
しかし、これらの開示請求は裁判上の手続きになります。最低でも2回の裁判手続が必要になり、費用と時間がかかってしまうのがデメリットで、投稿者の特定だけで半年以上かかるケースは少なくありません。
そこで、ネット中傷による被害をより簡易的に救済する取り組みがされ、改正プロバイダ責任制限法が2022年10月1日から施行されました。新しい手続では複数回の手続を取る手間が簡略化され、1つの手続きで投稿者の情報開示を求められるようになっています。
裁判所が必要と判断すれば判決というプロセスを経ることなく、コンテンツ事業者等に対し発信者が使用したアクセスプロバイダ等の情報提供を命じることが可能になったのは、被害者にとっては朗報でしょう。
段階的に行ってきた複数の手続を同時並行で行える状況になり、相手の情報を開示しやすくなりました。裁判の手間や時間の緩和が期待できます。
参考:法務省・プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律(概要)
参考:法務省・インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)
誹謗中傷の被害を受けたときの対処法
誹謗中傷の被害に遭ったら、すぐに対策を講じてください。その理由は一度SNSや掲示板などネットで情報が拡散してしまうと、傷ついた名誉が取り戻せなくなるリスクがあるからです。自身での対処が難しいと感じたら、弁護士に相談するのがよいでしょう。
誹謗中傷は法律に触れる行為であり、裁判に発展してもおかしくありません。裁判を有利に進めるためには証拠が不可欠ですので、投稿されたページをURLつきで印刷する、スクリーンショットをとるなどして、該当の書き込みを保存しておきます。
誹謗中傷の書き込みを見つけたら、すみやかに削除を依頼します。誹謗中傷のコメントがいつまでもネット上に掲載され誰でも閲覧できるようになっている限り、権利が侵害され続けることになるためです。
多くのサイトでは削除請求用の問い合わせフォームを用意しています。専陽フォームから依頼すれば、削除に対応してもらえる可能性があります。ただし、
請求に応じるかはサイト運営や管理者の判断次第になるため、必ずしも削除されるとは限りません。
運営側が削除依頼に応じない時は、裁判所に削除請求の仮処分を申立てます。
仮処分が認められると、裁判に勝ったときの判決と同様の効果が発生します。仮処分は判決までにかかる時間が通常の裁判より短いため、迅速な処理が可能になります。
誹謗中傷の発信者を訴えたいときは、書き込みを行った犯人を特定する必要があります。
投稿者を特定するには、コンテンツプロバイダ(インターネット掲示板などのサイト運営者等)にIPアドレス・タイムスタンプを開示請求します。
さらに、経由プロバイダ(ISP[携帯のキャリアなど])に対し、IPアドレス・タイムスタンプの利用者の氏名や住所の開示請求を行い加害者を特定します。
投稿者の個人情報を特定すると、民事裁判による損害賠償請求や刑事告訴による刑事責任追及が出来るようになります。
しかし、仮処分も含めて裁判手続きを進めるには、法律の知識を持っていなければ難しいのが実情です。個人での対応は大変と言えるでしょう。誹謗中傷の被害に遭って訴訟を考えているけど裁判の進め方がわからないのであれば、インターネットのトラブル解決に強い弁護士に相談するのがおすすめです。

まとめ
匿名性が高いインターネット上では、罪の意識を持たずに誹謗中傷している人が多い面があります。また、罪に問われないと思っているケースも多いです。
悪質な書き込みを取り締まるための法整備は進んではいますが、さらに誹謗中傷の減少につながるような改正が期待されます。
もし、誹謗中傷の被害にあったときは、被害が拡散を防止する対策が大切になります。困ったときは弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら