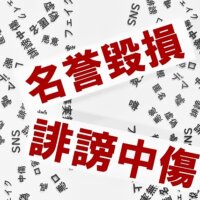ネット上の誹謗中傷は「オンラインハラスメント」「サイバーいじめ」などと呼ばれ、民事上の責任や名誉毀損罪、侮辱罪などの刑事上の責任を負う可能性があります。

執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
なぜインターネットで誹謗中傷するの?SNSの世界で起こっていること
いいねやリツイートなどとは違う、SNSのもうひとつの側面(自分の思いを発信できることが快感に)
今は、Twitter、Instagram、Facebook、ブログ、LINEなど、様々なSNSから情報発信ができます。自分の思いを発信することで「他者承認欲求」が生まれると言われています。
そもそも「承認欲求」とは、他人に認められたい、自分の考えを理解してほしい、自分に満足したいなどの欲望をいいます。
これはアメリカの心理学者アブラハム・マズロー氏による「マズローの欲求5段階説」で4つ目に登場します。「人間は自己実現に向かって絶えず成長する生きものである」と仮定し人間の欲求を5段階に分類したものです。
承認欲求には、大きく分けて「他者承認欲求(低位の承認欲求)」と「自己承認欲求(高位の承認欲求)」とがあります。
「他者承認欲求」は、他人に認められたいと思う欲求を指します。一方で「自己承認欲求」は、自分が自分を認めたいと思う欲求を指します。

SNSの利用状況と目的
SNSは、自分の思いを発信することに加え、人との繋がりをが実感できるツールと言えます。
ICT総研(2020年度)の調査では、日本のSNS利用者は7,975万人(普及率80%)、LINE利用率は77.4%、Twitter 38.5%、Instagram 35.7%となっています。
このうち、 SNSの利用目的は、「知人の近況を知りたい」が43%、「人とつながっていたい」が33%を占めています。
誹謗中傷している人の心理
SNSでは匿名で発信できるため、抑制が外れて日頃のストレスや怒りが抑えられなくなり、攻撃的な投稿をしてしまうことがあります。心理学では「没個性化(ぼつこせいか)」と呼ばれています。
「没個性化」とは、心理学者・ジンバルドー氏によって唱えられたもので、心理的なハードルが下がり、行動に対する責任感が低下することをいいます。
ジンバルドー氏は、匿名性が保証されているとき、または責任が分散されているときは、自己の言動をコントロールする能力が低下し、「没個性化」が生じると説明しています。また、没個性化は群集心理により、周囲が同じような言動を取る可能性が高いとも指摘しています。
このように、匿名性が担保されていると、人は攻撃的になってしまうことがわかります。
「フラストレーション攻撃仮説」とは、1930年代末にJ.ダラード氏とN.E.ミラー氏によって唱えられたもので、人は、何らかの欲求不満によって、攻撃衝動を起こしやすくするという仮説です。
SNSの誹謗中傷としては、ストレスや不満を特定の者に攻撃することによって発散させていると考えられます。
SNSでは、誰かが発信すると瞬く間に投稿した内容が拡散される可能性があり、それに同調するといった現象がたびたび起きています。
最初は、集団で誹謗中傷するのではなく、1人の投稿が群集心理によって広がり、同じようなネガティブな投稿がどんどん連鎖的に増えていくといった状態です。
これらの現象は、責任の所在がはっきりとしないため、たとえ根拠のない投稿であっても、安易に拡散されているといったデメリットもあります。

いじめやSNSの誹謗中傷が起きているにも関わらず、それを止めようとせず、極力関わらないようにしている人もいます。
なぜなら、このようなトラブルに関わると、今度は自分がターゲットになるのではないかと思い、あえて見て見ぬふりをした方が合理的な行動になると考えるためです。
このような一連の現象を「傍観者効果」といいます。「傍観者効果」とは、救助すべき者がいる状況において、傍観者が多数いることで行動が抑制される集団心理現象のことをいいます。
傍観者効果の有名な事件として、1964年に起きたキティ・ジェノヴィーズ事件があります。
キティ・ジェノヴィーズという女性が殺害された事件ですが、38人の目撃者がいたにも関わらず、誰ひとりとして警察に通報することはなかったとされています。
日本では、1985年に豊田商事会長刺殺事件で、犯行中に集まっていた記者は誰も警察に通報しなかったことが議論となりました。
日本人は、思いやりや気遣いを大切にするため、相手を傷つけたり、否定することが得意ではないといった特有の心理的要因もあります。
しかし、SNSでは相手の顔が見えず、誹謗中傷している加害者も匿名であるため、どうしても配慮に欠けた投稿内容になってしまう傾向があります。
誹謗中傷する人の心理的特徴
コンプレックスと嫉妬
自分の能力と他人を比較して劣等感を持つ人がいます。経済力、学力、容姿など、他人への嫉妬から誹謗中傷につながることがあります。
SNSで成功者やトップアスリート、芸能人などの投稿内容を見て、嫉妬心が生まれ、嘘の内容や嫌がらせ目的で投稿するといった悪質なケースもあります。
ストレスや鬱憤のはけ口に
中には、リアルの世界で何をやってもうまくいかないため、ストレスのはけ口としてネット上で誹謗中傷する人がみられます。

ゆがんだ正義感を持つ
誹謗中傷する加害者は、相手がどう思うかを理解せず、ゆがんだ正義感を持っていることがあります。
例えば、炎上したアカウントを特定し、執拗にプライバシー情報を晒してしまうケースです。悪意ある言葉は、凶器にもなりえます。一方、悪質な投稿をした人が、別の投稿者から誹謗中傷されるといった被害の連鎖が起きることもあります。
自分の優位性を確保する
誰かを誹謗中傷することで、優位性を確保するケースもあります。これは、人間の本能として「他者承認欲求」があるため、誰かの優位に立ちたいという欲求から生じます。
そのため、他人と比較しながら、自分の位置を確認したり、炎上した人物を攻撃することによって、優位性を確保するなどが挙げられます。
また、SNSでは学歴や経済力で相手を見下すような、いわゆる「マウントを取る」というようなケースもあります。
愉快犯による便乗
自分の行為が正しいと思い、相手への攻撃を続けることにより、相手からの反応を楽しむという愉快犯であるケースです。必要以上に相手すると、どんどんエスカレートする可能性が高くなります。
匿名性と集団心理によるエスカレート作用
SNSは匿名性が高く、書き込んでも特定されないという安心感から、相手への誹謗中傷が過激化するケースです。

誹謗中傷を受けたらどうする?
ネット上の誹謗中傷は、できることなら相手にしないのが一番です。無視を続けることによって、いずれ誹謗中傷がなくなる可能性も十分にあります。
しかし、攻撃がエスカレートする場合もあるので、事態が悪化する前に法律専門家の弁護士に相談することをおすすめします。
各サイトの専用フォームやメールフォーム、SNSの管理者に任意の削除依頼をする方法があります。
削除に応じてもらえなければ、サイト管理者やプロバイダへプロバイダ責任制限法(正式名称:「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)に基づく発信者情報開示請求を行います。
SNS上ではアカウントが削除されても「捨て垢(すてあか)」と呼ばれる、別のアカウントで攻撃を続けるといったことも考えられます。
被害者は相手を特定した上で、損害賠償請求を行うケースも多くあります。
いずれにしても、発信者情報開示請求や加害者の特定なども、専門の法律知識が必要です。
加害者へ責任を追求するには、民事上の損害賠償請求や刑事上の犯罪等(名誉毀損罪、脅迫罪、侮辱罪など)で刑事告訴するとも考えられます。また、情報開示に、現時点では最低2回の裁判が必要となります。

インターネットでの誹謗中傷まとめ
ここまで、インターネットやSNSで誹謗中傷する加害者の心理はどのようなものなのか、心理的な特徴から誹謗中傷を受けた場合の対処法を解説しました。
加害者は、日頃のストレスや鬱憤のはけ口として、ネット上に誹謗中傷する傾向がありますが、表現の自由があるからといって、何でも投稿しても良いわけではありません。相手の気持ちを考えながら、慎重に投稿することも大切です。


2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ