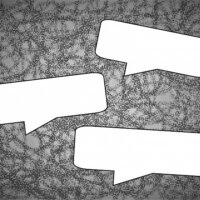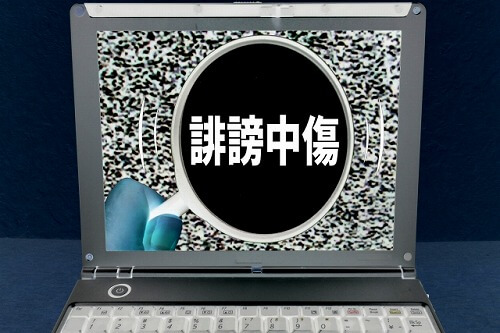最近、社会的な注目を集めるようになったネットでの誹謗中傷。実際に自分が被害者になった場合、どう対応すればいいのでしょう。

ネットで誹謗中傷を受けた場合の効果的な対策と現在の法制度を紹介
ネット上で匿名掲示板をはじめ、Facebook、Twitter などのSNS、YouTubeのような動画サイトなど、様々なメディアが発達している昨今、企業・個人に関わらず、誰もが誹謗中傷の被害者になりえます。
もし、そうした行為を受けてしまった場合、どのような対策をとればいいのか、現行の法制度を含めて解説していきます。
インターネット上での誹謗中傷とは何か
誹謗中傷とは根拠のないデタラメな内容で他人を非難したり、悪口を言う行為を指し、匿名で書き込みができるネット上では特に起こりやすいとされています。
はじめに、誹謗中傷の具体例と法的にどういった違法行為に該当するかをみていきます。
法的にはどういった違法行為に該当するのか
民事上の責任として、名誉毀損等による損害賠償責任、記事の削除に応じる必要があります。
また、民事上の責任の他に、刑事上の責任もあります。具体例としては、名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪、威力業務妨害罪などに該当する可能性があります。
名誉毀損は事実に基づき相手の名誉を侵害した場合に、侮辱罪は「きもい」「死ね」など単なる悪口を言った場合に適用されます。
嘘の情報で他人の信用を貶めた場合は信用毀損罪に。「店に爆弾を仕掛けた」と脅すた場合など、威力を用いて他人の業務を妨害すれば威力業務妨害になります。

SNS(FBやTwitter)を使った誹謗中傷の事例
- Twitterの匿名アカウントで特定の人物に対して「バカ」「きもい」など悪口を投稿した。
- 芸能人のSNSアカウントに「性格悪い」「死んだらいいのに」など中傷するコメントを送った。
- 就活で不採用になった企業のことを「ブラック企業」といってSNS上に悪口を投稿した。
- FBで自分が利用した飲食店を「まずい」「店員の接客が最低だった」などと非難する投稿をした。
誹謗中傷への効果的な対策方法とは?
実際に、ネットでの誹謗中傷の被害に遭ってしまった場合、どういった対応をとればいいのでしょうか。
ネットの誹謗中傷は初動が大切
ネット上で悪質な書き込みや投稿による被害を受けた場合、初動での対応を間違えないことが重要です。
まずは問題となる書き込みの記録・保存を行い、きちんと証拠を残すようにしましょう。その後、書き込みの削除請求や訴訟のための加害者の情報開示請求などを行います。
ネットの書き込みは投稿者自身が消去することも可能なため、証拠を残しておかないと、犯人の特定や訴訟になったとき、自分が不利になったり請求自体が難しくなってしまいます。
証拠を保存するには以下の方法があります。
- 画面に書き込みを表示してプリンターで印刷する。
- スクリーンショットとしてスマホやパソコンに保存する。このとき、URLと日時も同じ画面内に入るように。
- カメラ等で画面を撮影する。
- YouTube動画などの場合は、動画ダウンロードソフトやアプリを使って保存する。
しっかりと証拠を残した後は、サイトやSNSの管理者に書き込みの削除を依頼します。
不快な投稿はすぐにでも消してほしいところですが、先に削除してしまうと証拠が残らなくなるため、絶対に記録を残した上で請求を行うようにしてください。
しかし、サイト運営者が削除してくれない場合やそもそも削除依頼のフォーム自体が存在しないサイトもあります。

誹謗中傷は刑事上での様々な罪に問われるのみでなく、民事上においても不法行為に対する慰謝料や損害賠償請求の対象になります。
訴訟を起こすためには、プロバイダに発信者情報開示請求を行い、加害者の名前や住所などの情報を知る必要があります。
風評被害について 誹謗中傷を放っておくとどうなるか
書き込みの削除には、様々な手続きが必要なため、面倒に感じることもありますが、誹謗中傷を放置しておくのは風評被害につながるおそれがあるため危険です。
嘘の投稿であれば相手にする必要はないと考える方もいるかもしれません。しかし、ネットでは根拠のない投稿であっても拡散して、あなたやあなたの会社のイメージやブランド、信頼性を損なうおそれがあります。
風評チェッカーについて
風評チェッカーとは、企業や個人の名前を入力すると、Google やYahoo! で検索するときに表示されるサジェストや関連ワードにネガティブなワードが入っていないかや掲示板、質問サイトなどに誹謗中傷の書き込みがされていないかをチェックできるサイトです。
風評被害を出さないため、ネット上に誹謗中傷する書き込みがないかを見つけるときに有効なツールです。
誹謗中傷に遭った時はどこに相談すればいいのか
被害に遭った場合の相談先の一つにサイバー警察があります。警察のネットやコンピュータに関するハイテク犯罪を専門に扱っている部署で、誹謗中傷にも対応しています。
いきなり警察に通報するのが難しい場合は、警察相談専用電話の「#9110」に電話すれば警察署に足を運ばなくても、警察に相談することができます。

法的手段をとる場合は弁護士など専門家に相談を
誹謗中傷に対する損害賠償の請求のため、発信者への訴訟を行う場合や、裁判所に削除請求の仮処分を申し立てる場合など、法的な手続きで個人や企業では対応が難しくなりそうなときは、弁護士など法律の専門家に相談するようにしましょう。
削除請求や誹謗中傷問題を専門にしている弁護士もいますので、心強い味方として相談に乗ってもらえるはずです。
誹謗中傷に対する現在の法制度について
2020年3月現在、日本の法律では、誹謗中傷は正式な法律用語ではないため、どのような行為が該当するかの基準が明確になっていません。
そのため、最近の誹謗中傷問題への社会的な関心の高まりを受けて、法律の整備を進める動きが出ています。
法制度の見直し
ネット上での誹謗中傷に対する厳罰化を求める声が高まっており、署名運動なども行われています。政府は投稿発信者の特定をやりやすくする制度の創設、軽すぎるといわれる侮辱罪の厳罰化など法制度の改正を行う方針です。
警察庁でも、2021年4月からスタートする第4次犯罪被害者等基本計画のなかに、初めてネット中傷へ対策を取り入れました。
表現の自由との兼ね合いからこうした動きに反対する意見もありますが、ネット上の誹謗中傷取り締まりに力を入れていく方針をとっており、これからも厳罰化の流れは続いていくとみられます。
発信者情報の開示について
法制度の見直しに関して、総務省では、悪質な書き込みの発信者を特定しやすくする新しい制度の創設を決めています。
これまで、投稿の発信者を特定するには、プロバイダ責任制限法第 4 条に基づく発信者情報開示請求を行う必要がありましたが、手続きに時間がかかるため、被害者の負担になっていました。
新たな制度では、開示請求が簡略化され、裁判に寄らなくても裁判所の判断でプロバイダに情報開示を命じることができるようになります。
これによって、たとえ匿名であったとしても安易な書き込みはできなくなったといえます。
まとめ
ネット上での誹謗中傷は拡散しやすく、放っておくと取り返しのつかない被害を起こすことがあります。
嘘の書き込みだからと甘く見ないで、早い段階から正しい処置をとるようにしましょう。