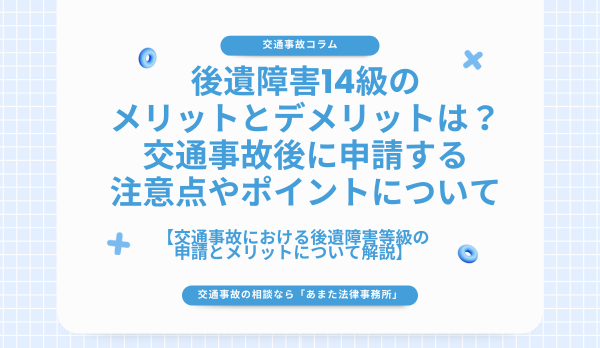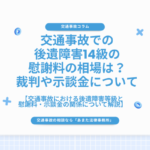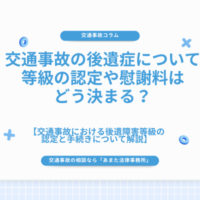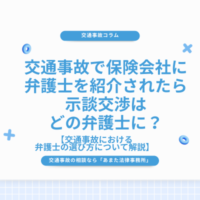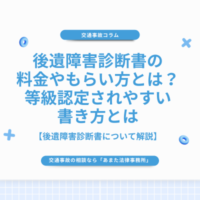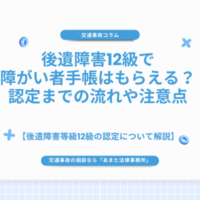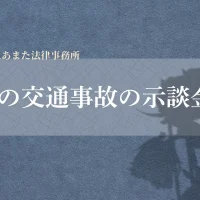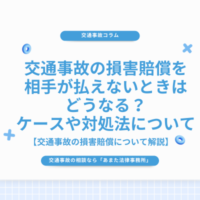後遺障害14級のように比較的軽度な等級であっても、申請するメリットは十分にあります。
たとえ軽い後遺症であっても、正式に後遺障害と認定されることで、慰謝料や逸失利益といった損害賠償を受け取れるからです。しかし、後遺障害の審査は厳しいもので簡単に認定されない事例が目立つ点には注意が必要です。

執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
後遺障害14級の認定を受けるメリット
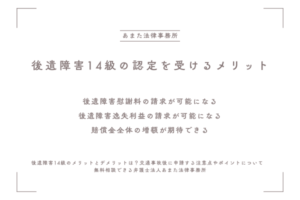
交通事故の後遺症に悩まされている場合、「後遺障害14級」の認定を受けることで得られるメリットは少なくありません。たとえ軽微な後遺障害であっても、正式に認定されることで補償や権利を得ることができます。
以下では、その具体的なメリットを見ていきましょう。
後遺障害慰謝料の請求が可能になる
後遺障害14級が認められると、精神的な苦痛に対する慰謝料を受け取る権利が生じます。
これは、事故によって身体に何らかの機能障害や痛みが残ったという事実に対する正当な補償です。
たとえば、自賠責基準で32万円、裁判基準では110万円前後の慰謝料が支払われるケースもあります。
見逃されがちな部分ですが、認定を受けることで精神的負担に対する金銭的評価が明確になります。
後遺障害逸失利益の請求が可能になる
後遺障害14級の認定は、将来的な収入減少に対する補償も可能にします。
具体的には、仕事のパフォーマンスが落ちたり、長時間の作業が困難になったりした場合、その分の損失を「逸失利益」として請求できるのです。
たとえば年収400万円の人が、労働能力喪失率5%、5年間影響を受けるとすると、おおよそ90万円以上の補償が見込めます。
これは、症状が見たところ軽くても、仕事や生活に支障があるならきちんと主張すべきと言えるでしょう。
賠償金全体の増額が期待できる
後遺障害等級がつくことによって、慰謝料や逸失利益が加算され、最終的に受け取れる賠償金全体が大きくなります。
ただの通院費や治療費の補償に比べて、等級があることで法的にも補償の根拠が明確になるため、交渉においても有利になります。
特に複数箇所に症状がある場合には、「併合認定」によってより高い等級扱いとなる可能性もあり、さらに賠償額が増えるケースもあります。
つまり、認定を受けるか否かで大きな差が生まれるのです。
後遺障害14級の認定を受けるデメリット
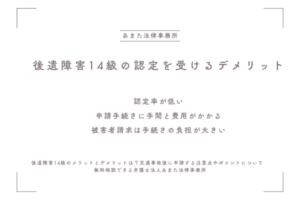
後遺障害14級の認定自体には大きなマイナス面はありません。むしろ、正当な補償を受け取るための重要な一歩です。
ただし、申請や手続きにおいては、いくつか煩わしさを感じる場面もあります。
ここでは、認定を目指す上で注意しておきたい「手間のかかるポイント」について整理しておきましょう。
認定率が低い
後遺障害14級は、比較的軽度な障害であることから認定のハードルが高いです。
身体に痛みや違和感が残っていても、それを医学的に証明できなければ認定されないケースも少なくありません。
実際に、14級の認定率は全体の申請のうち約2%程度とされており、提出資料や診断書の内容によって大きく結果が左右されます。
つまり、症状があっても「証明できなければ認められない」という厳しさがあるのです。
申請手続きに手間と費用がかかる
後遺障害の認定を受けるには、医師に診断書を書いてもらうことが必須。
この診断書の作成には費用がかかるうえ、内容が不十分だと認定に至らないこともあります。
加えて、必要書類の収集、事故後の経過記録の整理、保険会社とのやり取りなど、準備に多くの労力を伴います。
さらに、手続きが複雑であるため、初めての人にとってはストレスを感じやすい点も見逃せません。こうした事務的な負担が認定申請の壁となることがあります。
被害者請求は手続きの負担が大きい
被害者が自分で手続きを進める「被害者請求」は、自由度が高い反面、非常に多くの手間がかかります。
すべての資料を自力で収集し、自賠責保険に直接提出しなければならないため、交通事故に慣れていない人にとっては負担が重くなりがち。
必要書類の不備や記載漏れがあると、審査が遅れるか、最悪の場合却下されるリスクもあります。
つまり、慎重な準備と相応の知識がなければ、かえって不利になる可能性があるのです。
後遺障害14級にあたる後遺症とは?
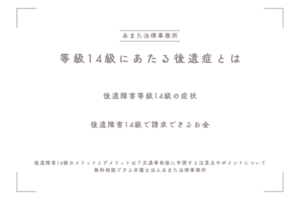
後遺障害等級の14級は主に目元や歯、手などの損傷やむちうちによる痛み、痺れなどの後遺症が該当します。後遺障害等級のなかでは最も軽い症状ではありますが、後遺症が残っている以上は今後の人生に大きな影響を与える可能性のある傷害に変わりはありません。
後遺障害等級14級の症状
後遺障害等級14級は1号から9号まで9種類の症状に分類されます。
| 1号 | 片方のまぶたの一部に欠損またはまつげはげを残す状態。 まぶたを閉じても白目が一部露出してしまう状態、またはまぶたが閉じると眼球は覆えるが、まつげの半分以上を喪失し、生えなくなってしまった場合。 |
|---|---|
| 2号 | 3本以上の歯に歯科補綴を行った状態。 歯科補綴は歯の欠損などを原因とする入れ歯・クラウンなど人工物による治療。3本以上の歯を失ったり、著しい損傷(歯肉の露出している部位の4分の3以上を失うなど)を受けたりで補綴治療が必要になった場合。 |
| 3号 | 一方の耳が1m以上の距離において小声で話しているのを理解できなくなった状態。 医学的には片方の耳で平均純音聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満。 |
| 4号 | 腕(上肢)に手の平ほどのサイズでひどい跡が残ってしまった状態。 肩から手の平の先まで(指は含まない)のどこかに手のひらほどの大きさの傷が残る場合。 |
| 5号 | 脚(下肢)に手の平ほどのサイズでひどい跡が残ってしまった状態。 脚の付け根からつま先までの(指は含まない)どこかに手のひらほどの大きさの傷が残る場合。 |
| 6号 | 片方の手の親指以外で指の骨の一部を失った状態。 片手の親指以外の指の骨の一部を失うまたは、骨がくっつかない遊離骨折をした場合。 |
| 7号 | 片方の手の親指以外で遠位指節間関節を屈伸させられなくなった場合。 遠位指節間関節とは親指以外の指の間にある2つの関節のうち、指先に近い方で一般には第一関節と呼ばれる。関節が癒着して可動性を失う強直や屈伸筋の損傷で同様の症状が出た場合にも認定を受けられる。 |
| 8号 | 片方の足で第3足指以下の1つまたは2つの指の用を廃した状態。 第3足指とは足の中指のことで、中指・薬指・小指が含まれる。用を廃するとは以下のような状態を指す。 ・第一関節から第二関節または第二関節から第三関節までの半分以上を失った状態。 ・第一関節または第二関節において切り離した状態。 ・付け根の関節または第二関節の可動域角度が2分の1になった状態。 |
| 9号 | 局部に神経症状が残った状態。 神経症状とは、手足の痛みや痺れ、感覚の麻痺などを指しており、多くはむちうちに該当する代表的な症状。CTやMRIをはじめとする画像資料では異常が見られなくても、医療機関への受診を続けたり医師の診断結果から医学的な証明が得られれば認定が可能。 |
後遺障害14級で請求できるお金
後遺障害等級14級の認定を受けると、慰謝料や各種損害賠償など加害者に対し以下のようなお金を請求できるのがメリットです。
・傷害慰謝料(入通院慰謝料)……交通事故のケガにより、病院への入通院が必要になったために生じる肉体的・精神的苦痛に対する慰謝料。
・後遺障害慰謝料……後遺障害が残ったことへの精神的苦痛に対する慰謝料。
・後遺障害逸失利益……後遺症が残ったためにこれまでの仕事を続けられなくなる事例など、後遺障害が原因で将来手に入るはずだった給与等の利益が得られなくなった損失への補償。
・休業損害……入院期間など、事故のため会社を休まなければならなくなったために生じた損失への補償。
・治療費……交通事故によるケガを治療するため医療機関を利用した際にかかった費用。
・通院交通費……交通事故のケガで医療機関に通院するためにかかった交通費。
・入院雑費……交通事故による入院のためにかかった日用品等の購入費用や通信費など。
・文書料……後遺障害等級の申請時、医師に診断書等を作成してもらうためにかかる費用。
後遺障害等級14級の認定を受ける際の注意点
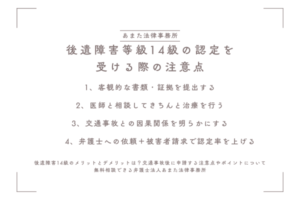
交通事故における後遺障害等級の認定率は年間5%しかありません。非常に厳しい基準のため認定される可能性は低くなっており、ほとんどは認定を受けられない「非該当」とされている現実があります。非該当を避けるための後遺障害申請時の注意点を押さえておくことは大切です。
1、客観的な書類・証拠を提出する
症状を証明できる内容を記載した客観的な書類や資料を提出しましょう。特に14級に該当するのは比較的軽い症状のため、しっかり医学的な根拠を示さないと認定を受けにくくなる可能性があります。
具体的には、医師による「診断書」や「後遺障害診断書」のほか、症状を示す画像資料(CTやMRI)など、医学的な根拠を証明できる書類を提出しましょう。
特に、むちうちなど神経症状が関係するケースでは、見た目では判断しづらいため、神経学的検査の結果を添えることが効果的。
また、注意したいのは、後遺障害の等級認定で重視される検査と、日常の治療で行われる検査とでは目的が異なる点です。検査の選定にあたっては、医師だけでなく、後遺障害認定に詳しい弁護士など専門家に意見をもらうことがおすすめ。
2、医師と相談してきちんと治療を行う
後遺障害14級の認定を目指すなら、病状固定と診断されるまで医師と相談しながら治療を継続することが大切です。
認定の前提となるのは「十分な治療を行っても症状が残った」という事実であり、通院を自己判断でやめてしまうと、その信頼性が損なわれます。
例えば、仕事や家庭の事情で通院を中断した場合、「症状は軽かったのでは?」と見なされ、14級すら認定されない可能性があります。これは、本来得られるはずの慰謝料や逸失利益といったメリットを失う結果につながります。
後遺障害14級のメリットを確実に得るためにも、途中で通院をやめず、医師の指示に従って治療を続けることが重要です。

3、交通事故との因果関係を明らかにする
後遺障害14級の認定を受けて適正な補償を得るためには、交通事故とケガとの因果関係を明確にしておくことが重要。
この因果関係が不明確だと、後遺障害として認められず、14級に該当するメリット(慰謝料や逸失利益の補償など)を受けられなくなる可能性があるからです。
そのため、事故に遭った直後には必ず警察に届け出て、「事故発生証明書」を取得してください。また、保険会社に提出する「事故発生状況報告書」では、事故の状況を正確かつ具体的に記述することが大切です。
特に注意したいのが、病院へ行くタイミング。事故から日数が経過してから受診すると、事故とケガとの因果関係がわかりにくくなる恐れがあります。
日数が開いてしまうほど後遺障害に認定の確率が下がりますので、交通事故の被害に遭ったら必ずその日のうちに医療機関に足を運ぶようにしましょう。
参考:厚生労働省
4、弁護士への依頼+被害者請求で認定率を上げる
後遺障害14級の認定を確実に得るためには、弁護士に依頼したうえで「被害者請求」を行うのが効果的。
被害者請求は保険会社による事前認定と異なり、用意する書類や申請内容などを全て被害者側で用意できます。症状や事故の関係をより詳細に記述したり追加の資料を添付したり、認定率を上げるための工夫がこらせます。
手続きを自分自身で行う手間は生じますが、弁護士に任せると資料作成をしてもらえるのはもちろん、異常個所に印をつけて画像資料を分かりやすくしたりとさまざまなサポートを受けられます。弁護士により被害者請求のデメリットは解消され認定率も高められると言えるでしょう。

後遺障害等級に納得できないときは異議申し立てできる
保険会社に事前認定を依頼したものの、後遺障害の認定を受けられなかった場合や認定された等級に納得がいかなければ、後遺障害等級の認定結果に対する異議申立てできます。
後遺障害等級認定では異議申し立て制度を設けています。後遺障害が認定されない、等級の認定に納得できないときは「異議申立書」を提出すれば、再審査を受けられます。
異議申し立ての方法にも、相手方の任意保険会社を通じて行う「事前認定」と被害者自身が自賠責保険会社へ申請を行う「被害者請求」の2種類があります。再審査により最初の結果が覆る事例はありますが、異議申し立てによる認定率は約12%と決して高くはありません。
以前と同じ内容で申請を行っても再び「非該当」になる可能性が高いという厳しい現実があります。そのため、異議申し立てをするなら認定のために前回は何が不足していたのかを考慮し、新たな書類や資料等の添付が必要になります。
「診断書などの大事な書類に漏れがあった」「画像資料など症状を客観的に説明できる資料が足りなかった」「申請書の書き方に不備があった」など考えられる原因はさまざまです。後遺障害に詳しくない一般の人が判断するのは難しいでしょう。
後遺障害14級のメリットについてまとめ
後遺障害等級の申請を行い認定を受ければ、14級でも後遺傷害慰謝料等を請求できるようになります。後遺障害等級の申請は被害者にとっては特にデメリットはなくメリットのほうが大きいため、後遺症が残ったのなら申請するのが良いでしょう。
申請方法は事前認定なら手続き自体は楽ですが、認定の確率を上げるなら被害者請求がおすすめです。不安があれば弁護士に依頼してください。被害者の代わりに申請書類を作成したり、資料を収集したりしてもらえるようになりますので、手続きの負担を大きく減らしつつ認定を受けられる可能性を高められます。
安心して後遺障害14級の申請をしたいのなら、ぜひ弁護士に相談してアドバイスをもらってください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ