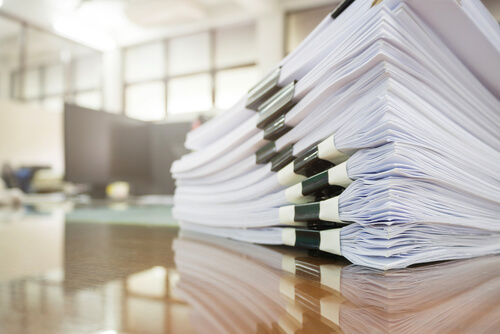「詐欺に遭って大事なお金を騙し取られた」
「暴力を受けて怪我をさせられた」
まさに犯罪が行われたタイミングで、犯人が逮捕されているならば、被害者として警察署に同行し状況を話ながら被害届を作成してもらいます。
しかし、事件の発生について警察が把握していないのであれば、自分で警察署に赴き被害届を提出する必要があります。
今まで犯罪に巻き込まれたことのない人が大半だと思いますので、どこで記載用の書類を手に入れるのか?何を記載すればいいかなど、被害届の提出のしかたはわからないと言う人がほとんどでしょう。


2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 ▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
この記事の目次
被害届とは??
加害者を逮捕して、懲役や罰金などの法的な罰を与えてもらうために届け出ると思っている方も多いですが、提出する目的は、被害があった事実と状況を報告するだけのものなのです。
被害届については法律上、警察に受理義務はありません。しかしながら、警察の内部規則である「犯罪捜査規範」第61条によれば、「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理する必要がある。」と規定されています。

告訴状とはどこが違う?
前述したように、被害届が受理されたところで、すべての事件を捜査がおこなわれるわけではありませんし、また、被害届には犯人に対して法的な罰を与えたいという自分の意思も含まれるものではありません。
犯罪の被害者となったときに届け出を行う「告訴状」というものがあります。被害届は受理された後に、警察側の判断によって捜査の可否か決定されますが、告訴状を受理した時には、検察に対して報告を行わなければならないため、捜査をする義務が生じます。
捜査を実際に行ってもらえるかわからないならば、最初から告訴状を提出した方がいいのではないか?そう思われるかもしれませんが、基本的に届け出たものが全て受理される被害届と違い、告訴状は提出したもの全てが受理されるわけではありません。
告訴状との違いを簡単にまとめるた表がこちらになります。
| ・被害届 | ・告訴状 | |
| ・目的 | ・被害状況の報告 | ・加害者に対しての捜査請求と処罰請求 |
| ・提出先 | ・管轄の警察署 | ・管轄の警察署 |
| ・届け出人 | ・被害者本人 | ・被害者本人 |
| ・捜査義務 | ・生じない | ・生じる |
| ・報告の義務 | なし | あり |
| ・受理について | 原則的には受理 | 捜査機関の判断によって不受理になる |
被害届を出しても捜査してもらえない理由
提出したのに、捜査をしてくれないのは次のような理由が考えられます。
刑事事件の可能性が低い場合
基本的に警察が取り扱うのは刑事事件のみ、民事事件については不介入の原則があります。ビジネス上のトラブルであったり、家族や恋人間の内輪揉めなど、刑事事件としての事件性が低い場合は動いてくれることは少ないです。
しかし、最近では最初は民事事件でありながら、捜査をせずに放置していたため、重大な刑事事件に発展してしまうケースが増えています。ストーカー行為などは、その時点で悪質性がよほど高くなければ、刑事事件として取り扱ってくれないことが多かったのですが、その後に殺人事件などに発展するケースもあったため、最近では捜査を行ってくれることも増えているようです。
被害が軽微の場合
被害者にとっては大きな問題であっても、客観的に見たときに被害が軽微であると判断された場合は、捜査してくれない可能性が高いです。
例えば、数百円を騙し取られたという事件の場合、詐欺罪や窃盗罪などに該当する可能性があったとしても、捜査員の人数は限られていますので、もっと重大な事件の捜査の方に人員を充ててしまうことがほとんどです。
事件の発生からかなりの時間が経過している場合
事件発生から時間が経過してしまうと、犯罪を立件するための証拠を揃えることが非常に難しくなります。また、目撃者や証人などの記憶も薄れてしまうので、時間の経過とともに立件できる可能性が低くなってしまいます。
また、殺人や強盗などの凶悪事件以外の刑事事件には公訴時効が設定されているため、時効が成立してしまった場合は捜査しても起訴しても裁判所は免訴の判決をする必要があるため、捜査を行う実益が失われることから、捜査はほぼされません。。
【主な刑事事件の公訴時効】
| 時効期間 | 犯罪の種類 |
| 1年 | 侮辱、軽犯罪法違反など |
| 3年 | 住居侵入罪、公然わいせつ罪、淫行勧誘、死体損壊、脅迫、威力業務妨害、名誉棄損など |
| 5年 | 収賄、受託収賄及び事前収賄、監禁、単純横領など |
| 7年 | 詐欺,窃盗、業務上横領,強制わいせつなど |
| 10年 | 強制性交等罪など |
| 25年 | 傷害致死、危険運転致死など |
| なし | 殺人、強盗致死など |
犯人を特定するのが困難
犯罪の根拠となる証拠が少なかったり、犯人を特定できないときも捜査を行ってもらえないケースが多いです。
インターネットでの書き込みによる侮辱罪や、海外サーバーを使っての犯行などは、犯人を特定するまで非常に時間がかかることが多く、被害者に大きな損害を与えていたり、被害者の数が少ない場合は捜査に至らない可能性が高いです。
警察への被害届の出し方
警察へ提出するときに必要なものと流れを説明します。
提出の際に必要なもの
基本的に被害者本人が提出するものになるので、提出者の身分を確認できる公的証明書が必要になります。免許証やパスポートなど、顔写真が掲載されていてその場で本人確認が可能な証明書を持参してください。
記載する用紙は警察署に用意されていますので、警察署で提出を行うことになります。普段とは違う状況のため、いざという時に思い出せなくなったりすることがないように、覚えていることについては箇条書きでもいいので内容をメモをしておくと安心です。
受理証明書の取得
詐欺被害に遭ったとき、カードの支払いを止めたり、損害補償を適用してもらうために、警察に届け出を出さなければいけません。届け出が受理されると受理番号が通知されます。このときに受理番号をメモするだけではなく、受理証明書を取得しておくと、その後の申請の際便利です。
被害届を出すかどうか迷ったときはどこに相談すればいい?
お金を失ったものの、果たして詐欺で騙されてしまったのか自分でも判断ができないときはどうしたらいいのでしょう?
被害にあったときに相談できる窓口を紹介します。
警察専用電話♯9110
警察への通報と言ったら「110」を思い浮かべますが、110番は緊急性がある場合の通報手段です。詐欺の被害については、犯人を逮捕しないと危険が及ぶというような緊急性があまりありませんので、110番には通報しにくいでしょう。
そのような事案に対して相談に乗ってくれるのが、各警察署に設置されている警察専用電話です。全国どこからでも「♯9110」をダイヤルすることで、各地の警察署にある担当部署に電話が繋がり相談をすることが可能です。
各警察署に設置されている警察専用電話「♯9110」に相談しましょう。

消費者センター
地方公共団体が設置する消費者センターのホットラインは、消費者トラブルや詐欺被害についての相談も受け付けています。被害にあったけれども詐欺に該当するのかどうか?被害届の提出をした方がいいかについても消費者ホットライン「188」でアドバイスを受けることができます。
弁護士の無料相談
詐欺で騙し取られたお金を取り戻す方法は、相手の口座を凍結して口座内にあるお金を被害者に分配する「振り込め詐欺救済法」などがありますが、口座内にお金が残っていなければそれ以上請求することができません。
相手に対して返金を求めるならば、弁護士に依頼して民事訴訟を起こすという流れになるでしょう。弁護士に依頼すると高い費用がかかると思いこまれている方も多いですが、弁護士事務所では詐欺被害に遭われた人に対して無料相談を行っています。
どのような流れでお金を取り戻すことができるのか?取り戻せる金額と弁護士費用のバランスはどうなるのか?無料相談を利用して自分にメリットがある方法をアドバイスしてもらうことができます。
詐欺被害似合ったときの対応についてまとめ
詐欺の被害に遭った場合、被害金額が少なかったり、同じ被害に遭っている被害者が少なかったりすると提出しても捜査をしてもらえる可能性は低いですが、振り込め詐欺救済法などを適用してもらうために、警察に提出することが必要になります。

被害届を出すことによって、刑法上の罰を与えられる可能性はありますが、損害賠償などの民事上の罰を与える、自分のお金を取り戻すという意思があるならば、一度弁護士の無料相談などでアドバイスを受けてみてください。
▶︎柔軟な料金設定 ▶︎いつでもご相談いただけます 1.交通事故の無料相談窓口
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!