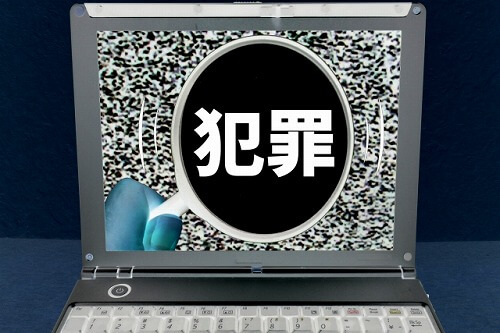インターネット上における誹謗中傷は、誰でも匿名で手軽に書き込めることが問題視され、最近では社会的に大きな注目を集めるようになっています。

執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
インターネット上の誹謗中傷はどんな犯罪になる?
匿名掲示板やSNSなどネット上でも頻繁に誹謗中傷にあたると思われる書き込みや投稿が発生しています。
誹謗中傷という言葉は、それ自体は法律用語ではないのですが、法律上にはこれに相当する犯罪が存在しています。ネットでの相手を傷つける書き込みをした場合、どういった犯罪になるのでしょうか。
脅迫罪
相手の生命や身体、財産などを傷つけると言って脅した場合に適用される犯罪です。「お前を殺す」などネット上での殺害予告は脅迫罪に該当する可能性が高く、相手の家族や親族を対象にした場合も罪になります。
相手を畏怖させるのに十分と判断されれば、相手が実際に恐怖を感じたかどうかに関係なく罪に問うことができます。
名誉毀損罪
相手の名誉を貶めるような書き込みを行った場合に適用される犯罪です。名誉毀損にあてはまる要件として「事実」をもとに相手の名誉を傷つけた場合に限られます。
ここで言う事実は真実であるかは問題でないため、たとえ本当のことを言っていたとしても罪に問われる可能性があります。
また、ほかの要件として、公然と名誉を侵害する必要があるため、個室で1対1の場合などは罪にあたらないと判断されることもあります。この点、ネット上の書き込みは不特定多数の人間に見られるのが基本のため、罪にあたるとされる可能性は大きいといえます。
侮辱罪
他人をバカにするような投稿をして相手に対する侮辱的な発言や書き込みなどをしたときに適用される犯罪です。
侮辱罪の場合も多くの人の目に入る状態であることが必要なのは同じです。違うのは、こちらは事実を言う必要がないところです。

信用毀損罪・業務妨害罪
わざと嘘の情報を流すことによって他人の経済的信用を貶めた場合に適用されるのが信用毀損罪で、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪となります。
威力業務妨害罪
威力を使って相手の業務を妨害した場合に適用される犯罪です。
「店に爆弾を仕掛けた」といった犯罪予告など企業や商店の営業を妨害するような書き込みは威力業務妨害にあたる可能性が高くなります。
親告罪と非親告罪について
上記の罪のうち、名誉毀損と侮辱罪は親告罪に分類され、被害者からの告訴がなければ公訴を提起することができません。
そのため、加害者に刑事責任を負わせるためにはあなた自身が行動する必要があるのです。脅迫罪や威力業務妨害罪は非親告罪のため、犯罪が発覚した時点で罪に問われる可能性があります。
インターネット上で名誉棄損されたらするべきこと
ネット上で誹謗中傷を受けた場合、相手を特定し、刑事告訴することができるほか、民事での責任を負わせることもできます。
しかし、やり方を間違えると相手に逃げられてしまったり、逆にこちらが名誉毀損に問われてしまうことも考えられます。ネットで被害を受けた時にとるべき正しい行動をみていきましょう。
相手と直接交渉するのは危険
気をつけなければいけないのは、相手の個人情報が分かった後の対応で、この時、直接相手のところへ話し合いにいくのは避けるようにしてください。
誹謗中傷はクラスメートやご近所さんなど身近な人間が行っているケースも多く、投稿者が判明すれば、相手と直接会って交渉することが可能な場合もあります。
ですが、こうした投稿を行う相手はあなたに恨みや怒りを抱いており、当事者同士の話し合いは上手くいかない場合がほとんどです。
地域の警察署に相談する
それでは、相手を特定してからはどういった行動をとればいいのでしょうか。
まず、相手の投稿が度を越えていて、明らかに犯罪行為に該当すると思われる場合は、住んでいる地域を管轄している警察署に相談するようにしましょう。

弁護士など専門家に相談する
書き込みの内容が曖昧で、名誉毀損に該当するかどうかが自分自身では判断できない場合は、弁護士など専門家に相談してみるのも1つの方法です。相談する場合は、誹謗中傷問題を専門に扱っている弁護士事務所を探すのがいいでしょう。
これまでいくつもの事件を解決してきた実績とノウハウをもとに、あなたの相談に対しても、きっと心強い味方になってくれるはずです。
相手が匿名でも罪に問える?
SNSや掲示板などネット上での書き込みを行う場合は、匿名であることがほとんどですが、相手の実名が分からない状態でも相手を訴えることが可能なのかを解説します。
ネット上の誹謗中傷でも相手を罪に問える
ネットやSNS上の書き込みは匿名で行われたものであったとしても、それが他人を攻撃したり名誉を貶めるものであれば罪に問うことができます。
訴訟によって刑事責任を追及するのとあわせて、民事でも不法行為の責任追及や賠償金の支払いなどを請求することが可能です。
匿名の相手でも特定できることがある
ネットでの誹謗中傷に対しても罪に問うことができますが、もちろん匿名のままでは不可能です。被害者になってしまった場合、まずは相手の身元を特定する必要があります。
投稿者の特定には発信者情報開示請求と呼ばれる制度を利用され、プロバイダに依頼を行うことで加害者の氏名や住所といった相手の個人情報を知ることができ、個人の特定ができる場合があります。
発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求とは、インターネット上で誹謗中傷を受けた場合に、書き込みを行った人間の特定を行うため、プロバイダに投稿者の情報開示を請求するための手続きをいいます。
回線をインターネットに繋げる役割を果たしている事業者をプロバイダといい、ネット上での権利侵害に対しては、プロバイダ責任制限法4条に基づき、プロバイダに情報の開示請求を行うことができるとされています。
ただし、掲示板の管理人などのサイト運営者が投稿者の情報を持っていることは少なく、発信者を特定するためには、まず掲示板の管理人などのサイト運営者に対して発信者の通信ログ等の開示を請求し、その情報をもとに、経由プロバイダ(携帯電話のキャリアなど)に対して、発信者の情報開示を請求するという手順を踏むことになります。
実際に犯罪となった誹謗中傷の例
ネット上での書き込みがもとになって犯罪にまで発展してしまったのにはどのようなケースがあるのでしょうか。実際の事例を見ていきたいと思います。
木村花さん誹謗中傷事件 侮辱罪
女子プロレスラーの木村花さんが出演したテレビ番組での発言をきっかけにSNSで激しいバッシングを受けるようになった事件で、木村さんは遺書のようなメモを残して亡くなる結果になりました。
彼女のSNSには1日100件を超える誹謗中傷コメントが送られていたといい、誹謗中傷に対する社会的な関心が高まるきっかけになった事件です。
木村さんの母親からの告訴により、中傷コメントを書き込んだ男性が侮辱罪で略式起訴され、東京簡裁は科料9000円の略式命令を出しています。
元AKB48 川崎希さんの事例 侮辱罪
元アイドルグループのメンバーだった川崎さんがネット上での執拗な誹謗中傷を受けた事件です。
匿名掲示板で川崎さんに対して、レストランで無銭飲食をしたといった虚偽の内容や妊娠発表の時には「流産しろ」といった書き込み、さらには家に火をつけるなどの悪質な書き込みが多数投稿されました。
本件では、発信者情報開示請求によって相手を特定し、そのうえで刑事告訴しており、侮辱罪により女性2人が書類送検されています。後に川崎さんは刑事告訴を取り下げています。
ラーメン店チェーン誹謗中傷事件 名誉毀損
あるラーメン店チェーンを運営している会社が、カルト宗教とのつながりがあり、この店で食事をすると売り上げの一部がカルト集団に入る、会社説明会の広告に嘘を書いている、などネット上の根拠のない書き込みによって被害を受けた事件です。
中傷を行った男性には名誉毀損による有罪判決が出ました。
動画サイト誹謗中傷事件 名誉毀損
東京都の行政書士の男性が女性トラブルから千葉県に住む男性に対して、自身のブログや動画投稿サイトにおいて、男性の経歴や髪型を誹謗中傷する内容の投稿を行った事件です。
被害を受けた男性はサイト運営者に削除を求めたものの、個人を特定できないとして拒否されたため、加害者を名誉棄損で刑事告訴しています。
罪に問えないこともある?
名誉毀損の場合、不特定多数の人が見聞きできる状態で相手の名誉を侵害することが要件になっています。そのため、ネット上の書き込みに関しても、不特定多数の人間が目にすることができる状態になっていなければ罪に問うことができません。
たとえば、鍵アカのように、限られた人だけが見ることのできる投稿では罪にあたらないと判断されるケースもあるでしょう。

例外的に、公共の利害に関する事柄に関して、公益を守るという目的のもとに行われた場合は、内容が真実であった場合には罪に問われないとされています。
たとえば、週刊誌が政治家の不正を暴くスクープをした場合などは、公益性があると判断されることがあります。ですが、ネット上の個人の投稿では起こりにくい珍しいケースといえます。
名誉を貶めた相手が亡くなった方の場合は、摘示した事実が真実のときは、罪には問われないこととされています。
インターネット上の誹謗中傷まとめ
他人への誹謗中傷は、たとえそれがネット上の匿名によるものであったとしても罪に問われる可能性があります。
こうした書き込みをしないことはもちろんですが、被害に遭ってしまった場合には、専門家の力を借りるなど、適切な対処を行うようにしましょう。


2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ