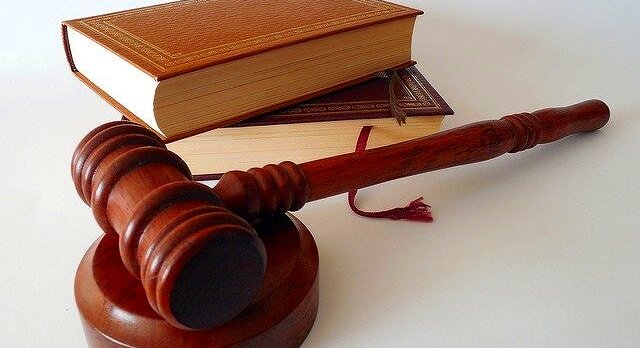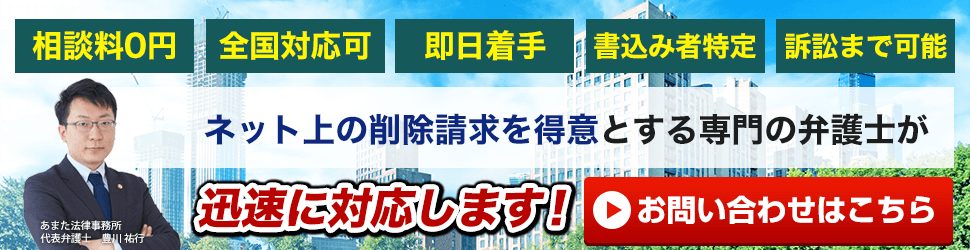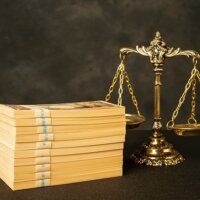SNSや掲示板などインターネット上で誹謗中傷の被害に遭ったら、法的措置を取ることはできます。ただ、匿名の加害者に慰謝料を請求したり刑事告発するためには、氏名や住所などの個人情報を特定する必要があります。

執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
ネット上の誹謗中傷に対し法的措置は取れる
掲示板やSNS上の誹謗中傷は名誉毀損や侮辱、信用毀損、脅迫など犯罪の要件を満たす可能性があり、投稿者に対しての法的措置は可能です。
刑事責任を問う
誹謗中傷の投稿が名誉毀損、侮辱罪、信用毀損罪、脅迫罪などに当たるなら、刑事事件として告訴できます。
名誉毀損罪
名誉毀損は刑法230条に規定されており、「公然と事実を摘示し人の名誉を傷つける」ものとされています。
ここで言う「事実」は真実か虚偽かは問わず、社会的な評価を低下させるような内容を流布している状況なら、該当する可能性があります。罰則は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円の罰金です。
例としては、「不倫している」「前科がある」「風俗で働いている」など、他人に知られたくないようなプライバシーにかかわる内容があります。
侮辱罪
侮辱罪は刑法231条にあり、「事実を摘示しなくても公然と人を侮辱する」とされています。
バカ、アホ、ブス、デブ、ハゲなどの悪口が該当する可能性があり、罰則は1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。従来、ネット上での誹謗中傷は侮辱罪での事件化が難しいとされてきたのですが、近年は書類送検に至った事例が出てきています。
信用毀損罪
信用毀損罪は刑法223条に定められており、「虚偽や偽計で信用を毀損、又は業務を妨害する」とあります。
個人だけでなく法人に対する誹謗中傷でも対象になり、「購入した食品に異物が入っていた」「もうすぐ倒産する」など、企業にダメージを与えるような虚偽の口コミなどが対象になります。罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
脅迫罪
脅迫罪は刑法222条にあり、「生命や身体、自由、名誉、財産に害を与える旨を告知する」とあります。
罰則は2年以下の懲役または30万円以下でです。「殺す」「放火する」「痛い目に合わせる」など危害を加えるような内容です。被害者は身の危険を感じるもので、誹謗中傷の中でも悪質だと言えるでしょう。また、「家族を狙う」など、本人だけではなく親族などに対する脅迫も該当します。
参考:刑法

民事責任を問う
誹謗中傷の投稿がプライバシー侵害、名誉侵害罪、肖像権侵害に該当すれば、民事裁判を提起できます。
インターネット上で他人に知られたくない内容を不特定多数が閲覧・認識できるSNSや掲示板に公開するのは、個人の権利侵害になる可能性があります。不法行為と認められれば、投稿者に慰謝料を含む損害賠償の請求ができるようになります。
プライバシー侵害や肖像権侵害は犯罪に巻き込まれるきっかけにもなり注意が必要です。たとえば、本名や住所、電話番号、メールアドレス、マイナンバー、犯罪歴などの個人情報をネット上で晒すのはプライバシー侵害、顔や容姿をネット上に掲載するのは肖像権侵害になる可能性が高いです。
法的措置の前に削除請求を検討
法的措置の前に考えたいのが、誹謗中傷に当たる書き込みの削除請求です。
X(旧Twitter)などのリツイートをはじめ、コメントを簡単に早く拡散できるのがインターネットの特徴です。放っておくと知らないうちに被害の規模が大きくなるリスクがあります。対象の投稿を放置していると、いつまでも自分に向けての中傷が続きエスカレートする危険性が生じます。
誹謗中傷は被害を拡大させないことが大切です。
誹謗中傷されると言い返したくなってしまうかもしれませんが、相手を刺激しさらなる誹謗中傷につながりやすくなります。また、荒い言葉を使ってしまうと、自身が誹謗中傷の加害者になってしまう可能性が出てしまいます。誹謗中傷に対し反論で対処するのは難しいと言えるでしょう。
誹謗中傷コメントの削除請求
誹謗中傷の書き込みに対する削除請求の手順は、運営者に連絡し対応がなされないときは仮処分を申し立てるのが一般的です。
運営者に削除請求する
削除したい書き込みを見つけたら、SNSや掲示板の運営者に削除依頼を行います。サイトに用意されている管理者の連絡先や削除依頼ができる投稿フォームを確認し、削除したい内容の投稿がある旨を伝えます。
削除依頼への対応や書き込みの削除基準はサイトによって異なるのが現状です。早いと数日で削除された例はありますが、中には返信さえなく無視するサイトも存在しています。
実際のところ表現の自由や利用している人のプライバシー保護の観点から、運営側は削除依頼に応じないことがほとんどです。応じてもらえない場合は、削除するための法的措置を取る必要性があります。
加えて、誹謗中傷の発言が削除されてしまうとIPアドレスの記録が消えてしまう点には注意が必要です。サイト運営者に対し発信者情報消去禁止の仮処分を行ってから、削除請求する方法もあります。
参考:X(旧Twitter)ヘルプセンター
削除を求める仮処分の申し立て
コンテンツ運営者が削除依頼に対応してくれなければ、裁判所に削除を求める仮処分の申し立てを実施します。
仮処分による決定は裁判所の決める暫定的な措置で、本訴による判決とは異なります。申し立てが認められるまで2週間~2か月程度と通常の裁判よりも結果が早いのが特徴です。仮処分命令が発令されれば、原則として裁判手続きを経なくてもサイト側で誹謗中傷に当たる書き込みを削除してくれます。

法的措置の具体的な手順
ネットの投稿に対し民事や刑事での法的措置を行う前に、しっかりと準備しておくことが訴訟を成功させるカギになります。
ネットでは本名ではなくハンドルネームが使われており、投稿者の身元がわかりません。結果、すぐには訴訟の提起はできないのが現状です。法的措置をとるにはいくつかの準備が必要になりますが、具体的な進め方と注意すべきポイントを解説します。
書き込みの証拠を残す
ネット上の書き込みは投稿者が自身の投稿を消すことができます。誹謗中傷の書き込みを発見したらURLとともにプリントアウトし証拠を残すようにしてください。
プリンターを持っていないなど印刷できなければ、スクリーンショットやカメラで画面を撮影したものでも構いません。
発信者情報開示請求で投稿者を特定する
匿名の投稿者を特定するために、プロバイダに対し個人情報の開示請求を実施します。
訴訟を起こすには誰が書き込みしたかを特定しなければならず、加害者の名前、住所、電話番号、メールアドレスといった個人情報が必要です。
最所に誹謗中傷の書き込みが行われたコンテンツプロバイダに、投稿者のIPアドレスを開示してもらいます。開示された情報を用いて接続プロバイダを特定し、投稿者の情報開示を請求することになります。
プロバイダが開示に応じてくれなければ仮処分の申し立てや民事での訴訟が必要になりますが、裁判になると開示されるまで6か月から1年ほどと長い時間を要することが多いです。
現在は改正プロバイダ責任制限法により、「発信者情報開示命令事件」という非訟事件類型での手続きができるようになりました。これまではコンテンツプロバイダと接続プロバイダへそれぞれ開示請求するシステムでしたが、1度で行えるようになっています。そのため、以前よりもスピーディな解決が望めるようになりました。
削除禁止の仮処分
プロバイダに対し、アクセスログの保全を実施します。ログが消されると投稿者の特定ができなくなるためです。
プロバイダはユーザーの通信記録に3か月から6か月程度の保存期間を設けているのが一般的で、一定の期間が経過するとログが消されてしまいます。訴訟による請求では開示を認める判決が出ても、ログの保存期間を過ぎていれば投稿者の特定ができなくなってしまうため、プロバイダにログを保存してもらう必要性が出てきます。
X(旧Twitter)などのSNSでは、アカウントが消されてしまうとログは30日程度しか残っていないと言われています。できるだけ早い段階での対処が求められます。

民事責任や刑事責任を問う
誹謗中傷の投稿者が特定できたら、慰謝料を請求する民事裁判や加害者を罪に問う刑事裁判を起こすことができます。
慰謝料を請求する
民事裁判では慰謝料を含む損害賠償を請求できます。また、二度と同じような悪質な投稿は行わないとする誓約書を書いてもらったりできます。
相手方に内容証明を送り直接交渉することはできますが、示談での解決は難しいこともあります。話し合いで折り合いがつかない状況になれば、民事で訴訟を起こすことになります。
裁判の判決が出るまでは半年から1年ほどと長期間かかります。
刑事告訴する
誹謗中傷した加害者の処罰を望むなら、名誉毀損罪などで刑事告訴する判断もあります。
警察が相手方に捜査に入り検挙や逮捕といった対応がとられます。
ただ、刑事告訴は事件として警察に受理してもらう必要がありますが、ネット上のトラブルでは警察がなかなか動いてくれないケースがあります。
誹謗中傷は社会問題にもなっており、以前に比べると警察も対応してくれやすくなっています。しかしいくら訴えても重大事件ではないと判断され、放置されることがあるのです。誰かに危害を加える可能性がある、著しい人権侵害があるなど、悪質性が明確でなければ後回しにされることがあるのは注意点です。
誹謗中傷の法的措置は弁護士に相談
民事訴訟や刑事告訴には法律知識が必要です。個人で対処するのは難しいのですが、頼りになるのが弁護士のサポートです。名誉の毀損やネットでの事案に強い弁護士に相談すれば、ケースに合ったアドバイスをもらえ心強い味方になってくれるはずです。
訴訟ができる弁護士に依頼する
誹謗中傷への法的措置は、訴訟行為を代理してくれる弁護士への依頼をおすすめします。
仮処分の申し立てや裁判の手続きを一人でできるケースは少なく、誰かの力を借りて問題を解決するのが良いと思われます。ネット上で発生した問題は国や民間団体が運営する窓口で相談できますが、結局は削除依頼などの手続きは自分自身で行う必要があり、訴訟等にも対応してもらえません。
弁護士なら法的措置の他、投稿者との示談や被害届を受理してくれない警察との交渉なども代行してくれます。
弁護士以外への依頼は契約が無効になることがある
弁護士などの専門資格を持たない者が報酬を得ることを目的に法律事務を行うことは、非弁行為として弁護士法違反になると定められています。
過去には書き込みの削除依頼を代行したネットサービス会社の行為を無効とした判決が出ています。この事件では10記事の削除を実施した業者が報酬として50万円の金銭を得ていましたが、裁判所は契約は無効として報酬の返還を求めました。

参考:東京弁護士会
ネット上の誹謗中傷に対する法的措置まとめ
ネット上での誹謗中傷は、相手が匿名でも民事および刑事で法的措置をとることができます。
ただ、投稿の削除依頼や証拠保全、情報の開示が必要など、ネットならではの複雑な手続きが伴います。個人でできないわけではありませんが、法律の知識がない人がスムーズに手続きを進めるのは難しいでしょう。
悪質なコメントに悩み法的措置を考えるなら、インターネット上のトラブル分野に強い弁護士の意見を求めてください。初回は相談無料の事務所を選べば、気軽に相談できます。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら