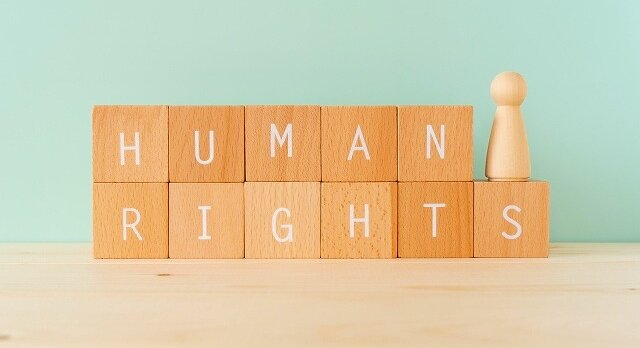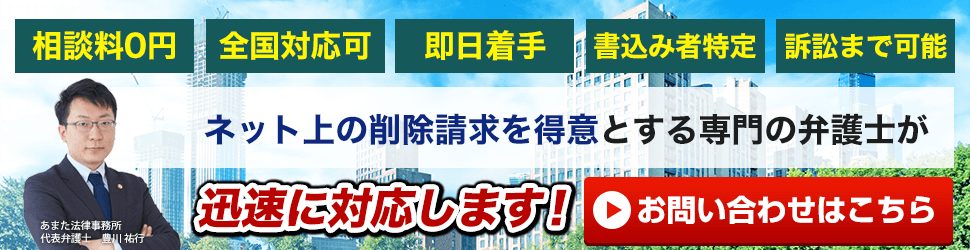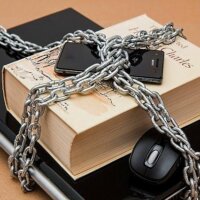2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
匿名での投稿が可能なインターネット上では無責任に誰かを攻撃するような人は多く見られ、誰でも誹謗中傷の被害者や加害者になるリスクが潜んでいます。

執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
人権侵害と表現の自由は異なる
誰かを人権侵害するような書き込みは犯罪になるリスクがあります。
普段、SNSや掲示板などネットに投稿する際に、人権侵害を意識する人はあまりいないと思われます。日本では表現の自由が憲法で保障されており、自由な意見や考えを発信する行為は認められています。表現の自由があるのだからと、どんな内容を書き込んでも問題ないと思っている人もいます。
しかし、表現の自由と人権侵害は異なります。
表現の自由とは
表現の自由は日本国憲法第21条1項の中で保障されている権利の1つです。自分の意見や考え、主張などを他人に向けて、自由に発表したり表現したりできる権利です。
表現の自由のなかでも代表的なものである言論の自由は音声や画像にも適用されます、また、報道の自由や出版、放送の自由なども含まれます。
表現の自由は歴史的に民主主義とともに発展してきた経緯があり、今でも民主主義を守るための大切な柱の1つと考えられています。表現の自由が認められていることにより、国民は説明責任を果たさない権力者を自由に批判できます。結果、権力に対し国民の監視機能が働き、民主主義に役立つことになっています。

表現の自由は常に危機に晒されており、特に独裁的といわれる国ではその傾向が顕著です。
一例として中国が香港の民主化運動を弾圧した事件が挙げられます。香港国家安全維持法により共産党への批判が犯罪とされ、人々は自由な発言をしにくくなりました。このような状況では国民が様々な自由を得ることや民主主義が実現されることは難しく、表現の自由はいかに重要かがわかるでしょう。
人権侵害とは
人権侵害は人権蹂躙(じんけんじゅうりん)とも呼ばれ、憲法が保障している基本的人権の尊重に反する行為を指します。
自由権・社会権・平等権などからなり、人間が誰でも生まれながらに持っている他人に譲ることができない固有の権利です。プライバシーの侵害や差別、暴力などのほか、相手を不快にさせるハラスメントや必要な世話をしないネグレクトも該当します。
人権侵害はもともとは国家による国民の権利侵害を指す言葉でしたが、現在では私人間(しじんかん:一般の人同士)にも適用されるようになりました。また、当初、基本的人権の範囲は表現の自由、職業選択の自由といった自由権が中心でしたが、その後、生存権や教育を受ける権利、労働権といった社会権が加わっています。さらに、現代では知る権利やプライバシーの権利などが含まれ人権の範囲は拡大されています。
ただ、国民1人1人が基本的人権をもっているものの、不当に他人の権利の侵害を行ってはならない考えが一般的です。

どんな内容でも表現の自由で済まされるわけでない
SNSなどネットの投稿は、他人の尊厳を傷つけるような内容は表現の自由を通り越して人権侵害になり、許されるものではなくなります。
どこまでが表現の自由でどこからが人権侵害になるのかの線引きは難しい面がありますが、社会的評価を下げるような誹謗中傷の投稿は人権侵害となる可能性が高いです。他人の悪口や真実ではない虚偽の書き込みは、表現の自由で保護されないと思って良いでしょう。
人権侵害に当たる内容なのか個人で判断するのは容易ではないため、法律に詳しい弁護士に意見を求めてください。
人権侵害になる書き込みの例を紹介
近年はネット上の誹謗中傷問題に注目が集まるようになり、加害者が警察に逮捕されたり、被害者が加害者に対し裁判を検討する事例が増えています。しかし、誹謗中傷の中には明らかな名誉毀損や侮辱罪など刑法での責任を問いにくく、明確に犯罪とは言えないものもあります。
ネット上のいじめやいやがらせ、プライバシーの侵害などは犯罪に該当しないケースもありますが、他人を傷つける行為であることに違いはありません。他人を嫌な気持ちにさせるような内容の投稿は避けるべきだといえるでしょう。
どのような書き込みが人権侵害にあたるか、もしくはあたる可能性があるか、事例を紹介します。
「バカ・アホ」「きもい」「ブス」「デブ」のような単なる悪口や差別的な発言や、「○○は犯罪者」といったデタラメな内容で他人を誹謗中傷する書き込みは、人権侵害に加え刑法上の侮辱罪や名誉毀損といった犯罪に該当する可能性があります。
「〇〇しないと殺す」「〇〇に爆弾を仕掛けた」といった殺害予告や爆破予告のような脅しのような書き込みは、刑法上の脅迫罪や威力業務妨害罪などにあたる可能性があります。本人だけでなく家族に対する脅しも対象になります。
第三者に知られたくないプライバシーに関する情報を勝手に書き込む行為は、人権侵害に当たると考えられます。プライバシーの侵害は法律で明確に犯罪として規定されているわけではありませんが、情報が悪用される恐れはあります。他者の権利を侵し、人権を侵害していると言えるでしょう。
誰かになりすまし相手の意思に反する内容を書き込む行為は、人格権を侵害する行為です。つまり、人権侵害の一種と言えます。
人権侵害をしないための注意点
手軽に自分の思いを発信できるのがインターネットの魅力ですが、知らないうちに誹謗中傷などで他人の人権を侵害しているケースは少なくありません。
人権侵害は法律による違法行為のみではなく、他人の尊厳を傷つけるような投稿も控える必要があります。

インターネット上はさまざまな人と繋がれる便利なツールですが、実際に誰かと顔を合わせることはなく相手の顔が見えにくいのが特徴です。面と向かっては言いにくいことも、ネット上では抵抗なく言いやすい面があります。
また、インターネット上のコメントは、不特定多数の人が目にします。自分の発言により誰かを傷つけないか、不快な思いをさせないか、考えて投稿するようにしましょう。
ネットでは嘘の投稿を信じた人たちが、誰かをバッシングする傾向があります。
ネット上には根拠のない嘘や不確かな情報が氾濫しているのが現状であり、本当に正しい情報なのか判断する必要があります。なんでも安易に信用して、他人を攻撃するのは危険な行為です。
ネットの書き込みは簡単に消せるものではなく、投稿してしまうと消すのは困難である点を理解しておきましょう。
自身の投稿は削除できるのが普通ですが、X(旧Twitter)のリツイート機能などで拡散されていれば、完全に削除するのは難しくなります。悪質な誹謗中傷のような書き込みを後から消したいと思っても、永遠に消えずネットに残り続けるデジタルタトゥーが発生します。こうなると後悔しても遅いので気を付けてください。
人権侵害にあたる書き込みをしないためには、送信する前のセルフチェックが大切です。自分の投稿を誰が閲覧しても問題ないか、もし消せなくても不都合はないか冷静に考えるようにしましょう。
自治体で配布されている以下のようなチェックリストを利用するのもおすすめです。
https://www.pref.osaka.lg.jp/jinken/internet/index.html
人権侵害への対処法
ネット上の書き込みで人権侵害の被害に遭ってしまったケースと、人権侵害をしてしまったケースの対処法をそれぞれ解説します。
人権侵害を受けたとき
人権侵害にあたる誹謗中傷を書き込みされたときは、削除要請や犯人を特定し民事や刑事上の責任を問うといった対応ができます。
自身への誹謗中傷が掲載されているサイトやSNSを運営するや管理者や事業者に問い合わせ、書き込みに対し削除依頼を行います。
だいたいのSNSやサイトには削除に関するガイドラインや削除申請のフォームが用意されていますので確認してください。もし要請に対応してくれない場合は、裁判所に削除仮処分の申立てができます。
加害者に謝罪を求めたい、法的措置を取りたいといったときは、誰が誹謗中傷をしたのかを特定する必要があります。SNSやサイトに発信者の情報開示を請求し、書き込んだ相手を特定します。
最初にコンテンツプロバイダ(サイト運営側)へ開示請求を実施し、開示されたIPアドレスをもとに特定した接続プロバイダへ、投稿者の氏名や住所など個人情報の開示を請求します。もし応じてくれなければ、裁判所に開示仮処分の申立てを行います。

参考:総務省
誹謗中傷した加害者が特定できれば、民事上で慰謝料などの損害賠償を請求したり、刑事告訴して罪を問うことができます。
書き込みが悪質で名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪に当たる可能性があれば、告訴により警察に罰金、逮捕、起訴など法的な措置を取ってもうらえます。
法律上の犯罪には該当しない内容と判断されても、民事で裁判を起こせば投稿者への慰謝料請求が認められるケースはあります。
人権侵害してしまったとき
自分が人権侵害の書き込みをしてしまったら、できるだけ早く対象の投稿を削除しましょう。
問題の書き込みをできるだけ早く削除します。加害者は被害者に発信者情報開示請求や損害賠償請求、刑事告訴などをされる可能性があるため、素早い行動が求められます。
ただし、該当の投稿を消しても、ネット上では一度書き込まれたものを完全に消去できるとは限りません。すでに拡散されていれば時すでに遅く、残り続けてしまうと考えられます。
人権侵害に当たるような書き込みをしてしまったと思ったら、相手に謝罪してください。
自分が間違っていたと誠心誠意謝罪をすれば、被害者の怒りが緩和される可能性があります。結果、民事や刑事による措置を回避できることもあるでしょう。
誹謗中傷の悩みは弁護士に相談
人権侵害のような誹謗中傷をされた、してしまったという悩みがあるなら、弁護士に相談するのがおすすめです。
被害者は削除要請や個人情報開示請求をする必要がありますが、相手がすんなり対応してくれるとは限りません。さらに、裁判は手続きが複雑であり法律の知識がないと進めるのが難しいのが現状です。
また、加害者は自分が訴訟の対象になるのかという不安があるかと思われます。どう対処すれば良いのか、弁護士のアドバイスを仰いでください。

誹謗中傷と人権侵害まとめ
インターネット上の誹謗中傷は人権侵害に該当する可能性があります。
名誉を毀損するような悪口や恐怖を与えるような脅迫、他人に知られたくないプライバシーを晒す行為などは人権侵害になり、加害者は民事や刑事上の責任を問われるケースは少なくありません。
ただ、被害者も加害者も正しい措置を取るには、法律の知識が必要になります。インターネット上のトラブルや人権問題に強い弁護士に相談し、スムーズな解決を図るようにしてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら