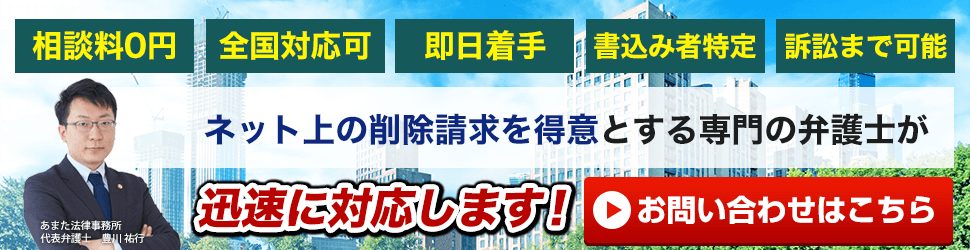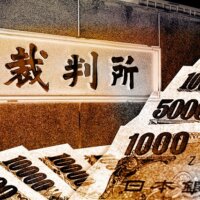インターネットネット上の掲示板やSNSなどで誹謗中傷を受けたら、相手が匿名であっても訴えることはできます。
悩んでいるのであれば、信頼できる機関へ相談し対策を練りましょう。

執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
誹謗中傷の被害を受けたときの相談先
ネットの匿名掲示板やSNSで悪口などの誹謗中傷を受けた際の相談先は、主に下記の3つが挙げられます。
- 国の相談窓口
- 民間の相談窓口
- 法律事務所や弁護士の相談窓口
それぞれの窓口に誹謗中傷の相談をするメリット・デメリットなど詳細を確認していきます。
国の相談窓口
主な相談場所になるのが「国の窓口」です。官公庁や警察など国が設けている窓口にて、ネットでの誹謗中傷被害を相談できます。
代表的なのは都道府県警察本部のサイバー事案に関する相談窓口です。
そのほか、ネット上のトラブル全般に対応している法務省の違法・有害情報相談センター、法務省インターネット人権相談受付窓口等があります。プロバイダやサイト運営者への削除依頼やトラブルの仲裁などは行っていませんが、誹謗中傷コメントを削除する方法の相談に乗ってもらえます。
国の相談窓口を利用する大きなメリットは、「無料で相談できる」点です。誹謗中傷の悩みを相談しても料金を支払う必要はなく、金銭的に心配しなくて良いのは強みと言えます。
もし、悪質性が高い誹謗中傷でありストーカーや傷害事件に発展する可能性があると考えられる状況では、最初から警察への相談がおすすめです。
民間の相談窓口
企業や法人が運営する民間の相談窓口を利用するのも一つの手です。
誹謗中傷ホットラインは民間企業の有志が集まり運営されている一般社団法人セーファーインターネット協会(SIA)が運営している相談窓口です。ネット上にある誹謗中傷が掲載されているサイトに、削除依頼を通知するといった対応をしています。
国内、海外のサイト問わず対象になり、相談料は無料です。インターネット環境があればスマホやパソコンから24時間利用できますので、誰でも気軽に利用できるWEB相談窓口と言えるでしょう。
誹謗中傷が記載されている掲示板やSNSの運営会社に直接被害を直接訴えると、相手方のアカウント凍結、各種調査の請け負いなどをしてくれることがあります。加害者のアカウントが無くなれば、以降は誹謗中傷に悩まされずサービスを継続して利用できる可能性が高まります。
ただし、悪質な誹謗中傷が行われていたとしても、サイト運営側が被害者に代わり相手方を訴えるのは極めて稀でほぼないと言ってよいくらいです。

法律事務所や弁護士の相談窓口
誹謗中傷した投稿者を訴えたいのであれば、法律事務所・弁護士に依頼するのがおすすめです。
法律事務所・弁護士はネット上の誹謗中傷の訴訟手続きや内容に関して熟知しています。訴訟に値する誹謗中傷に該当するかも判断してくれ、ケースに合わせた対応をしてくれます。
誹謗中傷した相手を訴えるのが前提なら、国や民間の窓口ではなく初めから法律事務所・弁護士に相談するのが早いでしょう。国・民間の窓口に相談しても、実際に訴訟に入るには法律事務所・弁護士のサポートが必要になると思われます。訴訟に移るまで余計な時間をかけてしまいます。また、いきなり警察に相談しても、インターネットのトラブルに関する法律に詳しくない個人だけで裁判を提起するのは困難なのが通常です。
法的手続きに移って相手を訴えるためには法律に詳しい弁護士に相談し、裁判の手続きをサポートしてもらうのが早いです。誹謗中傷の被害を訴えたいと考えるなら、法律事務所・弁護士を利用するようにしてください。
弁護士への依頼は費用が心配ですが、相談のみであれば初回は無料としている弁護士事務所は多数あります。

匿名の加害者を訴えるための準備
匿名の投稿者を誹謗中傷で訴える流れは、大まかに下記の流れに従って手続きをとっていきます。
- 誹謗中傷コメントなどの削除依頼
- 裁判所を通じた発信者の情報開示請求
- 損害賠償請求
ネット上の誹謗中傷は大半が「匿名」での行為です。匿名で身元がわからないことから、容易に他の人を傷つけるような文言を投稿すると考えられています。
匿名だと犯人が誰か分からず訴えられないというのは間違いで、実際のところ訴えることは可能です。
最近では芸能人やYouTuberなどがネットで誹謗中傷を行った加害者に対し、実際に訴訟を起こす事例が多くなっています。2008年にはお笑いタレントのスマイリーキクチさんに悪質な書き込みをしたとして多数の身元が特定され、18人が一斉に検挙されています。
デマを拡散されたり外見や人格を否定されるような書き込みだけでなく、殺害予告など危害を加えるひどい内容もあり見過ごすことが出来ないのは当然でしょう。「匿名だからバレはしない」と高を括って中傷していた人が、訴えられることはもはや珍しいことではありません。
誹謗中傷コメントを保存し削除依頼する
訴訟をするには誹謗中傷を受けた証拠を提出する必要があります。対象のコメントが表示された画面のスクリーンショットなど証拠の保存を忘れずに行うようにしましょう。その後、掲示板やSNSに投稿された誹謗中傷コメントの削除依頼を実行します。
コンテンツプロバイダ(インターネット掲示板やX(旧Twitter)などのサイト運営者や管理者等)に削除を求めると、対象の書き込みを削除してくれる可能性があります。
悪質なコメントであると判断されれば、サイト運営者が加害者の特定情報(IPアドレス)を開示してくれることがあります。IPアドレスはネット上の住所のようなもので、IPアドレスからアクセスプロバイダ(NTTなど)がわかるため、プロバイダ会社に個人情報の開示請求を行える状態になります。
裁判所を通じた発信者の情報開示請求
サイト運営者が加害者のIPアドレスの開示に応じてくれない場合は、サイト運営者に対し発信者情報の開示の仮処分を裁判所へ申立てます。
サイト運営者は情報開示に被害者である開示請求者の要望に必ずしも応じてくれるわけではありません。個人情報を守る義務があるため、誹謗中傷をしたとしてもユーザーの氏名、メールアドレス、電話番号といった個人情報を第三者に教えることは慎重にならざるを得ないのです。

損害賠償請求
個人情報開示請求により誹謗中傷した加害者の身元が特定できたら、内容証明や裁判を通じ民事上の責任を問う損害賠償請求を行っていきます。
慰謝料の相場
損害賠償請求(慰謝料)の相場は、内容によって異なります。
- 名誉毀損(個人):10~50万円
- 名誉毀損(企業):50~100万円
- 侮辱:10万円程度
- プライバシー侵害:10~50万円
罪の定義
どの罪にあたるかは、以下のような定義により決められます。
- 名誉毀損罪:公然と「事実を摘示して」第三者の評判を落とす行為
- 侮辱罪:「事実を摘示しないで」公然と第三者の評判を落とす行為
- プライバシー侵害:「公共の場で公開を望んでいない」個人情報・私生活の情報の暴露

示談での解決方法もある
加害者が損賠賠償請求を素直に応じた場合は、訴訟まで進まず示談交渉で解決を図る方法があります。訴訟を提起した後であっても、示談が成立すれば訴訟を取り下げることも可能です。ただ、加害者が否定する主張をしたり賠償金額に不服な態度を示した場合など双方が納得せず交渉が決裂になれば、裁判を通じて損害賠償の有無・金額が決定されます。
刑事告訴する
加害者に対し逮捕や起訴などの刑事事件としての罰を望むなら警察への告訴を行います。
誹謗中傷を行った加害者に対して科される刑法での罰は下記のとおりです。
- 名誉毀損罪:3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
- 侮辱罪:拘留(1日以上30日未満刑事施設拘置)または科料(1,000円以上1万円未満の罰金)
- プライバシー侵害:プライバシー侵害として処罰を受けることはない ※ただし、ほかの法令に触れた場合にはそれによって処罰される可能性あり
例えば、プライバシー侵害であるとともに名誉を棄損したと当たり得るのであれば、名誉毀損罪で処罰される可能性が出てきます。
発信者情報開示請求や訴訟に必要な弁護士費用
発信者情報開示請求や訴訟のために弁護士を依頼すると、さまざまな弁護士費用がかかってきます。数十万円からトータルで100万円以上かかることもあります。
加害者の情報を特定するために、合計60万円~100万円ほどの費用が発生します。損害賠償請求を行うまで、いずれも費用は被害者側の自己負担です。決して安い金額ではないため、損害賠償請求をしたくても経済的に難しくなる事態は少なくありません。

誹謗中傷した加害者を訴える方法まとめ
ネット上の匿名の書き込みであっても個人情報開示請求により投稿者が判明すれば、誹謗中傷の加害者として訴えることは可能であり、泣き寝入りする必要はありません。できるだけ早く国や民間、弁護士事務所などの窓口に相談し、悪質な行為であれば訴訟を検討してください。
ただし、加害者が誰なのかを特定する手続きは複雑で時間もかかります。また、損害賠償請求や刑事告訴するには法的な根拠が重要になり、法律に詳しくない個人が行うのは難しいといえます。インターネット上のトラブル事案を豊富に扱っている弁護士に依頼し、ケースに合わせたアドバイスしてもらうのが良いです。弁護士費用はかかりますが、悪質な誹謗中傷による悩みをスムーズに解決できるでしょう。
無料相談サービスがある弁護士事務所なら費用はかかりませんので、話だけでも聞いてもらうのがおすすめです。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら