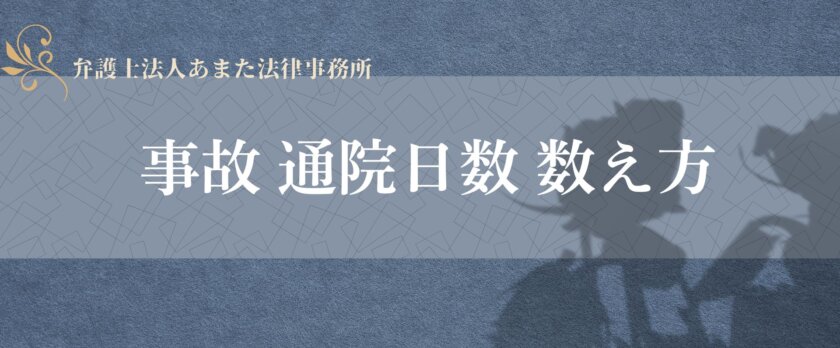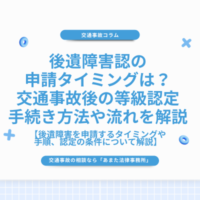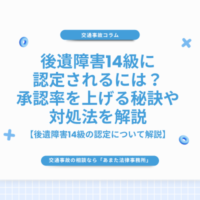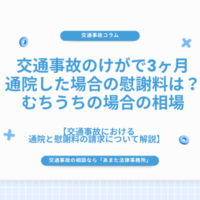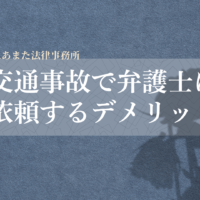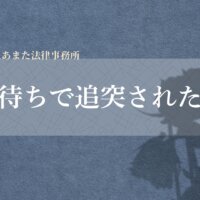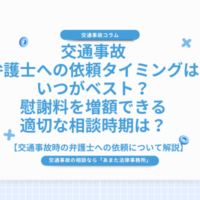交通事故に遭って治療を受けているが、慰謝料計算に使われる通院日数の正確な数え方がわからず困っていませんか?
保険会社から提示された金額が適正なのか判断できない、自分で通院日数を計算したいが実治療日数との違いがよくわからない、どの基準で計算されているのかさっぱりわからない、といった悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
特に自動車損害賠償保障法に基づく自賠責基準では「実治療日数×2」と「治療期間」を比較して少ない方を採用するため、通院頻度や計算方法を間違えると数十万円単位で損をする可能性もあるのです。
この記事では、事故で通院日数を数える時の基本的なポイントから、自賠責・任意保険・弁護士基準それぞれでの計算方法の違い、土日祝日や検査日の扱い、複数病院通院時の注意点まで、実際の計算例を交えながら詳しく解説します。
さらに適切な通院頻度の保ち方や記録の残し方など、慰謝料で損をしないための実践的なコツも紹介しています。
また弁護士相談が必要なケースの見極めもできるため、最適な慰謝料請求方法を選択できるようになるでしょう。
この記事の目次
事故で通院日数を数える時のポイント
正確な日数を把握することで、適正な慰謝料を受け取ることができるため、数え方のポイントを理解しておくことが大切です。
交通事故における通院日数の計算では、「実通院日数」と「治療期間」という2つの概念を区別して理解する必要があります。
実通院日数とは、実際に医療機関を訪れた日数のことで、治療期間とは治療開始日から治療終了日までの総日数を指します。

まず、治療期間(治療開始日から終了日まで)と、実通院日数の2倍のどちらか少ない方を選択するのが原則です。
ただし、通院頻度が極端に少ない場合には、実通院日数に3.5を乗じた日数が治療期間として採用されることもあります。
- 治療期間 vs 実通院日数×2(少ない方を採用)
- 通院頻度が少ない場合:実通院日数×3.5も考慮
- 1日あたりの基準額:4,300円
また、リハビリテーション施設への通院や、整骨院・接骨院での施術も通院日数に含まれる場合があるため、これらの記録も漏れなく残しておく必要があります。
📝 記録すべき書類・情報
- 診療明細書・領収書
- 通院日付の記録(手帳・カレンダー)
- リハビリ施設の通院記録
- 整骨院・接骨院の施術記録
通院日数の計算で注意すべき点として、同日に複数の医療機関を受診した場合でも通院日数は1日としてカウントされることが挙げられます。
さらに、医師の指示による自宅療養期間や、検査のための通院も治療の一環として認められる場合があるため、これらの日程についても記録を保持しておくことが推奨されます。
弁護士基準では通院期間を重視する傾向があり、自賠責基準よりも高額な慰謝料となることが一般的です。
適正な慰謝料を受け取るためには、これらの基準の違いを理解し、必要に応じて専門家に相談することも大切です。
| 算定基準 | 特徴 | 慰謝料額 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 法定最低限の基準 | 最も低額 |
| 任意保険基準 | 各保険会社の基準 | 自賠責より高額 |
| 弁護士基準(裁判基準) | 通院期間を重視 | 最も高額 |

通院日数の基本的な数え方
交通事故の慰謝料計算において、通院日数の正確な把握は非常に重要です。
通院日数には「通院期間」と「実通院日数」の2つの概念があり、それぞれ異なる意味を持ちます。
例えば、4月1日に治療を開始し6月30日に治療が終了した場合、通院期間は91日となります。
一方、実通院日数とは、実際に病院や整骨院などの医療機関に足を運んだ日数のことです。

通院期間と実通院日数は全く違う概念なんですね。
毎日通院していなくても、治療期間全体が通院期間になるということですね。
自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責保険基準での慰謝料計算では、日額4,300円に以下の計算式で算出した日数を乗じて算出されます。
- 通院期間の全日数
- 実通院日数×2
上記2つのうち、少ない方の日数が採用されます。

実際に病院に行った日数をカウント
基本的には、医療機関で実際に診察や治療を受けた日が対象となります。
- 病院や診療所での診察を受けた日
- 整骨院や接骨院での施術を受けた日(医師の指示がある場合)
- レントゲンやMRIなどの検査を受けた日
- リハビリテーションを受けた日
- 薬の処方のみでも医師の診察を受けた日
- 単純に薬だけを受け取りに行った日(診察なし)
- 予約をキャンセルした日
- 医療機関が休診で受診できなかった日

実通院日数を正確に記録するため、診察券や領収書、お薬手帳などを保管しておくことをお勧めします。
また、診断書や厚生労働省が管轄する診療報酬明細書(レセプト)にも実通院日数が記載されるため、これらの書類も重要な証拠となります。
通院期間と実通院日数の違い
例えば、3か月間(90日)の治療期間があった場合、実際に通院した日数が30日であっても、通院期間は90日となります。

📝 慰謝料計算の基本ルール
慰謝料計算では、自賠責保険基準(国土交通省)の場合、通院期間と実通院日数×2のうち少ない方が採用されます。
この仕組みにより、通院頻度が2日に1日以上(月の半分以上)であれば通院期間がベースとなり、通院頻度が少ない場合は実通院日数×2がベースとなります。
- 通院期間90日、実通院日数30日の場合:実通院日数×2(60日)<通院期間(90日)なので、60日が採用
- 通院期間90日、実通院日数50日の場合:通院期間(90日)<実通院日数×2(100日)なので、90日が採用

慰謝料計算で使われる通院日数の仕組み
慰謝料計算には主に「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があり、それぞれで通院日数の扱い方が異なります。

自賠責保険ポータルサイト(国土交通省)で定められた自賠責基準は国が定めた最低限の補償基準で、1日当たり4,300円の固定金額で計算されます。
任意保険基準は各保険会社が独自に設定した基準で、自賠責基準よりもやや高めに設定されているケースが多いものの、具体的な金額は非公開です。
弁護士基準は過去の裁判例をもとにした最も高額な基準で、「赤本」「青本」と呼ばれる算定表を用いて計算されます。
自賠責基準での通院日数の計算方法
自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準では、通院慰謝料の計算に特有の方法が用いられます。
対象日数は、①治療期間(事故日から治療終了日まで)と②実治療日数×2、この2つのうち少ない方の数字を採用します。
例えば、治療期間が90日で実際に病院に通った日数が30日の場合、①90日と②30×2=60日を比較し、少ない方の60日が対象日数となります。
この場合の慰謝料額は60×4,300円=258,000円となります。

実治療日数を2倍にする理由は、通院による身体的負担だけでなく、通院しない日も含めた精神的苦痛を考慮しているためです。
自賠責基準の特徴として、症状の重さや部位に関わらず日額が一律4,300円に設定されている点があります。
また、国土交通省の自賠責保険制度では、自賠責保険の支払い限度額は120万円(治療費・休業損害・慰謝料の合計)となっており、これを超える場合は任意保険や加害者本人への請求が必要になります。
- 対象日数は治療期間と実治療日数×2の少ない方
- 日額は一律4,300円(症状に関わらず)
- 支払い限度額は120万円(治療費等の合計)
任意保険基準と弁護士基準での違い
しかし、具体的な算定表は非公開となっており、保険会社によって金額に差があります。
通院日数については、実治療日数よりも治療期間を重視する傾向があり、定期的な通院が推奨されます。

弁護士基準は過去の裁判例をもとにした最も高額な基準で、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤本)や「交通事故損害額算定基準」(青本)の算定表を使用します。
この基準では、通院期間に応じて慰謝料が段階的に設定されており、例えば3か月通院の場合は73万円程度となります。
📝 弁護士基準の特徴
過去の裁判例に基づく最も公正で高額な基準として位置づけられています
弁護士基準の大きな特徴は、症状の程度によって「別表Ⅰ」と「別表Ⅱ」に分かれている点です。
むちうちや打撲などの軽傷は別表Ⅱを、骨折や脱臼などの重傷は別表Ⅰを適用し、別表Ⅰの方が高額に設定されています。
| 症状分類 | 対象となるケガ | 慰謝料水準 |
|---|---|---|
| 別表Ⅰ | 骨折・脱臼・神経損傷など | 高額 |
| 別表Ⅱ | むちうち・打撲・捻挫など | 標準 |
どの基準が適用されるかの判断については、示談交渉では任意保険基準、調停や裁判では弁護士基準が用いられるのが一般的です。
被害者自身で示談交渉を行う場合は任意保険基準での提示となることが多く、弁護士に依頼することで弁護士基準での交渉が可能となります。

- 任意保険基準は各社独自の非公開基準
- 弁護士基準は裁判例に基づく最高水準
- 症状により別表Ⅰ・Ⅱで金額が異なる
- 弁護士依頼で弁護士基準での交渉が可能
通院日数を数える時に注意すること
正確な通院日数を把握することで適正な補償を受けることができます。
交通事故などの事故後の通院日数の計算は、慰謝料や保険金の算定に直接影響する重要な要素です。
正確な通院日数を把握することで適正な補償を受けることができるため、数え方のルールを正しく理解する必要があります。

通院日数の計算では「実通院日数」が基本となり、これは実際に医療機関に通院した日数のことです。
自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責保険基準では、治療期間または実通院日数×2のうち少ない方を慰謝料算定の対象日数として使用するため、正確な実通院日数の把握が不可欠です。
計算ミスを防ぐためには、通院のたびに日付を記録し、診療明細書や領収書を保管することが重要です。
また、通院できなかった日や休診日の扱いについても事前に理解しておくことで、後のトラブルを避けることができます。
- 実通院日数の正確な記録
- 診療明細書・領収書の保管
- 自賠責保険基準の理解
- 通院できなかった日の扱いの確認
土日祝日や休診日は含まれない
通院日数のカウントでは、実際に医療機関を受診した日のみが対象となるため、土日祝日や医療機関の休診日は通院日数に含まれません。
これは「実通院日数」の定義に基づくもので、通院する意思があっても医療機関が休診であれば通院できないためです。
また、医療機関の都合による臨時休診日も同様に通院日数には含まれません。

通院予定日と実通院日を区別することが重要で、医師から「毎日通院してください」と指示されても、実際に通院できた日数のみが慰謝料等の算定対象となります。
風邪などの体調不良で通院できなかった場合も、実通院していない日は日数に含まれないため注意が必要です。
複数の病院に通った場合の数え方
整形外科と内科、または病院とクリニックなど、異なる医療機関への通院であっても、同一の事故によるケガの治療であれば全て通院日数としてカウントされます。

転院した場合も同様で、転院前の病院への通院日数と転院後の病院への通院日数を合計します。
例えば、A病院に10日間通院した後にB病院に転院して15日間通院した場合、総通院日数は25日となります。
- 同一日に複数の医療機関を受診しても通院日数は1日
- 各医療機関での診療記録を別々に保管
- 通院日程を明確に記録
午前中に整形外科、午後に内科を受診しても実通院日数は1日です。

検査だけの日もカウントされるのか
これは検査も治療行為の重要な部分であり、診断や治療方針の決定に必要な医療行為だからです。

診察なしで検査技師による検査のみを受けた場合でも、それが担当医の指示によるものであれば通院日数に含まれます。
ただし、検査結果を聞きに行くだけの日や、単なる薬の受け取りのみの場合については、医療機関によって取り扱いが異なる場合があります。
理学療法士によるリハビリテーション、薬剤師による服薬指導なども、医師の指示に基づくものであれば通院日数に含まれます。

📝 通院日数にカウントされる検査の例
- 医師の指示によるレントゲン撮影
- 医師の指示によるMRI・CT検査
- 医師の指示による血液検査
- 医師の指示による心電図検査
通院日数で損をしないためのコツ
適切な通院管理で損をしないポイントを押さえましょう。
通院日数は慰謝料算定の重要な要素であり、自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責保険では1日あたり4,300円の基準で計算されます。
しかし、単純に通院回数を増やせば良いというものではなく、適切な頻度と記録管理が重要となります。

医師の指示に従った適切な通院が大切ですね。
保険会社との交渉において、通院日数は「実通院日数」と「治療期間」の2つの基準で評価されます。
実通院日数は実際に医療機関を受診した日数を指し、治療期間は初診から治療終了までの期間を指します。
| 基準の種類 | 内容 |
|---|---|
| 実通院日数 | 実際に医療機関を受診した日数 |
| 治療期間 | 初診から治療終了までの期間 |
通院日数を最大化するためには、医師の治療方針に従いつつ、症状に応じた適切な通院を継続することが大切です。
過度な通院は保険会社から疑問視される可能性がある一方、通院間隔が空きすぎると症状の改善と判断され、治療の必要性を疑われるリスクがあります。
- 医師の指示に従った適切な頻度での通院
- 通院記録の正確な管理と保存
- 症状に応じた継続的な治療
- 保険会社との適切なコミュニケーション
適切な通院頻度を保つ方法
医師は症状の程度や回復状況を総合的に判断し、最適な通院間隔を指示します。
一般的には、急性期では週3~4回、症状が安定してきた時期では週2~3回程度が目安とされています。

保険会社は通院の必要性を厳格に審査しており、医学的根拠のない頻繁な通院は治療費の支払い拒否や慰謝料の減額につながる可能性があります。
特に、同じ治療内容で毎日通院している場合は、保険会社から不適切な通院と判断されるリスクが高まります。
⚠️ 過度な通院のリスク
医学的根拠のない頻繁な通院は、治療費支払い拒否や慰謝料減額の原因となる可能性があります。
一方で、通院不足も問題となります。
通院間隔が1週間以上空くと、症状が改善したと判断され、治療の必要性を疑われる可能性があります。 仕事や家庭の事情で通院が困難な場合でも、最低でも週1回は通院し、医師に症状の変化を報告することが重要です。

痛みの増悪や新たな症状の出現があった場合は、医師の判断により通院頻度を増やすことも可能です。
| 時期 | 推奨通院頻度 | 注意点 |
|---|---|---|
| 急性期 | 週3~4回 | 医師の指示に厳格に従う |
| 安定期 | 週2~3回 | 症状の変化を定期報告 |
| 回復期 | 週1~2回 | 通院間隔の調整が重要 |
通院の記録を残しておく大切さ
通院証明書や診療明細書は必ず保管し、通院日時、治療内容、症状の変化を詳細に記録しておくことが重要です。
これらの記録は慰謝料請求時の根拠資料として活用され、適正な補償を受けるための重要な証拠となります。

日常的な症状の記録も欠かせません。
痛みの程度、日常生活への影響、睡眠障害などの症状を日記形式で記録し、医師の診察時に報告することで、適切な治療方針の決定に役立ちます。
また、これらの記録は後遺障害認定の際にも重要な資料となる可能性があります。
- 痛みの程度を10段階で評価
- 日常生活への具体的な影響
- 睡眠の質や時間の変化
- 気分や精神状態の変化
通院に要した交通費は民法(e-Gov法令検索)第709条に基づく損害として請求できるため、公共交通機関の切符やタクシーレシート、駐車場料金の領収書などはすべて保管しておく必要があります。
積み重なると大きな金額になります。
治療開始から終了まで、いつ、どこの医療機関で、どのような治療を受けたかを明確に整理し、必要に応じて医師に診断書や治療経過報告書の作成を依頼することが重要です。
📋 提出書類の整理方法
時系列順に整理し、治療内容と症状の変化を明確に記載することで、保険会社への説得力のある資料となります。
デジタルでの記録管理も有効です。 スマートフォンのアプリや表計算ソフトを活用し、通院日、治療内容、症状、費用を一元管理することで、必要な情報をすぐに参照できるようになります。
これらの記録は弁護士に相談する際にも重要な資料となるため、体系的に管理しておくことをお勧めします。
| 記録項目 | 記録方法 | 重要度 |
|---|---|---|
| 通院日時 | カレンダーアプリ | ★★★ |
| 治療内容 | メモアプリ | ★★★ |
| 症状の変化 | 日記形式 | ★★★ |
| 交通費 | 家計簿アプリ | ★★☆ |

通院日数に関するよくある質問
通院日数には「実通院日数」と「通院対象期間」の2つの概念があり、慰謝料計算では通常、実通院日数の2倍と通院対象期間のうち少ない方が採用されます。

実通院日数とは、実際に医療機関を受診した日数のことで、通院対象期間とは治療開始日から治療終了日までの総日数を指します。
例えば、4月1日から9月30日まで治療を受けた場合、通院対象期間は183日となりますが、実際の通院が月に10回程度であれば、実通院日数は約60日となります。
この場合、慰謝料計算には実通院日数の2倍である120日が適用されることになります。
• 通院対象期間:183日(4月1日〜9月30日)
• 実通院日数:約60日(月10回×6ヶ月)
• 実通院日数の2倍:120日
• 慰謝料算定に使用される日数:120日(少ない方)
基本的に、継続的かつ定期的な通院が行われている場合は通院対象期間が、間隔が空いた通院の場合は実通院日数の2倍が採用される傾向にあります。
📝 通院日数計算の重要ポイント
通院の頻度や継続性によって、どちらの日数が採用されるかが決まるため、適切な通院計画を立てることが慰謝料算定において重要になります。
整骨院や接骨院の通院も含まれるのか
原則として、医師による診察と治療方針の決定が前提となり、医師の同意なしに整骨院のみへの通院を続けた場合、保険会社から治療費の支払いや通院日数の認定を拒否される可能性があります。

整骨院での施術は柔道整復師法(e-Gov法令検索)に基づいて行われますが、交通事故の場合は医師の管理下での治療が重要になるんですね。
保険会社が整骨院通院を認める条件として、まず医師による初期診断と継続的な経過観察が必要です。
また、整骨院での施術内容が事故による症状に対して適切で必要な範囲内であることも求められます。
むちうち症などの軟部組織損傷の場合、医師の診断書に「柔道整復師による施術が有効」といった記載があることが望ましいとされています。
- 医師による初期診断と継続的な経過観察
- 事故症状に適切で必要な範囲内の施術内容
- 医師の診断書に施術有効性の記載(望ましい)
また、整骨院と病院を併用している場合、同一日の重複通院は1日として計算されるのが一般的です。

通院をやめるタイミングの判断方法
自己判断や保険会社の打ち切り通告で通院をやめることは適切な慰謝料を受け取れない原因となる可能性があります。
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態を指し、この判断は必ず厚生労働省の定める医師資格を持つ専門家が行うものです。
自己判断や保険会社の打ち切り通告によって通院をやめることは、適切な慰謝料を受け取れない原因となる可能性があります。

症状固定の判断時期は、一般的にむちうち症では事故から3〜6ヶ月、骨折などの重傷では6ヶ月〜1年程度とされていますが、個人の症状や回復状況によって大きく異なります。
医師が症状固定と判断した場合、その日が治療終了日となり、それ以降の通院日数は慰謝料計算に含まれなくなります。
- 医師のみが症状固定を判断できる
- 症状固定日が治療終了日となる
- 症状固定後の通院は慰謝料計算に含まれない
保険会社から治療費打ち切りの連絡があった場合でも、医師が治療継続の必要性を認めているなら、自己負担でも通院を続けることが重要です。
後に示談交渉において、必要かつ相当な治療であったことが認められれば、自己負担分も請求できる可能性があります。
症状があるにも関わらず通院間隔を大幅に空けてしまうと、治療の必要性に疑問を持たれ、実際の症状よりも軽微な損害として扱われる可能性があります。
症状が改善している場合でも、医師の判断なしに勝手に通院をやめることは避けるべきです。

医師の指示に従うことが大切ですね。
📝 通院終了の判断で注意すべき点
自己判断での通院終了は絶対に避ける
医師の診断に基づいた適切なタイミングで治療を終了することで、適正な慰謝料を確保できます。