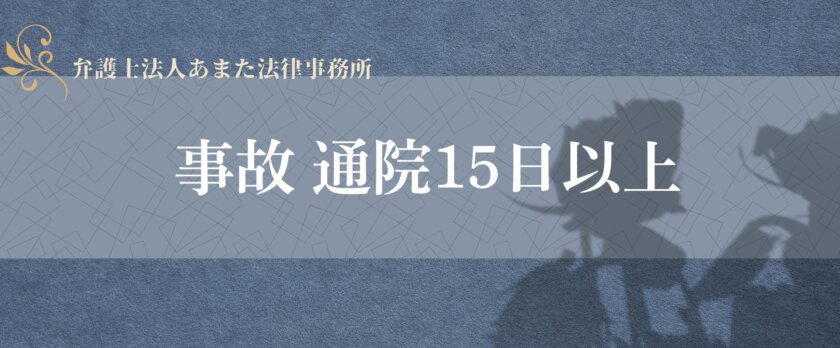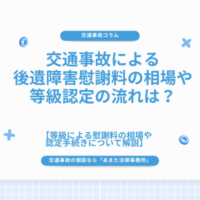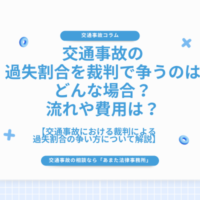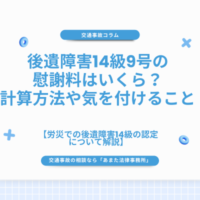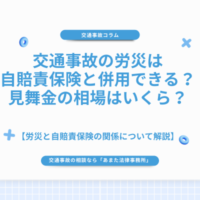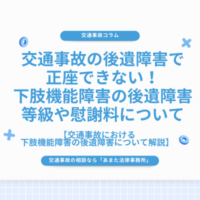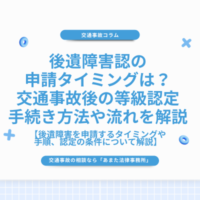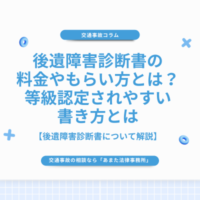交通事故で怪我を負い、「通院15日以上が慰謝料にどう影響するのか分からない」「自賠責基準と弁護士基準の違いが分からない」「保険会社から提示された金額が適正なのか判断できない」といった悩みを抱えていませんか?
通院15日以上という日数は、慰謝料計算において極めて重要な分岐点です。
この記事では、通院15日以上の慰謝料を自賠責・任意保険・弁護士の3つの基準で具体的に計算し、慰謝料を最大化するための通院方法や記録の残し方、保険会社との適切な対応方法を詳しく解説します。
さらに実際の手続きの流れや、やってはいけない通院パターンなどの注意点も分かりやすく説明します。
この記事を読めば、あなたのケースに最適な慰謝料額を正確に把握し、保険会社との交渉で適正な補償を受けられるようになります。
なお、自賠責保険については自動車損害賠償保障法に基づき、国土交通省が制度運営を行っています。
この記事の目次
事故で通院15日以上になったときの慰謝料はいくら?
日本では主に「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの算定基準があり、同じ通院期間でも受け取れる慰謝料に数倍の差が生じることがあります。

具体的には「治療期間」と「実際の通院日数×2」のどちらか少ない方の日数に4,300円をかけた金額になります。
通院15日の場合、実際の通院日数が15日であれば15日×2=30日となり、治療期間が30日以内なら治療期間の日数で計算されます。
例えば治療期間が20日の場合、20日×4,300円=86,000円が慰謝料額となります。
通院15日の場合、軽傷であれば約9万5,000円、重傷の場合は約14万円程度が相場とされています。 この基準は過去の裁判例をもとに設定されており、被害者が最も多くの慰謝料を受け取れる可能性があります。
| 算定基準 | 通院15日の慰謝料相場 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 約8.6万円 |
| 任意保険基準 | 約8〜12万円 |
| 弁護士基準 | 約9.5〜14万円 |
任意保険基準は各保険会社が独自に設定している基準で、一般的に自賠責基準と弁護士基準の中間程度の金額となることが多いです。
ただし、保険会社によって基準が異なるため、具体的な金額は個別のケースによって変わります。
むち打ち症などの軽傷の場合と、骨折などの重傷の場合では、同じ通院期間でも慰謝料額に差が生じることが一般的です。
また、通院の頻度や必要性についても、医師の診断書や治療経過が重要な判断材料となります。
- 医師による適切な診断と治療を受ける
- 通院記録をしっかりと残す
- 弁護士基準での算定を求める
- 必要に応じて弁護士に相談する
その上で、保険会社との交渉では自賠責基準ではなく、より高額な弁護士基準での算定を求めることが被害者にとって有利となります。
交渉が難航する場合は、交通事故に詳しい弁護士への相談を検討することをお勧めします。

通院15日以上で変わること・知っておくべきポイント
特に通院15日という日数は、慰謝料の算定方法に影響を与える可能性があります。

交通事故の慰謝料は、主に自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つの算定基準があります。
自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準では、慰謝料の対象となる日数は「治療期間」または「実通院日数×2」のうち少ない方を採用します。
例えば、治療期間が90日で実通院日数が24日の場合、24日×2=48日が対象日数となり、自賠責基準の日額4,300円を乗じて計算されます。
この基準では、月あたり15日程度の通院を前提とした算定が行われることが多く、実際の通院日数よりも治療期間に重点を置いた計算方法となります。
15日という日数が重要な理由
この基準は、一般的な傷病の治療において医学的に適切とされる通院頻度を反映したものです。

裁判所で使用される慰謝料算定表(通称「赤い本」や「青い本」)では、通院期間を基準とした算定方式が採用されており、月15日程度の通院を前提としています。
これは、医師の治療方針に従った適切な頻度での通院を評価し、過度な通院による不当な慰謝料請求を防ぐ目的もあります。
慰謝料の計算方法が変わるタイミング
自賠責基準から弁護士基準への移行で慰謝料額は大きく増額する可能性があります。
自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準から弁護士基準への移行により、慰謝料額は大幅に変わる可能性があります。
- 対象日数に日額4,300円を乗算
- 通院期間90日、実通院日数24日の場合
- 対象日数:48日(24日×2)
- 慰謝料:20万6,400円(4,300円×48日)
自賠責基準では、対象日数に日額4,300円を乗じて計算します。
例えば、通院期間90日、実通院日数24日の場合、対象日数は48日(24日×2)となり、慰謝料は20万6,400円(4,300円×48日)です。

弁護士基準では、通院期間を基準とした算定表を使用します。
同じ90日の通院期間でも、弁護士基準では自賠責基準を大幅に上回る慰謝料額が算定される場合があります。
この違いは、通院期間が長くなるほど顕著になります。
月15日を目安とした適切な通院頻度を維持し、必要な治療を継続することが、結果的に適正な慰謝料の算定につながります。
過度な通院は医学的に不適切とみなされ、かえって慰謝料減額の要因となる可能性もあるため注意が必要です。
通院15日以上の慰謝料を3つの基準で計算してみる
交通事故で怪我をして通院15日以上になった場合、慰謝料の算定には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つの基準があります。
これらの基準によって支払われる慰謝料額は大きく異なり、同じ通院期間でも数倍の差が生じることがあります。
自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準は最低限の補償を保障するもので、任意保険基準は保険会社が独自に設定する基準、弁護士基準は過去の判例に基づく最も高い水準の基準となっています。
通院15日以上のケースでは、これらの基準間で慰謝料額に大幅な格差が生まれるため、適切な基準を選択することが被害者の正当な補償を受ける上で極めて重要です。

自賠責基準での慰謝料額
2020年4月の法改正により従来の日額4,200円から4,300円に引き上げられ、現在はこの新基準が適用されています。
この基準は自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づき、国土交通省の自賠責保険支払基準で定められています。

被害者にとって重要な改正です。
自賠責基準では以下の2つの計算方法のうち、金額の少ない方が適用されます。
- 日額4,300円×治療期間(実際の治療開始日から終了日まで)
- 日額4,300円×(実通院日数×2)
実通院日数での計算:4,300円×(15日×2)=129,000円
→同額のため129,000円が慰謝料額
治療期間での計算では4,300円×30日=129,000円、実通院日数での計算では4,300円×(15日×2)=129,000円となり、この場合は同額の129,000円が慰謝料額となります。
実通院日数での計算:4,300円×30日=129,000円 →少ない方の129,000円が支払われる
任意保険基準での慰謝料額
多くの保険会社では、この基準を社外秘としているため正確な算定表は公開されていませんが、業界全体として一定の相場が形成されています。

| 通院期間 | 実通院日数 | 慰謝料額の目安 |
|---|---|---|
| 1か月(30日) | 15日程度 | 15万円~20万円程度 |
| 2か月(60日) | 15日 | 25万円~35万円程度 |
この金額は自賠責基準を上回るものの、後述する弁護士基準と比較すると相当低い水準に設定されているのが実情です。
被害者が保険会社の提示額をそのまま受け入れてしまうと、本来受け取れる適正な補償額を大幅に下回る可能性があります。

弁護士基準(裁判基準)での慰謝料額
日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に掲載されている基準表が広く使用されています。

通院15日以上のケースでの弁護士基準による慰謝料額は、症状の程度により軽症用と重症用の2つの表を使い分けます。
軽症(むちうち症で他覚症状がない場合など)では、通院期間1か月で約19万円、2か月で約36万円となります。
重症(骨折や他覚症状を伴う外傷など)の場合は、通院期間1か月で約28万円、2か月で約52万円が基準額となります。
- 自賠責基準:129,000円
- 任意保険基準:約30万円
- 弁護士基準(軽症):36万円
- 弁護士基準(重症):52万円
弁護士基準は自賠責基準の約2.8倍から4倍の金額となり、適正な損害賠償額を受け取るためには弁護士基準による算定が重要であることがわかります。
弁護士基準での適正な賠償額を受け取るためには、専門家のサポートが重要です。
通院15日以上で慰謝料を増やすためにした方がいいこと
自賠責保険ポータルサイト(国土交通省)では通院30日のうち15日以上の実通院で12万9,000円、60日のうち20日以上の実通院で25万8,000円と定められており、実際の通院日数が慰謝料額に直接影響します。
弁護士基準を適用すれば、さらに高額な慰謝料を獲得できる可能性があります。
ただし、そのためには適切な通院記録や医学的根拠が必要不可欠です。

慰謝料を最大化するために、通院期間中に取るべき重要な対策について詳しく解説します。
- 実通院日数が慰謝料計算の基準となる
- 医師の指示に従った継続的な通院が重要
- 症状の変化を詳細に記録する
- 適切な検査を受けて医学的根拠を残す
通院頻度と治療内容の記録を残す
保険会社は通院の必要性や治療の合理性を厳しく査定するため、詳細な記録が慰謝料増額の鍵となります。
保険会社は通院の必要性や治療の合理性を厳しく査定するため、詳細な記録が慰謝料増額の鍵となります。

通院日ごとに以下の内容を記録しておくことが重要です。
- 通院した日付
- 受けた治療内容(リハビリ、物理療法、薬物療法など)
- 治療時間
- 担当した医師や理学療法士の名前
- 処方された薬剤名と量
これらの記録は、治療の継続性と必要性を証明する重要な資料となります。
| 交通手段 | 記録すべき内容 |
|---|---|
| 公共交通機関 | 運賃、利用区間、領収書 |
| 自家用車 | ガソリン代、駐車料金、走行距離 |
公共交通機関を利用した場合は運賃を、自家用車を利用した場合はガソリン代や駐車料金を記録し、レシートを保管することで交通費も慰謝料とは別に請求できます。

仕事の都合や体調不良による通院困難など、やむを得ない事情があることを証明できれば、空白期間による慰謝料減額を防げる可能性があります。
仕事の都合や体調不良による通院困難など、やむを得ない事情があることを証明できれば、空白期間による慰謝料減額を防げる可能性があります。
慰謝料の法的根拠については、民法第709条(e-Gov法令検索)や自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づいて算定されます。
- 通院日ごとの詳細な記録作成
- 診療明細書・領収書の保管
- 交通費の記録とレシート保管
- 空白期間の理由記録
医師の指示に従った適切な通院をする
医師の治療方針に沿った通院は、慰謝料算定において治療の必要性と相当性を証明する重要な要素となります。
自己判断による通院の中断や過度な通院は、慰謝料減額の原因となる可能性があります。
例えば、「週2回の通院を3ヶ月間継続」という指示があった場合、可能な限りその頻度を維持することで、治療の必要性を客観的に証明できます。
仕事や家庭の事情で指示通りの通院が困難な場合は、医師に相談して代替案を検討してもらいます。

通院頻度を守ることで、治療の必要性を客観的に示すことができますね。
処方された薬剤は医師の指示通りに服用し、リハビリテーションなどの指示も忠実に実行します。
自己判断による服薬中止や治療の変更は避け、疑問がある場合は必ず医師に確認を取ります。
MRIやレントゲン検査の結果は、症状の客観的証明に役立ち、慰謝料算定において重要な医学的根拠となります。
検査結果のコピーを取得し、治療経過とともに保管しておきます。
- MRIやレントゲン検査は客観的証明に重要
- 検査結果のコピーを必ず取得・保管
- 治療経過と合わせて記録を整理
医師から症状固定の診断を受けるまで通院を継続することも重要です。
症状固定前の示談成立は、後遺障害慰謝料の請求機会を失うリスクがあるため、治療の終了時期は医師の判断に委ねることが賢明です。
症状の変化を詳しく記録しておく
主観的な症状であっても、詳細な記録により医学的根拠を補強できます。

日々の症状を具体的に記録することが重要です。
痛みの程度を10段階で評価し、痛む部位、痛みの性質(鈍痛、刺すような痛み、しびれなど)、痛みが強くなる動作や時間帯を詳細に記載します。
天候による症状の変化や、日常生活への影響も併せて記録します。
- 痛みの程度(10段階評価)
- 痛む部位の特定
- 痛みの性質(鈍痛・刺すような痛み・しびれなど)
- 痛みが強くなる動作や時間帯
- 天候による症状の変化
「首を右に向けると45度程度で痛みが生じ、それ以上回せない」「重いものを持つと腰に激痛が走る」など、具体的な動作と制限の程度を記載します。
| 記録項目 | 記録例 |
|---|---|
| 可動域制限 | 首を右に向けると45度程度で痛みが生じ、それ以上回せない |
| 筋力低下 | 重いものを持つと腰に激痛が走る |
| 動作制限 | 階段の昇降時に膝に痛みが走り、手すりが必要 |
症状による日常生活への影響も詳細に記録しておきます。
家事や仕事への支障、睡眠障害、精神的な苦痛などを具体的に記載することで、慰謝料算定における「精神的苦痛」の程度を証明できます。

「理学療法開始後1週間で可動域が10度改善」「投薬により夜間痛が軽減」など、治療による変化を数値や具体的な表現で記録することが重要です。
写真や動画による記録も有効な証拠となります。
ただし、プライバシーに配慮し、医師の助言を得た上で記録することが重要です。
プライバシーに配慮し、医師の助言を得た上で画像記録を行うことを忘れずに実践しましょう。
事故後に通院15日以上続く場合の手続きの流れ
通院15日という期間は慰謝料計算において重要な基準となるため、適切な手続きを行うことが必要です。

一般的に、交通事故の慰謝料は自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準で計算されます。
通院15日の場合、自賠責保険基準では1万7,200円から6万4,500円、弁護士基準では軽傷時に約9万5,000円、重傷時に約14万円程度となります。
各段階で適切な対応を行うことで、スムーズな示談解決につながります。
| 基準 | 通院15日の慰謝料目安 |
|---|---|
| 自賠責保険基準 | 1万7,200円〜6万4,500円 |
| 弁護士基準(軽傷) | 約9万5,000円 |
| 弁護士基準(重傷) | 約14万円 |
保険会社への連絡と対応
通院15日以上が予想される場合、早期の保険会社への連絡が重要です。
事故直後に加害者の加入する任意保険会社に連絡を取り、治療が長期化する可能性がある旨を伝える必要があります。
この段階で保険会社は事故状況の確認を行い、保険請求に必要な書類の送付準備を開始します。
- 事故の詳細状況
- 怪我の程度と症状
- 通院予定の医療機関
- 治療見込み期間
任意保険会社による一括対応が開始されると、治療費の直接支払いや慰謝料の計算が行われます。
ただし、治療が長期化する場合や症状が重篤な場合、保険会社が一括対応を終了することがあります。
その場合は自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく被害者請求制度の利用や健康保険への切り替えを検討する必要があります。

連絡時には治療の必要性を医師に診断してもらい、診断書や診療計画書などの医学的根拠を準備することも重要です。
これにより保険会社との協議がスムーズに進行します。
診断書、診療計画書、検査結果など、治療の必要性を証明する書類を整備しておきましょう
必要書類の準備と提出
主要な書類として、診断書、診療報酬明細書、通院交通費明細書、休業損害証明書、事故発生状況報告書などがあります。
- 診断書(治療開始時・症状固定時)
- 診療報酬明細書
- 通院交通費明細書
- 休業損害証明書
- 事故発生状況報告書
診断書は治療開始時と症状固定時の2種類が必要で、医師による正確な診断内容と治療期間の記載が重要です。
診療報酬明細書は治療費の詳細を示すもので、医療機関から発行される領収書と合わせて保管します。

通院交通費については、公共交通機関の利用証明や自家用車使用時のガソリン代計算書類が必要です。
タクシー利用の場合は領収書の保管が必須となります。
休業損害がある場合は、勤務先からの休業損害証明書と給与明細書の提出が求められます。
交通費は通院に直接関連する費用のみが対象となり、適切な証拠書類の保管が重要です。
書類の提出は治療終了後(症状固定後)に一括して行うのが一般的ですが、治療費の仮渡金請求や内払金請求を行う場合は、治療途中での書類提出も可能です。
提出先は加害者の加入する任意保険会社、または自賠責保険会社(国土交通省)となります。

専門家のサポートを受けながら確実に進めましょう。
治療費の支払い方法
加害者の任意保険会社による一括対応では、保険会社が医療機関に直接治療費を支払うため、被害者の経済的負担が軽減されます。

一括対応が行われる場合、被害者は医療機関での支払いを行う必要がありませんが、治療内容や治療期間について保険会社の了承を得る必要があります。
長期治療になる場合、保険会社から治療の必要性について照会されることがあるため、医師との連携が重要となります。
この場合、健康保険や労災保険(厚生労働省)の適用を検討し、自己負担額を軽減することが可能です。
健康保険を使用する場合は厚生労働省が定める第三者行為による傷病届の提出が必要となります。
- 健康保険:第三者行為による傷病届の提出が必要
- 労災保険:業務中・通勤中の事故の場合に適用
- 自己負担額の軽減が可能
治療終了後は、立て替えた治療費について加害者側の保険会社に請求を行います。
自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責保険の治療費支払い限度額は120万円となっているため、これを超過する場合は任意保険による対応が必要です。

通院15日以上で気をつけたい注意点
通院期間が長期化することで、保険会社からの治療費打ち切りの提案や不当な慰謝料減額の可能性が高くなるためです。
また、症状固定の時期や後遺障害の認定についても、医師との十分な相談が欠かせません。
通院期間が延びるほど、保険会社との交渉が難航する傾向があるため、事前の準備と正しい知識を身につけておくことが大切です。

通院期間が長期化すると、これらの基準の適用にも影響が出る可能性があるんです。
- 医学的根拠に基づく通院の必要性の証明
- 症状固定時期の適切な判断
- 後遺障害認定への準備
- 保険会社との交渉に備えた証拠収集
やってはいけない通院パターン
最も注意すべきは、医師の指示に従わない通院です。
医師法(e-Gov法令検索)に基づく医師の指示を無視することは、治療の必要性に疑問を持たれる要因となります。
医師が週3回の通院を指示しているにも関わらず、週1回程度しか通院しない場合、治療の必要性に疑問を持たれる可能性があります。

逆に、症状に見合わない過度な頻度での通院も問題となります。
軽微な症状で毎日通院を続けると、治療の妥当性を疑われ、慰謝料の減額対象となる場合があります。
整骨院や接骨院への通院では、医師の同意書なしに長期間継続することは避けるべきです。
- 医師の指示に従わない通院頻度
- 症状に見合わない過度な通院
- 医師の同意なしでの整骨院・接骨院通院
以下の行為は特に避けるべきです:
- 医師の指示なしでの通院間隔の大幅な変更
- 症状と関連性の低い複数の医療機関への同時通院
- 通院記録や領収書の不適切な管理
- 症状の一貫性を欠く証言
保険会社とのやり取りで注意すること
保険会社の担当者は示談金額を抑制する立場にあるため、被害者の発言を慎重に記録し、後の交渉材料として活用する可能性があります。

何気ない発言が後々不利になることがあるので注意が必要ですね。
「もう大丈夫です」「痛みはそれほどでもありません」といった症状を軽視する発言は、治療終了の根拠として利用される恐れがあります。
症状について説明する際は、客観的事実に基づいて正確に伝えることが大切です。
以下の対応を心がけましょう:
- 治療方針については医師の判断を最優先に伝える
- 症状の改善について楽観的な表現を避ける
- 示談提案に対しては即答せず、検討時間を求める
- 医療記録の提出要求には必要最小限の範囲で応じる
保険会社から提示される示談金額は、多くの場合、自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準または任意保険基準に基づいており、適正な賠償額(弁護士基準)を下回る可能性が高いことを理解しておくことが重要です。
- 症状を軽視する発言は絶対に避ける
- 電話での会話は必ず記録を残す
- 重要な連絡は書面で確認する
- 示談提案には即答せず検討時間を確保
自賠責保険の詳細については国土交通省の自賠責保険・共済ポータルサイトで確認できます。
治療打ち切りを言われた場合の対処法
治療の必要性は医学的判断に基づくものであり、保険会社が一方的に決定できるものではありません。

まず、主治医に症状の現状と今後の治療計画について詳細な診断書の作成を依頼します。
診断書には、現在の症状、治療の必要性、症状固定までの見込み期間を具体的に記載してもらうことが重要です。
・現在の症状の詳細
・治療の必要性
・症状固定までの見込み期間
健康保険を使用することで自己負担額を軽減し、治療を継続することが可能です。
ただし、厚生労働省が管轄する健康保険組合への第三者行為による傷病届の提出が必要になります。
以下の手順で対応することを推奨します:
- 医師による詳細な診断書の取得
- 健康保険への切り替え手続き
- 治療継続の必要性を記録として残す
- 弁護士への相談による法的アドバイスの取得
これが、後遺障害の認定や適正な慰謝料獲得につながります。

保険会社の言いなりにならず、しっかりと治療を受けましょう
通院15日以上の慰謝料でよくある質問
特に通院日数が15日以上になると、慰謝料の計算方法に特別な変化が生じるため、正確な知識を身につけておくことが重要です。

自賠責保険法(e-Gov法令検索)における入通院慰謝料の基準では、1日あたり4,300円が支払われますが、実際の通院日数と治療期間のどちらか短い方に基づいて計算されます。
通院15日以上の場合は、月あたりの通院日数が15日で慰謝料額が最大となる特徴があります。
これは自賠責基準の17,200円から64,500円と比較すると大幅に高額になります。
自賠責基準と弁護士基準では大きな差が生じるため、適切な請求方法を選択することが重要
| 基準 | 軽傷 | 重傷 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 17,200円~64,500円 | 同左 |
| 弁護士基準 | 約95,000円 | 約140,000円 |

整骨院・接骨院の通院もカウントされる?
医師からの指示や紹介に基づく整骨院・接骨院での施術については、原則として通院日数に含まれます。
自賠責保険では、柔道整復師法(e-Gov法令検索)に基づく柔道整復師による施術も医療類似行為として認められており、医師による診断書や同意書がある場合には治療費や通院慰謝料の対象となります。

ただし、医師の診断や指示なく独断で整骨院のみに通院している場合は、保険会社から治療の必要性について疑問視される可能性があります。
定期的な医師による診察を受けながら、並行して整骨院での施術を受けることで、通院日数として適切に認定される可能性が高まります。
- 医師の指示または紹介に基づく通院が原則
- 定期的な医師の診察と並行して施術を受ける
- 治療の必要性と合理性を証明できる記録を残す
通院日数が15日に満たない場合はどうなる?
例えば、治療期間30日で実通院日数が10日の場合、10日×2=20日と30日を比較し、短い方の20日×4,300円=86,000円が慰謝料額となります。

15日以上の通院がある月と比較すると、15日未満の場合は実通院日数を2倍にしても上限が設定されるため、実質的に慰謝料額が制限される仕組みになっています。
これは自賠責保険(国土交通省)が被害者の最低限の保障を目的としているためです。
- 実通院日数×2と総治療期間の短い方で計算
- 弁護士基準では症状の重篤さを考慮した増額の可能性
- 治療の必要性を適切に主張することが重要
慰謝料以外にもらえるお金はある?
主要なものとして治療費、休業損害、逸失利益、後遺障害慰謝料、物損などが挙げられます。
- 治療費(実費全額)
- 休業損害(収入減少分)
- 逸失利益(将来の収入減少分)
- 後遺障害慰謝料(等級に応じて)
- 物損(車両修理費等)
治療費については、事故による怪我の治療に要した実費全額が補償対象となります。
これには診察料、検査費用、薬代、リハビリ費用なども含まれます。

休業損害は、事故により仕事を休んだことで生じた収入の減少分を補償するものです。
給与所得者の場合は事故前3か月の平均日額に休業日数を乗じて算定されます。
事故前3か月の平均日額 × 休業日数 = 休業損害額
逸失利益は、後遺障害により将来的に得られるはずだった収入の減少分を補償するものです。
後遺障害等級が認定された場合には、等級に応じた後遺障害慰謝料も別途請求できます。
交通事故の損害賠償請求については、民法(e-Gov法令検索)や自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づいて行われます。

まとめ:通院15日以上の事故は早めに専門家に相談しよう
通院期間が長期化する場合、治療費や慰謝料の計算が複雑になり、保険会社との示談交渉においても専門的な知識が必要となるためです。
通院15日以上の事故における専門家相談の最適なタイミングは、治療の見通しが立った段階です。
完治が見込める場合は治療終了時、後遺症の可能性がある場合は症状固定の診断を受けた時点で弁護士に相談することで、適切な慰謝料算定や示談交渉が可能になります。
特に、保険会社から提示される示談金額は自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責保険基準や任意保険基準で算定されることが多く、弁護士基準(裁判基準)と比較して低額になる傾向があります。

- 入通院慰謝料の適正な計算
- 治療費打ち切り時の対応方法
- 後遺障害等級認定の手続き
- 過失割合の認定に関する法的主張
- 休業損害の適正な算定
まず、入通院慰謝料の適正な計算において、通院日数や期間に基づく正確な算定を行うことができます。
また、治療費の打ち切りを保険会社から打診された際の対応方法や、後遺障害等級認定の手続きについても専門的なアドバイスを受けられます。
さらに、過失割合の認定に争いがある場合や、休業損害の算定が複雑な場合にも、法的根拠に基づいた主張を行うことが可能です。
医師の指示に従った適切な通院を継続し、診断書や診療録などの証拠を保全することで、後の補償請求を有利に進めることができます。