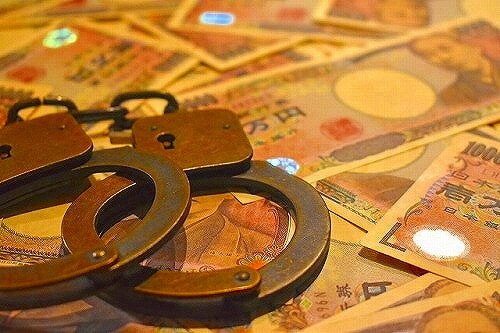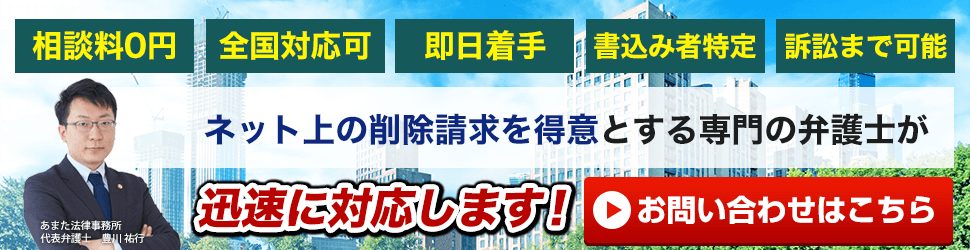2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら

執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
誹謗中傷が該当する罪
インターネットでの誹謗中傷は、主に名誉毀損罪や侮辱罪、脅迫罪、信用棄損罪、偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪などに該当するリスクがあります。それぞれ具体例を解説します。
名誉毀損罪
名誉毀損罪は公然と事実を摘示し、他人の名誉を傷つけ社会的評価を下げた際に成立します。
- 金を盗んだ。
- 暴力を振るった。
- 反社会的勢力とつながりがある。
- 不倫している。
以上のように、何らかの事実に基づき相手の社会的評価を下げた状況が該当します。
このときの名誉毀損罪での事実とは、真実か虚偽かは関係ありません。本当のことであっても罪になる可能性があります。
また、要件の1つに「公然」という文言が入っているため、他人に聞かれない1対1での会話では対象外になるのが一般的です。ただし、インターネット上での誹謗中傷は、通常不特定多数に見えるところで行われるため、公然の要件は満たしていると考えられます。
侮辱罪
侮辱罪は事実を摘示しなくても、不特定多数が認識できる状態で他人を侮辱すると成立します。
「バカ」「アホ」など具体的事実を伴わない表現、「チビ」「デブ」「ハゲ」「ブス」などの身体的特徴に関する暴言などが含まれます。

脅迫罪
脅迫罪は生命、身体、自由、名誉又は財産に対し、害を加えることを相手に告知し脅迫すると成立します。法律上、対象は個人となり、企業や会社といった法人は対象外です。
例えば、
- 殺す。
- 家に火をつける。
- ネットで都合の悪い事実をばらまいてやる。
など、相手を怖がらせるのに十分な内容であれば、実際に相手が恐怖を感じたかは関係なく成立します。
また、本人だけでなく親や子どもといった親族に危害を加えると脅した場合も同様です。「子どもを誘拐する」といった発言も脅迫罪になります。
信用毀損罪
信用毀損罪は嘘の情報を流し騙したりすることで、他人の信用・信頼を低下させる行為です。信用は経済的な信用である商品やサービスの質も含むとされており、個人だけでなく法人が被害を受けるケースもあります。
- 自己破産したことがある
- 倒産する
- 粗悪な模倣品を販売している
- あの店舗では賞味期限切れの材料を使っている
など、特定の会社の名前を出し他人の信用・信頼を低下させる行為で成立する可能性が高いです。ただ、信用毀損罪は投稿内容が真実なら問題なく、罪になるのは虚偽だけというのがポイントです。
偽計業務妨害罪
偽計業務妨害罪は不特定多数の者に向け嘘の情報を発信する、他人を欺くといった方法で業務を妨害する行為です。
事故や災害に便乗したデマ、試験中に不正な手段で入試問題をネット上に掲載する行為、大量の虚偽注文、バイトテロなどは、実際に偽計業務妨害罪に問われた例があります。
- 買った商品を送ってこない。
- 産地偽装の食品を使っている。
など、ネット上に嘘の書き込みをして不特定多数の人に誤った情報を信じさせると、該当する可能性が高いでしょう。
ただ、法的には投稿内容が真実なら問題はなく、偽計業務妨害罪に当たるのは虚偽の風説を流布した時です。
威力業務妨害罪
威力業務妨害罪は人の業務を妨害する犯罪です。
爆破予告、悪質なSNSの投稿、悪質なメール、迷惑電話、ビラ配布、バイトテロなどが該当し、以下のような事例があります。
- 店に爆弾を仕掛けた。
- アイドルグループの握手会が開催されていた会場で発煙筒を点火しイベントを中止におい込んだ。
- 業務用電力量計に工作をしメーターを逆回転させて使用電力量より少ない量を指示させた
- デパートの売り場の布団に縫針を混入させた

請求できる慰謝料の相場
ネット上の誹謗中傷に対し請求できる慰謝料の相場は、該当する罪の種類などケースにより異なります。実際の判例を見ながら、いくらくらい支払われているのか紹介し説明します。
名誉棄損罪
名誉毀損の慰謝料の相場は10万~100万円です。個人なら10~50万円、企業など法人なら50~100万円になることがあります。企業や事業者は業務に影響を与える可能性が高く、個人よりも慰謝料は高額になる傾向があります。
2019年に常磐自動車道で起きたあおり運転事件で容疑者の車に同乗していたとSNSで名指しされた女性が、愛知県の元市議を告訴しました。裁判では元市議に対し33万円の賠償金の支払いが命令されました。
特定の企業に対しあるブログが「○○商店最後の日」と題した記事を掲載し、「○○商店がマンションの隣の空き地にいきなり産業廃棄物保管所を作ったところ、粉塵で窓が開けられなくなり騒音でテレビが見られないなどの被害を受けている」という事実無根の情報を広めました。
○○商店の代表者はブログ運営者を訴え、加害者に賠償金100万円の支払いを認める判決が下されました。
侮辱罪
侮辱罪による慰謝料の相場は10万円程度です。単純な悪口でも成立する可能性があり、慰謝料の額は基本的に高くなりません。ただし、悪質性などを考慮し高額な慰謝料が支払われるケースもあります。
同じ職場に勤める夫の妻5人で構成されたグループLINEで、ある妻の夫に対して「変質者」「ポンコツ野郎」「汚いことを平気でやる」などの書き込みを行った事件では、裁判所は侮辱罪を認めました。結果、慰謝料等計33万円の支払いを命じました。
脅迫罪
脅迫罪による慰謝料の相場は数万円から数十万円です。ただし、脅迫行為を繰り返すなど悪質と判断されれば、数百万円と高額の慰謝料になる判例はあります。
熊本県で高校一年生の女子生徒がいじめを受けて自殺した事件で、遺族が元同級生に対し裁判を起こしました。同級生らがSNSに書き込んだ「レスキュー隊呼んどけよ」といったメッセージが脅迫に当たるとして11万円の支払いを命じられました。
業務妨害罪
業務妨害罪は刑事事件における罰金が50万円になっており、民事事件でも1つの目安にされています。
新型コロナウイルスが社会問題になっていた時期、名古屋市内のドラッグストアで「俺コロナなんだけど」と発言した上に咳をし、消毒作業などで店舗を一時的に閉店に追い込んだ事件です。
容疑者は逮捕されましたが、示談が成立し店側に閉店などの被害額83万円を弁償しています。判例ではありませんが、慰謝料の相場を判断するひとつになっています。ただ、一般的に裁判所での判決よりも示談のほうが慰謝料は高額になる傾向があります。
誹謗中傷の慰謝料を請求する流れ
SNSや匿名掲示板などネット上で誹謗中傷を受けた時、匿名の相手を訴え慰謝料を請求する流れを解説します。
ネットで誹謗中傷に該当する書き込みを見つけたら、証拠を保存するようにしましょう。
見つけた時点で画面をURLつきでプリントアウトするか、スクリーンショットを撮り保存することが重要です。さらに、書き込みが発生した日時も控えてください。
掲示板やSNSの運営者や管理者に対して、投稿者のIPアドレス開示を求めます。
プロバイダに問い合わせ、書き込みを行った相手が誰なのか個人情報を特定するためです。
サイト管理者は相手の個人情報を持たないケースが多くなっていますが、誰がいつ投稿したか証明するIPとタイムスタンプは持っています。もし開示してもらえない時は、裁判所に対して開示を求める仮処分の申立てを起こし開示を求めます。
サイト管理者から開示してもらったIPアドレスから犯人が契約している経由プロバイダを特定し、氏名、住所、メールアドレス、電話番号といった慰謝料の請求に必要な投稿者の個人情報開示を求めます。
プロバイダは相手に開示しても良いか許可をとり、相手が応じると情報が開示されます。もし拒否されれば、プロバイダに対して開示を求める訴訟を起こします。
開示された個人情報をもとに投稿者に民事で慰謝料を求めるため、内容証明を送り裁判を起こします。また、刑事告訴すれば、罪に問うことも可能です。
旧プロバイダ責任制限法は2022年10月1日に改正施行され、2025年4月1日には情報流通プラットフォーム対処法という名称に変更され施行されています。
発信者情報開示請求はサイト管理者とインターネットの接続プロバイダという2段階での裁判手続きが必要であり、時間や費用の負担が大きくなってしまうという問題がありました。しかし、改正後は1度でできるようになり、従来よりも投稿者を特定しやすくなったという大きなメリットが生じました。そのため、誹謗中傷の被害者は慰謝料を含む損賠賠償金の請求もしやすくなったと言えるでしょう。
インターネットでのトラブルを取り締まる法整備はさらに検討されており、今後も改正が期待され注目です。
ただ、慰謝料請求までの手続きは複雑なのが現状です。仮処分や開示請求など裁判手続きの必要が生じると、法律の知識がないと対応は難しい面があるため注意が必要です。

誹謗中傷の慰謝料まとめ
ネット上での誹謗中傷は名誉毀損をはじめ様々な罪に該当する可能性があり、慰謝料の請求は可能です。慰謝料の金額相場は数万円、高いと100万円ほどと、ケースバイケースでもあります。
自分の被害がどのような罪にあたり、慰謝料の相場はどれくらいになるのか、訴えるためにはどうすればいいのか、疑問や悩みがあれば弁護士に相談してください。初回の法律相談を無料としている事務所なら、費用がかからず気軽に利用しやすいでしょう。弁護士なら法の知識や経験により、ケースに合った慰謝料額の請求を手助けしてくれます。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら