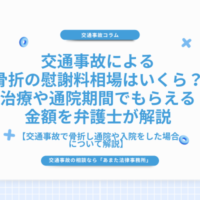任意整理や自己破産、個人再生といった債務整理を行う場合は、基本的に保証人に一括請求がされてしまいます。
ですが、任意整理であれば、保証人になってくれた人に悪い影響を与えないようにする対処法があります。

この記事の目次
任意整理が保証人に与える影響
お金を借りた本人が支払いを続けられなくなったとき、保証人は本人に代わり、返済する義務があります。
自己破産や個人再生をした場合は、全ての債権が対象となるため、保証人への一括請求は免れません。
任意整理でも、保証人がついている借金を整理の対象にしたとき、保証人に対して返済の請求が行きます。
保証人へ一括請求される
保証人がついている借金を任意整理をした場合、その借金の保証人は債権者から一括返済の請求を受けることになります。一括請求は元金や利息だけでなく、今まで発生した遅延損害金も加算された金額です。
保証人が一括請求に応じて、借金を支払えるならば問題ありませんが、保証人の経済状態によっては、突然一括請求されても返済できない場合があります。
一括払いの請求に応じることができなかった場合は、保証人も債務整理を検討する必要があります。
本人だけでなく、保証人まで借金が返済できずに、債務整理に踏み切らなければならない状態になれば、人間関係に影響を与えることになるでしょう。

次に、対処法を見ていきましょう。
任意整理で保証人への影響を小さくする対処法
任意整理であれば、保証人への影響を小さくする方法がいくつかあります。
大きく分けて、保証人に請求をいかせないようにする方法と保証人も債務整理をする方法の2種類になります。
整理する借金から外す
保証人に請求がいかないようにする方法です。
借金の総額や、自分の返済可能額にもよりますが、任意整理では、保証人が付いている借金を対象から外すことができます。
対象から外した借金を、そのまま自分が支払いを続けることで、保証人へ影響が出ないようにすることができます。
保証人と一緒に債務整理をする
保証人も債務整理をすることで、対処する方法です。
借金をした本人と保証人が連名で任意整理をすることで、保証人への一括請求を避けることができます。
この場合、保証人も任意整理のデメリットであるブラックリスト状態となり、クレジットカードの作成や、ローンの新たな借入ができなくなります。
ブラックリストの詳細についてはこちらの記事をご覧ください。
弁護士に相談する
弁護士に相談するのも保証人への負担を軽くすることができる可能性があります。
借金問題は個人の返済能力や借金額によってできる対応が異なります。
債務整理の経験がある弁護士に相談することで、自分の状況に適した具体的な対処法や対策を提案してくれます。
任意整理で借金問題の解決を検討されている方でも、保証人が付いている借金を外すことが、本当にいいことなのかは客観的な意見をもらったほうがよいでしょう。

客観的・総合的なアドバイスが必要であれば、いつでも弁護士にご相談ください。
任意整理における保証人と連帯保証人の違い
任意整理をする場合、保証人と連帯保証人で何か違いはあるのでしょうか?
実は保証人が複数人ついている場合であれば、違いが生まれますが、保証人が一人だけの場合は、大きな違いはないと言っていいでしょう。
保証人と連帯保証人の持つ権利の違い
そもそも保証人と連帯保証人には以下の違いがあります。
・自分への請求より先に主債務者へ返済の請求を求めることができる「催告の抗弁権」
・主債務者に弁済資力があり、かつ執行が容易であることを証明して、まずは、主たる債務者に対して執行するよう請求できる権利である「検索の抗弁権」
・複数の保証人が存在している場合、全ての借金を一人が責任をもって返済するのではなく、複数の保証人で負担を振り分けられる「分益の利益」
この3つの権利が認められています。
一方で、連帯保証人にはこの全ての権利がありません。
保証人なら一括請求を避けられる?
保証人には「抗弁権」や「分益の利益」などの権利が認められています。そのため、債権者から一括請求が来た時に、抗弁で対抗することは可能ですが、一括請求を避けることは難しいです。
抗弁権を主張しても、借金をした本人は債務整理の手続きを行っているため、結局、保証人に請求されてしまいます。
保証人が複数いる場合は分益の利益によって、1人1人に対しての請求金額が減る可能性はありますが、保証人が1人の場合、負担を割り振ることができないため、請求金額は変わりません。
このように連帯保証人と違い、3つの権利を有する保証人という立場だったとしても、一括請求をされたら、返済の義務が生まれます。
任意整理が進められていく中で、保証人が1人の場合、保証人と連帯保証人の違いは少ないと言えるでしょう。
まとめ
任意整理ならば、整理の対象業者を自分の意志で選択できるので、保証人をお願いした借金を対象にしなければ、自分で支払いを続けることで、迷惑をかけずに済みます。
ただし、個人再生や自己破産と違い、任意整理では借金の大幅な減額を見込めないため、借金の総額が大きければ、借金問題を解決できない可能性があります。
そのために必要なのは、多重債務状態に陥ったまま、返済のためにさらに借金を重ねたり、長期間の滞納をしたりしてしまう前に、いち早く弁護士に相談して借金問題解決に向けて動き始めることです。
弁護士法人あまた法律事務所は、債務整理などの借金問題の解決に力を入れている法律事務所です。
借金でお悩みの方は無料相談の機会を活かして、ぜひ一度ご相談ください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら