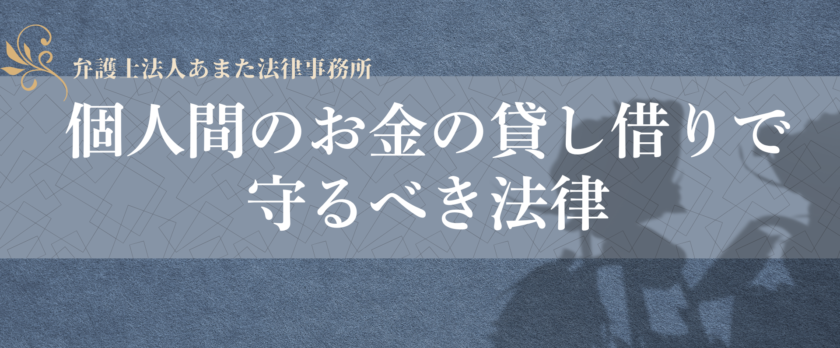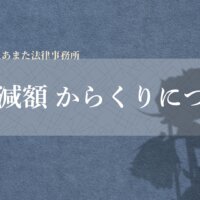友人からお金を借りたいけど法律的に大丈夫なの?
家族に貸したお金に利息をつけても問題ない?
個人間でのお金の貸し借りに借用書は本当に必要?
こんな疑問を抱えていませんか?
実は、個人間の金銭貸借も立派な法的行為で、民法・利息制限法・出資法などの複数の法律が適用されます。
「友人同士だから法律は関係ない」と考えていると、知らないうちに違法な利息を設定したり、贈与税の対象になったり、最悪の場合は刑事罰を受けるリスクもあるのです。
本記事では、個人間貸借に適用される法律の基本から、利息制限法による年15~20%の上限設定、借用書の正しい書き方、税務上の注意点まで網羅的に解説します。
さらに、トラブルが起きた際の具体的な解決方法や、実際の失敗事例から学ぶ注意点も紹介しています。
この記事を読めば、法的リスクを回避しながら安全にお金の貸し借りができるようになり、万が一トラブルが発生しても適切に対処できるようになります。
執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年
東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
民法による金銭貸借契約の成立要件
民法(e-Gov法令検索)における金銭消費貸借契約の成立要件は、2020年の民法改正により大きく変更されました。 改正前後の要件を正確に理解することが、個人間の金銭貸借を法的に適切に行うために重要です。 改正前の成立要件(要物契約)
改正前のポイント
改正前は「実際にお金を渡した時点」で契約成立という要物契約のみでした
改正前の
民法(e-Gov法令検索)では、金銭消費貸借契約は「要物契約」とされており、以下の要件を満たす必要がありました。
- 当事者間での貸借に関する合意
- 金銭の現実の交付(お金を実際に渡すこと)
この制度では、口約束だけでは契約は成立せず、実際にお金を渡した時点で初めて法的な契約として成立していました。
2020年4月施行の改正により、契約の形態に応じて異なる成立要件が設けられています。
2020年4月施行の改正
民法(e-Gov法令検索)では、契約の形態に応じて異なる成立要件が設けられています:
| 契約形態 | 成立要件 | 根拠条文 |
|---|
| 書面による契約 | 合意+書面作成(金銭交付不要) | 民法587条の2 |
| 口頭による契約 | 合意+金銭の現実交付 | 民法587条 |
書面による契約の場合(諾成的金銭消費貸借契約・民法587条の2)
- 当事者間での貸借に関する合意
- 書面または電磁的記録による契約の作成
- 金銭の交付は不要
口頭による契約の場合(要物契約・民法587条)
借用書やメール、LINEなどで契約内容を記録すれば、お金を渡す前でも契約が成立するようになったのですね。
この改正により、借用書やメール、LINE等の電磁的記録で契約内容を記録した場合、実際にお金を渡す前でも契約が成立することになりました。 これにより、契約違反や債務不履行に対する法的救済がより確実になっています。
契約で明確にすべき要素
以下の要素が曖昧だと、後日トラブルの原因となる可能性があります
- 貸付金額
- 利息の有無と利率
- 返済期限
- 返済方法
- 遅延損害金の取り決め
金銭消費貸借契約が適切に成立するためには、以下の要素を明確にしておくことが重要です:
- 貸付金額
- 利息の有無と利率
- 返済期限
- 返済方法
- 遅延損害金の取り決め
これらの要素が曖昧だと、後日トラブルの原因となる可能性があります。
特に利息については、当事者間で明確に合意されていない場合、
民法(e-Gov法令検索)上は無利息の契約として扱われます。
「友人同士だから法律は関係ない」は大きな誤解
個人間の金銭貸借でも、関係性に関わらず法律が適用され、契約関係が成立します。
「友人同士だから」「家族間だから」「恋人同士だから」といった理由で、個人間の金銭貸借に法律は適用されないと考える方が少なくありませんが、これは法的に全く根拠のない誤解です。
親しい関係だからといって、法律が適用されないということはありませんよ
民法(e-Gov法令検索)をはじめとする法律は、金銭貸借の当事者がどのような関係性にあるかを区別しません。 友人、家族、恋人、同僚など、どのような関係であっても、金銭の貸し借りが行われた時点で法的な契約関係が成立します。
実際の裁判例でも、友人間や恋人間の金銭貸借について、民法の金銭消費貸借契約の規定が適用され、返済義務が認められるケースが数多く存在します。 関係性の親密さは、法的拘束力の有無とは全く別の問題なのです。
親しい関係だからこそ、明確な契約条件がないと後のトラブルの原因となります。
明確な契約条件がないと、以下のような問題が発生します。
- 貸付金額の認識違い
- 返済期限の曖昧さ
- 利息の有無をめぐる争い
- 返済方法の不明確さ
個人間の金銭貸借でも法律を適切に活用することで、以下のメリットが得られます。
法的保護の4つのメリット
1.
明確な権利義務関係の確立:契約書により、双方の権利と義務が明確になり、後日の争いを防止できます。
2. 法的救済手段の確保:返済が滞った場合、民事訴訟や調停などの法的手続きを利用できます。
3. 時効の管理:金銭貸借の消滅時効(通常5年)を適切に管理し、権利の消滅を防げます。
4. 第三者に対する対抗力:借主が他の債務を負った場合や相続が発生した場合に、優先的な回収が期待できます。
親しい間柄だからこそ、後々の関係性を保つためにも最初から適切な手続きを踏むことが重要です。
個人間の金銭貸借であっても、以下の対応を心がけることが重要です:
- 金額に関係なく借用書を作成する
- 返済期限と方法を明確に定める
- 利息の有無を明確にする
- 保証人の設定を検討する
- 契約書は双方が保管する
親しい間柄だからこそ、後々の関係性を保つためにも、最初から法的に適切な手続きを踏むことが、結果的に双方にとって最善の選択となります。
きちんとした契約書を作ることで、お互いの信頼関係もより深まりますね
個人間貸借を規制する法律で知っておくべきこと
個人間の金銭貸借は3つの主要法律(利息制限法・出資法・貸金業法)で規制され、業として行う場合は業者と同様の規制が適用される場合があります。
個人間の金銭貸借は主に
利息制限法、
出資法、
貸金業法の3つの法律によって規制されています。 これらの法律は相互に関連しながら、個人間取引においても一定の制限を設けており、違反した場合には法的責任を問われる可能性があります。
特に重要なのは、個人同士の貸借であっても業として行う場合や、一定の条件を満たす場合には、業者と同様の規制が適用されるケースがあることです。
また、利息の設定や取引の頻度、相手方の属性によっても適用される法律や規制内容が変わるため、取引前に十分な理解が必要です。
ポイント
- 個人間貸借でも3つの法律で規制されている
- 業として行う場合は業者と同様の規制が適用
- 利息設定や取引頻度で適用法律が変わる
- 違反すると法的責任を問われる可能性
利息制限法による利率上限(年15~20%)
個人間の貸借でも適用される利息制限法により、元本額に応じて年15~20%の利率上限が設定されています。
は、金銭消費貸借において設定できる利息の上限を定めた法律で、個人間の貸借にも適用されます。 この法律により、元本の額に応じて以下の利率上限が設定されています。
| 元本額 | 利率上限 |
|---|
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
これらの利率を超える利息契約は、超過部分が無効とされ、借主は超過分の支払いを拒否することができます。
重要なのは、利息制限法の違反は民事上の効力に関する問題であり、直接的な刑事罰はないことです。
しかし、超過利息を受け取った場合は不当利得として返還義務が生じ、借主から返還請求される可能性があります。 また、継続的に利息制限法を超える利率で貸付を行っている場合は、業として行っているとみなされ、
貸金業法(e-Gov法令検索)違反となる可能性もあります。
ポイント
- 利息制限法違反は民事上の問題で刑事罰なし
- 超過利息は不当利得として返還義務あり
- 継続的な超過利息は貸金業法違反の可能性
出資法による刑事罰対象行為(年109.5%超等)
出資法では年109.5%を超える高金利貸付に刑事罰(5年以下の懲役または1000万円以下の罰金)が科せられます。
は、個人間貸借においても年109.5%を超える高金利での貸付を刑事罰の対象としています。 この法律に違反した場合、
5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。 出資法の特徴は、
利息制限法とは異なり刑事罰を伴う点です。 年109.5%という上限は、利息制限法の上限(年15~20%)と大きく乖離しており、この間の金利帯は
「グレーゾーン金利」と呼ばれています。 個人間貸借においては、年20%を超える利息でも109.5%以下であれば刑事罰は科せられませんが、民事上は無効となります。
📝 出資法の規制対象
高金利貸付以外にも以下の行為が処罰対象となります
また、出資法では高金利貸付以外にも、業として行う場合の無登録営業や、暴力的な取立行為なども処罰対象としています。
友人や家族への貸付であっても、反復継続的に行い、それが業として認定された場合は、これらの規制が適用される可能性があります。
貸金業法の適用除外と注意すべきケース
貸金業法は原則として業として金銭貸借を行う者を規制しますが、個人間貸借でも条件次第で適用される場合があります。
は原則として業として金銭貸借を行う者を規制する法律ですが、個人間貸借であっても一定の条件下では適用される場合があります。 完全に適用除外となるのは、真に個人的な関係での一時的な貸借に限定されます。
適用除外となる典型的なケース
- 家族や親族間での生活費の援助
- 友人間での一時的な金銭の融通
- 個人の資産処分に伴う一回限りの貸付
これらの場合、営利目的ではなく、継続性もないため貸金業法の規制対象外となります。
以下の行為は「業として」行っているとみなされ、貸金業法の適用対象となる可能性があります。
⚠️ 注意すべきケース
- 同じ相手に対して繰り返し貸付を行う場合
- 複数の相手に対して同時期に貸付を行う場合
- SNSやインターネットを通じて貸付相手を募集する場合
- 担保や保証人を要求する場合
これらの行為は「業として」行っているとみなされ、貸金業法の適用対象となる可能性があります。
貸金業法違反の罰則
貸金業法が適用された場合の罰則: • 無登録での営業:
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはその両方 • 適正な契約書面の交付義務 • 取立行為の規制 • 総量規制の遵守
また、適正な契約書面の交付義務、取立行為の規制、総量規制の遵守なども求められるため、個人であっても十分な注意が必要です。
合法的な個人間貸借をするために守ること
個人間貸借も法的な規制の対象となり、適切な手続きと契約書作成が必要
個人間のお金の貸し借りを法的リスクを避けて安全に行うためには、以下の重要なポイントを押さえる必要があります。 まず基本的な法的枠組みを理解することから始めましょう。 個人間貸借においても、貸金業者と同様に
利息制限法(e-Gov法令検索)が適用されます。 これは借り手を高金利から保護するための法律で、違反すると超過部分の利息は無効となります。 また、
民法(e-Gov法令検索)上の契約として、貸主と借主双方に権利と義務が発生することも重要な点です。
ポイント
契約の内容は書面で明確にし、返済条件や利息について曖昧な部分を残さないことが法的トラブルを防ぐ鍵となります。 特に親族間や親しい友人同士では、信頼関係に甘えて契約内容を曖昧にしがちですが、後のトラブルを防ぐためにも正式な契約書の作成をおすすめします。
信頼関係があっても、必ず書面での契約書作成を行いましょう
利息設定時の計算方法と上限を守るポイント
個人間貸借において利息を設定する場合、利息制限法(e-Gov法令検索)による上限を必ず守らなければなりません。
2024年現在の利息制限法では、元本の金額に応じて以下の上限が定められています。
利息制限法の上限金利
- 元本が10万円未満:年利20%
- 元本が10万円以上100万円未満:年利18%
- 元本が100万円以上:年利15%
これらの上限を超える利息を設定した場合、超過部分は法的に無効となり、借り手は支払う義務がありません。
上限金利を超える利息設定は法的に無効となるため、必ず事前に確認しましょう。
利息の計算方法については、年利で表示し、日割り計算を行うのが一般的です。
例えば、50万円を年利15%で貸し付けた場合、1日当たりの利息は50万円×15%÷365日=約205円となります。
月利や日利での表示は混乱を招きやすいため、必ず年利で統一しましょう。
計算ミスを防ぐため、利息計算は専用の計算機やExcelなどを使用することをおすすめします。
実際に利息を設定する際のポイントとして、市場金利との比較も重要です。
銀行の個人向け融資金利や消費者金融の金利水準を参考にし、極端に高い利息設定は避けるべきです。
また、利息の支払い方法(元利均等返済、元金均等返済など)についても事前に明確に定め、計算方法を両者で確認しておくことが大切です。
📝 利息設定時の重要ポイント
- 利息制限法の上限金利を必ず遵守する
- 年利表示で統一し、日割り計算を行う
- 市場金利と比較して適正な水準に設定する
- 返済方法と計算方法を明確に定める
借用書の書き方と法的効力を持たせる要件
借用書は
民法(e-Gov法令検索)に基づく重要な契約書類です。法的効力を持たせるには、必要項目の記載と正確な作成手順が不可欠です。
法的効力のある借用書を作成するためには、必要な記載項目を漏れなく含める必要があります。 借用書に記載すべき基本的な項目は、貸主と借主の氏名・住所、借入金額、借入日、返済期日、利息の有無と利率、返済方法、そして両者の署名・押印です。
借用書は口約束と違って、書面で残る証拠になるので、しっかりと作成することが大切ですね。
借用書に必要な基本項目
- 貸主と借主の氏名・住所
- 借入金額(改ざん防止の記載方法)
- 借入日
- 返済期日
- 利息の有無と利率
- 返済方法
- 両者の署名・押印
これらの項目の中でも特に重要なのは、金額の記載方法です。 数字は漢数字と算用数字を併記し、改ざんを防ぐため「金参拾万円也(¥300,000)」のように記載します。 また、返済条件については「令和6年12月31日までに一括返済」や「毎月末日に3万円ずつ10回に分けて返済」など、具体的で明確な内容にしましょう。
注意: 金額の記載は改ざんを防ぐため、必ず漢数字と算用数字を併記し、「也」を付けて確定させましょう。
📝 金額記載の正しい例
・金壱万円也(¥10,000)
・金拾万円也(¥100,000)
・金参拾万円也(¥300,000)
法的効力を確実にするための追加的な要件として、借用書の作成年月日の記載、連帯保証人がいる場合はその記載、そして可能であれば公証人による認証(法務省)を受けることも検討に値します。 また、借用書は複数部作成し、貸主と借主がそれぞれ保管することで、紛失リスクを軽減できます。
| 項目 | 記載内容 | 注意点 |
|---|
| 作成年月日 | 借用書作成日 | 必須項目 |
| 連帯保証人 | 氏名・住所・署名押印 | いる場合のみ |
| 公証人認証 | 公証役場での認証 | 任意だが推奨 |
| 複数部作成 | 当事者数分作成 | 紛失リスク軽減 |
返済が行われた際の処理についても事前に定めておくことが重要です。 一部返済の場合の処理方法、完済時の借用書の返却について明記し、返済の都度、受領書を作成することでトラブルを防げます。
ポイント
返済時の処理を明確にしておくことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。特に分割返済の場合は、返済の都度受領書を作成することをおすすめします。
税務上の注意点(贈与税・所得税への影響)
個人間貸借では適正な利息設定が重要。無利子や低金利の場合、贈与税のリスクがあります。
個人間貸借における税務上の注意点として、まず贈与税への影響を理解する必要があります。
国税庁の見解によると、個人間での金銭貸借において、適正な利息を設定せずに無利子または著しく低い利率で貸し付けを行った場合、利息相当額が贈与とみなされ、借り手に贈与税が課される可能性があります。
贈与税のリスクと対策
贈与税の対象となるのは、通常の金利水準と実際の金利との差額部分です。 例えば、市中金利が年3%の環境で無利子貸付を行った場合、その3%相当額が贈与とみなされるリスクがあります。
安全な利息設定のポイント
税務実務上の安全策として、最低でも年0.5%程度の利息を設定することが推奨されています。
市場金利との差が大きすぎると贈与とみなされるリスクがあるため、適正な利息設定が大切ですね。
貸主側の所得税への影響
貸主側の税務上の注意点としては、受け取った利息は所得税の対象となることです。 利息収入は雑所得として申告する必要があり、年間20万円を超える場合は確定申告が必要となります。 また、貸し倒れが発生した場合の損失の取り扱いについても、事業性がない個人間貸借では損失控除が認められない場合があるため注意が必要です。
個人間貸借での貸し倒れ損失は、事業性がないため所得控除の対象外となる可能性があります。
親族間貸借の特別な注意点
親族間での貸借については、特に税務署の目が厳しくなる傾向があります。 形式的な契約だけでなく、実際に返済が履行されているか、市場金利水準との乖離がないかなど、実質的な判断が行われます。
📝 親族間貸借で重要な証拠書類
- 正式な契約書の作成
- 返済実績の記録保持
- 振込による返済の実施
- 客観的に貸借関係を証明できる体制
そのため、契約書の作成だけでなく、返済実績の記録保持や振込による返済など、客観的に貸借関係を証明できる体制を整えておくことが重要です。
特殊なケースでの税務処理
また、借り手が法人の場合や、不動産購入資金の貸付など特殊なケースでは、さらに複雑な税務処理が必要となる場合があります。 高額な貸付や特殊な条件での貸借を行う際は、事前に税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
専門家への相談が必要なケース
- 借り手が法人の場合
- 不動産購入資金の貸付
- 高額な貸付(数百万円以上)
- 特殊な条件での貸借契約
個人間貸借でトラブルを防ぐためにやるべきこと
個人間の金銭貸借では契約書作成と適切な手続きが大切な人間関係を守る鍵となります
個人間でのお金の貸し借りは、親族や友人など身近な関係であるがゆえに、契約書の作成を怠ったり、口約束だけで済ませてしまうケースが多く見られます。 しかし、このような曖昧な取り決めは後々のトラブルの原因となり、最悪の場合、大切な人間関係を破綻させてしまう可能性があります。
「お金を貸すとき、親しい関係だからこそきちんとした約束事が大切なんですね」
法律的な観点から見ると、個人間の金銭貸借においても民法の規定が適用されます
法律的な観点から見ると、個人間の金銭貸借においても
民法(e-Gov法令検索)の規定が適用され、貸主には返済を求める権利があり、借主には返済義務が生じます。 2020年4月に施行された改正
民法(e-Gov法令検索)では、個人間の金銭貸借における法定利率が年3%に設定されており、利息について特別な取り決めがない場合でも、この利率が適用されます。
📝 改正民法のポイント
2020年4月施行の改正民法により、個人間貸借でも法定利率年3%が適用されるようになりました
ポイント
トラブルを未然に防ぐためには、事前の準備と適切な手続きが不可欠です
トラブルを未然に防ぐためには、事前の準備と適切な手続きが不可欠です。 以下では、個人間での金銭貸借において実践すべき具体的な対策について詳しく解説していきます。
個人間の金銭貸借において最も重要なのは、確実な証拠を残すことです
お金のやり取りの証拠を残す方法と記録管理
個人間の金銭貸借で最も重要なのは、貸し借りの事実を客観的に証明できる証拠を残すことです。 口約束だけでは、後日「貸した」「借りていない」という水掛け論になり、法的な解決が困難になります。
トラブルを避けるためには、必ず書面での記録を残すことが大切です
最も確実な方法は、金銭消費貸借契約書を作成することです。 この契約書には以下の事項を明記する必要があります。
- 貸主と借主の氏名、住所、連絡先
- 貸借金額(漢数字で記載し、改ざんを防ぐ)
- 貸借日
- 返済期日と返済方法
- 利息の有無と利率
- 遅延損害金の取り決め
- 両者の署名・押印
契約書は2通作成し、貸主と借主がそれぞれ1通ずつ保管します。 重要なのは、借主の直筆による署名があることで、これにより契約の存在を否定することが困難になります。
金銭消費貸借契約書まで作成しない場合でも、最低限借用書は作成しておくべきです。 借用書は借主が作成し、貸主に渡すものであり、「借りた」という事実を借主が認めた証拠となります。
ポイント
借用書でも法的効力は十分あります。最低限でも必ず作成しましょう
現金の手渡しではなく、できる限り銀行振込を利用することを強く推奨します。 銀行振込であれば、振込明細書や通帳記録が客観的な証拠となり、金銭の移動があった事実を明確に証明できます。 ATMからの振込の場合も、必ず振込明細書を保管しておきましょう。
💡 銀行振込のメリット
・客観的な証拠として法的効力が高い
・金額や日時が正確に記録される
・改ざんが困難で信頼性が高い
これらの証拠は民事訴訟において重要な役割を果たすため、時効期間(個人間の貸借の場合は5年)まで確実に保管しておく必要があります。
時効期間は
民法で定められています。書類は大切に保管しましょう
重要:すべての証拠書類は時効期間満了まで確実に保管することが必要です
返済条件を明確にする方法と変更時の手続き
曖昧な返済条件は、トラブルの温床となります。 返済に関する条件は、可能な限り具体的かつ詳細に設定し、両者が理解・合意していることを明確にしておく必要があります。
返済期日の設定
返済期日は「○年○月○日まで」というように具体的な日付を設定します。 「余裕ができたら」「ボーナスが出たら」といった曖昧な表現は避け、必ず期限を切るようにしましょう。
一括返済が困難な場合は、分割返済の回数と各回の返済額、返済日を明記することが重要ですね。
返済方法の明確化
返済方法についても詳細に定めておきます:
- 銀行振込の場合:振込先口座の詳細、振込手数料の負担者
- 現金手渡しの場合:受渡し場所と時間
- 分割返済の場合:毎月の返済日(「毎月末日」「毎月25日」など)
利息と遅延損害金の取り決め
利息を設定する場合は、
利息制限法(e-Gov法令検索)の上限(10万円未満:年20%、10万円以上100万円未満:年18%、100万円以上:年15%)を超えない範囲で設定します。
返済が遅れた場合の遅延損害金についても事前に取り決めておくことで、返済の促進効果が期待できます。
返済条件の変更手続き
当初の契約後に返済条件を変更する必要が生じた場合は、以下の手続きを踏みます:
STEP
双方の合意
まず貸主と借主の双方が変更内容について合意する必要があります
STEP
既存契約書の取り扱い
変更契約書には「本変更契約書に定めのない事項については、従前の契約書の定めによる」旨を記載し、元の契約書も引き続き有効であることを明記します
変更契約書に記載する項目
- 元の契約の特定(契約日、金額等)
- 変更する内容
- 変更理由
- 変更日
- 両者の署名・押印
返済期日の延長や分割回数の変更などは、借主にとって有利な変更となるため、貸主の合意を得ることが重要です。
公正証書や第三者立会いを活用するメリット
個人間の金銭貸借において、より確実性を高め、将来のトラブル防止を図るための効果的な手段として公正証書と第三者立会いを解説します。
個人間の金銭貸借において、より確実性を高め、将来のトラブル防止を図るためには、公正証書の作成や第三者立会いの活用が効果的です。 これらの手段は、法的な強制力や客観性を高める重要な役割を果たします。
公正証書作成のメリット
日本公証人連合会によると、公正証書は公証人が作成する公的な文書であり、以下のような強力なメリットがあります:
メリット1
執行力(強制執行認諾文言付き公正証書)
通常の私文書による契約では、返済が滞った場合、まず訴訟を起こして勝訴判決を得てから強制執行に移る必要があります。
しかし、強制執行認諾文言が付いた公正証書があれば、裁判所の判決を経ることなく直接強制執行(給与差押え、預金差押えなど)を行うことができます。
これにより債権回収の時間とコストを大幅に削減できます。
メリット2
証明力の高さ
法務省管轄の公証役場で作成されるため、その存在と内容について高い証明力を持ちます。
契約の成立や内容について争いが生じることを防止できます。
メリット3
保管の安全性
公正証書の原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
当事者が保持するのは正本や謄本であり、必要に応じて再交付を受けることも可能です。
公正証書は国の機関で作成される公的な文書なので、とても信頼性が高いんですね。特に強制執行の効力は大きなメリットです。
公正証書作成の手続き
公正証書を作成する際の流れは以下の通りです:
STEP1
事前準備
貸主と借主が公証役場に出向く日程を調整し、必要書類(身分証明書、印鑑証明書など)を準備
STEP3
公正証書の作成
当事者双方が公証役場に出向き、公証人の面前で契約内容を確認・署名
STEP4
費用の支払い
公証人手数料(貸借金額に応じて数千円~数万円)を支払い
第三者立会いの効果
公正証書ほど法的な強制力はありませんが、信頼できる第三者の立会いにも重要な効果があります。
信頼できる第三者の立会いには以下のようなメリットがあります。
- 契約の客観性確保:第三者が契約の成立を証明できるため、「そのような約束はしていない」という否認を防げます
- 心理的プレッシャー:第三者の前で約束することにより、借主に対する心理的プレッシャーとなり、返済意識の向上が期待できます
- 将来の証人:万が一トラブルが発生した場合、立会い人が法廷で証言することができます
適用場面の判断
公正証書や第三者立会いは、以下のような場合に特に有効です。
| 適用場面 | 詳細 |
|---|
| 高額な貸借 | 100万円以上など |
| 返済能力への不安 | 借主の収入状況が不安定 |
| 過去のトラブル | 以前に返済問題があった |
| 長期返済契約 | 返済期間が長い場合 |
| 複雑な利害関係 | 多数の関係者が存在 |
ただし、これらの手段は親族や友人間では関係性を悪化させる可能性もあるため、状況を慎重に判断して活用することが重要です。
手続きの手間や費用も考慮し、貸借の性質や当事者の関係性に応じて適切な方法を選択する必要があります。
📝 まとめ
個人間の金銭貸借は、適切な準備と手続きを踏むことで、トラブルを大幅に減らすことができます。
大切な人間関係を守るためにも、面倒に思わずに必要な対策を講じることをお勧めします。
【事例で学ぶ】よくある個人間貸借の失敗パターン
個人間のお金の貸し借りでは、法的知識不足による思わぬトラブルが多発しています。事前の知識習得でリスクを回避しましょう。
個人間でお金の貸し借りを行う際、法的知識が不足していることで思わぬトラブルに発展するケースが数多く発生しています。 善意で始まった貸し借りが、結果的に法律に抵触したり、税金の問題を引き起こしたりすることは決して珍しいことではありません。
ここでは、実際に起こりがちな失敗事例を通じて、個人間貸借における法的リスクとその対処法について詳しく解説していきます。 事前に適切な知識を身につけることで、トラブルを未然に防ぎ、安心してお金の貸し借りができるようになるでしょう。
このセクションで学べること
• 個人間貸借で発生しやすいトラブルパターン
• 法的リスクの具体的な内容と対処法
• 安全な貸し借りのための事前準備方法
利息制限法違反となった実例と対処法
個人間の貸し借りにおいても利息制限法は適用されます。
この法律では、元本の額に応じて以下のような上限金利が定められています:
利息制限法の上限金利 ・元本10万円未満:年20% ・元本10万円以上100万円未満:年18% ・元本100万円以上:年15%
実例:友人への高金利貸付けケース
Aさんは友人のBさんに50万円を貸し付ける際、「リスクが高いから」という理由で年25%の利息を設定しました。
しかし、利息制限法では50万円の貸付けに対する上限金利は年18%であるため、7%分の利息は法律上無効となってしまいます。
年109.5%を超える利息を取った場合、
出資法違反として刑事罰の対象となる可能性があります。個人間の貸し借りであっても、この規制から逃れることはできません。
対処法
利息制限法に違反してしまった場合の対処法は以下の通りです:
STEP
利息の再計算と返還
既に受け取った超過利息については、借り手に返還する必要があります。
法定利率を超える部分は元本に充当されるため、残債務を正確に計算し直すことが重要です。
STEP
契約条件の見直し
現在進行中の貸付契約については、利息を法定上限以下に変更し、新たな合意書を作成します。
STEP
適切な記録の作成
利息の返還や契約変更について、後日のトラブルを避けるため書面で記録を残します。
重要なポイント
利息制限法違反は民事上の問題だけでなく、高すぎる金利設定は刑事罰の対象となる可能性もあります。個人間の貸し借りでも必ず法定上限を守りましょう。
借用書なしで貸したケースの回収方法
個人間の貸し借りで最も多いトラブルは、借用書なしで貸付けを行ったケースです。
個人間の貸し借りで最も多いトラブルが、借用書を作成せずに貸付けを行ったケースです。 口約束だけでお金を貸してしまうと、後で「借りていない」「もらったお金だ」と主張される危険性があります。
親しい間柄だからこそ、きちんとした書面を残すことが大切ですね。
実例:親友への無担保貸付けケース
Cさんは長年の親友であるDさんから「急にお金が必要になった」と相談され、信頼関係があるからと借用書を作成せずに30万円を貸し付けました。 しかし、返済期日になってもDさんは「そんなお金は借りていない」と主張し、連絡も取れなくなってしまいました。
信頼関係があっても、金銭の貸し借りは必ず書面で残すことが重要です。
回収のための具体的方法
借用書がなくても、適切な証拠収集と法的手続きにより回収が可能です。
- 証拠の収集と整理
- 内容証明郵便による督促
- 法的手続きの活用
STEP1
証拠の収集
借用書がない場合でも、以下のような証拠により貸付事実を証明できます:
- 銀行振込の履歴や通帳の記録
- メールやLINEでのやり取り
- 第三者の証言(貸付けの場面を目撃した人など)
- 録音データ(相手が借金を認める発言をした場合)
STEP2
内容証明郵便による督促
証拠を整理した上で、内容証明郵便(日本郵便)により正式に返済を求めます。
この際、貸付けの事実、金額、返済期日を明記し、一定期間内に返済がない場合は法的措置を取る旨を記載します。
STEP3
法的手続きの活用
| 手続き名 | 特徴・対象 |
|---|
| 支払督促 | 簡易裁判所に申し立て、相手方に支払いを命じる決定を出してもらう手続き |
| 少額訴訟 | 60万円以下の金銭トラブルについて、1回の審理で解決を図る簡易な訴訟手続き |
| 調停 | 裁判所の調停委員が間に入って、話し合いによる解決を目指す手続き |
借用書がなくても、適切な手続きを踏めば回収の可能性があるのですね。
📝 重要なポイント
借用書がない場合の回収は困難ですが、証拠の収集と適切な法的手続きにより解決が可能です。ただし、今後は必ず借用書を作成することが最も重要な対策です。
家族間貸借で贈与税がかかった事例
家族間の金銭貸借は税務上「贈与」とみなされるリスクが高く、意図しない贈与税課税を受ける可能性があります。
家族間でのお金の貸し借りは、税務上「贈与」とみなされるリスクが特に高く、意図しない贈与税の課税を受ける可能性があります。
親族間での資金援助は、きちんとした手続きを踏まないと思わぬ税金がかかってしまうケースが多いんです。
実例:親から子への住宅資金援助ケース Eさんは息子の住宅購入資金として1,000万円を「貸付け」という名目で渡しました。 しかし、利息の設定もなく、返済計画も曖昧だったため、税務署から「実質的な贈与である」と判断され、息子に対して贈与税約177万円が課税されました。
無利息・返済計画不明確な貸付けは、
国税庁により贈与とみなされる可能性が高くなります。
贈与とみなされるパターン 以下のような場合、
国税庁は貸借ではなく贈与と判断する可能性が高くなります。
- 利息の設定がない、または著しく低い利息
- 返済期限が設定されていない
- 実際に返済が行われていない
- 返済能力を超える金額の貸付け
- 借用書などの書面がない
贈与税回避のための対策
STEP1
適切な利息の設定
無利息や極端に低い利息での貸付けは贈与とみなされる可能性があります。 市場金利や国税庁が定める基準利率(年1.6%程度)を参考に、適切な利息を設定することが重要です。
STEP2
明確な返済計画の作成
借用書には以下の事項を明記します:
- 貸付日と借入日
- 借入金額
- 利率
- 返済方法(月々の返済額、返済日など)
- 返済期限
- 遅延損害金
STEP3
実際の返済実績の記録
計画通りに返済が行われていることを証明するため、銀行振込などの客観的な記録を残します。 現金での受け渡しの場合は、受領書を作成し保管します。
STEP4
借り手の返済能力の確認
年収や資産状況に比べて過大な貸付けは、返済の意思・能力がないものとして贈与認定のリスクが高まります。 借り手の経済状況を踏まえた現実的な貸付額に留めることが大切です。
特に高額な資金援助の場合は、事前に専門家に相談することで安心ですね。
これらの対策を講じることで、家族間であっても適切な貸借関係を維持し、贈与税の問題を回避することができます。 特に高額な資金援助を行う場合は、事前に税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
ポイント
家族間貸借で贈与税を回避するには、適切な利息設定・明確な返済計画・実際の返済実績・返済能力の確認が重要です。
トラブルが起きた時の解決方法と相談先
個人間の金銭トラブルは段階的なアプローチで解決を目指すことが重要です
個人間でお金の貸し借りをした際にトラブルが発生した場合、適切な解決方法を知っておくことが重要です。 相手が返済をしてくれない、連絡が取れなくなったなどの問題が起きた時は、段階的なアプローチを取ることで解決の可能性を高めることができます。
まずは相手との話し合いから始まり、それでも解決しない場合は法的手続きの検討、必要に応じて専門家への相談という順序で対応していくことが基本的な流れとなります。
感情的になって無理な取り立てを行うと、逆に法的な問題を引き起こす可能性があるため、冷静かつ適切な手順を踏むことが重要です。
なお、金銭の貸し借りに関する権利義務については、民法(e-Gov法令検索)において詳細が定められています。
返済してもらえない時の請求手順と注意点
返済されない場合は段階的な請求で解決を図る。書面催促→直接催促→支払い計画提案の順で進める。
相手が約束した期日に返済をしてくれない場合、以下の手順で段階的に請求を行うことが効果的です。 第1段階:書面による催促 まずは
内容証明郵便(日本郵便)を利用して、書面による催促を行います。 口頭での催促よりも法的効力が強く、相手にプレッシャーを与える効果があります。 内容証明郵便には、貸付金額、返済期日、催促日などを明記し、一定期間内の返済を求める内容を記載します。
内容証明郵便は公的な証拠になるため、後々裁判になった場合にも重要な証拠として活用できます。
第2段階:電話・直接面談での催促 書面での催促に応じない場合は、電話や直接会って催促を行います。 この際、相手の都合を考慮した時間帯に連絡し、威圧的な態度は避けることが重要です。 会話の内容は記録として残しておくことをおすすめします。
催促時のポイント
- 相手の都合を考慮した時間帯に連絡
- 威圧的な態度は避ける
- 会話内容を記録として保管
第3段階:支払い計画の提案 一括返済が困難な場合は、分割払いなどの支払い計画を提案することも考えましょう。 相手の経済状況を確認し、現実的な返済プランを作成することで、解決に向けた道筋をつけることができます。
STEP
経済状況の確認
相手の収入や支出状況を把握し、返済可能な金額を算出します。
STEP
合意書の作成
合意した内容を書面にまとめ、双方で署名・捺印します。
注意すべきポイント
催促行為には法的な制限があります。違法な取立行為は刑事罰の対象となる可能性があります。
催促を行う際は、以下の点に十分注意する必要があります。
深夜や早朝の連絡、職場への頻繁な連絡、暴力的な言動などは法的な問題を引き起こす可能性があります。 また、相手のプライバシーを侵害するような行為や、第三者に借金の事実を暴露するような行為も避けるべきです。
絶対に避けるべき行為
- 深夜・早朝の連絡(午後9時~午前8時)
- 職場への頻繁な連絡
- 暴力的な言動や威嚇行為
- 第三者への借金事実の暴露
- プライバシー侵害行為
適切な催促方法を守ることで、トラブルを避けながら回収の可能性を高めることができますね。
法的手続き(調停・訴訟)を使う判断基準
個人的な催促では解決しない場合、法的手続きの利用を検討する必要があります。 どの手続きを選択するかは、借用金額や状況によって判断します。
個人的な催促では解決しない場合、法的手続きの利用を検討する必要があります。 どの手続きを選択するかは、借用金額や状況によって判断します。
民事調停(裁判所公式サイト)は、調停委員が仲介役となって話し合いの場を設ける手続きです。
民事調停法(e-Gov法令検索)に基づく制度で、以下の条件に当てはまる場合に適しています。
- 借用金額が比較的少額(数十万円程度)である場合
- 相手がある程度話し合いに応じる可能性がある場合
- 費用を抑えて解決したい場合
60万円以下の金銭の請求については、
少額訴訟(裁判所公式サイト)の利用が可能です。
民事訴訟法(e-Gov法令検索)に基づくこの手続きは1回の審理で判決が出るため、迅速な解決が期待できます。
少額訴訟のメリット
証拠が明確で、相手の所在が分かっている場合に特に有効です。
- 手続きが簡単
- 迅速な解決(原則1回の審理)
- 費用が比較的安い
借用金額が高額な場合や、複雑な事情がある場合は通常訴訟を選択します。 時間と費用はかかりますが、最も確実な法的解決手段となります。
特に、相手が返済能力があるにも関わらず返済を拒んでいる場合や、借用書などの証拠が整っている場合に適しています。
📝 手続き選択の検討ポイント
手続きを選択する際は、以下の要素を総合的に検討する必要があります。
| 検討要素 | 詳細 |
|---|
| 借用金額 | 少額訴訟は60万円以下、高額は通常訴訟 |
| 証拠の有無 | 借用書、振込記録等の証拠の整備状況 |
| 相手の資力 | 返済能力の有無と推定 |
| 解決までの時間 | 迅速性を重視するか、確実性を重視するか |
| 費用対効果 | 手続き費用と回収見込み額との比較 |
また、
相手が行方不明の場合は、まず所在調査を行う必要があります。
弁護士に相談した方がいいケースと費用目安
個人間の金銭貸借トラブルにおいて、弁護士への相談が必要になるケースがあります。
高額な借用金や証拠不十分な場合は、弁護士への相談を強く推奨します
以下のような状況では、弁護士への相談を検討すべきです。
- 借用金額が高額(100万円以上)の場合
- 借用書などの証拠が不十分で法的な立証が困難な場合
- 相手が弁護士を立てている場合
- 強制執行が必要な場合
- 相手から逆に訴訟を起こされた場合
相手が暴力団関係者である場合や脅迫的な言動を受けている場合は、安全面からも必ず弁護士に依頼してください
複数の債務者がいる場合や、連帯保証人の問題が絡む場合も、法的な判断が複雑になるため専門家の助言が必要です。
弁護士費用の目安
弁護士費用は事務所によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
| 費用項目 | 金額目安 |
|---|
| 相談料 | 30分5,000円~10,000円程度
(初回無料の事務所も多数) |
| 着手金 | 借用金額の10~20%程度
(最低10万円~30万円) |
| 成功報酬 | 回収額の15~25%程度 |
多くの事務所では
初回相談を無料で行っています。 着手金は借用金額の10~20%程度が目安となり、最低金額として10万円~30万円程度を設定している事務所が多いです。 成功報酬は回収額の15~25%程度が一般的です。
費用対効果の検討
少額の借用金の場合、弁護士費用が回収額を上回る「費用倒れ」になる可能性があります
弁護士費用は決して安くないため、費用対効果を慎重に検討する必要があります。 借用金額が少額の場合、弁護士費用が回収金額を上回る「費用倒れ」になる可能性があります。 多くの弁護士は、相談時に費用倒れのリスクについて説明してくれるため、率直に相談することが重要です。
弁護士選択のポイント
良い弁護士選択のポイント
- 債権回収の経験と実績が豊富
- 費用の透明性が高い
- 連絡が取りやすい
- 説明が分かりやすい
債権回収に経験のある弁護士を選ぶことが重要です。 初回相談で、類似案件の取り扱い経験や成功実績について確認しましょう。 また、費用の透明性、連絡の取りやすさ、説明の分かりやすさなども選択の重要な要素となります。
日本弁護士連合会の地域の弁護士会や
法テラス(日本司法支援センター)を通じて弁護士を紹介してもらうことも可能です。 経済的な理由で弁護士費用の支払いが困難な場合は、
法テラスの民事法律扶助制度の利用も検討できます。
💡 弁護士選びで迷ったら
複数の弁護士に相談して比較検討することも大切です。相性や説明の分かりやすさも重要な要素となります。
金銭消費貸借契約書の作成は必須
個人間の金銭貸借では適切な契約書の作成が最重要。口約束では法的証拠能力が低く、トラブル時の権利保護が困難。
個人間での金銭貸借において最も重要なのは、適切な契約書の作成です。 口約束だけでは法的な証拠能力が低く、トラブル時に貸主の権利を守ることが困難になります。
民法(e-Gov法令検索)に基づく金銭消費貸借契約書には以下の要素を必ず含める必要があります。
契約書に記載すべき必須項目
- 金銭消費貸借に合意したことの明記
- 貸借金額の明確な特定
- 返済期日や返済方法の詳細
- 利息の計算方法と利率
- 遅延損害金の設定
- 期限の利益喪失条項
- 連帯保証人の設定(必要な場合)
これらの項目を明確に記載することで、後日のトラブルを防ぎ、法的な効力を持つ契約書として機能します。 特に金額や返済条件については、曖昧な表現を避け、
具体的かつ明確に記載することが重要です。
注意:口約束による金銭貸借は法的証拠として弱く、回収困難になるリスクが高まります
利息設定時の法的上限の遵守
個人間貸借でも利息設定には法的制限があります。上限を超えると法的リスクが発生します。
個人間貸借であっても、利息の設定には法的な制限があります。
利息制限法(e-Gov法令検索)と
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(e-Gov法令検索)という二つの法律によって上限金利が定められており、これを超える利息設定は法的に無効となる可能性があります。
📊 利息制限法の上限金利
| 元本金額 | 上限金利(年率) |
|---|
| 10万円未満 | 20% |
| 10万円以上100万円未満 | 18% |
| 100万円以上 | 15% |
この上限金利は個人間貸借でも適用されるので、必ず確認しておきましょう。
で定める上限金利を超えて契約をした場合、超えた部分のみが無効となり、借主は超過部分について返済義務を負いません。 さらに
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(e-Gov法令検索)における上限金利を超えた場合は、契約全体が刑事罰の対象となる可能性があります。
無利息貸借のポイント
無利息での貸借も可能ですが、この場合でも契約書の作成は必要です。 利息を設定しない場合は、契約書にその旨を明記しておくことで、後日の誤解を防ぐことができます。
税務上の注意点と贈与税のリスク
個人間の金銭貸借では、税務上の問題も考慮する必要があります。 特に以下のケースでは、
贈与税(国税庁)の対象となる可能性があります。
贈与税の課税対象となる可能性があるため、適切な契約書の作成と返済記録の保存が不可欠です。
📝 贈与とみなされるリスクケース
- 無利息または著しく低い利息での貸借
- 返済期限が設定されていない貸借
- 返済能力に見合わない高額な貸借
- 返済が実際に行われていない場合
は、形式的には貸借であっても実質的に贈与と判断される場合は、みなし贈与として
贈与税(国税庁)を課税することがあります。 このリスクを避けるためには、
適正な利息の設定、明確な返済計画、実際の返済実績の記録が重要です。 親子間や夫婦間での貸借の場合は特に注意が必要で、税務調査の際に贈与でないことを証明できるよう、契約書の作成と返済記録の保存を徹底する必要があります。
リスク回避のポイント
契約書作成の重要性- 適正な利息率の設定(市場金利を参考)
- 明確な返済期限・返済方法の記載
- 実際の返済記録の保存・管理
公正証書作成による法的効力の強化
公正証書は通常の契約書を超えた強力な法的効力を持つ公文書です
より確実な法的保護を求める場合は、
公正証書(法務省公証制度)による契約書の作成を検討することが重要です。 公正証書には通常の契約書にはない以下のような強力な効力があります。
公正証書の特別な効果
- 無用な言い訳や契約の否定を抑制できる
- 裁判を経ずに強制執行が可能
- 裁判時の有効な証拠として高い証明力を持つ
公正証書は
公証人(法務省公証制度)が作成するため、法的な不備がなく、借主が返済を怠った場合に迅速な債権回収が可能になります。
特に高額な貸借や、返済に不安がある相手との契約では、公正証書の作成を強く推奨します
📝 公正証書のメリットまとめ
公正証書なら相手が「約束していない」と言い逃れすることはほぼ不可能で、約束を守らない場合は裁判なしで強制執行できるため、確実な権利保護が実現できます。
連帯保証人設定時の法的要件
連帯保証人設定時は改正民法の新たな法的要件に注意し、保証人の理解と同意を十分に得ることが重要
貸借契約において連帯保証人を設定する場合は、
改正民法(e-Gov法令検索)の規定に注意する必要があります。 個人を保証人とする根保証契約については、新たな法的要件が設けられています。
連帯保証人設定の注意点
- 保証人の財産状況の事前確認
- 保証債務の具体的な内容の説明
- 保証人の署名・押印の適切な取得
- 保証限度額の明確な設定(根保証の場合)
連帯保証人は主たる債務者と同等の返済責任を負うため、十分な説明と理解が不可欠ですね
連帯保証人は主たる債務者と同等の返済責任を負うため、保証人となる人の理解と同意を十分に得ることが重要です。 また、保証人の返済能力についても事前に確認し、実効性のある保証とする必要があります。
保証人の返済能力の事前確認を怠ると、実際の債務不履行時に回収できないリスクがあります
トラブル回避のための記録保存
契約後も継続的な記録保存が重要。トラブル時の証拠として活用できます。
契約後も継続的な記録の保存が重要です。 以下の書類や記録は、トラブル発生時の重要な証拠となります。
記録を残すことで、後々のトラブルを防げるだけでなく、信頼関係も維持できますよ
保存すべき記録
- 金銭の授受記録(振込明細、受領書等)
- 返済記録(入金確認書、返済計画書等)
- 当事者間の連絡記録(メール、書面等)
- 利息支払い記録
これらの記録は、契約の履行状況を客観的に証明し、
国税庁による税務調査や法的紛争の際に重要な役割を果たします。 特に現金での授受は記録が残りにくいため、できる限り銀行振込等の記録が残る方法を選択することが重要です。
現金の授受は避け、必ず記録が残る方法を選択しましょう
📝 まとめ
個人間の金銭貸借は、適切な準備と手続きを行うことで安全に実施できます。 法的な要件を満たし、十分な記録を残すことで、大切な人間関係を守りながら適切な貸借関係を築くことが可能になります。