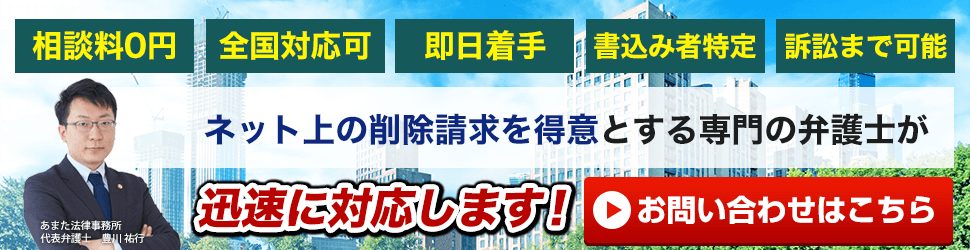2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら

執筆・監修:豊川祐行
2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら
この記事の目次
誹謗中傷が抱える問題
誹謗中傷は悪口や根拠のない事を言いふらし、他人の名誉を傷つけること行為です。
誹謗中傷という言葉自体は法律用語ではありません。しかし、SNSなどのネット上に悪質な書き込みをすると名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪、信用毀損罪、業務妨害罪などの罪に問われる可能性があります。
便利なSNSは利用者が多い
厚生労働省の研究チームが発表した調査によると、日本におけるX(旧Twitter)の月間利用者は17年10月には4500万人を超えています。また、総務省の「令和5年情報通信に関する現状報告の概要」では、日本でのSNS利用者数は2022年時点で1億200万人になっており、日本人のほとんどが何かしらのSNSを利用している状態です。
SNSは様々な情報を得られる、便利なコミュニケーションツールです。天気、電車の遅延、学校の休講、事件、事故、災害などの情報をスピーディー知ることができますので、情報ツールとしても使わざるを得ない状況と言えるでしょう。
誹謗中傷は消せるが心の傷は残る
誹謗中傷はプロバイダーに要請するなどで、ネット上から削除してもらうことは可能です。しかし、たとえ削除されても、心に負った傷は一生残ると言えます。芸能界では人気女優が「最初はめちゃくちゃ驚きました。だって、会ったことも話したこともない顔の見えない人から、言葉でグサグサと刺されるんだから」とSNS上でつづっていたことがありました。
心ないネット上の悪口や根拠のない事を言いふらす行為は増加しており、自死のきっかけになることも多く社会問題になっています。キーボードによる殺人として“指殺人”と表現されることもあります。
被害者が自死を選ぶ現状
2020年にはリアリティー番組の出演者がネット上で誹謗中傷を受け、自らこの世を去ったというショッキングなニュースがありました。
さらに韓国では元女性アイドルグループメンバーが、自宅で亡くなっているのが見つかったと報じられた事件がありました。この女性アイドルは、誹謗中傷に悩まされていたと言われています。
コロナ禍で家で一人になる時間が多くなるなど、被害者の悩む環境が整ってしまったことも自死につながったと考えられています。

誹謗中傷に対する日本の取り組み
誹謗中傷をなくすため、日本でも法改正などの動きが出ています。
日本政府の動きと法改正の動き
政府は2021年2月にプロバイダー責任制限法の改正案を閣議決定し国会へ提出しました。
新たな情報開示の裁判手続きを簡略化するといった内容で、匿名の投稿者を特定しやすくし被害者に対し迅速な救済を行うことを目的としています。
一方、総務省は2020年8月に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項」の発信者情報を定める省令の一部改正を制定し、加害者に対し電話番号の開示を請求できるようにしました。
自民党ではプロジェクトチームをつくり、プロバイダ責任制限法、民法、刑法などの改正を視野に入れているということです。また、日本新聞協会は、被害者救済と表現の自由のバランスの重要性やSNS事業者の責任範囲についてなど、総務省に意見書を提出しています。
警告やAIの活用
誹謗中傷の加害者や被害者を出さないための施策として、悪口など人を傷つける言葉を投稿すると警告が現れる方法があります。あるいじめ防止アプリでは警告がポップアップで出るようにすると、9割の人が書き込みをやめたという実験結果が得られました。投稿する前にいったん考える時間を与えられると、誹謗中傷を抑えられることがわかります。
そして、SNSの運営者側の対策として、AIの導入を推奨するネット専門家もいます。AIが誹謗中傷の内容と判断すると、これまでの裁判の事例や結果などがポップアップで出るようなシステムを作るべきとしています。
ネットリテラシー専門家は、誹謗中傷は「表現の自由」の1つではあれど「責任」を伴うと述べています。

有料会員制の導入
有料会員制のSNSは不特定多数を対象にしたSNSと比べると、誹謗中傷は起きにくいと言えます。近年は欧米を中心とした有料会員制のクローズドSNSがブームになっています。有料会員向けコミュニティアプリなどもあり、誹謗中傷のコメントが書き込まれず、ファンとのエンゲージメントが向上するといった効果を得られています。
中には、Facebookでのログインを必要とし、信頼の向上を図っている有料会員制サービスもあります。
実名投稿の義務化は難しい
匿名性が高いインターネット上では誹謗中傷が起きやすいと言われており、なくすためにはSNSの実名投稿を義務化すれば良いという意見があります。ある調査ではウェブニュースサイトのコメントは、実名投稿が好ましいと考える人が40%程度いたという結果もあります。
しかし、SNSの場合、実名投稿は表現の自由を侵す危険性があります。また、韓国で実名投稿が実施されても誹謗中傷の数を減らす効果はそれほど得られなかったという実例もあります。誹謗中傷をする人は「自分は正義であり正しい」という思いが強く、実名でも投稿を控えない傾向があったとのことです。
また、SNSの実名投稿は個人情報が流出しやすい問題があります。
誹謗中傷に対する世界各国の取り組み
誹謗中傷に対し世界はどのように対処しているのか、アメリカ、フランス、ドイツ、韓国の事例を紹介します。
アメリカの事例
アメリカではX(旧Twitter)の不適切なツイートに対しては、投稿ボタンを押す前に警告を表示させる機能を試験的に導入しています。
しかし、2020年にトランプ大統領はSNS(交流サイト)の規制強化に向けた大統領令に署名しました。SNSの運営側が政治的な投稿の制限や削除をしたとき、投稿者が運営事業者に法的な責任を問えるようにしたものです。投稿の監視をけん制するのが狙いでしたが、言論の自由を侵害するとして批判されました。
そして20205年にはSNSの言論に政府が介入し検閲する行為を禁止する大統領令に署名しています。
アメリカでは言論の自由が認められており、悪質な投稿といえども規制しなくすのは簡単ではありません。誹謗中傷のほかわいせつや児童ポルノ、脅迫、喧嘩、虚偽広告などは規制の対象にはなっていますが、どこまで「表現の自由」なのかの線引きの判断は難しい面があります。
フランスの事例
2020年5月にネット上の有害コンテンツを通報から1時間以内の削除を求める法律が可決されました。
- 生命・人格に対する侵害等を称揚(擁護)するもの
- 出自又は特定の民族・人種・宗教を理由とした差別・憎悪・暴力を扇動するもの
- 児童ポルノを拡散するもの
投稿者には最大1年の実刑または最大200万円の罰金が課せられます。しかし、この法案は「表現の自由」を損なうものとして批判の声が多くあり、違憲とされる内容が多いと判断されています。また、24時間以内に削除というスピーディーな対応が可能なのは規模が大きな事業者に限られ、すべてのSNSに対応するのは現実的ではないとの指摘もあります。
ドイツの事例
ヘイトスピーチが深刻な問題となっているドイツでは、2018年1月から事業者に違法な投稿の削除などを義務づける「SNS対策法」が運用開始しました。
国内200万人以上のユーザーが登録しているプラットフォームが対象となり、削除対象は、刑法が禁止する違法情報です。適切に行わない場合には、最大5000万ユーロ(約60億円)の過料を科されます。
参考:インターネット上の違法・有害情報を巡る独・仏の動向
韓国の事例
警察庁によると韓国のネット上の誹謗中傷をめぐるトラブルは2012年の5684件から19年は1万6633件に急増しています。このような事態を受け韓国の大手ポータルサイトでは、芸能ニュースへの書き込み機能廃止を発表しました。
2007年には書き込みをする際は本人確認が必要になるインターネット実名制を導入しましたが、違憲と判断され2012年には廃止されています。
参考:韓国芸能人を苦しめる「指殺人」悪質コメはどれだけ酷く、なぜなくならないのか
インターネット上の誹謗中傷まとめ
社会問題となっているインターネット上の誹謗中傷をなくすため、日本をはじめ世界で対策が考えられています。
ただ。言論の自由、表現の自由も確保しなければならず、すべて規制するのは難しいのが現状と言えるでしょう。
もし、誹謗中傷の深刻な被害に遭ってしまったら、ひとりで悩まず弁護士に相談するのがおすすめです。法律に基づいて投稿を削除させたり、投稿者を特定し加害者として罪に問うこともできます。慰謝料などの損害賠償金の請求もできますので、弁護士は力強い味方になってくれます。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ